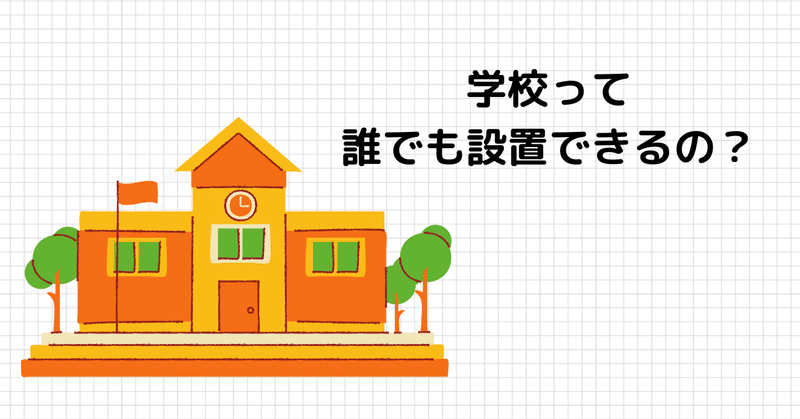
【教育】学校って誰でも設置できるの?
今回は学校は誰でも設置できるのかについてお伝えしたいと思います。
ちなみに株式会社の設立については設立のために動く発起人(ほっきにん)が定款を作成して出資して登記のために必要な事項を決めて登記申請をして設立するのですが、この発起人は誰でもなることができます。
では、学校の設立はどうなのでしょうか。
学校教育法を見てみます。
第二条
学校は、
国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、
地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)
及び
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)
のみが、これを設置することができる。
② この法律で、
国立学校とは、国の設置する学校を、
公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、
私立学校とは、学校法人の設置する学校を
いう。
学校を設置できるのは3者のみということです。
国、地方公共団体そして学校法人です。
国には国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含みます。
地方公共団体には公立大学法人を含みます。
学校法人というのは私立学校法という法律に規定されています。
自分が国や地方公共団体になることは不可能です。そこで働くことはできますが。
そこで自分で設置したいという方は、学校法人を設立する必要があります。
学校法人はどうやって設立するのでしょうか。
私立学校法を見てみます。
長いのでまとめて後記します。
要約すると以下の通りです。
まず学校法人とは何かについては以下のように定めがあります、
第三条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この学校法人を設立しようとする場合、株式会社でいう定款のように目的等を定めるための「寄付行為」というものを定めなければなりません。
寄付するという行為を指すのではなく、学校法人における基本的事項を定めたものを指します。
なぜ寄付行為という名称なのかはわかりません。
そして、株式会社の定款の場合は公証人による認証が必要となるのですが、学校法人の場合、所轄庁に対して認可を得なければなりません。認可のための申請が必要となります。
そして所轄庁は、その設立しようとする学校法人が法律で定められた資産を有しているか否かなどを審査して認可を決定することになります。
株式会社は1円でも設立できますが、学校法人は学校を経営するための資産が求められるということです。
以下の規定もあります。
第三条 学校を設置しようとする者は、
学校の種類に応じ、
文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、
これを設置しなければならない。
設備、編成など設置基準があるわけですね。
法律の条文を読む限りですが一番大変そうなのは資産でしょうか。
また、資産以外の設置基準というのもハードルがありそうです。
こういったことを審査する所轄庁の認可というのは大変そうですね。
認可されなければ設立のための登記申請もできませんからね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
(申請)
第三十条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
(認可)
第三十一条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
(寄附行為の補充)
第三十二条 学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第三十条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(設立の時期)
第三十三条 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
(資産)
第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
(所轄庁)
第四条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。
一 私立大学及び私立高等専門学校
二 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
三 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
四 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
五 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
