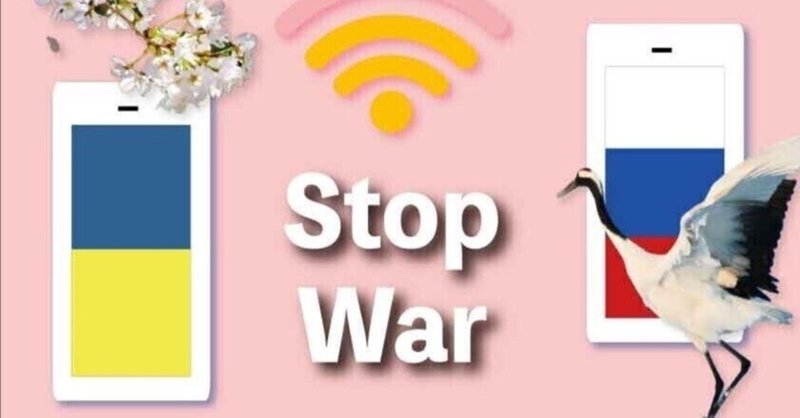
バカの一つ覚え
仕事が上手くいかなかった時、負け戦になりそうな時、もめ事が起こった時、人は自分のせいではないと信じたいものです。しかしそれを口にすると見苦しい事になったりします。この頃TVのニュース番組を視ているとそういうケースが色々あります。
バカの一つ覚え
洋の東西を問わず、成功したら『自分がやった』失敗したら『お前の責任だ』と言う人がいます。もちろんこう言う人は信用されません。『誰があんな人間の為に働いてやるか』となります。でもこういう人間は少なくありません。
狡猾な人間は表現が巧ですから、ついつい上層部は騙されます。例えば責任を取っているようで実は責任を転嫁する技術さえ持っています。『今回の失態は私の指導不足です。彼がきちんと処理したかどうか、忙しいとは言えチェックするタイミングを逸しました。もっと早く指導すればよかったのです。そうすればこんな事態にはなりませんでした』と責任を取っているふりをしています。
一方、バカの一つ覚えに対して利口の一つ覚えもあります。それは何か。失敗したら『自分が悪かった』成功したら『君のお陰だよ』たったこれだけです。こんな会話が二人の人間関係をぐっと縮めます。
人は自分の為に生きています。しかしそれだけではありません。人には誰かに喜んでもらおうとする本能があります。完全な利己主義者はそうはいません。家族の為に、取引先の為に、部下の為に、同僚の為に、・・・。色々対象は変わるでしょうが誰かの為に働きたいと思っています。
禍は口より出て病は口から入る
人は最も口を慎まねばなりません。口は二つの役割を持っています。一つ目は言葉を発する事であり、他方は飲食物を取り込む事です。人が言葉を慎まないと禍を招く事があり、飲食を慎まないと病気になる場合があります。
毒舌は大変高度な技で、例えるならF1レーサーがすごいスピードでコーナーを曲がっていくようなものです。誰も傷つけないように考えています。傷つけたとしても、それは暗黙の了解が取れているような高度なテクニックです。
言葉は水の中に落としたインクのようなもので、ほんの一滴でも全体をその色に染めてしまいます。例えば99回いい事を言ったとしても、残りの一回でちょっと不愉快にさせてしまったらそれでアウトです。
最近、世間では傷つく事を激怒に変えていく人たちがいて、いわば潜在的な悪意が増幅するような装置があるとも言う事ができます。そこでは善意も悪意も増幅します。
言ってはいけない事を言わない方が言うべきことを言い損ねるよりもましな所が在る為、日本ではどうしても防衛的な守りの強い地味な社会になる傾向があります。西洋では言いたい事を言って、マイナスの失言があったとしてもお互いに反省して我慢します。そういう攻めの方向に行った方が全体的にはプラスポイントの大きい場合もあります。
長所を指摘する
『あなたって心が優しい人なのね』『どうしてそんなに親切なの?』『嘘がつけない正直者なのですね』『君ほど仕事が早い人はいないよ』他人からこんな風に褒められて嬉しくない人はいません。『そんな事はありませんよ』と応じたとしても内心は『へえ、そんな風に思われているのか、自分では気づかないものだなあ』などと喜んでいます。
人は他人から自分の長所を指摘されると、たとえそれが嘘やお世辞であっても信じてしまう傾向があります。これは『バーナム効果』と呼ばれています。人は他人からの評価を、それが自覚している長所であれば、なおさら嬉しく、信じやすい傾向があります。
もし恋人にもっと優しく接してほしければ『あなたって本当は優しい人なのですね』『あなたのそういう優しい所が私は好きなの』と一言指摘すれば相手は『もっと優しくしよう』と思います。その恋人は指摘された性格を信じてしまい、本当に優しい人に変身していくでしょう。
仕事が雑な部下には『仕事がいつも丁寧だね、これからも頼むよ』と言います。すると部下は仕事を正確にするようになります。自分に自信がない生徒を変えるには『自分の優れた能力をまだ知らないだけだ』と言います。すると生徒は自分の可能性を信じるようになります。ポジティブな指摘であれば、なおさら人はそれを信じて変わっていきます。

それぞれに個性的でリーダーシップのある指導者ですが、ロシアのプーチン大統領、トルコのエルドアン大統領、ベラルーシのルカシェンコ大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領等の一国を代表して責任を取らなければならない立場の人たちの発言を聞いていると時節柄それなりによく考えた内容になっていると感じます。またあのような重要な内容を紙を見ないで自分の言葉で語っているのは素晴らしい言語能力をお持ちなのだと思います。それにしても思い出のある地ウクライナに早く平和が戻る事を切に祈ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
