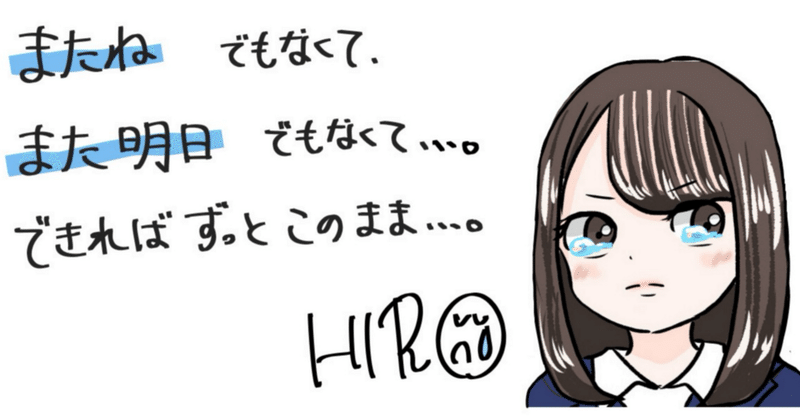
卒業式の思い出
制服を自分に似合うように着こなし、家族と思われる大人と共に歩く学生の姿を、街中でよく見かけるようになった。頭、両手には花を添え、いつになくカラフルである。
この光景を見ると、
ああ、もう卒業式シーズンかと、
期待と切なさと様々な感情が混沌とした気持ちとなる。
自己紹介として、私は静岡で予備校講師をしている。
20歳の自閉の傾向が強かったセダンの走り屋ヤンキーと、24歳の愛着障害をかかえたヤンキーの無計画子作り行為により、私はこの世に誕生した。家族の間に愛などなかったので、わずか3年で両親は離婚した。
私が一番心に残っている卒業式は、中学校の卒業式だ。
私は今までこれといってなにかを努力した経験が無かったのだが、バレーボール部に入り、初めて努力と向き合った。おそらく人生で1番怒られ、1番よく考えた部活動人生だった。
何となくうちの家はやばいと悟った3年間。
家での会話や笑顔がなかった私は、
学校こそが自分らしく、わがままや甘え等、自分の素を出せる環境であった。
恋にこんなにも感情が動いて、恋のことをこんなにも考えた経験も初めてだった。恋を知らない15歳の少女の恋はなんと、尊いものだろうか。そんな恋をしたのもこの中学校3年間だった。
そんな中学校の卒業式は、
非常に、非常に、苦しかった。
泣きすぎて嗚咽が出た。
過呼吸になった。
辛かった。分かり合える友と恩師と離れるのが嫌だった。
当たり前が当たり前でなくなることが辛かった。
卒業式後、帰りたくなくてずっとみんなで集まって写真を撮っていた。(泣きすぎてみんな不細工である)
しかし、私はあることに気がつく。
一緒にいる友人の制服のボタンが消えていくことに。
私の周りの友人の制服からボタンが消えていくのだ。
なんなら、ワイシャツのボタンまでなくなっていくのだ。
これはどういうことなのか。
その友人たちのボタンに価値があり、
その友人たちのボタンを欲しがる人達が続出しているのだ。
それを知った私は青ざめた。
私のボタンに価値がないので、私の制服にはしっかり全てのボタンがついているのだ。
その瞬間、私はここから消えてしまいたくなった。
「私(のボタン)に価値はない」
と、自身の制服が物語っているかのようにみえた。
少し不貞腐れ気味に、母親に「もう帰りたい」と告げ口をした。
その瞬間、バレー部の後輩の女の子が泣きながら私の元にやってきて、
「ひろ先輩、ボタンください!」
私は嬉しかった。
待ってましたとばかりに、
ボタンをひきちぎり、
その子にあげた。
私は誇らしかった。
その後、何人かの後輩がやってきて、私の制服からもボタンが無くなった。
それは、
「私(のボタン)に価値がある」
と、私の制服が物語っているようだった。
私はその制服を見せびらかすかのように、
その後もその場に滞在した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
