
学会活動から、創価活動へ 〜師の旅立ちと共に〜
2023年11月18日、同15日に池田先生が亡くなられたと、公式に発表された。
第一報に触れたのは、仕事の合間に、なんとなく開いたスマホの画面。
「知ってるかもですが
私は今知ったので
15日に池田先生お亡くなりになられたそうです」
末尾には、合掌する手とキラキラの絵文字がついていた、ある女性部員からのLINE。
こういう形で師の訃報に接するとは想定外であったが、人生とはそういうものかもしれない。
ちょうど、池田先生が亡くなられた(とされる)日に私は、地元に住む関西女性部幹部と面会していた。
創価学会の「変化」を示唆的に語る私とは、意識して距離を置いておられた。私も相手の心情を慮り静観していた。
その方が、わざわざ訪ねてきてくださったのだ。
「近頃の学会や公明党について部員さんから聞かれても、答えに窮することが多くなってきた」とつぶやいておられた。
それを受け、私は「先生はもういない」という話をした。
この関西女性部幹部、律儀にアレ用のアレを7回されている。何度か、大変な副反応に苦しまれたようだが、7回もやればそうなるだろう。
ご一緒されていたご主人は、3回目か4回目で胆嚢を劇的に悪くされた。その後、心臓まで悪くされて長期入院。退院された今も、健康とは程遠い状態だ。
もともと矍鑠(かくしゃく)とされていた人物で、老いて(といっても70代だが)なお盛んという方だった。時期が偶然重なって、内臓を患われたのかもしれない。
アレ用のアレとの因果関係は知らないし、それぞれが自分で考えれば良いことだ。
ご夫妻は、それでも公明党を支援し続け、アレ用のアレをこれからも続けるそうだ。これも一種の「死身弘法」なのかもしれない。私は、思考停止して自分の身体を傷めつけることを、そうは思わない。
が、それも、それぞれが自分で「価値創造」すればいい。
関西女性部幹部との話を要約すると、こうだ。
「池田先生は、もういない。
だから、自分たちで価値創造しなければならない。
池田先生は自由に価値創造して学会を教導してくださった。
『創価』とは、『価値を創造する』ことであって、『創造された価値を踏襲する』ことではない。
これからは『学会活動』より『創価活動』が大切である。
学会員より、『創価員』を増やす活動が大切ではないか。」
「私もそう思うわ。
でもね、それはあなたたちの時代。
私たちは、もう変えられないの」
つまり、引っ込みがつかないということか。
それとも、考えを変えるのが億劫なのか。
あるいは思考停止してしまって脳が拒否しているのか。
その全部なのか。
別に構わない。
自分の使命は、自分で自覚するものだ。
そういう人もいる。
家族の命より大切にしていい活動など無い。
これは(師から教わった)私の価値観だ。
家族の命を犠牲にして良い推進など無い。
これも(師から教わった)私の価値観だ。
価値観(正しさ)は時代と共にありようを変える。
いっぽう、人が考えを変えることは難しい。
なぜなら、面倒くさいからだ。
面倒くさいことについて、人は誰も、何が何でも忌避しようとする。
面倒くささを避けるためなら、手段を選ばない。
詭弁を弄し、約束をやぶり、体調を悪くすらしてしまう。
家族や自分の命も顧みず、考えと行動習慣を変えないことだけに腐心する。
そして「自分しか納得できない理由づけ」を、さも「正当な物である」と信じ込んで疑えない。疑わないのではない。疑えないのだ。
面倒くさいことに挑戦するときは、もっと面倒くさいことを避けるときだけだ。
頭では「もっと面倒くさくなる」と分かっていても、それがマジでリアルに出来(しゅったい)するギリギリまで、人は動かない。
価値創造とは、
面倒くさいことをスムーズにすること。
面倒くさいことをお得にすること。
面倒くさいことを歓喜(よろこび)に変えること。
これ以外に無い。
つまり「何のため」を突き詰めることだ。
池田先生は、これの達人だった。
ここから先は
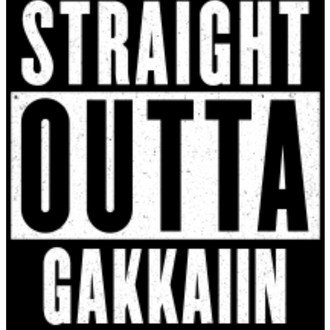
歓喜を取り戻す創価学会論 ストレイト・アウタ・学会員
学会活動が、おもんなくなった(異和を感じた)人が、学会活動をおもろくしていくための本。有料だけど、無料部分だけ読んでも学会員には有益と自負…
なにぶん、いい加減なことは書けないテーマゆえ、記事を書くための取材、調査、また構想から執筆、編集までかなりお金と時間と労力をかけております。 サポート、記事、マガジンの購入は本当に助かります。いただいたお志で、更に精度の高い文体を提供できます。本当にありがとうございます。
