
再び狂犬病予防を考える③:色んな矛盾…
前回まで2回にわたり、犬を海外から日本に連れてくる場合の検疫についてご紹介しました。基本的には、以下の3つの条件を満たすとすぐに一緒にお家に帰れます:
1)狂犬病ワクチンを2回以上接種
2)抗体検査で基準値を満たしていることを確認
3)その抗体検査から180日が経過
今回ウクライナから来たワンコは、「3」に当てはまらないのに検疫施設の外に出ることが認められたため、「狂犬病のリスクが上がる」と反対する声があるようです。農林水産省(農水省)は、この処置が「特例ではない」ことと、「狂犬病のリスクは上がらない」ことを強調しています。日本獣医師会も、農水省の主張をサポートしています。
色々、いろいろ、イロイロ、政治的な力が働いているようなので、この議論は現状の整理にとどめます。農水省と獣医師会、それから"何とか犬保存会"の役員(兼、国会議員)…。
科学的根拠との矛盾
今回は、抗体価と免疫による発症防止、潜伏期間、暴露後のワクチン接種といった予防の本質部分を整理します。ワクチンのところでもご紹介しましたが、狂犬病対策には不可思議に感じる点があります。
農水省の考え方からすれば、私は狂犬病で死んでたかも…
犬の免疫は「暴露後予防」に反応しない?
疑問①-1:ウイルス感染への対処が違う?
これまでご紹介したように、検疫制度(農水省管轄)では180日間の隔離が強く求められます。潜伏期間を考慮してのことです。
…待機期間をおく理由は、予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するためであり、潜伏期間に相当する180日間を待機期間としました。(海外から日本への犬、猫の持ち込みについて)
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/qanda/dogcata.html#5
狂犬病の場合、人間も犬も発症前にウイルスに感染しているかどうかの確定診断はできないそうです。したがって、海外から来た犬が、ワクチンを打つ前にウイルスをもらっている可能性はゼロではありません。潜伏期間を考慮して、発症しないかどうかを確認するのに180日は必要というのが根拠とされています。
でも、この論理だと「ウイルスが体に入ってしまえば、症状が出る前にワクチンを打っても、発症は防げない」ということになります。これ、日本を含む世界中で行われていることと矛盾します。人間のケースではありますが…。
狂犬病ウイルスに感染しても、発症前、つまり、症状が出ちゃう前にワクチンを打てば狂犬病は防止できることが知られています。「暴露後予防(PEP: Post-exposure prophylaxis)」は世界中で行われています。狂犬病の恐れがある犬に咬まれた場合:
1)狂犬病のワクチンを接種
2)日数を空けて、さらに数回接種
3)抗体検査で抗体価を確認 => 基準値を満たせばOK
これ、実体験です。20年近く前ですが、ベトナムを貧乏旅行中、犬に咬まれました。帰国後に保健所に相談し、がん・感染症センター東京都立駒込病院で専門のお医者さんに対処して頂きました。

おかげさまで、今でも元気に生きています。180日間、ビクビクしながら暮らした記憶もありません。確か先生からは、「今、発症していない状態で、これだけ抗体があれば心配いりません」と言って頂きました。
で、今回ウクライナから来たワンコが仮に狂犬病ウイルスをもっていたとしても、発症はしないのではないでしょうか?ワクチン接種後に抗体価の確認が済んでいます。犬の場合は違うのでしょうか?
疑問①-2:厚労省と農水省の見解が矛盾?
約20年前のこととはいえ、自分の狂犬病について不安になりました。まだ潜伏期間?
私は一応人間なので、農水省ではなく厚生労働省(厚労省)のウェブサイトで調べてみました:

…連続したワクチンを接種(暴露後ワクチン接種)をすることで発症を抑えることができます(原文ママ;強調は筆者)
「国立陸軍病院」を起源とし、戦後は厚生省(当時)の管轄下で国立東京第一病院として運営された、「国立国際医療研究センター病院」(現在)も同じスタンスです。
良かった ^_^
だとすると、犬も発症前にワクチン接種を受ければ、万が一ウイルスに感染していても狂犬病の発症は免れるのでははないでしょうか???

犬と人間では、狂犬病ウイルスへの暴露後ワクチン接種による効果に免疫システム上の違いがあるのかもしれません。農水省(と厚労省)に確認して、またご紹介したいと思います(これが1つめの疑問)
疑問②:潜伏期間は10日?数ヶ月?180日?
さらに、暴露後のワクチン接種については、こうも明記されています:
咬んだ動物が10日間の観察期間後も健康である場合、適切な検査による評価で感染がないことが証明された場合には治療を中止する。
この内容は、WHO(世界保健機構)の「WHO Expert Consultation on Rabies」の内容を日本語に訳して作成されたものです。
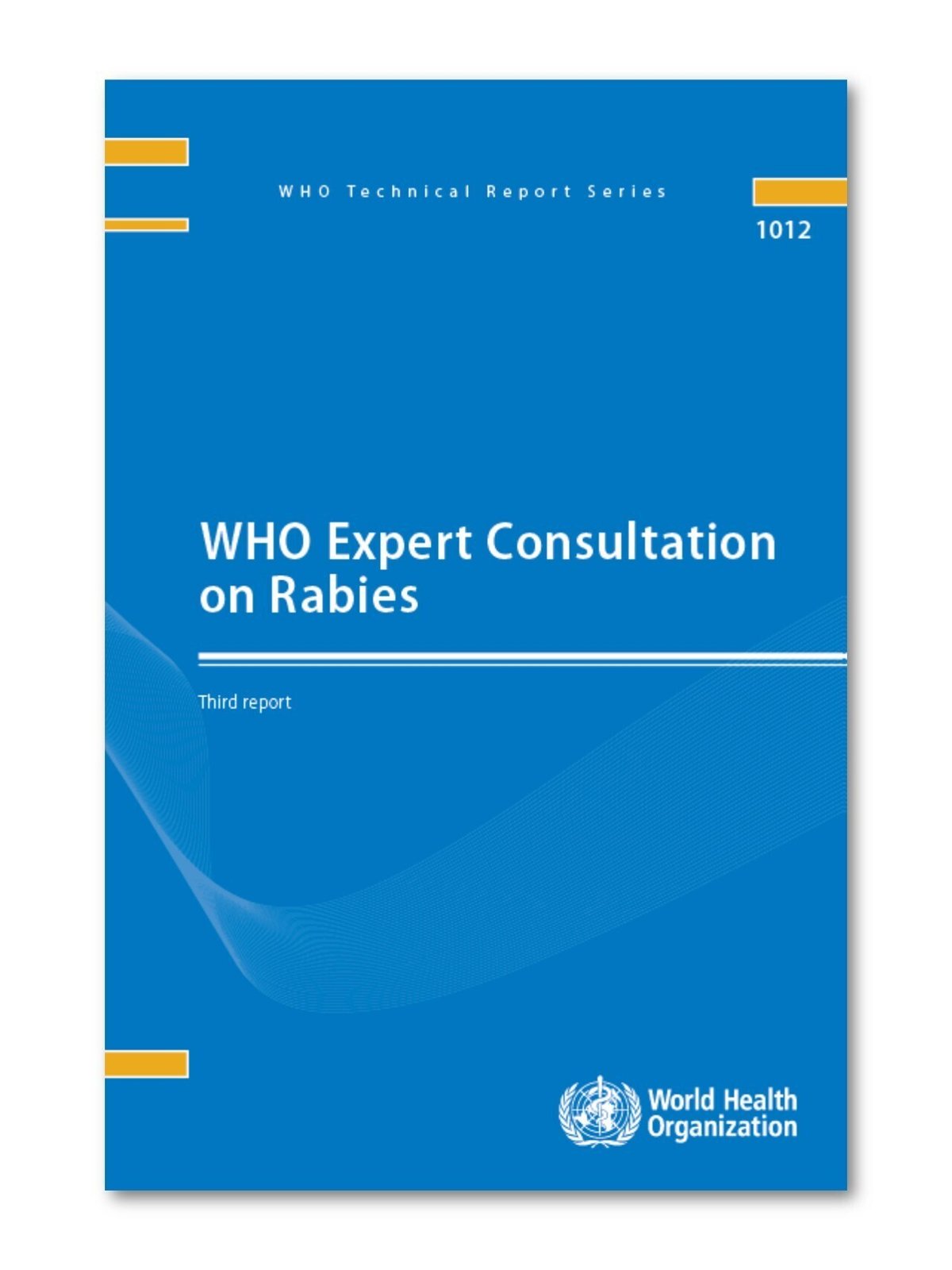
したがって、世界的な統一基準と言えます。要は、
狂犬病ウイルスをもっているかも知れない犬に咬まれた人は:
1.複数回の「暴露後ワクチン接種」をしましょう
2.それで、発症を防ぎます
3.咬んだ犬を捕獲できた場合、10日間観察しましょう。その犬が狂犬病を発症しなければ、それ以降はワクチン接種不要(≒その犬は狂犬病に感染していないでしょう)
ということです。詳細な条件が分からないので厳密な比較はできませんが、農水省が言う潜伏期間が(最大)180日。国立国際医療研究センター病院、厚労省とWHOの資料にあるのは、10日経って犬が発症しなかったら咬まれた人は治療をやめても大丈夫…。
これ、農水省(と厚労省)に聞こうと思います。
ちなみに、イギリスは日本の180日(6ヶ月)にあたる期間が、3か月とされています。("Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain")
また、WHOの文書で潜伏期間を調べてみると、
潜伏期間は5日~数年の幅がある(通常2~3か月で、稀に1年を超える)。ウイルスの量、咬まれた場所にある神経筋接合部(神経が筋肉につながる場所)の密度や咬まれた場所の中枢神経系からの距離によって異なる(筆者訳)
The incubation period varies from 5 days to several years (usually 2–3 months; rarely more than 1 year), depending on the amount of virus in the inoculum, the density of motor endplates at the wound site and the proximity of virus entry to the central nervous system(WHOの英文)
これは人間のケースですが、犬よりも遥かに体が大きくても、通常は数ヶ月とのことです。これもイギリスの資料では、犬も人間もほとんどが数週間から12週間だとしています。
潜伏期間は非常に幅があるが、犬と猫では一般的に感染から2週間~12週間と考えられている…。人間の場合は、1週間に満たない場合や1年を超えるなどの幅もあり得るが、典型的なケースでは3~12週間である。
The incubation period can vary considerably but for dogs and cats it is generally considered to be between two and twelve weeks postinfection…
In human cases, the incubation period is typically three to twelve weeks, but may vary from less than a week to more than a year.
もちろん、この病気の場合、念には念を入れることは大切です。とはいえ、農水省が想定する180日とは大きな乖離があります。以前もご紹介したように、180日に関しては科学的根拠も見つけられていません。
これも、農水省(と厚労省)に聞いてみたいと思います(これが2つめの疑問)
「専門家」の見解
4月22日には、NHKがこの件を取り上げました。ウェブサイトにも記事が掲載されています。「ウクライナ避難犬めぐり…日本が65年前に撲滅した狂犬病とは?」という番組/記事の中で、大分大学医学部微生物学講座の西園晃教授に聞いています。

西園教授は、狂犬病の発生が多いフィリピンで早期発見と予防の支援を実際に行っている専門家だそうです。
NHK:現在、動物検疫で行われている180日の隔離期間は妥当?
西園教授:「現在の法律(筆者注:狂犬病予防法を指していると思います)は70年以上前にできた法律で、当時は血液による抗体検査のしくみもない時代でした。検査でウイルスに対する抗体が十分あることなどが確認できれば、180日という検疫期間も短くすることが可能なのではないでしょうか。」
このコメントが、個人的には一番理解できるような気がします。でも、私は医学者でも獣医学者でも疫学の研究者でもありません。信頼に足るような「専門家」の方々を見つけて、引き続き、この摩訶不思議な狂犬病、というよりも狂犬病関連の制度について謙虚に勉強していこうと思います。
より効果的で安全な狂犬病予防
発症すればほぼ100%死に至る感染症を予防することには何の異論もありません。ただ、狂犬病予防法は、基本的には70年以上も前につくられた法律です。検疫に関連する各種の法律や制度も、おおむね、同法に基づいています。今のままで、本当に人やコミュニティーの防御は万全なんでしょうか?
国際獣疫事務局(OIE;人間の病気を扱うWHOに対して動物の感染症を扱う世界的な組織)は違うことを言っています。
犬用のワクチン接種ばかりを強調しても,接種率は不十分な水準にとどまり,また,免疫付与効果も100%でない以上,野生動物狂犬病の発生リスクは否定できない。(原文ママ;強調は筆者)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jve/17/2/17_132/_pdf
3回にわたって考えたことのまとめ:
・抗体検査でノンレスポンダーを見つけなくて大丈夫?
・抗体があるのに、毎年自動的に再接種する必要ある?副反応のリスクを冒してまで…
・犬だけで大丈夫?野生動物や野生化した哺乳類、特に接触機会の多い猫への接種は不要なのか?場所によってはアライグマなども…
みなさんは、どう思いますか?
