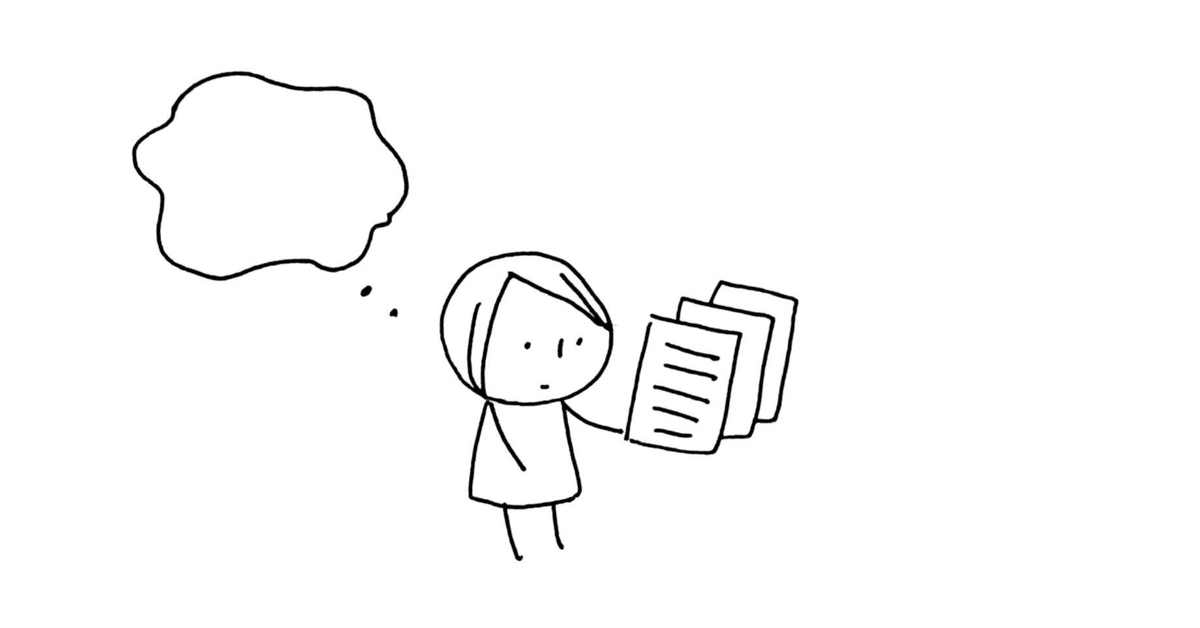
日記5-疑うこと。考え続けること。
どうも、陽毬(ひまり)です。
今日は自省の意味も込めて、情報の信憑性について書くことにしました。
情報に溢れるこの世界、何を求められる
ネット上にはさまざまな情報が流れている。
しかし、どの情報は信頼に値するものなのかについて考えたことあるか?
誰でも簡単に情報発信ができる時代になったことにより、自分が持っている知識を多くの人に伝えることができるようになった。
しかしその一方、他人から間違った情報が入ってくる可能性も高くなっている。
また逆も然り、自分が正しいと思い込んだ知識を他人に伝えてしまうこともある。
間違った情報と正しい情報が混じり合うこの世の中で、何を信じれば良いのか。
Twitterでバズったツイートに間違った情報が含まれる場合に、たまに良知がある人が声をあげて誤解を解こうとしてくれる。
とてもありがたい。
しかしTwitterを出れば、間違っていることをわざわざ教えてくれる人がいない。
自分で判断しなければ、間違った知識をそのまま使ってしまい何かしらの不利益を被ることになる。
いつまでも他人に頼りっきりでは、一人で判断を求められる時に、キッパリと決断をし、さらに自分の決断に責任を持つ能力の低下にもつながる恐れがある。
目に入った情報をすべて真に受けるのは非常に楽である。
また、怪しいと思いながら、知らぬふりをして信じたいものを信じることも非常に楽である。
しかし、それは果たして賢い行為と言えるのか?
そう自分に問いかけてみると、自ずと答えが見えてくるはずである。
疑い、考えること
では、どう情報の信憑性を確認すれば良いのか。
一番わかりやすい方法は、情報源を確認することである。
知識を伝える記事には、必ず根拠というものが存在する。
その根拠が書かれていなければ、記事の信憑性がグッと減る。
なぜならば、どこの誰がそういったことを言ったのかすら分からないのだから、極端に言えば目を引くために書き手がそれっぽいことを適当に書いているだけかもしれない。
もちろん正確に書くように気をつけながら書く人がたくさんいると思うが、そうではない人も必ず混ざっているので、読み手としては決して油断してはいけない。
一方、情報源がはっきりと書かれている記事であれば、通常的に比較的にまともである。
しかし、本当に信じて良いのかを判断するために、さらに情報源はどこなのかを確認することも重要である。
サイトから引用した情報や出版した書籍であれば、信憑性がある程度確保されている。
また、影響力がややあるジャーナルに載っている論文が参考文献になっていたら、より信憑性が高い。
(ただ論文は解釈が難しく、論文を参照しているとはいえ、書き手の解釈によっては必ずしも誤解が生じないわけでもなく…それはまた悩ましいところである。)
情報源を確認することは手間がかかるうえ、確認したからって結局その情報は信じていいのかを判断することが難しい。
それでも、確認する習慣を身につけて、常に疑い続け、考え続けることが大切だと思う。
自分が発信する内容に責任を持つ意識
先ほどは読み手として情報の信憑性を自分で判断することの重要性について書いた。
一方で、書き手として情報を伝える際にも、読み手を意識しながら発信する内容に責任を持つ必要があると思う。
自分が書いたものを裏付ける根拠があるのかくらいはしっかり確認しておいてほしい。そして、使用した参考文献もぜひ載せて欲しい。
言いたいことだけ言ってずらかります。
今日も読んでくれてありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
