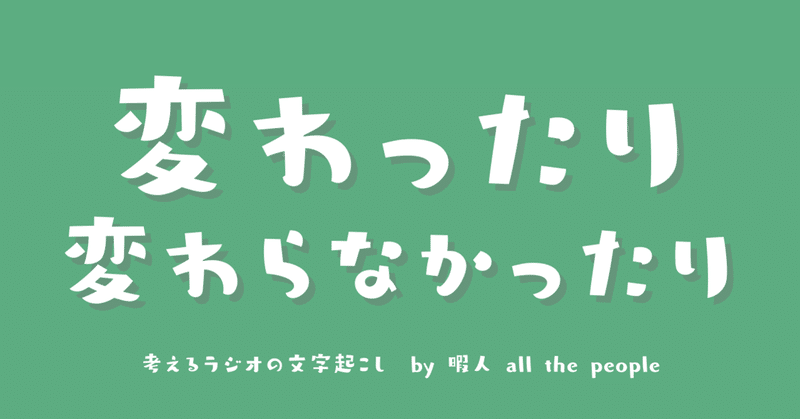
#17 夏休みの宿題のやり方は大人になってからの仕事のやり方と一緒説
こんにちは。暇人 all the peopleの考えるラジオです。
今日も考えていきます。
お便りを紹介します。
Q. 子どもから大人になると見た目も性格も変わりますが、根本的な性格みたいなところは変わらないんじゃないかと思います。どうでしょうか。
なるほどね、僕もそう思いますね。生まれた時から決まってる遺伝的な、先天的な要素が半分、生まれてから決まる後天的な要素が半分だと思うので、子供の頃から変わらない部分は全然あるんじゃないですかね。あの特にね、小学校の夏休みの宿題のやり方って、大人になっっての仕事のやり方にそのまま出てる人多いと思うんですよ。
夏休み入った瞬間に終わらせる子、ちょっとずつ計画的に進める子、最終日に泣きながらやる子。偏見ですけど、考えるラジオのリスナーは最終日ギリギリにやってた人が多いと思います。完全に偏見ですけどね。
ちなみに僕は、そもそも宿題をやる意味があるのかと疑って、どうにかやらない方法を探すタイプの子どもでした。宿題も期限ギリギリにやると直じゃなくて、出さなくても済まされる関係性を先生と築くことに力を注いでました。でも関係性だけじゃ逃げられない宿題もあってね、読書感想文とか。そういうのはいかに楽をするか考えて、小学校3年生の夏休みに読書感想文書くために読んだきつね山の夏休みっていう本があるんですけど、それ1冊で小学校卒業まで行きました。3年生の夏休みに1回だけ読んだ本を、残りの3年間記憶を頼りに書くっていう。
担任の先生は毎年変わりますから、僕が去年の夏休みに何の本を読んだかなんて知らないじゃないですか。仮に知ってたとしても、この本めっちゃ好きなんですって言えば乗り切れると思ってたんでね。でも1回だけ読んだ本の内容を3年間も覚えてるわけないんですよ。だからもう6年生の時とかは、勘で読書感想文を書いてましたね。きつね山の夏休みっていうタイトルだけ合ってて、主人公の名前もストーリーも全部違う。全然違う架空の物語を頭の中で作りながらそれに対する読書感想文を書くっていう。それもう普通に本1冊読んで書いた方が楽じゃんっていうね。
夏休みの宿題のやり方って、締め切りが決まってる長期的な問題に直面した時の反応というか、やらなきゃいけないとされることへの態度ですよね。やっぱり小学生ってまだ色んなものに影響を受ける前の段階だと思うので、けっこうその人の本質的な反応が出ると思ってるんですよね。
だから夏休み終わるギリギリに宿題やってた人って大人になっても今も締切に追われてたり、計画的にやってた人は今も計画的に仕事してたり。まぁね、なんの根拠もない、自分と自分の周りの人を見ててそう思うなってぐらいの話でね。
みなさんどうでしょう。
昔の自分と今の自分、問題に対する同じ反応するんでしょうかね。
易不易なんて言葉もありますけどね、易というのは変わること、不易というのは変わらないこと。変わるところと変わらないところが両方あってこその自然だと思いますから、僕らも自然の一部ということで、変わったり変わらなかったりしていきましょう。
ということで今日はここまで。
最後まで聴いていただいてありがとうございました。
暇人 all the peopleの考えるラジオでした。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
