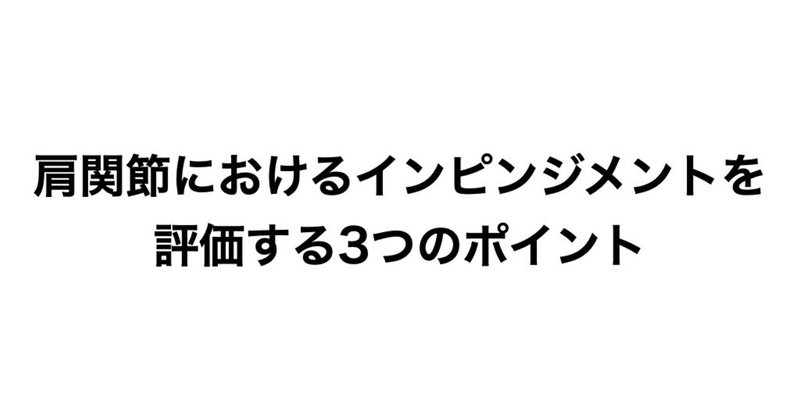
肩関節におけるインピンジメントを評価する3つのポイント
リハ塾の松井です!
肩の挙上時に疼痛の訴えがある時、「これは骨と筋肉(腱)がぶつかって痛いんですよ。」とか説明したことありませんか?
いわゆるインピンジメントですが、何でインピンジメントするのか、どう介入していくのか説明できますか?
僕はできませんでした。
インピンジメントで痛いんだなーとは何となく分かっても、実際は介入してもあんまり変わらないし、結局何をしていいか分からなくなっていました。
僕と同じような経験をしている方ってきっといると思うので、今日は肩関節のインピンジメントに焦点を当て、インピンジメントをどう考えるか、どう介入するかを解説します!
インピンジメントは大きく2つあります。
肩峰下インピンジメント
Neerによると、肩関節挙上時に肩峰と烏口肩峰靭帯からなる烏口肩峰アーチと、その下を滑走する腱板と肩峰下滑液包床との間に生じる衝突現象の総称であるとされています(参考文献①)。
インピンジメントが起こる要因として、外科的な治療が必要な場合と保存的な治療がメインとなる場合に分かれます。
前者は肩峰の形態変化や骨棘によるもの、後者の要因としては以下の通り。
・腱板、滑液包の腫脹
・腱板筋群の機能不全
・関節拘縮
・肩甲骨位置異常
・上腕骨、鎖骨の位置異常
理学療法の適応となるのは、この後者の問題ですね。
これらが複合的に組み合わさった結果、インピンジメントを引き起こし、腱板や滑液包、靭帯の侵害受容器を刺激し、痛みが出現するという流れです。
関節内インピンジメント
腱板が上腕骨頭と関節唇に挟み込まれる現象を指し、肩関節外旋・外転位で挟み込まれます。
投球動作における肩関節最終外旋・外転時に起こることが多く、比較的若年層に発症する場合が多いです。
こちらは、肩甲骨や胸椎、胸郭の可動性低下、もしくは筋力低下による最終域での上腕骨と肩甲骨との適合性の悪さが引き起こします。
インピンジメントを評価するポイントは以下の3つ。
・肩関節外転
・水平外転
・肩甲骨面挙上90°での内旋
この肢位が肩峰下での接触圧が特に高まるため、この肢位における疼痛の有無が一つのポイントになります(参考文献②)。
それを踏まえて、評価のポイントとしては以下の通り。
・接触圧上昇肢位で、肩甲骨操作して痛みが減る方向を探る
・接触圧上昇肢位で、伸張されている筋はないか、また、徒手的に縮めると変化があるか
・接触圧上昇肢位で、緊張している筋はないか、また、徒手的に伸張すると変化があるか
対象者によって、痛みが出る方向は変わるはずですが、痛みが出る肢位にて上記の評価ポイントを参考に操作してみてください。
また、外転、水平外転、肩甲骨面挙上90°での内旋以外の肢位で痛い場合も同様です。
もし、痛みに変化が見られる誘導方向があれば、それが何らかの影響を与えている可能性が高いので、痛みがあればそこへアプローチしていくという流れです。
経験的に多いのは、棘下筋、小円筋、大円筋、肩甲下筋、広背筋といった筋群です。
参考文献
1. Neer, C.S.II.: Anterior Acromioplasty for the Chronic Impingement Syndrome in the Shoulder. J Bone Joint Surg Am 54-A (1): 41-50, 1972.
2.Muraki T, Yamamoto N, et al.: Effects of posterior capsule tightness on subacromial contact behavior during shoulder motions. J Shoulder Elbow Surg 2012; 21(9): 1160-1167.
ご質問はLINE@までどうぞ!
登録者900人越えのLINE@で週2~3回専門的な情報を発信しています!
ご質問も随時受け付けていますので、ご登録お願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

