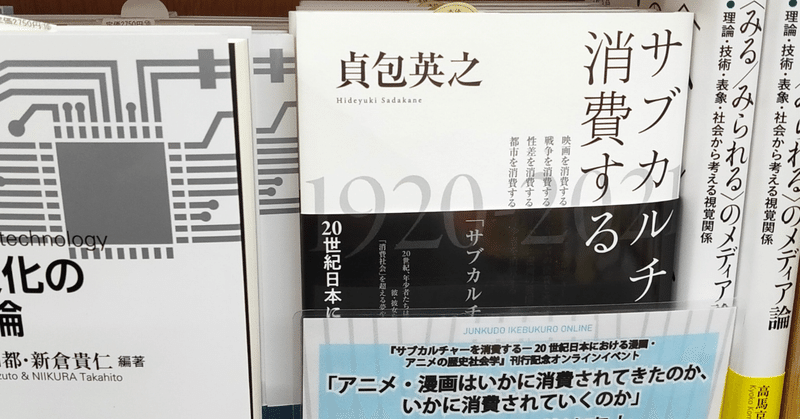
『サブカルチャーを消費する』に書いたこと
はじめに
2021年に『サブカルチャーを消費する:20世紀日本における漫画・アニメの歴史社会学』という本を書きました。人の評価はわかりませんが、個人的には、少なくとも挑戦的な本だと思っております。
おそらく誰も書いてくれそうにありませんので、少々不格好ですが、著者としてはここは頑張ったということをまとめておきたいと思います。
本書では多くのミッキーマウス映画や、戦記漫画や戦争にかんするアニメーション、バレエ漫画などの作品を取り扱っています。しかしその内容を解釈することは、かならずしもむずかしいことではありません。より困難だったのは、いかなる水準からそれを扱うかさまざまな角度から調整し、それを実現するために、これまでにないデータを分析することです。
いくつかの部分ではよくやれたのではないかと考えています。あくまで筆者の視点からですが、本書にとくに価値があるのではないかと思う部分についてここでは書いておきたいと思います。
① 1930年代の映画状況を実証的にあきらかにしたこと。
『サブカルチャーを消費する:20世紀日本における漫画・アニメの歴史社会学』第一章では、1920年代後半から年少者がいかに通常の活動写真、映画から排除され、アニメーション映画に囲い込まれていったのかを分析しています。
その際におもに利用したのが 『活動写真「フィルム」検閲年報』、『映画検閲年報』、『映画検閲時報』などの戦前の統計報告や、検閲史料です。これらの史料は、よく知られているように、戦前の映画の状況についてかなり精緻に記録されています。にもかかわらず、史料を主題的に分析する論考は、管見ではあまりないのではないかと思われます。
ひとつには、私も指摘しています通り、これらの記録がどのように作成され、どこまで正しいのかいまいち不確かなためかもしれません。とはいえ戦前の映画、あるいはそもそも映画を中心とした娯楽文化に関してあきらかにする上で、とても豊穣な史料であることにまちがいないと思います。
『サブカルチャーを消費する』では、年少者がいかに映画館から追い出されていったのか、またミッキー・マウスシリーズを中心としたディズニー映画が戦前にどれほど公開されていたのか――資料からわかるのは検閲状況ですが――を探るためにこれらの史料をひたすら調べましたが、そうした視点以外にもまだまだあきらかにできることは多そうです。
今後はそれを誰かにやっていただければと思いますし、機会があれば、共同研究もできそうな気がします。問題は史料が膨大すぎることですが、今後デジタル化が進めば、戦前の映画状況について、記述的な方法と組み合わせ、より立体的にあきらかにできるのではないかと思います。
いずれにしろ本書はこうした統計的研究に先鞭をつけたのでは、という思いがあります。
② 年少者のこづかい状況について、大(または中)規模の調査によってあきらかににしたこと。
『サブカルチャーを消費する』では、年少者が「消費社会」にいかに参加していったのかをあきらかにするために、そのこづかい状況について注目しています。働く場から徐々に遠ざけられていった年少者にとって、年長者からどれほどのお金を、いかなる仕方で貰うのかが、時がたつにつれ、より大きな問題になっていくためです。
そのため『サブカルチャーを消費する』では、4500人以上の人びとにアンケートをおこない、こづかいをどのように、いかに貰ったかについて検討しています。
それを使って、日本の漫画やアニメなどのサブカルチャーが、年少者が親から比較的自由に使える金を定期的に貰うようになることを前提に開花したことを本書は確かめました。その詳しい分析は、本文に譲りますが、いずれにしろ重要だと思うことは、こうした調査が今までなかったこと、そして少なくとも戦前にかぎれば、これからは同様な調査はむずかしいだろうということです。
予備的な調査を含めれば、本書の調査はすでに5,6年前からスタートしています。その過程でも、年齢的な問題から、戦前に関してはますます調査が難しくなっていきました。本書でも、ぎりぎり1930年代なかば以降のこづかい状況はあきらかにできましたが、それ以前は文献に頼るしかなかったのです。
もちろん本書の調査は、それほどネット調査が一般化する前にそれを利用したもので、設計の不備もあり、そもそもランダム性にかけているという意味で、厳密な過去の状況を映すものではありません。せいぜい階層的な生存バイアスの大きい、一断面でしかないというべきでしょう。ただ実体験を証言できる人びとがどんどん消えていく中では、不備はあっても、とにかくデータを収集することが重要だと感じられたのです。
その意味では、解釈の是非はともあれ、本書の調査に一定の価値は残ると自負しています。今後、より周到な調査をしてくださる人もいるかもしれません。また実体験を裏打ちするために、本書ではおもに国会図書館検索を利用しつつ、多くの言説を拾っていますが、これもデジタル化がますます進めば、新資料が出ることもあるのではないかと思います。
ただし時間との戦いのなかで、そうしなければ埋もれてしまっただろう記録について本書はあきらかにすることができたと自負しています。それによって、サブカルチャーの少なくとも1つの起源について確かめることができたのです。
③ 人流調査を用い、都市とサブカルチャーの関係についてあきらかにしたこと。
時代は流れ、本書の4章では、消費社会化が深く浸透していくおもにバブル期以後のなかで、サブカルチャーが、都市の文化としていかに根付いていくのかを検討しています。
それは一方で、年収者向けのサブカルチャーが年長者に「密猟」(ヘンリー・ジェイキンス)されていく流れに並行したもので、そのはてに、たとえば秋葉原という街は、90年代後半からいかにマニア化し、その過程で、男性のそして年長者の集まる街になります。自然な過程というより、行政の介入によってそうなったのですが、いずれにしろこうした街の変化を、NTTドコモのGPSデータを利用してあきらかにしたことは、本書のひとつの売りになっています。
もちろんコロナ禍の中で人流は大きな注目を集め、GPSデータの利用も日常的におこなわれるようになりました。その意味で本書の分析には現実に追い越された部分があります。それでも重要になるのは、人流のデータそのものというよりも、それをいかなる歴史の流れの中に位置づけるかです。
『サブカルチャーを消費する』では、人流があきらかにする秋葉原の成長を、東京という都市が高齢化し、デフレに巻き込まれ、少なくとも最新のモードの場としては脱落していくという大きな歴史過程を背景に分析しました。そうした都市の変化のなかで、安価かつ次々と新しいものが送り出されるかつての年少者向けのサブカルチャーが、年長者向けのものとして「密猟」されていったのです。
日本の都市の現在をいかなるものとして捉えるかについては、21世紀に入って以降は、なお十分に説得的な見方は生まれていないと私は思います。バブルの時代前後に郊外化やそれに応じた渋谷や新宿の発展がさかんに議論されてきましたが、それ以降、東京がどうなったかについては、大局的にうまく論じられていないと思われるのです。
それをあきらかにすることに、ひとつには人流といったデータをもとに、本書は挑戦しています。簡単にいえば、少子化と高齢化、そしてデフレ下のなかで、都市的なるものの場は大きく後退していくと、本書は主張しました。その簡略かつ図式的な見方としては、韓国語ですが、拙稿「都市の冷却:東京において平成とは何だったのか?」を参照してください。
④ 日本のサブカルチャーとは何かについて考えたこと
最後に、これは個々のデータにかんしてではなくて、全体の話ですが、日本の漫画やアニメーションを中心とするサブカルチャーとは何かについて、長期的な視点から考えたことは、本書の他にない特徴です。
本文でも述べていますが、サブカルチャーの「起源」についてはこれまで、①戦前の赤本、アニメーション映画文化や、②戦後すぐの手塚治虫を中心とした革新、さらに③高度成長期の週刊誌文化やTVアニメーション文化の出現の3つの視点からおもに考えられてきました。
「消費」されるものとしてサブカルチャーをみなす本書が注目するのは、そのうち、③の1950年代半ば以降を重視する視点です。その時代、こづかいの質や量の変化に伴い、年少者はかなり自由な消費主体として消費社会に参入していきます。それがそれまでなかなか難しかった「大衆文化」としてのアニメーションや漫画の流行を可能にしていったのです。
たとえば関連して注目されるのは、その時代に、男性向け、女性向けというジェンダーにサブカルチャー現象も分けられ、強く制度化されていくことです。本書はその例として、2章で戦記漫画の流行、3章でバレエ漫画の流行を分析しています。
この意味で、日本において漫画やアニメなどのサブカルチャーは、年少者が「消費社会」に次から次へと参入していくある種、特有の時代現象としてあったといえます。そのなかで、さまざまな多様なコンテンツが生まれ、ジェンダー的な区分も制度化されました。
重要になるのは、だからこそサブカルチャーが、大人たちが営み始めていた戦後的社会に対する反抗を核心的な内容としていったことです。結果として、サブカルチャーは戦後日本社会を否定し、それを乗り越える道を探る特有の内容をくりかえし語っていくことになります。その具体的な詳細はぜひ本書を参照してください。
ここで一つだけ言っておくべきことがあるとすれば、現代におけるサブカルチャーの変質も、この意味では必然的だということです。少子化は年少者の購買力集団としてプレザンスを下げます。その代わりにサブカルチャーは年長者に「密猟」されつつ、その内容も変質させているのです。
おわりに
以上、本書は、いくつかの新しいデータを使って、日本の漫画やアニメが特有の歴史的かつ社会的現象として、20世紀に発達し、成長していくことについて論じました。もうすこし言えば、日本の漫画やアニメは、「消費社会」化していく社会が、その際に周縁化された年少者を媒介として、現実に対抗する「幻像」として生み出されたと言えます。それ以上は、煩瑣になるので、ぜひ本書を読んでください。
このことは、「消費」を中心に、また100年という歴史的なスパンをとり分析していかなければ、みえなかったことだと思います。そしてそうだとすれば、人生の長い時間を消耗し、この本を書いた意味もあるということになるでしょう。
もちろん紙面の都合上、細かくは書けなかったことは多く、記述として不十分な所も多いと思われます。あの作品やこの作家を取り上げるべきという話は無限にあり、それはこれからの誰かに補っていただければ幸いです。
ただしそもそも本書は、サブカルチャーの歴史を書きたかったわけではありません。私が試みたのは、サブカルチャーの歴史をデータとして、サブカルチャーを消費しつづけてきたこの社会がいかなる場所なのかををあきらかにすることです。
その意味でこれはあくまで、わたしたちが生きてきた「歴史の現在」をあきらかにするひとつの社会学的試みとしてあり、少しだけ背伸びをさせていただければ、フーコー的な意味で「哲学」的試みでもありました。
それを、少しでも実現できたでしょうか。それは本を読んでくれた人、一人ひとりに判断していただければよいことですが、少なくとも私はそうであると思い、まただからこそこの本に一定の価値を認めてあげたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
