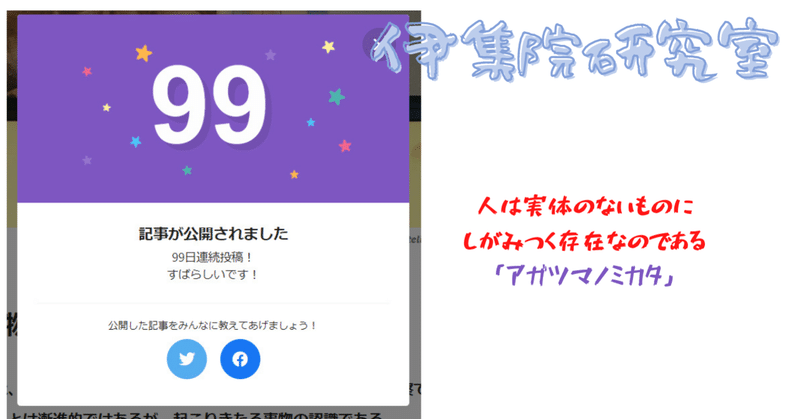
「苦悩」する「存在」って、一体どこにあるのですか?というお話。「意識を失うのは案外真理かも」
前回ちらっと出た話で、「苦」を思い悩むから苦悩ですが
その苦悩する存在って、何をもって存在といい、
悩むのは、なんであたし自身なの?って
いう素朴な疑問が生まれた人は、前回の単位認定ばっちりです。
自分という存在は5つの要素で構成される
ざっくりいうと、実は五つの要素でできており、
これをひっくるめて仏典では、「五蘊(ごおん)」と呼んでおります。
まず自分の肉体であるとか目に見える物体、
聞こえたり味わったり触れることで認識できる
言ってみれば「形あるものとか現象」です。
この肉体や実体のことを「色(しき)」と呼びます。
あたしたちは、これをもって
自分のすべてだとも思うんですが、
どっこいそれだけでは存在とは呼べません。
これらを見たり聞いたりする「事」がなくては
存在とはいえません。
で、この感覚のことを「受(じゅ)」といいます。
さらには、それが何であるか、
たとえば丸いとか四角とか、
堅いとか柔らかいとか
冷たい、熱いなどという認識がないと存在とはいえません。
で、このことを「想(そう)」といいます。
そして、それに反応する作用があります。
快と不快、痛いとか、
そういう反応のことです。
このことを「行(ぎょう)」といいます。
そして、喜怒哀楽のように
自分がどんな心の状態にいるのかを認識すること
これを「識(しき)」といい、
ぶっちゃけていえばどれがかけても
「人の存在」ではないと言われています。
人間の心身の活動全体のことであり、
たとえば死んだ人はこれらがなくなっちゃいますよね。
もの(色)に作用し、認識し、感じ,分別する集合体
蘊とは集まりを意味しています。
人はこれら五つの要素の集まりなんだという意味です。
実は、思うとおりにならない「苦」は、
この五蘊があるからだとブッダは言っておるんですな。
五蘊である存在が生み出す苦こそ
「煩悩」と呼ばれるものなのでございます。
「煩悩」を生み出す3要素
この煩悩の根源をさらに示すと、
三つの毒に突き当たります。
それは「貪(どん)」「瞋(しん)」「癡(ち)」の三つで、
それぞれ「むさぼり」「怒り」「無知」のことを言います。
人の心はこれらの三つに支配されやすいものです。
際限なくものをほしがったり、
また物惜しみして独り占めしたくなることが
よくございましょう。
今の世の中はこの心をうまく使い、
次々と流行を生み出して、
人々は爆買いなんかにも走りますよね。
スーパーのバーゲンとか安売りなんかもそう、
これらの物欲は限度を知らない。
こういう状態がまさしく「貪」なわけです。
で、当然だれもがみな
際限なくものをほしがると、
そこには当然不公平や奪い合いが始まります。
不平不満もこれに応じて、際限なく大きくなってきます。
当然ながら怒りの心が生まれます。
しかもそれは欲からきた、
まったく自己中な怒りでございますな。
それが「瞋」という状態。
まさしくケンカや戦争の原因でございます。
こういう事が愚かで無駄なことだと気づかず、
意固地になってやめられない。
というか、むしろ、そうすることが正しいとさえ思って、
破滅に向かって盲目的につきすすんでいる状況。
それが「癡」というわけでございます。
「五蘊である存在」はともすれば
こういう煩悩を生み出すのだと言うわけなんです。
これは実体がない(空)と気づき、
こだわりを無くしたら、
これらの苦や厄いをコントロール(度)できる、
と言っているわけなんですな。
それが、「照見五蘊皆空 度一切苦厄」という
般若心経にあるフレーズの意味なんでございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
