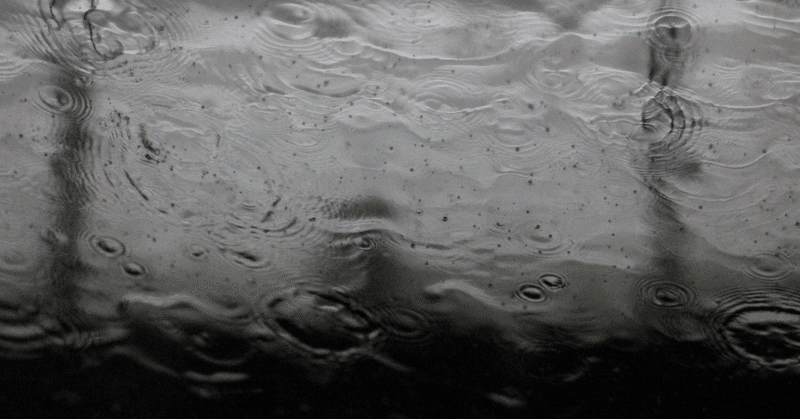
長編小説「きみがくれた」中‐⑭
「涙の底」
夜はどしゃ降りの雨になった。
ドアベルの音に顔を上げたマスターが「やぁ」と言う間もなく、冴子の第一声はやはり「央人は?」だった。
両手に白い包みを抱えた冴子は濡れた服にも構わずマスターに詰め寄り、いきなり不平不満をぶつけ始めた。
「央人のアパートのカギがなかったの、央人帰って来てるの?」
息を荒げて問い質す冴子に、マスターは素直に謝った。
「ごめん、カギは僕が持ってるんだ」
「なにそれどういうこと?央人は?帰ってないの?」
「うん、冴子ちゃんに話していなくて悪かったね」
「信じらんない、私すっごく心配したのよ?いつもの隠し場所にないからもしかしたら央人が帰って来たのかと思って、でも部屋のドアは鍵がかかったままだし、泥棒にでも入られたんじゃないかと思ってカギを変えなきゃいけないかもって、私がいない間に誰か入っちゃうかもしれないって不安ですっごく心配したのよ、何で言ってくれなかったの?央人がここにいるかもしれないと思って飛んできたのよ、――言っておいてくれたらそんなこと考えないで済んだのに!なんで言ってくれなかったのよ!酷いじゃない!!」
冴子は“情緒不安定”だった。
だから気を付けて、――亮介からそう話を聞いていたマスターは、次第に昂っていく冴子に対していつもよりいっそう丁寧に、冷静に応じていた。
「本当に、心配をかけて申し訳なかった。冴子ちゃんには一番最初に話をしておくべきだったよ。」
そう言って静かに頭を下げるマスターに、冴子の怒りは行き先を見失った。
「アパートのカギを、僕が預かっていたのは、夏目君に頼まれたからなんだ。」
「‥え?」
「サプライズだから、って、万が一央人がアパートへ入ってしまわないように、カギをかけて置いて欲しいって‥僕は夏目君から言われていたんだ。」
「サプライズ―――?」
「だいぶ前に夏目君から荷物が届いていてね。それが央人への誕生日プレゼントだったようで‥僕にアパートの冷蔵庫へ入れておいてくれって、そう言われていたんだ。」
「荷物‥って――?」
“そんなことよりマスター聞いてよ”
“僕ね、すっごいの見つけちゃったんだ”
「―――うん‥」
“あのねマスターにお願いがあるんだ”
“これほんとにすごいから”
“超ウルトラハイパーサプライズ間違いなしだからね”
暗いガラスに打ち付ける雨音が、さっきよりもずっと強く大きくなっていた。
流れ落ちていく雫に紛れ、窓際に佇む冴子の顔が哀しく歪む。
“今までで一番の誕生日プレゼントだよ”
“僕もう今から待ちきれないんだ!!”
力なくテーブルの上に降ろした紙の包みは、そのまま放置されていた。
“霧島喜ぶだろうなぁ”
“あいつの喜ぶ顔が早く見たいよ!!”
マスターがさっき集めて置いたテーブル花は、“白バラ”、“ホワイトスター”、そして触ると“独特な香りがする”“シルバーグリーンのユーカリ”。
「あの子は必ず…誕生日までには帰って来ると思ってたのに―――‥」
冴子は窓の外へ視線を向けたまま、ぼんやりとそうこぼした。
「夏目君がパーティーを楽しみにしてるって、知ってるはずなのに―――」
“あいつ結構”
“楽しみにしてたから”
「マスター!!」
不意に冴子が大声を上げ、カウンターの中のマスターに駆け寄った。
「やだっどうしよう!大変だわ!!そうよ、あの子が夏目君を放って帰らないなんてあり得ないわ!!やっぱり何かあったのよ!おかしいと思った、そうよ、何かあったのよ!!」
突然取り乱した冴子にマスターは驚き、けれどその動向を注意深く見守っていた。
「ねぇ?!おかしいでしょ?!こんなに長いこと帰らないなんてやっぱり変よ!!どうしよう、なんでもっと早く警察に行かなかったのかしら!亮ちゃんやマスターの言葉を鵜呑みにして、私―――私がもっとちゃんとしなくちゃいけなかったのよ―――こんなとにいる場合じゃないわ、今すぐに警察へ行かないと!あの子にまで何かあったら私―――どうしよう、ねぇマスター!私、あの子まで―――!!」
すがるようにそう訴える冴子は今にも店から飛び出しそうな勢いだった。
「ねぇマスターも一緒に来て!保護者なんだから!!今すぐ行って央人を探してもらわなくちゃ!!」
涙ながらに必死で頼む冴子に対し、マスターはけれどもちろん、一歩も動こうとはしない。
「落ち着いて、冴子ちゃん」
袖を掴むその華奢な指をそっと握り返しながら、マスターは冷静な口調でそう言った。
「何言ってるの?!あの子に何かあったらどうするつもり?!もしかしたら今、この瞬間にも何か事件に巻き込まれてるかも――!!」
「大丈夫だから」
「何が?!何がどう大丈夫だって言うの?!あの子がもう何日帰ってないか分かってるの?!マスターも亮ちゃんもどうしてそんな平気でいられるの?!あの子が心配じゃないの?!夏目君にあんなことがあったっていうのになんで―――?!」
「帰って来るよ、‥央人はもうすぐ、帰って来るから」
「なぜ分かるの?どうしてそんなことが言えるの?あの子から連絡があった?いつ?いつあったの?どうして私には教えてくれないの?私にもちゃんと教えてよ!!あの子は今どこにいるの?!知ってるなら教えて!ねぇ教えてよ!!」
「――それは―――」
「なんの根拠もなく帰って来るなんて気休めやめてよ!!ほんとは何も知らないんでしょ?!ねぇマスターはあの子が心配じゃないの?!どうしてそんな悠長にしていられるのよ?!」
冴子の不安な眼差しが激しくマスターを追い詰めていく。
「もちろん、僕だって心配だよ」
「だったらなんでっ‥――?!」
「――、あぁ‥うん、いや――」
「もうなんなの?!その反応のイミが分からないわ!!ちゃんと話してよ!マスターは何を知ってるっていうの?!一体何を隠しているの?!ちゃんと説明してよ!!」
冴子の勢いに押されながら、けれどマスターは話すわけにはいかなかった。
“重要なのはそのタイミングと言葉選び”
“ぬかりない下準備と入念な計画、完璧な段取り”
「冴子ちゃん、央人はもうすぐ帰って来るから、――今はそれしか言えないけど――」
「‥どういうことなの?」
冴子の鋭い尋問に、それでもマスターはなんとか説得を試みた。
「ごめん、冴子ちゃん、ただ――信じて欲しい‥央人は必ず帰って来るから――」
マスターの曖昧な、そして頑なな返答に、けれど冴子は全く納得していなかった。
今はどうか、一端引いて欲しい―――マスターのそのぶれない姿勢に、冴子はマスターを睨みつけた。
「嫌!!」
「大丈夫だから、央人は、大丈夫だから」
「それだけじゃわからないわ!!」
「‥うん、そうだね、でも――本当なんだ」
「きっともうすぐ戻って来るから、安心して――」
「―――‥‥‥」
冴子は拝むようなマスターの態度に、それ以上の抵抗はできなかった。
「帰って来たらうんと叱ってやる‥勝手なことばかりして、みんなに心配かけて」
髪の毛が逆立つくらい憤慨しながら、冴子はようやく仕事に取り掛かった。
「こんな時に帰って来ないなんて――帰って来たらタダじゃおかないんだから――」
冴子は口の中で文句を吐き出しながら投げるように器から花を取り出していく。
マスターはその器が空になると、トレーごとキッチンへ運んだ。
その間に冴子はいつものように花を寄り分ける。けれどその指の動きはおぼつかず、止まったり動いたりを繰り返していた。
「今回は白とグリーンの組み合わせだね‥涼し気で今の季節にピッタリだ」
花材を切り分ける冴子の手元を覗きながら、マスターは「これは何ていう名前?」と指をさした。
「トルコ桔梗の八重咲き」
「最近はバラよりも高価な品種もあって、ブライダルでも人気の花なの」
「バラみたいに立派な花だね、ブーケにも好まれそうだ」
「これはビバーナム」
「ラナンキュラスの大輪、これもバラみたいに存在感があるでしょ。ラナンだけのブーケも人気なのよ」
そしてマスターは緑色の花に目を向けた。
「これは?」
「それもバラよ、グリーンのスプレーバラ」
「へぇ、これもバラなんだ‥僕初めて見たよ」
そうマスターが笑いかけた時、ついに冴子の瞳から涙がこぼれた。
「‥冴子ちゃん?」
手にしたハサミを下に置き、冴子は片手で目元を拭った。
「マスター私、まだ信じられないの―――」
白くてフワフワのトルコキキョウ
白くてフワフワのラナンキュラス
「ねぇ―――‥‥信じられないわ―――」
「うそでしょう?‥もう――あの子が――もう、いないなんて―――」
冴子の大粒の涙が白い包みの上にいくつも零れ落ちていく。
「ぅぅ‥‥うぅぅ‥‥‥―――」
数日前、亮介はある決断をした。
“冴子に夏目のことを話すよ”
マスターは亮介の決意に“そのほうがいいね”と答えた。
“父親が帰って来て、身元が判明した”
“遺留品の特定から、諦めていたDNA鑑定もできることになった”
「ぅぅぅ‥‥‥‥―――」
“掘り起こされたラジオらしきものに差し込まれていたイヤホンが役に立った”
“それと恐らく―――”
その手指はしばらく土の中にあったとみられている。
“ラジオを土に埋めようとしていたからでしょう”
“最後の力を振り絞って”
“せめてそれだけでも”
“よほど大切なものだったと思われます”
「うぅぅぅぅ――――あぁ―――ぅぅぅうっ―――‥‥‥‥・・・・」
“その僅かに残されていた部位で鑑定ができる運びに―――”
「うぅぅぅぅ―――っ―――あぁぁっ――――‥‥っ――――」
呻くような冴子の泣き声が店内に響き渡っていた。
「あぁ―――‥‥‥―――っ・・・・―――」
あの子に‥‥―――もう会えないなんて――――――
冴子は両手で顔を覆い、涙ながらに声を絞った。
「うん――――」
「央人が―――このことを知ったら――――」
昔から、いつでも人一倍霧島のことを心配している冴子の悪い予感は、よく当たる。
その夜の冴子はすっかり涙に暮れていた。
“まるで機械みたいに速くて正確”な動きも、““魔法がかかったように”“あっという間に“完成する”はずのテーブル花も、一向に完成しなかった。
マーヤが好きだった冴子の“仕事”は完全に見失われていた。
なかなか終わらないその作業を、マスターは止めることもできなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
