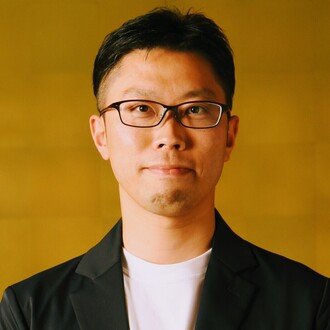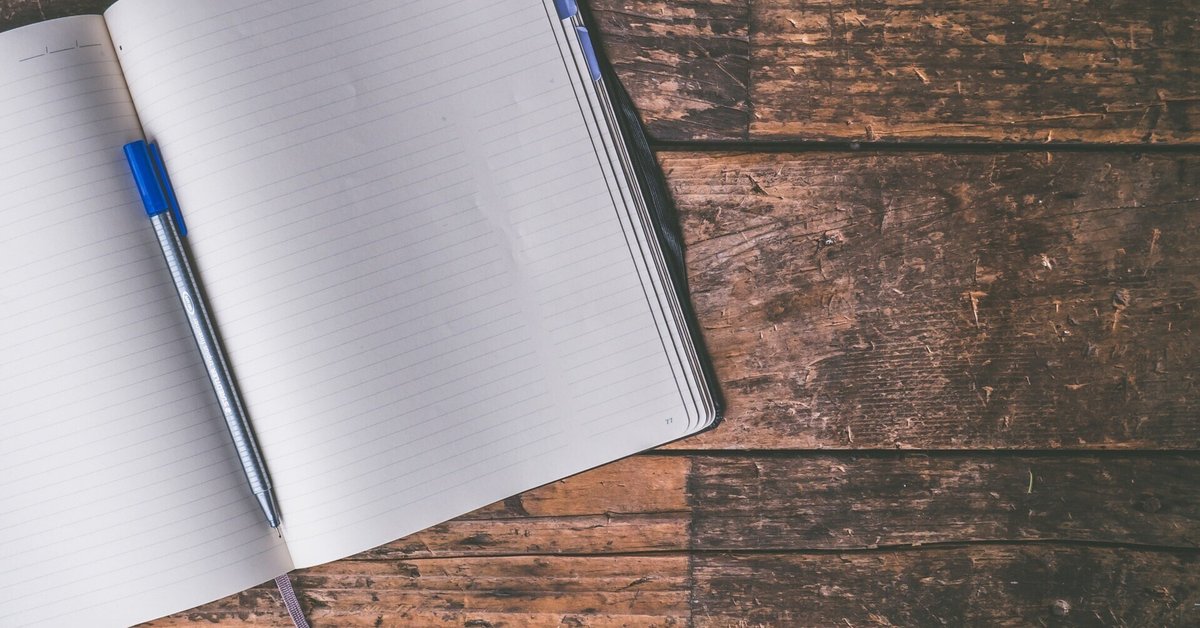
1月23日:へいなかの20代を彩った小説7選
おはようございます。
大学時代、ダンスをやっているという理由で塾講師のバイトを落とされた男・へいなかです。
#不良の趣味だと思われた
#10年後ダンス必修化
#まだ面接官の顔憶えてる
さて今日は…先日の研修後にアンケートでいただいた質問に答えるべく、僕が何に触れてきたのか…その一部を紹介します。
・・・・・・・
頂いた質問は…
「どうやって語彙を増やしましたか?」
でした。
結論ですが…
一番いいのはやっぱり、実力者たちと語らうことです。伝え方を磨きたいなら伝える力が強い人の話を大量に浴びたほうがいい。それは伝える力に限った話ではない。なんにせよ、求める力をすでに持ってる人と語らうことが一番いいと僕は思います。
法務教官はだいたい、6日に一回当直があるのですが…僕は一緒に当直する教官たちの中に実力者がいる時には、その人の事務時間を自分の質疑の時間にする位いろんな質問をしまた。
今、こども発達支援研究会では毎月3〜4回、会員が無料参観できる対談イベントに出ています。これも、仕事であると同時に僕にとってのインプットでもある。(次回は1/30)
実力者と語らうのが一番たのしいし、勉強になる。
ただ…
結局そんな機会はなかなか日常的に恵まれるもんじゃないし、自分ひとりでできることもある。
僕は教育書や専門書のたぐいはほとんど読まないのですが…代わりに映画やマンガ、小説にたくさん触れてきました。
大学の卒業直前には毎日1本映画見てたし、法務教官時代も一番多い時で年間200本くらい映画を観た。
去年は全然読めなかったけど、基本的には年間50冊くらい小説を中心にいろんな本を読んでます。
家にはマンガも数百冊ある。引越のたびに百冊単位で捨ててるけど、結局なかなか減らない。
ただの知識や技術のまとめではなく、メッセージ伝えるために生み出された作品たち。それらが僕に与えてくれた影響は数え上げればキリがないように思います。
なので今日は、「どうやって語彙を増やしましたか?」への回答代わりに、僕の好きな小説をいくつか紹介してみます。
せっかくなのでメジャーなところはスルーします。司馬遼太郎や吉川英治、北方謙三は一旦スルー。東野圭吾や伊坂幸太郎もスルー。隠れた名作やちょっと昔の作品など、20代の僕に影響を与えてくれた作品たちです。
気になったら覗いてみてください。
へいなかの成分(の極めて一部)。
・・・・・・・・
1)『くちぶえ番長』重松清
へいなか的重松作品ベスト1
転校生の女の子が、その学校のいじめっ子たちと格闘しながら成長していく物語。一輪車に乗り、くちぶえを吹く。賢く強い女の子。でも実はちゃんと苦手なこともある…。そんな転校生とのび太くん的な男の子の成長物語。
少年院で一番多く紹介した本。
強さの意味をはき違えたすべての非行少年に捧ぐ…少年院で学ぶべき全てのことが詰まった1冊。
数多の重松作品の中でもかなり短く、読みやすい。読書が苦手な子でも読める薄さ。乱暴な子の指導に使えるへいなか文庫の入門書。
・・・・・・
2)『蹴りたい背中』綿矢りさ
とにかく最初の一文が美しい。
小説は1ページ目が8割。一文目がすばらしいものは、高確率で最後まですばらしい。
そういう意味で、僕の中ではこれが最上級。
芥川賞を受賞した名作だが、まだ読んでいない人は読んでみてほしい。孤独、さびしさ…そんなものを表現するのに、こんな書き方があるのかと、読み替えずたびに唸る。
本当は冒頭を引用したいけれど、でもあの感動は直接体験していただきたいので、ここでは別の文を紹介しておく。孤独な時間を量的に示すこんな表現…同世代の著者がデビューまもない頃に書いた作品だが、僕には到底できる気がしない。
黒い実験用机の上にある紙屑の山に、また一つ、そうめんのように細長く千切った紙屑を載せた。うずたかく積もった紙屑の山、私の孤独な時間が凝縮された山。
・・・・・・・
3)『教祖誕生』ビートたけし
ある山の上空で、イヌワシが山鳩を捕らえた。巣から落ち、人の手によって育てられたイヌワシ。山の麓で見守っていた育ての親は、野生で生きていけそうな立派な姿を見て安心して去っていく。
もう一人…同じ光景を反対側から見てた人がいた。
山鳩を育て、山に返しにきた人。「元気に暮らせ」と言って送り出した山鳩が、その直後にイヌワシに捕まった…。
本書の冒頭で淡々と描かれる犬鷲と山鳩の話。その後の「教祖」のストーリーもさることながら、様々な示唆をもって語られるこここそが、本書の最大の価値だと思っている。
前述の『くちぶえ番長』と同じく、あっという間に読めてしまう小さな作品だけれど、僕の中ではビートたけしの最高傑作。
・・・・・・・
4)『4teen』石田衣良
雄と男の狭間で…
14歳という年齢は、きっと多くの男にとって節目になるのだと思う。エヴァのシンジも14歳。中途半端に身に着けてしまった自意識が、失いつつある万能感との狭間で揺れる。
14歳の仲良し4人組が、友情や性、病気や死に触れながら、短く切ない中二という瞬間を生きる…そんな話。
続編もあるようだが、とりあえずこれは良書。
男ってこんな感じ。
・・・・・・
5)『MISSING』本多孝好
キザな会話の名手が描くミステリー短編集
本多孝好はとにかく会話がおしゃれ。ちょっとモテなさそうな男とか、いたずらっぽく笑う美女を描かせたら天下一品だ。モテないメンズはどれでもいいから彼の作品を読んで見るといい。
が
あえて一冊選ぶなら、本書がベストだと僕は思っている。
独特の雰囲気の中で描かれる、真相が見えそうで見えないストーリー。
恋ゆえに自ら死を選ぶ少女
母の不倫を目撃し、大切な存在を死に追いやった上、自分を偽ることで家族を取り戻そうとする少女
そんなちょっと胸が痛むストーリーを、淡々とミステリーに仕上げるセンスと技量に引き込まれる。
・・・・・・
6)『本日は、お日柄もよく』原田マハ
言わずと知れたスピーチの教科書
新郎の上司が、お経よりも苦行と呼べそうな退屈で間の抜けたスピーチをする…。あまりの退屈さに晴れ着を台無しにする大失態をかましたOLが、伝説のスピーチライターと出会い、言葉の深みに触れていく。
本書の中で様々な登場人物が繰り出すスピーチと、その前後に語られる「伝える」ことの極意は、下手な話し方の教科書よりもよっぽど勉強になる。
とりあえず…
すべての教育関係者は読んだ方がいい一冊。
僕の講義を聴いたことのある人は、きっとこれを読めばわかるはず。僕…この本から超影響を受けてます。
・・・・・・
7)『800』川島誠
僕を小説の世界に引きずり込んだ名作
陸上800m…日本ではマイナーな中距離。
ヨーロッパでは結構話題になるトラックの格闘技。
そんなマイナー競技でしのぎを削る対象的なライバルと、彼らの周りに現れる個性や偏りのいびつな女子。
2人の主人公が交互にモノローグで語るそれぞれの青春。
陸上競技の疾走感と、青春の刹那さが混じり合う名作。
大学1年でこの小説を手にしたことが、僕の読書人生の分岐点。
ちょっとひねくれた会話も魅力。
・・・・・・・
8)まとめとオマケ
ここから先は
放デイのスタッフをしながら、わが子の非行に悩む保護者からの相談に応じたり、教員等への研修などを行っています。記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。