
ヘーゲル『法の哲学』試論—「対外主権性」篇
はじめに
以下では,ヘーゲル『法の哲学』第3部「人倫」第3章「国家」A「国内法」II「対外主権性」を取り扱う.
ヘーゲル『法の哲学』第3部「人倫」第3章「国家」(承前)
対外主権性における個体性
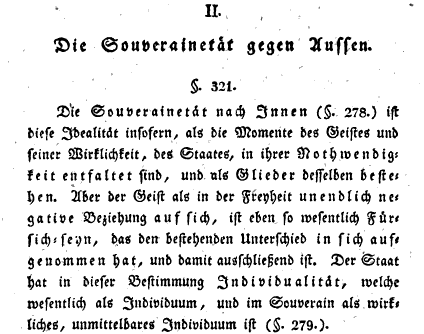
第321節
対内主権性(第278節)がこのような観念性であるのは,精神の諸契機と精神の現実性である国家の諸契機が,それらの必然性において展開されて,国家の分肢として存立するかぎりにおいてである.だが精神は,自由において自己に対する無限に否定的な連関として,同じく本質的に対-自-存在であり,これは,存立する区別を自己内に取り込んでしまっており,これによって排他的である.国家とは,このような規定において個体性を持ち.そしてこの個体性は本質的には個体として存在し,そして主権者においては現実的で,直接的な個体として存在する(第279節).
最初の一文が「対内主権性 Souverainetät nach Innen」(第278節)の振り返りであるのに対して,「しかし Aber」以下の文章は「対外主権性」(Souverainetät gegen Aussen)*1について述べたものだといえる.「このような観念性 diese Idealität」については第276節にも詳しい.
ここでは「対-自-存在」「排他的」「個体性」といった語によって「対外主権性」が特徴づけられている.要するに,「対内主権性」では君主権や統治権や立法権などの詳細な諸々の区別が展開されていったが,「対外主権性」の場面ではそれらの区別が一括りにされて,ひとつの自立的な個として登場するのである.
さらにヘーゲルは「必然性 Nothwendigkeit」と「自由 Freiheit」という言葉を用いている.すなわち「対内主権性」は君主権や統治権や立法権といった契機は論理必然的に展開されたが,「対外主権性」は自立した個として存在するがゆえに,同様に他の自立した個として存在する他国に対して「自由」に振る舞うことができるのである.
ここで参照指示されている第279節を見ると,そこには「君主 Monarch」が登場する.したがって,上で「現実的で,直接的な個体」と呼ばれているのは具体的には「君主」のことである.「君主」が「現実的で,直接的な個体」と言われる所以は,彼が国民から恣意的に選ばれた存在ではなく,直系の継嗣として「主権者」の身分をその生まれから自然な肉体によって体現する存在であるからである.
国家関係における自立性と統合の問題
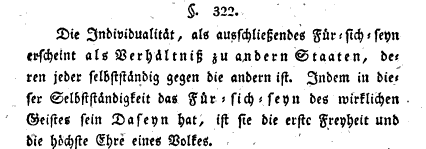
第322節
個体性は排他的な対-自-存在としては,他の諸国家との関係として現象し,その〔諸国家の〕おのおのは他〔の諸国家〕に対して自立している.この自立性において,現実的精神の対-自-存在がその定在を持つのであるから,この自立性は,一国民〔民族〕の第一の自由であり,最高の名誉である.
概ね前節と同様の内容であるが,前節では国家がまさに「排他的な対-自-存在としての個体性」であることが示されたのに対して,ここではそうした一つの自立した個としての国家が「他の諸国家との関係 Verhältniß zu andern Staaten」においても同様であることが示されている.
しかし,一つの国家が個体として自立しているということは,ある意味で厄介な問題を孕んでいる.というのも,それによって諸国家の統合というのは容易ならざるものとなり得るからである.この点については,同節注解で言及されている.
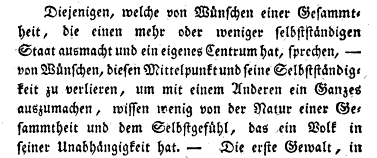
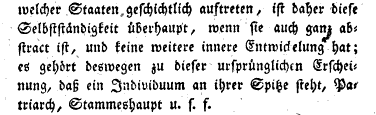
多かれ少なかれ自立した一国家をつくりなして,それ自身の中心をもつような統合体が望ましいと語るひとびとは,——他国とともにひとつの全体を形成するために,みずからのこのような中心点とその自立性を失うことが望ましいと語るひとびとは——,統合体の本性と一国民〔民族〕がその独立性においてもつ自己感情についてほとんど知らないのである.——したがって,国家が歴史的に出現するさいの最初の権力は,たとえまったく抽象的であって,何らそれ以上の内的発展をもたないにせよ,そもそもこの自立性なのである.それゆえに,国家のこの原初の現象には,家父長,族長等々といった一つの個体がその〔権力の〕頂点にたつことが属している.
要するにドイツの諸邦はそれぞれに独立した中心点を持っているのだから,それらの個々に独立した中心点を捨ててひとつの全体を成そうとすれば,それは中心点を失うと同時に自立性の側面をも失ってしまうことになるのである.しかしながら,個体としての自立性なくして対外主権性もまたあり得ないのである.(ちなみにここで後半の国家の「原初の現象」すなわち国家の樹立に関する議論については,本書C「世界史」の第394節以下で詳しく述べられているので割愛する.)
坂本清子は当時のドイツの状況について次のように述べている.
フランス革命後のドイツでは,多数の領邦国家に分立している「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」の現状を何かの欠如あるいはF. ハルトゥングの言う「帝国国制の欠陥」とする意識が顕著になっていた。ウェストファリア条約(1648年)によって帝国等族(Reichsstädte)が国家主権を獲得してドイツの小国分立体制が法的に固定化されたという事実だけでなく,意識の上でも領土や領邦のレベルを超えた何か「全体」を喪失しているということが認識されたのである.
ヘーゲルの時代にはドイツの諸邦はまだ統一されておらず,実際のドイツ統一が成し遂げられるのはもっと後のことであった.1870年の普仏戦争を経て,1871年のドイツ帝国の成立をゴールとするならば,ヘーゲルの時代はまだまだナショナリズム運動の黎明期に差し掛かった頃である.フィヒテの講演『ドイツ国民に告ぐ』(1807-08年)はその先駆けであり,さらに1815年に結成された学生の結社ブルシェンシャフトは自由主義とナショナリズムを主張したが,1819年にブルシェンシャフトの急進派であったカール・ザントが保守派のコッツェブーを殺害した事件により,カールスバード決議をもってブルシェンシャフトは徹底的に弾圧されることになる.こうした過激な事件のこともあるから,ヘーゲルとブルシェンシャフトとの関わりを描くことは微妙に難しいが,概ねヘーゲルはブルシェンシャフト運動には強い関心を持っていたとされる.
とりわけ,なんの義務もないのに,かれは学生連盟の問題にたえず関わりをもっている.
……(中略)……
学生連盟に対するヘーゲルの関心,「扇動家」訴訟問題における執拗なとりなし,あるいはまた「クーザン事件」への関与は,あらゆる種類の秘密の会合を想定させるであろう.
先の諸国家の統一の困難さについて語るヘーゲルにとって,それを目指すブルシェンシャフトは,ともすればその困難さを埋め合わせるほどの熱量を持った無視できない存在だったのではないかと思われる.
国家の自己に対する否定的連関
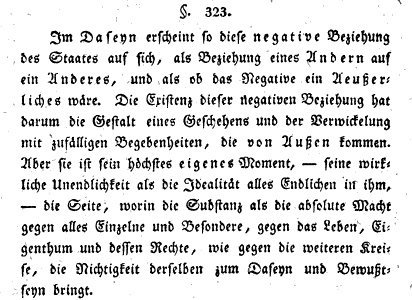
第323節
それだから,定在における国家の自己に対する否定的連関は,或る他者の或る他者に対する連関として現象し,そして否定的なものが外面的なものであるかのようにして現象する.この否定的連関の現実存在は,そのために,ある出来事のすがた,外側からやって来る偶然的な諸事件との錯綜というすがたをとる.しかし,その否定的連関は,国家固有の至高の契機——国家におけるあらゆる有限なものの観念性としての国家の現実的無限性——あらゆる個別と特殊に対して絶対的な,生命・所有およびその権利に対して絶対的な,同じくさらなる諸集団に対して絶対的な威力としての実体が,それらの空無性を定在と意識にもたらす側面である.
国家は一つの国家だけで成立しているのではなく,つねに他の諸外国との関係において存在する.これは国家関係の外部性とでも言えば良いだろうか.そして他の諸外国の動向は,一国にとっては常に偶然的な出来事として対峙しなければならない.そして戦争では国家の存亡を賭けて国民は文字通り命懸けで戦わねばならぬ時がある.そのような極限状態では,普段は国家によって保護されているような個人や集団,「生命・所有およびその権利」は「無 Nichtigkeit」に帰する.ここで「絶対的な威力」とは,要するに国民に対して「国家のために死ね」と要請できる権力のことである.このようにして国家の実体は「絶対的な威力」としては,個人や集団のような実存よりも,自立的な個体としての国家という理念的なあり方を重要視する.そのため,個体としての国家の存立が危機に瀕するような時には,個人や集団の実存は蔑ろにされてしまうのである.
ここでは国家の否定的な側面が取り上げられているが,これに対して国家の肯定的な側面については次節で述べられている.
肯定的なものとしての国家の独立性と主権性
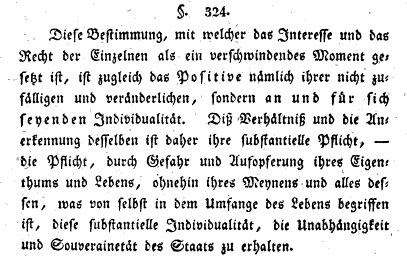
第324節
個々人の利害と権利とが一つの消滅する契機として定立されるこの規定は,同時に肯定的なものであり,すなわち個々人の偶然的で変わりゆくものではなく,それ自体で独立して〔絶対的に〕存在する個体性である.したがって,この関係とこれを承認することは,個々人の実体的義務であり,——すなわち,個人の臆見やその生活の範囲に自ずから把握されているすべてのものはいうにおよばず,個々人の所有や生命をも危険に曝し犠牲にして,国家の独立性と主権性という,この実体的個体性を保持するという義務である.
「個々人の利益と権利が消滅する一契機として定立される」という事態は,一見すると否定的なものであるように思われるが,ヘーゲルはこの契機を弁証法的に「肯定的なもの」と見る.というのも,「個々人の利益と権利」が「消滅する」ことによって,かえって「国家の独立性と主権性」という「実体的個体性」が保持されるからである.むろん個々人が国家に対してこのように屈服するような関係に対しては個々人側からの反発を招くことが当然予測される.だが,まさに国家に対する個々人のそうした反抗的な事態をヘーゲルが想定しているからこそ,国家と個々人との関係を「承認すること Anerekennung」が個々人にとっての「実体的義務」だとヘーゲルは説くのである.本節注解で述べられるように,こうした理論の背景にあるのは戦争である.
(つづく)
注
*1: ここでヘーゲルはタイトルを„Souverainetät nach Außen“ではなく„Souverainetät gegen Außen“としている.ただし別の箇所では「対外〔主権性〕 die nach Außen s.」(第278節注解)と述べている.
文献
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
