
日本の国歌は妻の天下なのです!
『海行かば』(うみゆかば)は、日本の国民歌謡の一つ[1]、歌曲[2]、合唱曲[2][3][4]。特に大東亜戦争中は準国歌、第二国歌とも呼ばれた(ただし、法的に認められたものではない)[5]。
海行かば 水漬く屍
山行かば 草生す屍
大君の 辺にこそ死なめ
かへりみはせじ
(長閑には死なじ)
歌詞は2種類ある。「かへりみはせじ」は、前述のとおり「賀陸奥国出金詔書歌」による。一方、「長閑には死なじ」となっているのは、「陸奥国出金詔書」(『続日本紀』第13詔)による。大伴家持が詔勅の語句を改変したと考える人もいるが、大伴家の「言立て(家訓)」を、詔勅に取り入れた際に、語句を改変したと考える説が有力ともいわれる[誰によって?]。万葉学者の中西進は、大伴家が伝えた言挙げの歌詞の終句に「かへりみはせじ」「長閑には死なじ」の二つがあり、かけあって唱えたものではないか、と推測している。
「かへりみ」は「かえり身」つまりバ〇クなのです。「長閑(のど)」は「喉」つまりフェ〇チオなのです。「正常位で大君=妻と一緒に果てる」という歌なのです。ただし古代では正常位は騎〇位なのです。
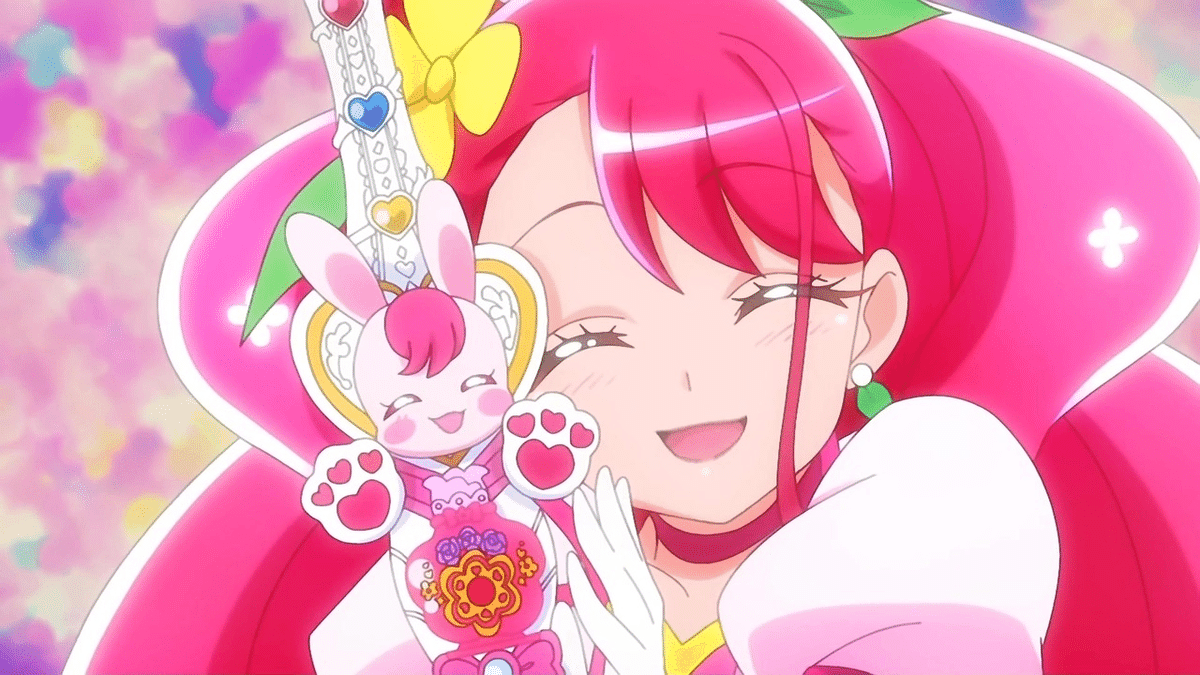
葦原の 瑞穂の国を 天下り 知らし召しける 皇祖すめろきの 神の命みことの 御代重ね 天の日嗣ひつぎと 知らし来る 君の御代御代 敷きませる 四方よもの国には 山川を 広み厚みと 奉る 御調宝みつきたからは 数へえず 尽くしもかねつ しかれども 我が大王おほきみの 諸人を 誘ひたまひ よきことを 始めたまひて 金かも たしけくあらむと 思ほして 下悩ますに 鶏が鳴く 東あづまの国の 陸奥みちのくの 小田なる山に 黄金ありと 申したまへれ 御心を 明らめたまひ 天地あめつちの 神相かみあいうづなひ 皇御祖すめろぎの 御霊みたま助けて 遠き代に かかりしことを 我が御代に 顕はしてあれば 御食国みをすぐには 栄えむものと 神かむながら 思ほしめして 武士もののふの 八十伴やそともの緒を まつろへの 向けのまにまに 老人おいびとも 女めの童児わらはこも しが願ふ 心足らひに 撫でたまひ 治めたまへば ここをしも あやに貴み 嬉しけく いよよ思ひて 大伴の 遠つ神祖かむおやの その名をば 大来目主おほくめぬしと 負ひ持ちて 仕へし官つかさ 海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見は せじと言立ことだてて 丈夫の 清きその名を 古いにしえよ 今の現をつつに 流さへる 祖おやの子どもぞ 大伴と 佐伯の氏は 人の祖の 立つる言立て 人の子は 祖の名絶たず 大君おほきみに まつろふものと 言ひ継げる 言ことの官つかさぞ 梓弓あずさゆみ 手に取り持ちて 剣大刀つるぎたち 腰に取り佩はき 朝守り 夕の守りに 大君の 御門の守り 我れをおきて 人はあらじと いや立て 思ひし増さる 大君の 御言みことのさきの聞けば貴み

み-かど 【御門】
名詞
④国家。天皇が治める国。
出典伊勢物語 八一
「わがみかど六十余国の中に、塩竈(しほがま)といふ所に似たるところなかりけり」
[訳] 我々の国家六十余りの国の中に、塩竈という所に似ている所はなかった。◆「み」は接頭語。
当時の「御言」はわかりませんが、現代では「イ〇ちゃう」なのです。
我が君は 千代にやちよに さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで
さざれ石のように小さくてかわいらしかったのが、巌の巨体となり、ご無沙汰で苔がむすまでが妻の天下なのです。

キリスト教の「三位一体」は
父ー娘
子ー母
精〇ー妻
なのです。神は「女」なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
