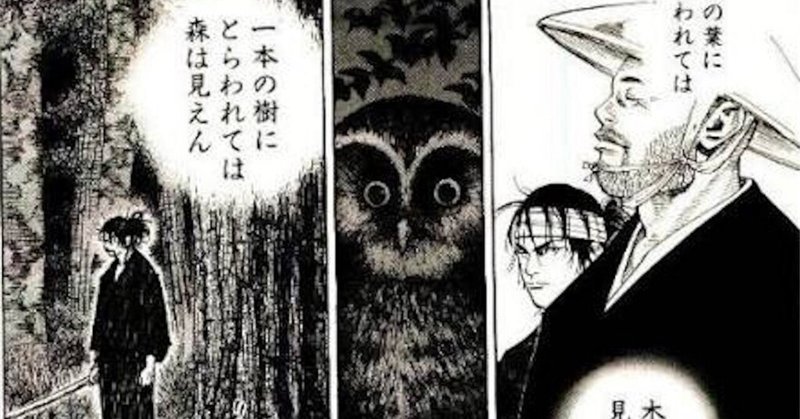
経産省の怪文書の感想とこれから起きる退職ラッシュのこと
大学は経済学部でしたが、高校の時に進路を考えた時には個々の企業よりもマクロな?経済をやっておいた方が潰しが効くんじゃないかという田舎の高校生なりに考えて決めましたが、あまり意味はなかったかと思います。生憎と島根では経済学部や経営学部を学んだらその先どうなる?みたいなことに答えられる大人が居なかった。公認会計士や税理士とかどこかに居たのかもしれないが見たことが無かったし何をするのか知らなかったです。
ただ、経済はミクロの積み上げなのか?個々の企業が最適な選択をしたらその集合体である国や地方に取って最善な結果になるのか?というのは重要な視点だと思います。個別最適は必ずしも全体最適にはならないように思います。
よく、欧米企業と比較して日本の企業の経営について言われることの一つに利益率・収益性が低いというのがありますが、これは裏を返せば社会としての失業率の低さ≒余剰人員を企業が抱えていることの裏返しかもしれませんし、欧米の若年人口の失業率の高さを考えると新卒一括採用をして企業が真っ白な学生を教育するという仕組みにも一定のメリットはあると思います。
確かに失われた30年みたいな文脈で日本企業の凋落については色々と思うところはあるものの、マクロ視点では個別企業が非効率ゆえに失業率が低く安全な日本に寄与してるわけで、米国企業的な経営を導入してファイナンス重視の意思決定をして(スキルが無い)失業者が世の中に溢れたり非正規雇用ばかりになるのがいいとも思いません。
例えばこれまで取れてなかった海外の売上を増やすことができれば雇用と収益性の両立は可能かもしれませんが、雇用と効率性がある程度トレードオフの関係にあるならばいいとこ取りはできない。

まあ日本的経営とやらが上手く行っていたら氷河期世代が助かっていたのかは甚だ疑問ですが。
個人としては、所謂外資系企業の方が経営効率が良かったりするが故か給料なんかも良いですし、今の日本の大企業も40歳を超えると普通にリストラすることを踏まえるならば結果的には解雇リスクもあまり関係なかったように思いますが、自分が就活していた時にはやはり外資系企業の解雇リスクについては色々な議論がありました。(生き残れるならば)欧米企業の経営のメリットを社員も甘受することができるかもしれませんが、これを当たり前のものとして日本社会に当てはめることについては慎重にした方がいいと考えています。
前置きが長くなりましたが、経済産業省が「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」という怪文書を公開していたので拝読はしてみました。まあこの資料については色々な方が思うところを書かれているので内容についてはここでは触れませんが、コーポレート機能の強化やファイナンス、ITの活用みたいなことを提言しているようです。
ちょっと話題になってたやつを斜め読みしてみたのだけど。
— (っ╹◡╹c) (@Heehoo_kun) May 25, 2024
製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性
016_04_00.pdf (https://t.co/PtTMcxmQU9)
てっきり官僚というのは国家や産業をどうするのか?を考えるのが仕事だと思っていたので、こんなコンサルティング会社の寄稿文みたいなものを作るとは知りませんでした。ERPやFP&A組織やKPI管理みたいな。そんなことでも十分にやっていない会社があるならば世の中のベストプラクティスを知る意味では多少は意味があるのかもしれませんし、天下国家を語るという視点から日本企業のプレゼンスが下がり続けていることへの危機感という意味でお前らちゃんとやれよって言いたいのなら、それはそれでわからなくはないです。それにしても経産省の役人に言われてもなっていう。それこそお前が来てやってみろ(OKY)でしょう。
そんなことよりもFP&Aとしても企業の事業計画をまとめたりしてきた自分から見ると、日本企業の低収益性の改善なんかよりも大量採用されたバブル世代がこの数年で退職ラッシュになる事の方がよほど危機感を持ってしまいます。
JRに限らずある程度の歴史ある大企業の年齢構成はこんな感じで、右端の層が大量に引退し始めるのでその分の人件費を現役世代で分配するなら利益を圧迫することなく普通に毎年5〜10%の賃金の伸びを今後15年はできると思うんだよな。その後どうなるのかはよくわからない pic.twitter.com/K2xw7bwcXz
— (っ╹◡╹c) (@Heehoo_kun) April 1, 2024
JRの人員構成が一般化として適切かというのはありますが、バブル世代の下が氷河期世代で正社員採用が抑制されたというのは事実であり、大手企業の人員構成は企業の歴史が色濃く反映しています。バブル期採用の50歳後半社員が非常に多く、40歳台社員が少なく、30歳台社員が極端に少ないという構成です。年齢別の人員構成では55歳以上社員に大きなコブがあり、逆に40歳台30歳台が非常に少ないという歪な構成です。
経理財務なんかでも中途採用を募集するとある程度のスキルでフィルターを掛けるとすぐに40半ばになってしまうという。
企業としての課題はバブル世代がこの先5~10年で引退するのをどのように少ない人員で知識の継承していくのか。マネジメント経験を積んだ社員は少なく、ブラックボックス化された業務をそのまま引き継ぐにはリソースが足りないのでDXや標準化で乗り切らないといけません。
一方で国や産業という視点で考えると、高い給料をもらっていた層が年金受給をするということは日本全体で可処分所得が減る&負担が増えるわけで、浮いた人件費をどう現役世代に再配分させるのかということを考える必要があるように思います。それこそ現役世代の賃上げを必ず実現するくらいの勢いで。
そういう意味では先の経産省の資料なんかは完全に的外れで、余剰人員が解消されるのだから企業の生産性は後数年で勝手に良化するんですよ。個別の企業のPLだけを見るならバブル大量採用のお荷物社員がやっと減って人件費を抑制して収益性が拡大するわけです。しかしながらそれをやってしまうと社会全体で使えるお金が減る。経産省が国としての発展を真剣に考えるならば国としてのコストセンター≒高齢者をどうするのかを考えて欲しいという気はしますがこれは財務省なのかもしれません。
割と最悪なのは企業が人件費を現役世代に再分配しないので訳の分からない社会保障がどんどん増えて訳の分からない補助金やバラマキになることだと思うし、一方で高確率でそうなるのがシルバー民主主義の末路だと思っている
— (っ╹◡╹c) (@Heehoo_kun) April 1, 2024
まあこんなことを考えると、どうやっても詰んでしまい高齢化社会については解決策は革命くらいしかないんじゃないかって思えてくるのですが、ここまでにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
