
行動科学と投資
「そのように行動したいと感じることは自然」「事実を認識できない」と実験の例を並べつつ、それが投資の世界ではマイナスの結果につながっていることが説明されています。投資心理を解説した本です。
ダニエル・カーネマンとかを読んだことのある人は、既に知っている内容も多いかも。
各章の終わりに要点がまとめられています。

認知パターン
人間の考え方にはクセがある。例えば
公平な情報を与えられても、現在の選択を「正しい」と信じる気持ちが強くなるだけ。自分が選んだものは、選ばなかったものより「正解」であるように見える。
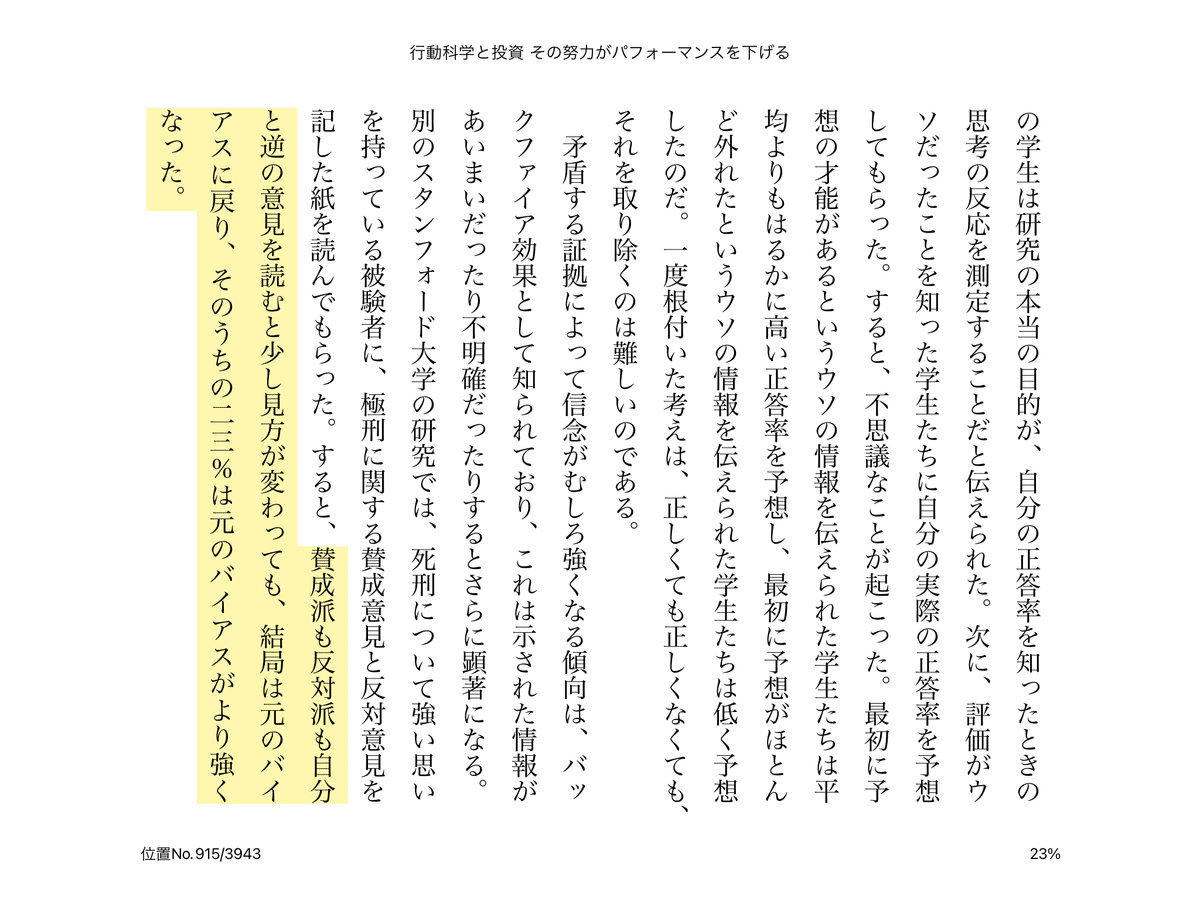
保守主義は、後悔回避、つまり持っているものを持っていないものよりも高く評価し、利益を求めるよりも損失を恐れるという自然な傾向によってさらに強くなる。
また、情報(ノイズ)が多すぎると
行動しなくなるか、合理的ではない判断をするようになる。

「リスク下での方針は、すべての雨粒に対応しなければならないため、最適化が必要だ。しかし、不確実性の下ではやるべきことは逆になる。複雑な環境では単純な決定規則が必要になる。なぜなら、単純なルールは未知の減少に対してロバストだからだ。つまり、不確実性の下で対応しなければならないのは各雨粒ではなく雷雨だけであり、そのためには粗い調整で十分なのだ。」
犬は物理学の知識ナシでフリスビーを上手に捉えるが、計算しているわけではなく経験による結果である。人間の直感も非常に優れているけれども、目の前の事象(行動からのフィードバックがすぐに起こるもの)でなければ、直感は育ちにくい。
人間の選択について、こちらの本もオススメです。「ジャムの売り場で、24種類と6種類の味を試食できるようにしたところ、人が集まるのは前者だけど、売れるのは後者」みたいな実験についていろいろ載ってます
具体的な事例

さまざまなバイアス、判断ミス、感情的なふるまいによる損失から逃れるために、どのような方法があるかが後半に紹介されている。
基本的にはルールを作って機械的に動くことがパフォーマンスが良くなるということらしい
間違った考えを軌道修正するのはほぼ不可能だということと、事実ではないことから身を守るためのシステムを設計するほうがはるかに良いということを知っておく必要がある。
バブルの話
本書の最後の方にあった「バブルが崩壊するのは半分強に過ぎない」という部分が興味深かった(バブル=2年以内に100%高騰した事象、崩壊=2年以内に40%以上の下落)

長期の積み立てについて
インデックス投資も、時期が悪ければプラスになる前に投資家本人が寿命で死んでしまう場合がある。
それを防ぐための一例として、月足終値が10ヶ月平均を上回るときだけ買う、という方法が紹介されている。

S&P500だとこんな感じ(2023年3月現在)

行動経済学?
最近、行動経済学は実験に再現性がないのでは?という批判もあったようなのでリンクを置いておきます。
こちらもどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
