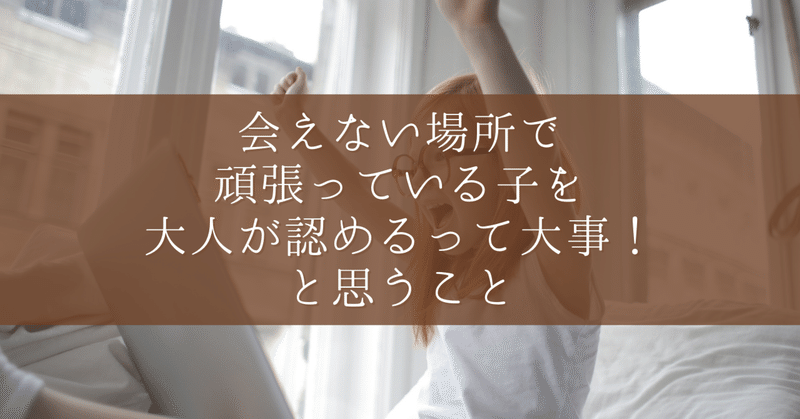
会えない場所で頑張っている子を大人が認めるって大事!と思うこと
コロナ禍により学校でのオンライン授業が実施されている地域が増えました。そこで、最近、ニュースで目にすることが増えてきたのが、
オンライン授業は出席扱いにならない。だけど、欠席扱いにはならない
という内容です。
保護者から、この先の進路や内申に響くのではないかと不安の声が上がっているということで、再度、文科省から学校へ通知するそうです。
ただ、その内容は、教育新聞の記事によると
「ルールを変えることは現時点では考えていない」と指摘し、登校できない児童生徒は「出席停止・忌引等」として扱い、オンライン授業は特例として記録するという、従来の対応を堅持する考えを示した。
ということでした。
結論は、
欠席扱いにならない。つまり、出席すべき日数から日数を減らすから欠席としてカウントされません。出席すべき日数が減ったのだから、出席として扱う必要はない。
ということですね。
具体的にいうと
出席すべき日数が10日ありました。
オンライン授業に2日出席しています。
ということで、
出席すべき日数10日-オンライン授業2日=出席すべき日数8日
という計算になるということでしょう。
私は、それは根本的な解決になっていないと感じています。
なぜなら、オンライン授業だって、子供たちも先生も授業をしているから。
しかし、今の規定は
登校による対面授業に出席すれば、通常と同じく出席扱い
(教育新聞記事より引用)
となっており、オンライン授業は特例手段。だから、出席扱いにはなりませんという解釈です。
実はこれ、今、始まった課題ではありません。不登校児童が、自宅にいてオンラインで学習しても同じ取り扱い。つまり、基本的には欠席扱いです。
ただし、自治体によっては出席扱いになる地域があります。
つまり、地域によって、学びの評価基準が違うということでしょうね。
学校に行けない。または、行きづらい子供たちは、対面授業が受けられないことで、どんなに違う場所で学んでいても出席としては認められないのが現状です。
ということは、結果的に、不登校や不登校傾向の子供たちが安心できる場所で過ごしづらい状況を作り出している気がします。
なぜなら、学校の先生や親から
「学校に行かなくちゃ」
と言われ、どんなに頑張っても行けない。
「じゃあ、仕方ないから学校に行かなくていいよ。」
という状況にならないと、子供たちは安心できる場所で過ごすことができないから。
そうではなく、本当の意味で、子供たちが安心できる場所で過ごしていいと、大人が言っていると感じてもらうためには、学校以外の場所で学んでも学習していると認める体制が必要だと思います。
その1つとして、オンラインで学べたら出席扱いにする。
これが、どのくらいの効果があるかは、子供たちや子供たちと真剣に関わっている大人じゃないとわからないのかもしれません。
・出席扱いではなく、欠席扱いにはならない。
・オンライン授業は特例措置。
と、目の前の緊急事態の対処だけに目を奪われていると、
未来を見据えた時、本当に必要な制度が何なのか。
見えないのかもしれませんね。
学校に行く行かないが、本当の意味で子供たちが選択できるようになることで、学びの多様性が認められるのでしょう。
そうなる日が、1日も早く来ることを願っています。
ひとり親でも、不登校でも、学ぶことや働くことを諦めないでやっていることをシェアするための活動費として使わせていただきます!
