
【マチメグリ】HBPワールドツアー訪問記:海外視察報告会 大阪編・東京編(2018/8/10公開)
7/27(金)・28(土)の2日間、ドイツ・デンマークへの海外視察報告会を実施しました。
計50名以上の方に会場までお越しいただき、楽しく、かつ白熱した議論も生まれる報告会となりました。
その様子をレポートにしてご紹介します。
今回の報告会では、訪れたまちの事例をただ紹介するようなものではなく、
それぞれのメンバーが各自でテーマを設定し、20分ほどにまとめて発表しました。
そして各自のプレゼンの最後に、旅で撮影した膨大な写真(約3万枚!!)の中から
その旅を象徴するような一枚を選び、発表をしめくくりました。
それぞれのテーマは以下になります ⇓
★泉編『ツアー概要』
★岸本編『都市における食の役割』
★有賀編『自治のあり方と、その持続可能性について』
★園田編『都市デザインの力と本質的なガバナンス』
発表内容は、リンク先のブログ記事に記載していますので、ぜひご一読下さい。
以下レポートでは各会場の様子や、プレゼンの最後に行った旅の1枚、質疑応答の内容をご紹介していきます。
大阪編:『デンマークビールとカーリーウルストの夕べ』
大阪編の開催は夜風の気持ち良い中之島公園での野外開催。
デンマークのビールである、カールスバーグの生ビールと、ベルリン名物・カーリーウルストを振舞っての、
和やかな会となりました。


□暑い…けど昼から会場設営。ビールサーバーも準備しました。


□ちょうど報告会が始まった頃に日没を迎えました。
—————————————————————————————————————————————————————-
※前半が始まりました⇓
【泉『ツアー概要』】
今回の旅の大きな目的のひとつでもあった、ヤン・ゲール事務所への訪問内容を中心に、今回のツアーの旅程や訪問先の概要を紹介しました。

★旅の一枚

これはコペンハーゲンの施設なんですけど、ついこの間出来たごみ処理場です(Syndhavns Recycling Center)。これ、実は上がスキー場になってるんですよ。あと、それ以外にも子供たちが遊べる空間があり、遊びながら産業廃棄物の勉強ができます。デンマークはエネルギー政策も進んでいますが、普通は近づかない産業廃棄物処理場のような所を、子ども達が楽しく過ごすような所に変えてしまう所がさすがやな、と。思ったらとことんやる民族だなと感じました。
【岸本『都市における食の役割』】
世界一予約の撮れないレストランコペンハーゲンのNOMA(ノーマ)を始め、廃棄物スーパー・レストラン、ビーガンレストランなど、多様な食のあり方をシビックプライドや持続可能性、食の主義などの切り口で紹介しました。


★旅の一枚

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”kishimoto.jpg” name=”岸本”]
NOMAでテンションが上がる泉さん、を紹介したい訳ではなくて、左側の男性を紹介したいんです。彼は料理のサーブをしてくれる人なんですけど、まず最初に受付に行くと彼が出迎えて、どこから来たの?と明るく話かけてくれます。彼がいるだけでお店がハッピーになるようなムードメーカーです。
実は彼は共同経営責任者の一人なんですけど、その前はNOMAで11年間皿洗いをしていたそうです。しかも彼は移民なんですが、NOMAの料理人であるレネは、「彼はNOMAの心だ、かれは移民で生活も苦しいはずなのに、いつも周りをハッピーにする、そういう人が組織にいることはなかなか評価されないが、NOMAではそれを評価したい」といって共同経営責任者の一人に迎えたそうです。NOMAが体現したい根源的な食の楽しさを、料理だけでなく社会のあり方としても問うているのがすごいと思いました。
【質疑応答】

Q.大阪でNOMA的なお店というのはあるのでしょうか?
[大阪でNOMAに近いというと、大阪割烹のスタイルはとても近いのではないかと思います。北新地の「弧柳」さんへ行ったことがあるのですが、カウンター越しに会話が生まれたり、ひとつひとつの料理についての説明があり、コミュニケーションの中から人によって出すものを変えたりだとか、店内でただ食事をする以上のことが起こっている。ごはん+会話があり、食の場に楽しさがあるのは近いのではないでしょうか。
Q:コペンハーゲンの冬は寒いイメージがあるのですが、季節に合わせた川沿や自転車などの工夫はありましたか?
コペンハーゲンの冬、確かにめちゃくちゃ寒いんですね。でも冬でも自転車で走れるように、レインウェアが準備されていたり、タイヤやブレーキが雪でも走れるように整備されていたしました。それから、僕らが行った時は少し気温が低くて、上着がないと寒いくらいだったのですが、それでも公共空間で普通に人が寛いでましたね。ちょっと日本とは感覚が違います。
それから、少し話がそれますが、デンマークは福祉がすごい、幸福度が高いとか言われますけど、個人の収入の7割くらいが税金なんですよね。だから当たり前のように行政が「市民が幸福に暮らすために」と発言するんですよね。僕はそれがあまりにも優等生過ぎて、ちょっと気持ちが悪いなと思ってしまった。何でも政府直轄で全てコントロールされているシンガポールでも違和感を感じたことがあったんです。それとは少し違うんですが、デンマークもやっぱり頭の良い人達がちゃんとコントロールしてて、でもそれがあまりいやらしく感じない、という不思議な国だなと感じました。基本的には全て保障されていて、仕事は職種ごとに労働組合があるので、大企業でも小さな企業でも同じ職種だと給料は同じなんですよね。飛びぬけるというよりは、80点とればOKみたいなところもあって、それを続けることで国全体としてのレベルもあがっているというシステムも面白いなと思いました。
Q:NOMAなどの高級ラインは日本にもあると思うのですが、廃棄食品レストランやスーパーのようなものは、日本にとって取り組みづらいけれど必要なものだと感じます。日本に導入される動きや可能性は感じましたか?
日本でも可能性はあると思います。廃棄物スーパーは、商品仕入れの為に大型スーパーと組んで運営しています。その構図は日本でも成り立つものだと思います。そういうものを受け入れる価値観を持っている人は確実に増えていると思うので、出来る可能性は感じています。
出来るか、というよりもやっていかなきゃいけない、と僕は思います。紹介のあったレストランも、最初は週2回でやっていたのが月1回になったそうです。コペンハーゲンにも賞味期限切れ食品を扱ったレストランがあると聞いて見に行ったんですけど、そこは閉店していました。資本を確保して、仕入れもメニューも相当クリエイティブにやらないと成り立たないと思います。やり方によっては残飯のようにも見えかねない訳ですから。スキルは求められているけどお金はそれほどもうからない。問題意識をもっている国でも経済的には難しい。その中でどう成り立たせていくか、難しいけれども考えていかないといけない問題だと思います。
—————————————————————————————————————————————————————-
※休憩をはさんで後半戦へ!
【有賀『自治のあり方と、その持続可能性について』】
ベルリン・ホルツマルクルト、ハンブルグ・ローテ、コペンハーゲン・クリスチャニアという背景の違う3つの自治的地区を取り上げ、持続可能な自治のあり方や問題点について考察しました。



これはハンブルグの「ローテ・フローラ」と呼ばれる劇場と後ろに広がる公園にある、クライミングウォールですなんです。これは防空壕の跡を利用したもので、壁全体がグラフィティに覆われています。誰でも自由に使用することが出来、行った時にもグラフィティを描いている人がいました。日本でやろうとすると安全面だとかグラフィティの問題でなかなかこうはならない。こういう風な突き抜け方は自治だから出来ることかなと思います。自己責任で好きにやる、というか。これ目の前に子どもたちの遊び場があって、何も区切っていないんですね。子どもたちの生活のすぐ近くにこういう場所があることはすごく豊かだなと思います。
【園田:『都市デザインの力と本質的なガバナンス』】


★旅の一枚

これはマルメのボードウォークの先にある、海で泳ぐための桟橋です。手すりもないんですが、これが地区の海沿いに3つ出ているんです。だんだん写真を引いていくと分かるんですが、どこにも堤防がなくて外海に繋がっているんです。危険ではあるんですけど、こういう最小限のものをデザインして、シンプルなものをつくるというのが北欧のデザインの根底にもあるのかなと思いました。
今回ゲールアーキを訪問しても感じたんですが、僕らの仕事っていうのは別に欧米に追い付け追い越せで仕事してるんじゃないんですよね。根本的に人間として感じていることは通じ合えるし、だからディスカッションが成り立ちました。今回行って、本当の意味で世界にはボーダーはないなと思いました。
【質疑応答】
Q:クリスチャニアはどのような人たちがコアメンバーとして運営しているのでしょうか?自治会などが組織されているのでしょうか?
クリスチャニアには自治会があり、合議制で運営されています。基本的には多数決なんですが、80対20くらいの割合だと結論は出さず、9割以上が賛成になるまで何時間でも話し合うそうです。また、クリスチアニアに新しく住む人は、今住んでいる人の全員の合意がないと住めないという仕組みなっています。元々同じような意識を持っている人が住んでいるので、意思決定はしやすくなっているようです。一方で、ヒッピーの人たちと、その後から入ってきたもう少し緩やかにヒッピーを体現している人たちの間で意見対立が起こり、問題になっている側面もあるようです。
Q.先にスケートボードパークを作ってから集合住宅を作る、という話がありましたが、そこまでしてスケーターを守るということにはどういう判断があったのでしょうか?
厳密に開発サイドに取材した訳ではないのですが、案内して下さったデイビッドさんに聞いた限りでお答えすると、あちらでもやはりスケボーをしている人はマイノリティみたいなんですね。けれどスケボーはスポーツで決して危ないものではないし、趣味嗜好のひとつとして認められるべきものであるわけです。そこで新しく作る地区のアメニティとして取り入れることで、この地区の多様性を表すひとつの表明になるということは言っていました。既成市街地ではなかなか出来ないけれど、新しく作る地区にはそういうものを取り入れていく。開発自体はマルメ市と複数の企業体でやっているようですが、そこと協議しながらそのような開発のやり方をした、と言っていました。
Q.1970年代まだ橋や鉄道が開通していない時代に、何度かコペンハーゲンからマルメにフェリーで足を運んでいました。「コペンハーゲン・マルメ間に橋が出来た」ということの効果をどのように評価しますか?経済的な発展や、食などの文化交流は起こっているのでしょうか?私は高松から来たのですが、四国の場合は橋が出来たことによりストロー現象で本州に人が吸われている、と感じます。四国では地元が期待したような効果は得られていないと思っています。
実状としては、マルメはどんどん人口が増えています。また企業誘致を進めていたり、国内の大学を移転させたり、インキュベーションのようなことも起こっています。コペンハーゲン-マルメ間は距離的に20-30分なので、ベッドタウン的な性格も影響していると思います。
コペンハーゲンがあるからマルメの人口が増えているということは言えると思いますね。食についてはデンマーク料理はまずいと言われていたのが、この15年で大きく変わっているそうです。なぜそんなに変わっているかというとやはり「国策」だから相当力が入っている。日本は飲食店はあくまでも個人シェフベースですが、食を国策としてしている所は違います。デンマークの場合は、NOMAを国がバックアップしているのですが、NOMAが出来る、と決まった段階から映画を撮り始め、研究所を作って全正解にPRし、世界のコンテストで賞を取っていく。食については橋などはあまり関係なく国策という側面が大きいです。
四国についてはおっしゃる通りストロー効果になっていると思います。とはいえそれはどこでも起こる話で、アクセスはどんどん便利になっていく中で、そこにどれだけ人を引き寄せるコンテンツのようなものを埋め込んでいくか、ということが大切だと思います。橋が出来たらハッピーという発想は妄想です。橋のあるなしに関わらず、そこで何をするか、が重要だと思います。
【最後は全員で記念撮影!】

東京編:『ドイツ・デンマークの都市デザインを巡る旅』
翌日の東京開催は、台風が上陸中の中での開催になりましたが、多くの方にご参加いただきました!

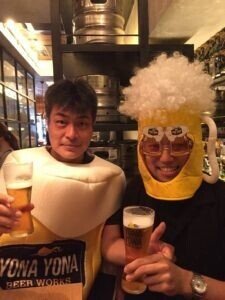
□台風と共に東京に向かいます。始まる前に喉をうるおす。
※プログラムについては大阪編と同様ですので、写真にて雰囲気をお伝えします!












【質疑応答】
Q:NOMAの料理は7万円の価値があるものだったでしょうか?率直に聞かせて下さい。
NOMAの美味しさは奇をてらっていなくて素朴なところにあると思います。味の感想を正直にいうと、ちょっとすっぱいかなと笑 国の味付けがあると思うので。ただNOMAはこの空間を体験出来ることに私はすごく価値があったと思うし、もう一度いけるなら行きたいです。ちなみに大阪でも同じくらいの値段の所に行ったことがあるのですが、そこはシェフの世界感を体験する、というような料理でした。NOMAはあくまでも食の楽しさをきちんと丁寧に伝えていることが他とは違うと思いました。
Q:泉さんが紹介していた、コペンハーゲンの産廃処理場の様なものが何故日本で出来ないのでしょうか?日本ではゼネコンがあの規模ものを作るわけですが、ランドスケープ的な観点はほとんど入りません。そもそもそのための予算も組まれていないし、公共工事の要件に入ってこない。なぜそれをデンマークが出来ていると思いますか?
いやぁ、僕も知りたいですよ笑 こういうものを普通にやっているのがすごいです。日本だと機能をきっちり作ることが重要視されて、他の要素は入らないんですよね。
でも例えば、大阪では今回一緒に旅をした建築家の岩瀬さんが設計した「トコトコダンダン」という木津川沿いの遊歩道があるんです。この遊歩道のコンペは日本初の形で行われました。普通は河川の遊歩道は土木設計なので土木コンサルタントしか設計出来ない。でも今回は大阪府の河川課とアート関係を取り扱う文化課が組んで、最初のデザインを土木だけでなく建築家やデザイナーにも門戸を開いたんです。それで最初に5人選んで、それぞれに土木コンサルをつけて構造的にどう成り立たせるかということを担保した。その中で選ばれたプランが実現された結果、すごく良い遊歩道が出来ています。
そういう風にやっぱり民間だけでなく、行政でも全然違う所と組まないと面白いものは成り立たないですね。
Q:日本は食が豊かだと思うんですが、食で都市をプロモーションしていくのはことごとく失敗しているように思います。NOMAにしても、ベルリンの話にしても、個々の根付いている文化に対して店が頑張っている印象を受けています。日本で食での都市プロモーションが成功するにはどのようなことが必要なんでしょうか?
NOMAなどは国がものすごくバックアップしています。NOMAはコーヒーの世界でも知られていてすごい賞を取っているのですが、世界の〇〇というような世界的な評価ランキングにランクインするということを目標に定めるとそのために国を挙げて尽力する。それに比べると、やはり日本は個々のお店の取り組みに終始しているし、国も任せきれない。私としては発信するための権限をもう少しシェフに与えるべきだと思います。
日本で一番積極的に取り組んでいるのは鶴岡ですね。ユネスコのクリエイティブシティーのガストロノミ―部門で唯一手を挙げています。デンマークではニューノルディック料理の10か条を打ち出したり、複数の店舗を国が国策としてバックアップしている。ベストレストランの審査員も買収してますからね笑 世界をみても美食都市サンセバスチャンでも、国や食品メーカーが相当お金を出していて、教育機関をつくったり、世界にPRしたりしています。その結果、最終的にはやっぱり観光で戻ってくる。お客さんが来ると周辺の産業も潤うわけです。フランスなどもお客さんが来て食が潤えば産業が潤うので、食を通して世界のリーダーになる、という崇高な目的があるわけです。日本でちょっとあそこのお店頑張ってますね、なんとかグルメ大賞で表彰しましょう、というレベルとはちょっと訳が違うなぁと思いますね。
Q:「自治」というのが僕も好きではあるんですが、表現の自由を広場や公共空間で守ろうとする、基本的な合意が国民全員に浸透しているを感じました。また、ヒッピーとパンクは仲が悪いと思うんですけど、どちらかというと新しい仕組みを作って生き抜いていく、という姿勢ヒッピーというよりはパンクぽいなと思いました。
ドイツの人に話を聞くと、ドイツ人というのは自己の決定をめちゃくちゃ重んじるという風土があって、誰かの表現を尊重する、という雰囲気が自然にあると思います。デンマークはについていえば「デンマークは85%の国だ」という事をききました。みんなそれぞれに、おこなったことや表現を尊重する。みんな「いいねいいね」と言ってくれるから、85点くらいのものは自然に出来るようになっている。でもその反面突き抜けるものは生まれない、ということでした。それぞれに少し違いはありますが、どちらとも個人の表現を尊重する所は共通しています。
ヒッピーの話についていえば、最近ヒッピーが資本化しているということは言われていて、インテリの人たちもヒッピーの文化に入ってきていてます。クリスチアニアも住人のほとんどは外で働いていて、弁護士の人や建築家の人などもいます。元々あったヒッピーの世捨て人的な要素から、もう少し社会に適応しながら自由に表現していくという方向に移り変わってきているということはあると思います。[
自治の話で付け加えると、自治の単位で最も大きくなるのは「自治体」ですよね。ドイツのドルトムントで行政関係の方に聞いたのは、自治体とはいえ当然まちの経営者であるし、必要な最低限のインフラはきちんと投資する。でもその上で個人の趣味嗜好の中でいろいろと行うことは基本的に当人同士でやるもんだという意識は感じました。行政サービスのクオリティは高いんですが、規制はそれほどないんです。行政が、民間が、公民連携が…という話ではなく、行政はみんなのお金を預かっているだからやるべきことはやりますよ、という姿勢が日本とは決定的に違うと感じました。
Q:様々なプロジェクトを行ってきたハートビートプランが自治に注目しているのは面白いと思いました。立場の違う人たちがカルチャーによって繋がって、役割やセクターを超えるような動きが、クリスチャニアやホルツマルクトではあったと思うのですが、それに類するようなことが日本ではどのように実現されると思いました。
それは僕もものすごく大きいテーマだと思っています。ホルツマルクトはクラブカルチャーが元で集まっているし、政治思想やヒッピーというライフスタイルなど、自治をする単位というのが、そこに起こる事象が好きだから集まっているということになっています。自治会・町内会というような土地に縛られた自治組織ではないんですよね。日本において悩ましいのは、そういうカルチャーや思想で集まる組織体が公共空間を管理するという指針はなくて、結局自治会などでないと認められない。うまく自治会などを活用しながら、そういう方向にシフトしていける方法はないかなと僕もすごく悩んでいます。土地に縛られるのではない自治のありかたを何とか実現したいと思っています。
今は地縁の世代からテーマ型のコミュニティに移ってきていると言われていますよね。今進めている具体的なプロジェクトだと、愛知県豊田市のプロジェクトでは、スケボーをやる人たちと一緒に広場を活用しようという動きがあります。全面的に禁止にするわけでなく、きちんとしてもいい場所を設けてその人たちの自主ルールのもと運営していくような場所を作れないかと取り組んでます。行政側が意思決定していく時も、顔の見える使いそうな人が自分たちの責任のもとやりたいと言ってきたことは民意と捉えて、任せていくことが必要かなとおもいます。僕らは仕事の中で地縁のみによらない枠組みを作りたいと思っているし、そういう枠組みが作れれば、こういうことが出来るんだよ、ということをプロジェクトの中で示していきたいと思っています。
【こちらでも最後は全員で記念撮影!】

—————————————————————————————————————————————————————-
これまでさまざまなプロジェクトに関わってきたハートビートプランですが、
実は会社主催としてこのようなイベントを行うのは初めての事でした。
せっかく2拠点で行うのだから、来た人に楽しんでもらいつつ、見て来たことや考えたことについて意見交換できるような場となるように、またハートビートプランのメンバー、それぞれの個性が現れ、ハートビートプランという会社が目指すものをもっと知ってもらう機会となるように、プログラムを組み立てていきました。
メンバー一同、楽しく白熱した、実り多い時間を過ごさせて頂きました。
今回のツアーで得た知見や、報告会での発表や議論も活かしつつ、
今後もプロジェクトに取り組んでいきたいと思います!!
みなさん、ありがとうございました!
(山田友梨)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
