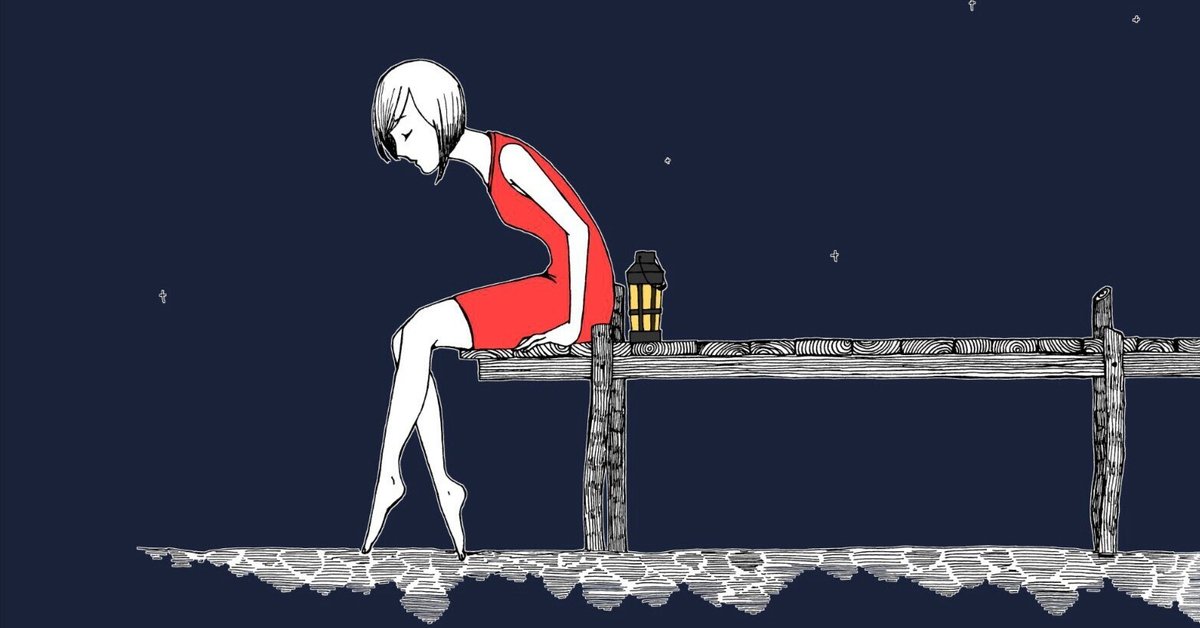
「静かな夜のマーレ」第6話
「今夜は平和でよかったねえ~、チェンさん?」
安いウィスキーを飲み過ぎてすっかり出来上がってしまっている ”ディー ”は、カウンターを枕にしながらカットグラスの輝きをキラキラと見つめている。深夜0時、”レジテ・ソーシャ ”は閉店時間を迎えていた。
「あなタ、働きもしないで飲み過ぎデショ」
店長のチェンがたしなめるのは無理も無い。このディーなる大男は勝手にこの店に居着いて勝手に酒を飲んでいる無法者で、「俺はこの店が気に入った。ここにいる時間は用心棒をするからタダ酒を飲ませろ」と、半分押しかけ状態で今の地位を勝ち取った男である。店にいない時間はどこで何をやっているのかはわからないが、店で問題を起こしたならず者たちをときには話術で、ときには拳で従えてきた実績から、どうやら同じ穴のムジナではないかと専らの噂だ。ただし他人の過去をあれこれ掘り返さないのがこの街のルールでもあるので その真相は本人しかわからない。
「昨日はちゃーんと働いただろお? 好きでもねえ野郎2人とお遊びしたから、かわりに今日は何もしなくて良い日だったのだねえ~~?」
「ディー、無理させてごめんね」
最後の客を見送ったリコが後ろから声を掛ける。
「いいよいいよぉ、店の前にゴミが落ちてたから遠くに捨ててきただけさ。それよかオマワリがろくに仕事しねえからイライラするぜ。イラついてたからさ、ちょっと殴っちゃった。へへ」
悪びれもせず、さらっと恐いことを言う。
「それよりもリコちよぉ、あの後ちゃんとあのお姉ちゃんをホテルに連れて行けたのかい?」
「ううん。ラブホもどこも満室だったから家に連れてった」
肩をすくませるリコを横目に、グラスを拭いていたチェンの片眉が上がる。
「ええ~~! リコセンパイの自宅なんて私も行ったことないのにずる~~い」
私服に着替えて戻ってきたタリタ嬢が地団駄を踏むたびに、衣装の隙間から褐色のおへそがチラチラと覗く。
「いやいや、お前さん昨日酔い潰れてソファーでいびきかいてただろ客まだいたのに」
「かいてないし!!」
なんだかんだ、ディーとタリタ嬢は仲がいい。
リコはやりとりを横目で見ながら、確かに自分がなぜ見ず知らずの観光客にあそこまで手を貸してしまったのか考えあぐねていた。
あの夜、外でタバコを吸っていたら、店の前で外国人の女性が男2人にホテルの場所を訪ねていた。彼女は無防備にも、札付きのろくでなしに英語でホテルの場所を聞こうとしていたのだ。店の中で飲むでも無く繁華街をふらついている男のほとんどは「自由恋愛」を売り買いしている客引きか、運が悪ければ昨日のようにクスリを売るクズ野郎である。そんな輩にとって知識のない外国人は格好の標的だ。
――だから。
だから可哀相に思って?
どうにもしっくりこない。
「まあ、昨日はなんとかしたけど リコち、ああいうのはタチが悪いから関わらんほうがいいぜ? バカな上にしつこいからね~。無視が一番」
「そだね。ガラにもなくお節介したわ」
「そういえばあの ”サックン ”ってやつにもまだ金渡してるんかい? たしかにちょっとイケメンではあるけどよ。俺には劣るだろお」
ディーはそう冗談めかしつつタリタ嬢にちょっかいを出して、反対におでこを叩かれている。
「貢いでるわけじゃないわ、ちょっとした仕事をお願いしてるだけ。じゃあ私も上がるね。お疲れ」
リコは適当に会話を切って店の奥へと消えていった。
帰り道、バーから徒歩15分の住宅街をリコはひとり歩いている。街灯はまばらで、知った道でないと恐くて歩けない。もちろんバイクの免許は持っているが、店の周辺に駐車して盗難にあってからというもの、面倒だが歩いて出勤するようになっていた。すべての輝きを繁華街に吸い取られたかのように、住宅地は暗く静まりかえっている。
リコはひとりで歩きながら、昨日の彼女の手のぬくもりを思い出した。二人して雨に濡れて、子供みたいに笑って。手を引いたその一部分に朝日が宿ったみたいに温かく感じたことを、思い出した。今、その手にはひんやりとした小さな鍵が握られている。その鍵をアパートの自室のドアに差し込んだ、その時だった。
「リコちゃん、だよね」
暗闇が喋った。
とっさに鍵を抜いて身構える。
「誰? 姿をみせろ」
「そんな警戒しないでよ。ボクだよ」
暗がりから近づいた影は輪郭を表す。それでもリコにはこの声の主が誰なのかわからなかった。
「ナッポンで一緒に ” 仲良し ”したトンチャイだよ」
ナッポンは以前リコが都市部にいた頃に務めていた繁華街の名前だ。そこまで聞いてようやくこのトンチャイなる人物が誰だか掴めた。と同時に、猛烈な悪寒が足下からよじ登ってくる。
「黙って引っ越しちゃうなんて水くさいじゃないか。お陰で探すのに苦労したよ」
トンチャイは昔のお店の常連で、しつこく関係を迫ってきた客のひとりだった。それなりに金を落とすし店のママからもお願いされて一度だけアフターを共にした相手だった。あの夜を思い出そうとすると心が拒絶してしまうくらいに強引で嫌な男だった。でも、どうして引っ越し先のここがわかった・・? うまく頭が働かない。
「帰ってくるのがこんなに遅くなったってことは、まだ夜の仕事をしているんだろう? 金なら払うからさ、家の中にいれてくれよ」
トンチャイは さも当然といった態度だ。
「冗談じゃない。あの強姦まがいのプレイのお陰で私は次の日病院に行ったわ。店を出禁になってるんだからそのくらい知っているでしょう?」
「――なあ、頼むよその小さな穴が忘れられなくてここまで来たんだからさ。中に入れてくれよ。ああ、中に入れるのはボクだけどさ」
リコは鳥肌を立てつつもきっぱりと拒絶した。
「帰って。もう二度と顔を見せないで。同じ空気を吸っているだけで吐き気がする」
生きる目的の希薄だったあの頃とは違う。今はもう、こんな変態ストーカーに馴れ合っている暇などないのだ。
「なんでわかってくれないんだよボクのお人形さん。だいたいレディーボーイなんてこの街じゃ流行らないだろ。老けてボロボロになる前にたくさん遊んでやるって言ってるんだ」
「・・死ね。」
思わず口をついた言葉にリコは「しまった」と後悔した。男がズボンのポケットから小型のナイフを取り出したからだ。
「わかってないな。別にお願いしてるわけじゃないんだ。めんどくさいことさせないでよ」
リコは意識的に深呼吸をしていた。こちらの分が悪いときの対処法は・・。兵役中に教わった教訓を思い出す。男を刺激しないようにその場でゆっくりとヒールを脱ぎ、胸に抱く。トンチャイは何を勘違いしたのかニヤニヤ顔をくずさずいやらしい視線を送っている。リコは次の瞬間、全速力でその場を走り去った。なるべく暗く複雑な道へ。
「な・・!!」
男はすぐに追いかけようとするが目の前に飛んできた固いヒールを避けることもできず悶絶する。それでも追いすがろうとするが、暗がりの中で道路の凹凸や障害物に足をとられ豪快にすっ転んだ音がした。静かな住宅街に男の唸り声が響く。
その様子をリコは電柱の影から盗み見る。ひとまず危機を脱したらしいが、反撃する手立てなどない。裸足のまま音を立てずにその場を離れることしか、リコにできることはなさそうだった。
――※――
煌々と光る着信画面には「Lico」の表示。内緒で番号を登録してくれていた女神・・! 藁にもすがる思いで真理恵はスマホに飛びつき、必死に声を絞り出す。
「リコ・・助けて・・! 家の前にだれかいるの・・!」
スマホを強く押し付けた真理恵の耳に盛大なため息が吹き込んできた。
「・・・マーレさん。あけてください。扉をあけてください。私は今、あなたの家に来ています」
「・・・は??」
毛布から頭を出して小動物のようにフリーズ状態になっている。何を言っている? リコが家に・・なんで?? 昨日の男とグルになって私を騙そうとしている? いや、そんなはずは。半信半疑のまま玄関に向かう。
「何度もメッセージを送信したのにあなたに気づいてもらえず、私は悲しかった」
ちょっとハスキーな音色で淡々と語られる美しい英語。ドアチェーンを掛けたまま恐る恐る扉を開けて、隙間から外の様子を伺う。すると、そこには疲れ切った顔をした女神が首をかしげたまま恨みがましそうに真理恵を見ている。なぜか、彼女は裸足で靴はどこかに置いてきたようだ。
「ひょっとして酔ってる?」
「いいえ。ここはあなたの家で、夜も遅いので不審に思うのは当然のこと。でももし、このいたいけな美女を助けるならば、その尊い行いはかならず仏様が見ていてくださるでしょう」
( 自分で「美女」って言った・・! それより仏様って・・?)
「一晩、泊めてくださいますよね?」
早朝、まだ世界が青空を思い出していない頃。民家の間にもうけられた小さな広場に朝食用の屋台が1台、商いを始めていた。大きな鍋に湯気が立ち、白髪で日焼けをした老人が麺を湯がいている。その隣にはどんぶりがふたつ。器に魚醤を垂らして、鶏ガラと思われるスープをその上から注ぐ。たいして湯切りもしないまま麺を分け入れ、細かく刻んだ緑色の香草を乗せた。具もなにもないシンプルな料理。
屋台のそばに置かれた小さな長テーブルに丸い背中が二つ。結局寝付けなくて寝不足な日本人の女と、足の痛みで満足に眠れなかった現地人の女が並んで麺をすすっている。
ハイこれ。かけるといいよ
なんです?赤いし、ひょっとして辛いのでは?
辛くないとおいしくないでしょ
いや、そんなことないですし
じゃあこれ
今度はなんです?
砂糖
麺に砂糖とか寝ぼけてます?
両方いれるとおいしいんだよ
・・味覚どうなってるんですか?
お互いを見るでもなく、低いテンションで。
太さが不揃いの短い麺はフォークで食べにくさがあるものの、思いの外スープに良く絡んで潮の香りを口の中に運んだ。冷めることもないスープからは湯気が上がり続け、まるで蒸し器に飛び込んだみたいに顔を覆う。熱々のもちもち麺が喉を降りていくと、深い夜を超えた身体の芯に火が灯ったみたいだ。
これは、沁みる・・。
ほふほふ。はふはふ。鼻をすすりながら。
まだ騒がしくない早朝の空気の中に、ふたりの食事の音だけが耳に届いた。優しい薄味のスープも飲み干して、他愛も無い会話をひとしきりした後、美女はおもむろに尋ねた。
「決まった?この国でなにをするか」
う――ん
少し考えて、日本人は答えた。
「そうですね。まず、海を見に行こうと思います」
2人ははじめて目線を通わせて、そして笑った。
――いいね。そうこなくっちゃ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
