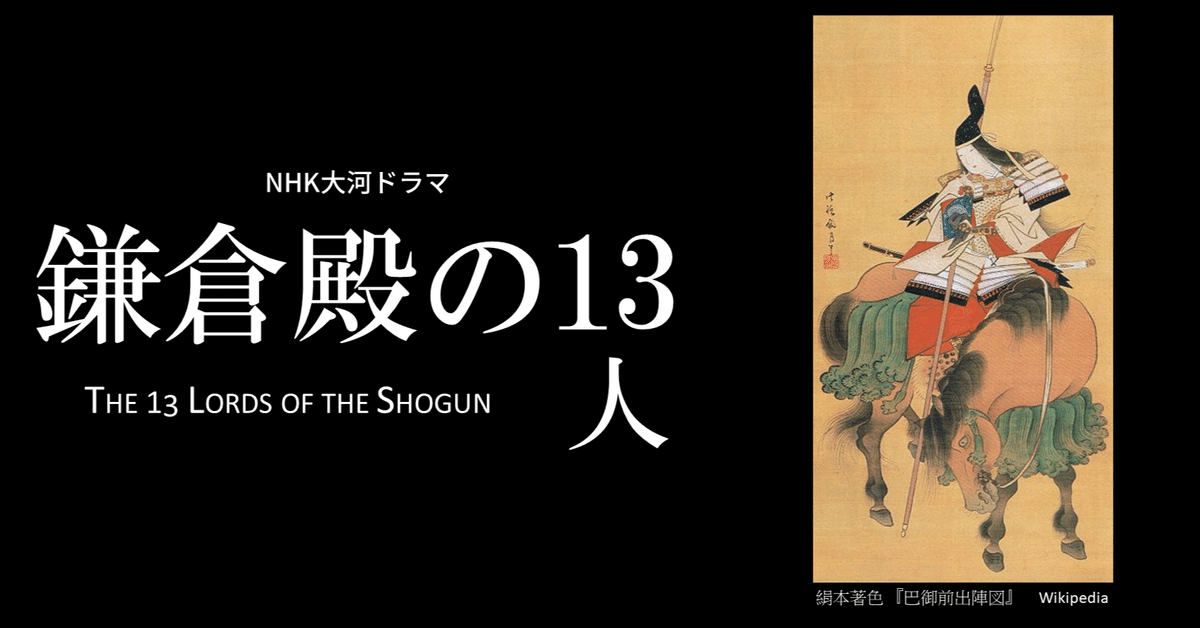
【感想と解説】NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』第16回「伝説の幕開け」
2022年4月24日(日)20時放送、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』第16回「伝説の幕開け」を視聴しました。
<始まる前に>
さて、今回から義仲、平家討伐へと進むようです。
義経の活躍をどのように描くか?気になります。
通説のように義経は英雄なのか、あるいはそれほど大した者ではなかったとなるのかな?
<NHKのあらすじ>
御家人たちをまとめ上げた源頼朝(大泉洋)は、弟・範頼(迫田孝也)を総大将、梶原景時(中村獅童)を軍いくさ奉行とした本軍を派兵。
八重(新垣結衣)に見送られた義時(小栗旬)も従軍し先発した義経(菅田将暉)と合流する。
後白河法皇(西田敏行)を捕らえて京に籠もる木曽義仲(青木崇高)、福原を拠点に復権を伺う平宗盛(小泉孝太郎)に対し、鎌倉方は義経の天才的な軍略に導かれて奮戦。
畠山重忠(中川大志)らが華々しく駆ける……
■プロローグ
八重と義時の嫡男は頼朝によって金剛と命名されました。
誰かに落ち度があればその所領が自分のものになる、疑われぬよう時政(坂東彌十郎)が政務に復帰しました。
「北条が生きていく手立てはただ一つ、源氏に食入り従うこと」(時政)
---曲---
エバン・コール
■ナレーション(長澤まさみ)
大きな代償を払い、頼朝は、御家人たちをまとめあげた。
義経は鎌倉からの援軍を待っている。
戦が近づいている。
■政子たち
政子(小池栄子)は、御家人たちの駆け込みどころという役割を演じる決意をします。
子を作ることが役目というりく(宮沢りえ)は、最低三人は必要、北条の跡継ぎを生んで見せると宣言します。
■鎌倉殿
頼朝は、義仲を成敗することを宣言、総大将は源範頼、軍奉行は梶原景時、留守居役は北条時政と比企能員。
やぶったら、義仲の所領、平家の所領を分け与えることになりました。
■八重と義時
義時は幼い金剛を残し、戦にでることになりました。
■先発隊と合流
範頼(迫田孝也)と義経が久しぶりの再開です。
義経は約束を破り木曽の兵と小競り合いをしてしまい、範頼は自分が命じたことにすると義経をかばいます。
■京・義仲の館
盟約を結んだはずだと、文を頼朝に出すよう指示する義仲、まだ頼朝を信じているようです。
■作戦会議
「京を攻めるなら、瀬田と宇治だ」(義経)
義時は和田と梶原の内輪もめを諌めます。
そこに義仲より文が届きました。
そこには、ともに平家を倒したいと書かれていましたが、文を持ってきた使者の首をはねて送り返せと義経は残酷にも言い渡します。
義仲がまだ仲間だとおもっていることを察した義経、軍勢を少なく偽る噂を流すよう命令します。
■義仲軍
使者の首が届き、怒りまくる義仲、ここは挑発に乗ってはならぬと落ち着きます。
義経軍が1000人の軍勢で南に下ったという情報が入ります。
鎌倉に兵を残したと誤解した義仲、軍勢を見て、してやられたことに気づきます。
京を捨てることにしました。
■宇治川の陣
敵の目を他に向け、先陣争いをしているすきに、畠山重忠が川を渡るという作戦です。
■京・院御所
義仲は、後白河法皇に北陸に向かうことを告げます。
義仲が果たせなかったことを必ず頼朝が継いでくれると信じ、一目法皇にお目通りしたかったが不徳の致すところ、もう合うことはない、と語り去っていきました。
「手前勝手は平家と変わらんわ」(後白河法皇)
■鎌倉軍
義経勢が京へ入りました。
義経は、後白河法皇に謁見します。
体を休めろという法皇に、休んでいる暇はないと拒否、平家を滅ぼすと宣言します。
■義仲
京を出た義仲は、近江に向かうが範頼の軍勢が待ち構えている。(長澤まさみ)
義仲は、巴御前に落ち延びるよう、わざと捕らえられろと指示します。
巴御前(秋元才加)は途中、敵に捕まり、争いとなりますが、和田義盛に捕らえられ保護されました。
義仲と息子は、もはやここまでと悟り、ここで自害して果てようとしたとき矢が頭を撃ち抜きました。
■鎌倉殿
土肥実平(阿南健治)からの書状には、とても読めたものではない字で書かれていました。
和田義盛(横田栄司)からの書状も読めたものではありません。
義時の書状は、内容が細かすぎて入ってきません。
梶原景時(中村獅童)の書状は実に読みやすく見事な出来栄えです。
しかし、その内容は義時から朝一番で知らせが届いていたのです、義仲を討ち取ったと。
一方、義高を決して死なせたりしない、政子の決意です。
■京・範頼の陣
梶原景時の作戦では、北から攻め、義経軍が敵の脇腹をつくというもの。
それに義経はダメだしします。
義経の作戦は、「意表をついて山から攻めるのは子供でも思いつくこと。敵に手の内をみせ、それぞれの兵力が弱まり、予想外のところから攻める」というものでした。
しかし、どこから攻めるかはは、考え中だといいます。
坂東武者は口だけか、と挑発。
梶原景時は、九郎殿が正しいとその策を認めました。
九郎の策で行くことに決まりました。
「戦神・八幡大菩薩の化身のようだ」(梶原景時)
義経は、法皇に文を書き、平家に和議を申し出るよう法皇に指図いただくことを義時に命じます。
法皇様のことばを知らなかったことにする、だまし討の何が悪いという考えです。
■後白河法皇
「平宗盛に文を出せ。平家をハメるのだ、こういうのが大好きじゃ」(法皇)
「今度の源氏の大将と法皇様と気が合いそう」(丹後局/鈴木京香)
■義経軍
福原に向かい、山中を進みます。
断崖絶壁の中でなだらかな場所が鵯越です。
鉢伏山という崖の山を降りることを考えつきます。
梶原景時は多くの兵士が無駄死にすると反対します。
「誰が馬に乗っていくといった、まず馬を行かせ、次に人が行く。戦に見栄えなど関わりない」(義経)
■八重
三浦義村(山本耕史)は自分の赤子・はつを八重にみせます。
この子を生んだ女性は、産後死んでしまったそうです。
義村は、はつを八重に強引にあずけてしまいました。
■鉢伏山の断崖
畠山重忠と義経は断崖の上に居ます。
鹿の糞があるということは馬も降りられるということ。
「糞に命運を賭けた!」(義経)
福原の東、生田口で範頼軍と知盛軍がぶつかる。
一ノ谷の戦いとわれる源平合戦最大の攻防が始まった(長澤まさみ)
■平家本陣
戦では劣勢という報告を受けた平宗盛ですが、安徳天皇に敵は入ってこないと安心させます。
■義経
八幡大菩薩の化身・義経が敵をなぎ倒します。
----つづく----
次回は第17回「助命と宿命」5月1日放送です。
■感想
今回は義仲の最期がメインテーマでした。
悲劇のヒーロー義仲が、悲劇のヒーローになる義経に討伐されるのは歴史の皮肉ですね。
通説の野蛮で粗野な義仲というイメージを見事に覆してくれました。
生き延びたとみられる”眉がつながった”巴御前は今後、どう描かれるのかも気になります。
話の流れとしては和田義盛の妻になるのでしょうか?
■勝手に解説
木曽義仲は、法皇がたてこもる法住寺合戦に及んで法皇と後鳥羽天皇を幽閉し、寿永三年(1184年)1月15日、自らを征東大将軍に任命させました。
義仲は京都の防備を固めるものの、法皇幽閉などにより既に世間の不評を買っていたため、義仲に追従する兵はほとんど無く、北国に逃げる途中、宇治川や瀬田での戦いに惨敗し(宇治川の戦い)、源頼朝が送った源義経とその兄・範頼の軍勢により、粟津の戦いで討伐されました。
1月26日、後白河法皇は、頼朝に平家追討と三種の神器奪還の勅令を出し、平氏一族の所領500余ヶ所が頼朝へ与えられました。
そして、寿永三年/元暦元年1月、一旦北九州の太宰府に落ち延びていた平氏は、みるみる勢力を立て直し、瀬戸内海を制圧し、中国、四国、九州を支配し、大輪田泊に上陸、福原まで進出していました。
平氏は数万騎の兵力を擁するまでに回復し、同年2月には貴族や義仲との連合軍を画策し、京奪還を起こすまでに計画を練っていました。
寿永三年/元暦元年(1184年)2月4日、義経は搦手軍1万騎を率いて播磨国へ迂回し、三草山の戦いで夜襲によって平資盛、有盛らを撃破し、範頼は大手軍5万6千余騎を率いて出征しました。
平氏は福原に陣営を置いて、その外周(東の生田口、西の一ノ谷口、山の手の夢野口)に強固な防御陣を築いて待ち構えていました。
2月6日、福原で清盛の法要を営んでいた平家へ後白河法皇からの使者がやってきて、和平を勧告し、交渉中は武力を行使しないよう命じました。
平家はこれを真に受けたため、警戒を緩めていたところに源氏の総攻撃があり、戦いの勝敗を決したといわれています。(諸説あり)
2月7日、一ノ谷の戦いで義経は精兵70騎を率いて、鵯越の峻険な崖から逆落としをしかけて平氏本陣を奇襲すると、平氏軍は大混乱に陥り、鎌倉軍の大勝となりました。(鵯越の位置については諸説あり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
