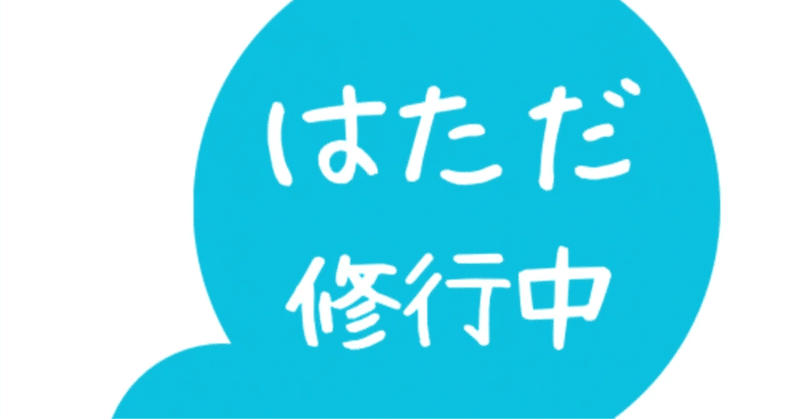
費用対効果をきちっと計測しよう。
PRESIDENT Onlineで、「年功序列で働く日本企業が世界に太刀打ちできるわけがない…日本企業の給料が一向に上がらない根本理由」(谷本真由美)という記事を読みました。
日本人の給料が上がらない理由のひとつとして、まず、「日本企業のアウトプットが増えていない」という点が指摘されています。
にもかかわらず、インプットが多い…と。
その例として、「6,500円かけて、1,000円のラーメンを売る」と表現されています。その比喩の具体性を検証できませんが、言わんとすることはイメージできます。
日本企業がこのような状況になっていることの原因のひとつとして、「外国なら15分ですることを、日本ではムダなプロセスや細かいことにこだわり、1時間、2時間とかかる」という労働時間の長さがあげられています。
…日本の労働スタイルが世界でも秀でたこともあったのに。
このような状況になってしまうのはなぜか?というと…
製造業を除き、日本の多くの産業では費用対効果をきちっと計測をしないからです。計測してしまうと、管理職の無能さがばれてしまうので、なんとなくうやむやにされているのです。
もっと言うと、組織の規模や予算を維持するために、簡単にできることも難しそうに見せたり、短時間でできることも長くかかるように見せかけたりしたほうが得をするわけです。
と指摘されています。
「そうだね」と思うのですが、その中でも特に気になったのが、「費用対効果をきちっと計測しない」という点です。
中小企業診断士の勉強をして、「管理運営」で様々な効率化を図る取り組みや、効率化を測る方法などを知りました。でも、これらは製造業で活用されている…というか、製造のために開発されたように見受けられます。
このような取り組みや方法を知って思ったのが、「他の活動にも使える」ってことでした。
なお、記事では、このあと「非効率なままでインプットに見合ったアウトプットが出せていない」のは、「日本企業のビジネスモデル自体が今の社会の変化に合わなくなってきている」からという話しになっていきます。
さらに、「オープンな働き方」についての事例が示され、未だ続く日本の年功序列型の働き方の問題点が指摘されます。
こういうのも面白かったのですが…
今回は、前半で気になった
「費用対効果をきちっと計測しない」ということ
一方で製造業で活用されている取り組みや方法が他にも生かせるし、これにより様々なフェーズで効率的なアウトプットを志向すようになるのでは…ってこと
について書いてみました。
勉強にせよ、仕事にせよ、最近では「インプット3割、アウトプット7割」など、アウトプット重視の考えが紹介されるようになってます。
これが定着すると、日本企業の姿勢も変わればいいな。
中小企業診断士になって企業の支援ができるようなったら、この点は気にかけておこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
