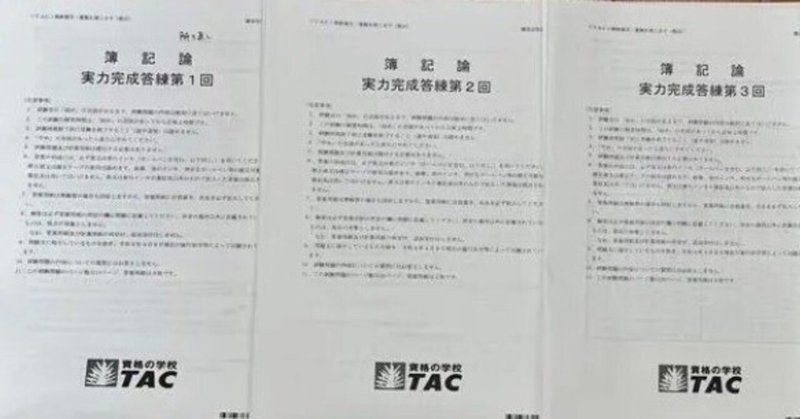
「4か月&独学」で簿記論に合格した新卒1年目社会人②~【演習期】~
こんにちは。あおです。
今回は簿記論を学習するうえでかなり苦労した演習期についてお話します。
前回の記事をご覧になっていない方はこちらからお願いします!↓
【演習期】
<使用した教材> ★が多いほどおすすめ教材です(最大5個)
・個別計算問題集(★★)
・総合計算問題集 基礎編(★★★)
・総合計算問題集 応用編(★★★★)
・TACの答練(★★★★★)
・LECの答練(★)←LEC信者の方には申し訳ないです・・・
個別計算問題集(★★)
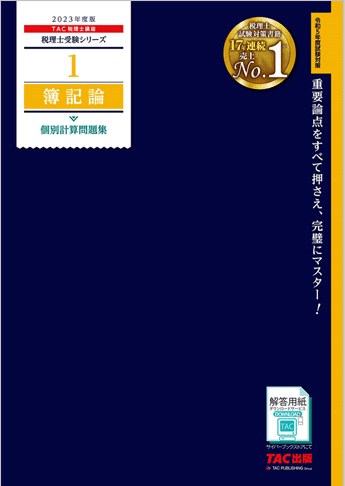
最初に結論から申し上げますと、この教材はあまり使いませんでした・・・
というのも、基礎固め期で使用していた問題集(特に直前対策トレーニング)を周回するのにかなり時間がかかったからです。
1周はしたのですが、正直基礎固め期のテキストをやりこんでいれば、こちらの問題集はやる必要がないかもしれません。
言ってしまえば個別計算問題集は直前対策トレーニングの劣化版でした。
【主な理由】
・問題数はそれなりにあるものの似たような問題が重複している
→網羅性に欠けている
・試験には出そうにない問題が割とある
→7月くらいから解き始めたのもあったからなのかもしれませんが、「これって本当に試験に出るのか?答練とか解いてても見たことない形式だぞ?」ってパターンが多く感じたので微妙でした。
総合計算問題集 基礎編(★★★)
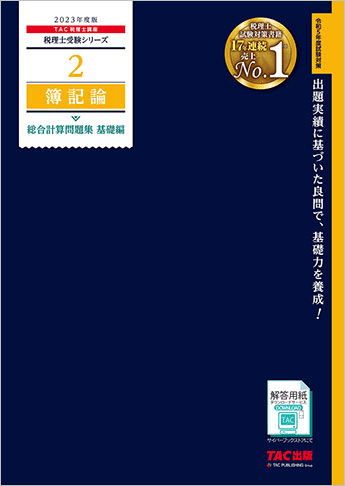
こちらの問題集は「そもそも簿記論の総合問題ってなに?」という方が最初に解くのにお勧めです!
前半は総合問題の中でも個別で問われることが多い分野を中心に学ぶことができ、最後に4問ほどまとめ問題という形式で普段の試験に近い総合問題を解くことができます。
最初からいきなり過去問題を解いて挫折をするよりは、こちらの参考書から始めて、なんとなくでいいので総合問題の全体像を学んでいただくことをお勧めします!
【注意事項】
こちらの参考書ですが、「基礎編」と書かれているだけあって問題の難易度はかなり低めです。
そのため、この参考書だけやりこめばいいというわけではなく、最低でも「応用編」までをやりこむ必要があります。
「基礎編」はあくまで全体像を把握するための参考書として扱うべきだと考えていたので、僕はそこまで周回せずにすぐに「応用編」にいきました。
くれぐれも「基礎編」だけ解いて「総合問題ってこんなもんなのか」って思わないようにしてください!
総合問題はコツをつかむまでは全然点数が安定しません!(笑)
総合問題計算問題集 応用編(★★★★)
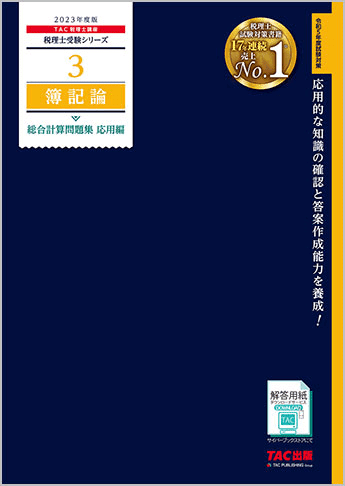
さきほどの「基礎編」に続いて「応用編」のご紹介です。
こちらの参考書はTACの市販テキストの中では「個別問題の解き方(★★★★)」と同じくらい良書だと思っています。
【本書の良い点】
・問題数が約15問と非常に多い
・難易度が本試験と同じレベルとまではいかないがそれなりに近い
・解説もそこそこ丁寧
・ひねくれた問題がほとんどない
僕は「応用編」を6月くらいから解き始めて、苦手な分野は3周以上はしてました。
総合問題は問題のパターンを覚えると同時に、設問ごとの関連性を理解することが重要なので、その感覚を本書で身に着けることができたと思っています。
具体的に言うと、例えば賞与引当金や退職給付引当金といった分野は設問単体で完結するため、ほかの勘定科目に影響を与えませんが、売掛金・買掛金が出てくる設問は複数あるため、1つでも集計ミスが起こると0点になってしまう。という風なことが学べます。
(総合問題の解きやすい設問、捨てるべき勘定科目については別の記事で詳しく取り扱います。)
TACの答練(★★★★★)

来ました。
僕が簿記論に合格できたのはTACの答練があったからだといっても過言ではありません。
【答練が神過ぎる】
・本試験と同じか若干難しいレベルの難易度
・毎回違うパターンの問題が出るので網羅性がある
・ひねくれた問題が少ない
・・・いや、良い点っていう割には当たり前じゃない?と思った方、
この当たり前の条件を満たす問題を見つけるのが独学をするうえで一番難しいんです!!!
結局、試験に合格するための最短ルートというのは過去問をどれだけ多く解くかだと僕は考えています。(大前提として基礎が固まっている必要はあります)
しかし簿記論は市販の教材では過去問が5年分しかありません。
もっというと、総合問題に関しては「総合問題の解き方」という参考書で2年分くらい過去問が取り扱われているので、初見で解けるのは3年分となってしまいます。
はっきり言います。過去問5年だけ解いて受かるほど簿記論は甘くありません。
とにかく本番と同じレベルの良質な問題にどれだけ多く触れることができるかが、短期間&独学で合格するためには重要です。
僕は直前対策講座に4月末に入って、確か5月に初めてTACの答練を家で解いたのですが、「これは市販の問題集だけじゃ確実に落ちるな」って思っていました。
そのため、実は22年度の直前対策講座で配布された答練だけではなく、21年度の答練もメルカリで購入して解いていました。↓

22年度で10回分+21年度6回分=16回分の答練を解いていたことになります。
6~7月末までの2か月間は特に答練の復習に時間を割きました。
一度にすべて解く必要はありません。
苦手な分野を集中して解いて、その日のうちにつぶし切るという風にしていました。
これができたのも16回分の答練があったからです。
最後にもう一度言いますが、TACの答練が無ければ僕は確実に落ちていたと思います。
LECの答練(★)
LEC信者の方、大変申し訳ございません。
LECで受講して合格しているかたももちろんいらっしゃると思うので、あまり大きな声では言えないのですが、正直答練の問題内容が明らかにひねくれていました。
「こんなの絶対出ないでしょ!!」って問題がうじゃうじゃあったのでおすすめしません。
TACか大原の答練を解きましょう。
つらい「演習期】を乗り切るためのコツ
演習期、なかなかしんどいですよね。
これはどんな資格試験でも一緒だと思います。
TOEICだって単語の暗記とか文法問題みたいにいつでも区切れる勉強なら隙間時間でもできるイメージがありますが、演習問題となるとそれなりの時間を確保して集中しないといけないですもんね。
ましてや、簿記論の場合は電卓を使う必要もあるのである程度のスペースを確保して勉強しないといけないですし、「時間との勝負だ!」って言われているので個別問題と総合問題を合わせて2時間解く練習もしないと!って思ったりもするかもしれません。
2時間通して解かなくていいんです。
総合問題の中の1問解くだけでもいいんです。
ここが非常にポイントです。
結局、個別問題・総合問題といっても色々分解すると複数の設問から成り立っています。
そしてその設問をさらに分解すると仕訳にたどり着きます。

最初のうちはこの仕訳がしっかりできるようになることが大切なので時間は二の次です。
とにかく1問ずつ解きましょう。
そして、1問ずつ答え合わせをしましょう。
最初のうちは総合問題を解いても3割くらいしか解けません。
いきなり通して解いて、間違えた7割の問題を復習するのってしんどすぎませんか?
復習するしんどさのせいで演習問題に手を付けるのが億劫になってしまっては合格するのは厳しいです。
なので、演習期だからといっていきなり長時間勉強するのではなく、できるだけ小分けにしてやりましょう。
勉強へのハードルを下げることが演習期を乗り切るコツです!
今回はこの辺で終わりにします!
次回はテクニックに関するお話をするのでお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
