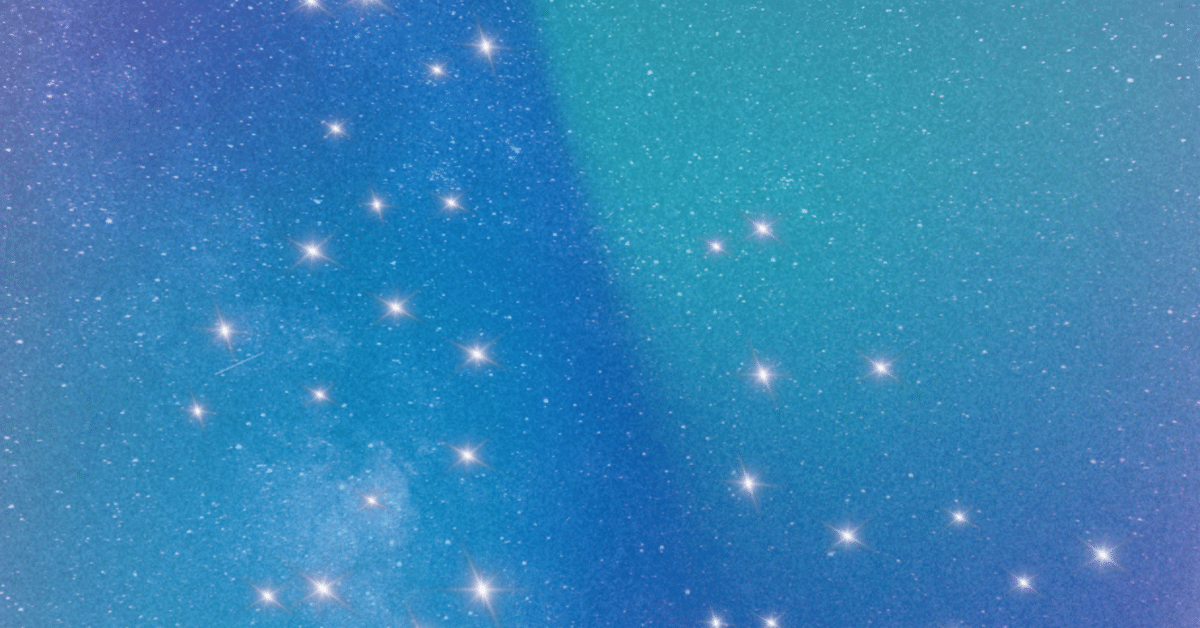
【小説】菜々子はきっと、宇宙人(第5話)
季節は春、3月の終わり。長かった冬の季節も終わりを告げようとしていて、ぽかぽかとあたたかな昼間の陽気の中で、愛おしいピンク色をした桜たちがまるで、私の新生活を応援してくれているようで、私の胸は躍った。
人生、心機一転、新しい生活がはじまる。そう意気込んで、期待に胸ふくらませて、新しい私の住みかとなる、あの川に面した小さな古民家のドアを開けたその先にいたのは、とてつもなく大きなゴキブリだった。
「ひぃ」
外で待っている引っ越し業者さんに恥ずかしくないよう、できる限り小さな声で私は悲鳴を上げたのだけれど、小さな古民家とはいえ、それなりの面積のある家の中に、素早い足取りでその大きなゴキブリは逃げていって、捕まえることができなかった。というか、そもそもゴキブリなんて、自分の素手で殺せるような術は人生において持ち合わせていない。
しまった、ゴキジェットとか買ってこればよかった。せっかくワクワクしていた私の心は、見てしまった黒い姿によって、一気に盛り下がっていた。
とはいえ、今日は無事引っ越しを終えなければいけない。家の前で待ってくれている引っ越し業者さんのことを思い出して、彼らとともに、私は引っ越し作業をはじめた。
私の住みかとなる古民家は2階建てになっている。昔、大家さんの息子なる人がほぼほぼ手作りで建てた家らしい。そのためか、家の作りが少しいびつだ。
1階は現在、大家さんのもの置きになっているので、私が住むのは2階だった。1階は本当に出入り禁止のため、2階に続く外階段が設置されている。けれど、その階段こそ一番手作り感が満載で、1歩1歩上るごとにギシギシと不吉な音が鳴った。
滑り止めなんてついていないので、大きな荷物を挙げるのはかなり危険のように見えた。
「これ、冷蔵庫とか洗濯機大丈夫ですかね?」
「とりあえず、小さな荷物から挙げていきましょう。もしよかったら流れ作業で荷物をあげていきたいので手伝ってもらっていいですか?」
「もちろんです!」
そう言って、地獄の引っ越し作業がはじまった。引っ越し業者さん2人が、トラックから階段の上まで荷物を挙げてくれて、その挙がってきた荷物を私が2階の入り口から中へと次々に運んでいく。運動不足のためか、1つの荷物を持ち上げるだけで、汗が噴き出る。
引っ越し業者さんもまさか、こんなに足元の悪い中の作業を想定していなかったのか、かなり息を切らしながら荷物をあげてくれている。
そしてなんとか、小さな荷物たちの搬入が終わって、問題の洗濯機と冷蔵庫のターンになった。
「この2つはこちら2人で一気に挙げていくので、家のドアが閉まらないように上で待っててもらえませんか?」
「了解しました!」
そう言って、不安そうに業者さんを上から見守った。階段を1段1段、挙がってくるのだが、本当に尋常じゃないくらいに「ミシッ」という不吉な音が聞こえた。尋常じゃない汗を噴き出しながら業者さんがなんとか冷蔵庫を運んでくれて、無事、冷蔵庫はキッチンの隣に設置が完了。そして、洗濯機は、2階のこちらも手作り感満載のベランダの隅に設置が完了した。特に洗濯機を置いたときは、その手作りのベランダが「ミシミシミシッ」といかにも崩れ落ちそうな音がして恐怖だった。
「本当に、本当にありがとうございました。。。」
心から引っ越し業者さんにお礼を言って、何とか無事、引っ越し作業が終わりを告げた。
ただでさえ、引っ越し自体エネルギーがいるのに、見てしまった黒い姿、不吉な足元の音、申し訳ないくらいに疲弊している引っ越し業者さんの表情、まだ荷ほどき1つしていないのに、どっと疲れがきて、私は広い畳の上に寝そべった。
天井を見上げるとまた、そこには大きな黒い姿をした彼がまた動いている。さっき見た彼と同一人物なのだろうか、もしそうでなかったとしたら、この空間は彼らの巣窟なのではないだろうか。
彼らの姿のように、黒く、私の心がかげる。おもむろにバッグの中から通帳を取り出して、残高を見つめる。引っ越し初期費用、新しい車の手配、移動費もろもろによって、次々とその残高が減っているのに改めて気づく。
そもそも、この家の初期費用、家賃は妥当なのだろうか、人が新しく入居するというのに、黒い姿をすでに2回も見かけているし、よく見れば天井の隅には蜘蛛の巣がきれいにはられている。この町に住むにあたってもちろん、他の住居も検討したかったのだけれど、インターネット上に、こんな山奥の物件は1件もヒットしなかった。菜々子に勧められるがまま、杖をついた、いかにも仙人みたいなおじさまと直接の契約を結ぶことになったとき、かなり不安な気持ちが押し寄せて、はじめて、不動産仲介会社という存在の重要な役割を知ったけれど、ときすでに遅しだ。今更住居を変えられるような残高は私の口座には残っていない。
どうしようもない不安に襲われたけれど、私には今、どうしようもできない。
眠れるはずもなかったけれど、とりあえず目を閉じて、目の前の現実からどうしようもなく離れたくなった。
「おーい!はるー!入っていい?」
ドシドシと階段を上がってくる音とともに、菜々子の声が外から聞こえた。そういえばこの家にはインターホンと呼ばれるものがない。どのくらい時間が経ったのだろう。結局一睡もできず、だからといって、荷ほどき1つできず、気が付けば、夕日はとうの昔に沈んであたりが暗くかげっている。
「いいよー入って!」
「うわー無事引っ越し終わったんだね!ほんとにうれしい!」
仕事終わりの菜々子は靴を脱いで、まるで他人の家とは思えない足取りで、家の中をくまなく歩き回っている。
「えー--。思ってはいたけど、このベランダからの川の景色最高じゃん!絶景だね!私の家からは見えないからうらやましい!」
いつのまにか菜々子が閉めていた網戸を勝手にあけて、ベランダからの風景に浸っている。
「ねぇ、やめてよ。また虫が入ってくるじゃん。」
「ごめんごめん。」
せっかく来てくれたのに、私には今、菜々子に優しくできるような余裕がない。
「うわー。キッチンもすごく広くて素敵だね!めっちゃ料理できるじゃん。」
「キッチンのところ以外、全部畳なのいいね!すごくくつろげるよ!」
次々と菜々子が私の家の感想を告げていく。その1つ1つに私はイライラして、沸々と怒りが込み上げてきた。
「ねぇ、菜々子」
「何どうしたの?」
私は立ち上がって、引っ越し作業で疲れていたけれど、手のこぶしを握り締めた。
「私さ、すごくすごく怖かったんだよ。ここに来るまで、退職願いだしてさ、上司とか同僚にいろんなこと聞かれてさ、引継ぎしないといけないから、3月有給消化するまで、ギリギリまでバタバタ働いてさ、辞める決断だって、親にもまわりにも、たった1年足らずしか働いてないのに何がわかるんだって、これから大変だぞって、ちゃんと生活していけるのかって、新しい仕事見つかるのかって、心配なんだろうけど責め立てられてさ、貯金だってそんなにないしさ、なのに、こんな山奥にくる選択しちゃってさ、大家さんだってなんか怪しそうだったし、こんなボロボロの家なのにそれなりにお金かかったし、実際入ってみたら虫だらけだし、運転だってさ、したことないからほんとにここまでくる山道怖かったんだよ。仕事だって、また新しく1から覚えないといけないから不安なのにさ、もうすぐはじまるのにさ、今日だって全然準備進まなかったんだよ。こんなところで、生活ができるなんて思えないし、、、、もうほんとに嫌だ、、、。」
そう言って、菜々子をまくしたてながら、気づいたら、自分の疲れ切った目元から、ボロボロと涙があふれ出ていた。
涙でぼやけている視界の先で、菜々子が困ったような表情を浮かべて立ち尽くしているのが見える。せっかく来てくれたのに、私は何をぶつけてしまっているのだろう。
すると、菜々子は何も言わず、私のもとにかけよってきて、私をくるっと抱きしめた。
「つらかったんだね、大変だったんだね、頑張ったんだね。」
そうやって言葉をかけながら、菜々子が私の背中をさする。
菜々子は汗臭かった。きっと仕事終わり、すぐに駆けつけてくれたのだろう。その汗の匂いが愛おしい。
そしてその腕の中、さする背中に添えられた手があたたかくて、私の涙はさらに溢れた。
「つらかったし、怖かったし、不安だったんだよ、、、、。」
まるで、好きなものを買うことを拒否されて泣きじゃくっている子どものようにわんわんと私は泣いている。
「そうだよね、、。大丈夫。大丈夫だよ。」
さらに菜々子が腕の力を強くして、背中をさすってくれる。
「大丈夫じゃないじゃん。どう考えても、私全然大丈夫じゃないよ。私菜々子みたいに強くないもん。」
「大丈夫、大丈夫だよ。はるは強いから大丈夫。それにこうしてさ、ハグしてると元気が出てくるんだよ。だから大丈夫。」
結局どうしようもなくて、私は菜々子の腕の中で、しばらくの間泣きじゃくった。少しずつ、少しずつ、私の心が落ち着いてきて、少しずつ、少しずつ涙がひいていくのがわかる。
「大丈夫だから。私がそばにいるから。」
完全に涙が引くまで、菜々子はずっと私を抱きしめてくれた。そしてやっとのことで、私が落ち着いたタイミングで、すっと手を放して、入り口に置いていた大きなエコバックのもとへと移動して、その中からいくつかのタッパーを取り出した。
「引っ越し大変だっただろうなって思って、ちょうどさ、昨日作り置きしてたお味噌汁とごはんと野菜の炒め物なんだけど、一緒に食べない?」
「うん、食べる。」
「鍋とフライパンってどの段ボールに入ってるか覚えてる?せっかくなら温めて食べようよ。」
菜々子の身体から離れて、力なく座り込んだ私は、「調理器具」と記載された段ボールを、力なく指さした。
「そこの本って書かれた段ボールの下にあるやつ」
「それね。わかった!準備するから、はるはベランダで風の音聞きながら待ってて!」
申し訳なかったけれど、何か行動をする力が残っていなかったので、仕方なく、菜々子に言われる通り、ベランダに出て、腰掛けて、網戸をきちんと閉める。後ろでガサガサと菜々子が荷ほどきをする音が聞こえてくる。
ふと、ベランダの隅に置かれた洗濯機に目をやると、ベランダの目の前に位置する外灯に照らされて、蓋の部分に、早速と言わんばかりにどこかの鳥たちがつけた糞が見えた。
「ふぅ」
ため息をついたけれど、さっき黒い姿を見たときよりは嫌悪感が薄くなっていることに気づいて、少しだけど前向きな気持ちになる。
目を閉じて風の音、それとともに、目の前に流れる川の音に耳を澄ませる。
昼間、あれほど汗を噴き出すまでに外に暑さを感じていたのに、今はひんやりとした風が肌にあたって、もはや寒さを感じるまでになっている。
ここには、人の音がない。あの雑多な、ゴミゴミとした特有の人混みの匂いもない。澄んだ空気を思い切り吸い込む。味も匂いもしないけれど、冷たくひんやりして、綺麗な空気だった。
「はるー。できたよー!食べよう!」
後ろから声がしたので、ベランダから部屋の中に入る。
いつの間にか菜々子は、調理器具だけではなく、その横に「食器」と書かれた段ボールまで荷ほどきをして、食器棚にしまってくれていて、そこからいくつか持ち出して、いかにも食卓の晩御飯という感じにテーブルの上におかずが置かれている。
「ありがとう。」
「さぁ、食べよう。いただきます!」
その声かけとともに、私はとりあえず、少し冷えてしまった身体を温めようと味噌汁から口を付けた。
「おいしくない。」一口飲んだだけで分かった。味噌汁がおいしくないと思ったことは人生で一度もなかった。どうしておいしくないかはわからなかったけれど、とにかくおいしくなかった。
「どう?おいしい?」
「うん!おいしいよ!ありがとう!」
きっと菜々子は料理が得意ではないのだろう。けれどそんなおいしくない味噌汁も含めて、なんだかかわいらしくて、笑みがこぼれた。
「そんなにおいしく食べてくれてうれしい!私もっと料理頑張ろうっと!」
私の浮かべた笑みを勘違いしたらしい。そして、菜々子は特にその味噌汁に違和感はなかったらしい。目の前ですごい勢いで夕ご飯を平らげている。
その食べっぷりと、おいしくない味噌汁と、あと、抱きしめられたときのあたたかさを頭の中でかき集めて並べてみたら、結局のところ、私がずっと探し求めていた答えだったような気がして、私の心は驚くほどに安堵していた。
「ねぇ、明日私休みだから荷ほどき手伝うよ!それにさ、ゴキブリ出なかった?なんかね、私の家も来たとき出てさ、ゴキキャップ置いたらすごく効果あったから、家に余っているやつ持ってくるね!」
黒くかげっていた私の目の前の現実の中に、きらりと、まるで宇宙のどこかから光がさしたような気がした。宇宙人、そう呼ばれる彼女に導かれて今、私の新しい人生が、生活がはじまろうとしている。
「私の選択は間違ってない。」
そう確信を持てた気がして、前向きな気持ちになった私は、目の前にあったおいしくない味噌汁を飲み干した。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
