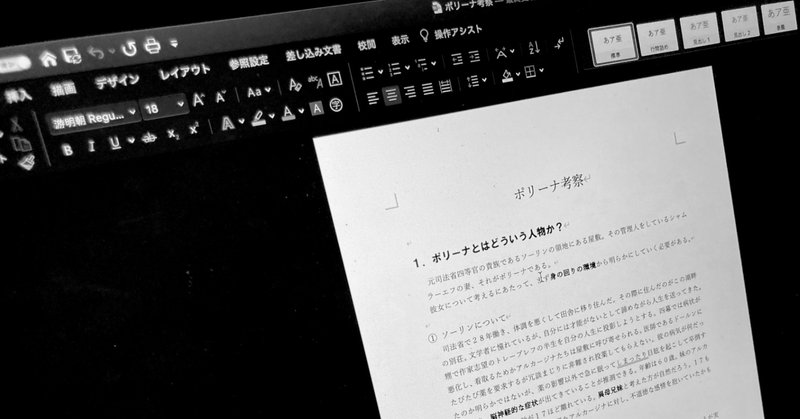
2020.10.20 ポリーナ考察
最近、「家」のメンバーとしきりに会っている神保です。
昨日は、歩ちゃんとご飯にいって肉を食いました。
そのあと、渋谷にある、レコードが聴けるミュージックバーに行きました。
近況の話でも盛り上がりましたが、やはり話の軸は「かもめ」です。
「喪」や「女」でどんなことをやるのか、根掘り葉掘り聞かれ。(笑)
ちょうど昨日、「喪」の会場下見に行っていたので、会場についても話しました。
原宿某所です。楽しみですね。
数日前に遡ると、ポリーナa.k.aアキエを演じる植木さんとも話しました。
ポリーナの役について、そして今後どんな筋書きになっていくのか、
本当は台本をお見せしたいところだったんですがまだ書き上がっておらず、
脳内にある構想をお伝えすることに。
ただ話せれば良かったのですが、うまく言葉にまとめるのが難しかったのであらかじめwordで書き出していました。
一週間ほどかけて、気付いたら2万字以上書いていました。(笑)
ポリーナだけ考察しなおせばよかったんですが、
結局は他の人物についても考察する必要があり、そもそも「かもめ」とは何か? そして、現代日本に置き換えるとは何か? ということを問い直すことになってしまい、
とんでもない量の文章をお渡しすることになってしまった。
でも、こうして上演を終えた後にもう一度考え直すことってなかなかないので、とても良かったです。
本質的な理解は変わらないのですが、なんというか、新たな発見はありました。
せっかくなので、ネタバレしない程度に掲載します!!!
マジで長文なので覚悟してください。(笑)
ポリーナ考察
1.ポリーナとはどういう人物か?
元司法省四等官の貴族であるソーリンの領地にある屋敷。その管理人をしているシャムラーエフの妻、それがポリーナである。
彼女について考えるにあたって、まず身の回りの環境から明らかにしていく必要がある。
1.①ソーリンについて
司法省で28年働き、体調を悪くして田舎に移り住んだ。その際に住んだのがこの湖畔の別荘。文学者に憧れているが、自分には才能がないとして諦めながら人生を送ってきた。甥で作家志望のトレープレフの半生を自分の人生に投影しようとする。四幕では病状が悪化し、看取るためかアルカージナたちは屋敷に呼び寄せられる。
医師であるドールンにたびたび薬を要求するが冗談まじりに非難され投薬してもらえない。彼の病気が何だったのか明らかではないが、薬の影響以外で急に眠ってしまったり目眩を起こして卒倒するあたり、脳神経的な症状が出てきていることが推測できる。
年齢は60歳。妹のアルカージナは42歳。年齢が17ほど離れている。異母兄妹と考えた方が自然だろう。17も年下の、女優として活躍する端麗なアルカージナに対し、不道徳な感情を抱いていたかもしれないことも想像できてしまう。
1.②アルカージナについて
イリーナ・ニコラーエヴナ・アルカージナ。42歳。有名な舞台女優とされているが実のところはわからない。(アルカージナという名前には「田舎」という意味が込められているという説もある。)息子の名前はコンスタンチン・ガヴリーロヴィチ・トレープレフであることから、彼女が旧性(または芸名)を名乗っていることがわかる。すでに離婚・もしくは死別している可能性も否めない。トレープレフも父のことはほとんど語らないため、記憶に残らないほど会っていないか、出産後早くに離別していたのだろう。
トレープレフの包帯を巻き直しながら、間借りして暮らしていた頃の話題になるのだが、その暮らしぶりには慎ましさが窺える。しかも、その顛末については忘れているが、来客の劇団員にコーヒーを飲ませてやったことだけは記憶していたという(あるいは忘れてしまいたい過去だったか)。その時、国立の劇場に「出ていた頃」との言及がある。つまり「今は出ていない」。国立というのだから小劇場ではなく大きな劇場だろう。アルカージナは若い一時に名声を得たが、以降はさほど忙しくしていないのではないだろうか。四幕ではハリコフで歓迎を受けた、と自慢げに語るが、ハリコフは工業が盛んな街で、どちらかというと軍事色の強い場所のようだ。(資料不足。もう少し調べる必要あり。)このことからも、彼女が過去の栄光にすがって、もしくは屋敷ではそのように振る舞っているのではないだろうか。
そう考えると、彼女が屋敷に連れてくる人脈というものも、些か怪しさを増す。湖周辺で婦人たちの人気を博していたという産婦人科医・ドールンや、彼女と腐れ縁のようにくっついたり離れたりを繰り返す人気作家・トリゴーリン。もし彼らが「そこまで大した上流の人間たちでない」となれば、マーシャ目当てとはいえ貧しい家の出であるメドヴェージェンコが違和感なく(本当はあるのかもしれないが)あの屋敷を出入りしていることの説明もつく。トリゴーリンは確かに名も知れていて次々と新作に追われてはいるが、果たして彼もどの程度セレブなのかはわからない。作家デビューして「ぽつぽつ載り出した」というトレープレフの新作と同じ雑誌に彼の掲載もあるというし、実は本人が言うように「トルストイやゾラには及ばない」のかも知れない。
このあたりから、「かもめ」に初めて触れる読者や観客が抱く「上流階級の家の物語」というのは、チェーホフによって導かれるミスリードなのではないだろうかという疑念を抱かずにはいられない。
1.③ドールンについて
湖の近くで有名な数少ない産科医。よほど魅力的な人物なようで、女性が絶えないという。アルカージナともかつて肉体関係があったと仄めかされているが、今はもっぱらポリーナににじり寄られている。三幕の間に海外旅行で財産を使い果たしたという。それも果たして、一人での旅行だったかどうかは怪しい。しかしこの発言は、どう捉えるにもまっすぐ受け取ることは難しい。
ドールンが医師として大きな富があったとすると、一度の海外旅行で使い果たすことは想像できない。だとすると「使い果たした」という発言は嘘になる。「やっと貯めた貯金を使って海外旅行に行き、本当に使い果たしてしまった」と考える方が自然なのではないか。そう考える理由には、彼の性格の「真摯さ」が挙げられる。
彼は自分の口から出る言葉、耳に入る言葉一つ一つを吟味し、そこに嘘がないか、確かめるようにしながら会話をするような節がある。彼は芸術にも見識が深い。トレープレフの抽象的で挑戦的な劇に感銘を受け、彼に「イメージを書け」とアドバイスする。舞台などの芸術への見識が余程ないと、一度の観劇でそれほどの視座で語るのは難しいだろう。彼はおそらく医学の探究の副産物として、心理学や哲学の道を通ってきたのだろう(当時ロシアではそうした学術・哲学論議が盛んだったという)。『かもめ』の登場人物は多くが俳優談義や芸術論についてこぞって話すが、彼らの中ではその洞察力と言語化能力は抜きん出ている。ソーリンに対しタバコをやめるべき、と注意する時に、求められてもいないのに「自我」の話に発展させてしまうくだりがある。これはおそらく、ソーリンを説得するために「人の生きる道」つまり「道徳」という根本的な部分から理解させる必要性を感じたための発言であり、真に彼の「徳」について考えていることの表れである。彼の人生に向き合わず、麻酔薬を提供することは誰にでもできるはずだ。彼はとても正直だし、嘘をついてまで人からよく見られることに意義を見出だしていなさそうだ。自分の意思をしっかり持って貫こうとし、筋を通そうとする。
海外旅行で貯金を使い果たしたのは事実だろうし、ということは、一度の海外旅行でほとんど使ってしまうほどしか貯金を持っていないのである。彼もやはり、そこまでセレブというわけではなさそうだ。
町一番の産科医とのことだが、なぜ彼は湖周辺にとどまったのだろう。開業して30年間苦労したと本人が語っていることから、少なくとも本人は精一杯仕事をしていたことがわかる。しかし、そこは田舎であって、都会の大きな病院で忙しくしていたのとは意味が違う。もしかすると、近くに他の産婦人科がなかったのではないだろうか。彼の腕がどれほどのものだったのか、それでは誰も測り知ることができない。田舎の医者というのはそういう側面をどうしても持ってしまう。田舎の開業医であり、貯金もそこまでたくさんは作れなかった。でも知識と見識だけは人一倍ある。そうしたところから、彼自身も、自分の人生に充足感を見出せてこなかったのではないだろうか。そのくせ、医者という肩書きもあり、容姿もいいのでモテてしまう。そこが彼の喜劇的な点であり、同時に、悲しいところなのかもしれない。
マーシャからは特別慕われているようで、トレープレフを愛していることを唯一じかに明かされる。マーシャ曰く、親身な感覚があるという。彼はマーシャのかぎタバコを、すごい剣幕で奪い取って投げ捨てる。これも、ドールンがマーシャに対し特別な感情を持っていることの現れだ。おそらくマーシャはドールンとポリーナの子なのだろう。マーシャはそれを感じ取っているし、ドールンやポリーナもおそらく、それらのことは感づいているはずだ。シャムラーエフもまた知っており、マーシャとの関係が芳しくないのも、そのためだろう。
ポリーナのことを、彼はどう思っているだろうか? きっと面倒くさいと思っているに違いない。でも、呼ばれると屋敷に遊びに来てしまう。それは何かしらのメリットがあるからだろう。きっと彼もまた、アルカージナやトリゴーリンのような文化人に憧れを抱いていて、自分の閉じかけた人生に花を添えたいと思っているのかもしれない。そこまで考えていなかったとしても、少なくとも面白そうだと思っていることは事実だろう。興味の赴くままに語り、行動するのが、彼のポリシーなのかもしれない。
彼はトレープレフの文才を発見した第一人者として、いくらか得意気になっているとも捉えられる。若い才能が育つことに喜びを感じるのだ。しかし、自らの手で育てようとはしない。直接金を与えたり、経験をさせるのではなく、あくまで「アドバイス」するだけ。そして若い才能の芽を伸ばしてやったという気になる。こういう人間は割とあちこちにいる。彼はもしかすると、充足感を味わうために、華々しい「医師ドールン」を演じるべくここに現れたのではないだろうか。しかしそれでいて身を削るようなことはしたくない。どうにも手の施しようがない。本人が好きでやってるのだから、文句など言うまでもないが、彼は一体、この劇の中で何を成し遂げるだろうか? 大した事件も起こさないわりに、いつも主役気取りで美味しいせりふをかっさらっていく。まさに大御所俳優が後輩の現場にふらっと現れ、テキトーやってたかと思うと美味しいところは持っていくという、最悪な大人のパターンではないか。
『かもめ』を初めて観る観客はそれに気づかない。現実世界でも、往々にして一見では彼らのような人間の喜劇性に気づくことは難しい。チェーホフが彼に課した運命とは、そういうものなのではないだろうか。
1.④マーシャについて
シャムラーエフとポリーナの娘であるが、どうやら本当はポリーナとドールンの間にもうけられた子である可能性が高い。マーシャというのは愛称で、日本で言う「幸子→さっちゃん」のようなものだ。「マーシェンカ」と呼ばれる場面もあるが、それはより砕けた呼び方。チェーホフの実の妹も名前がマーシャであると言われており、そこに何か特別な思い入れがあることが想像できる。マーシャの本名はマリヤ・イリイーニチナ・シャムラーエワであることが予想されるが、配役表には本名でなくマーシャとだけ記されている。それはきっと父姓(=シャムラーエワ)ということを明言しないためだろう。もしかしたら戸籍上は「ドールナ?ドールエナ?」なのかもしれない。否、本人が自らを「身元不明」と表現することから、本当に苗字や父姓が明らかでないのかもしれない。今の日本では考えられないが、124年も前のことだからあり得る。
彼女は黒い服をいつも着ている。本人曰くそれは「人生の喪服」であるという。つまり自分や誰かの死を悼んでいると。もうずっと生きていたような感じがする、とこぼすことから、自分はもう一生を終えたような感覚さえ持っているのかもしれない。マリヤは「マーシャ」という人格を俯瞰して眺めており、「マーシャ」という人間を「着る」ようにして生活しているとも言えよう。
ポリーナやシャムラーエフに対しても心を開くことがなく、終始冷たくあしらうような節がある。トリゴーリンに、自らをネタにしてもいいと告げることからも、不幸な「マーシャ」というブランドを持っているかのように考えているのかもしれない。しかし、ある時には「マーシャ」が見ている景色や環境にすっかり感情移入して怒ったり嘆いたりすることもある。つまりその役作りは不安定なのだ。
「かぎたばこ」は、マリヤとマーシャをきれいに分離するためのいわば「精神安定剤」のような働きをしているのではないだろうか。ドールンのいうところの「プラスなにがし」というのがまさにこれであり、マリヤは黒い服やかぎたばこ、ウォッカやワルツのステップなどの儀式を介して、自らを不幸な「マーシャ」へと昇華することで心の安定を図っているのではないだろうか。
1.⑤シャムラーエフについて
ソーリンの屋敷の管理人である。どの程度の収入があるのかはわからないが、畑だのミツバチだの、いろいろな土地活用をしているらしい。つまり、土地を有効活用してお金に換えないと当然やりくりすることができず、かつ、その運用は決して余裕があるわけではないようだ。可能性としては、シャムラーエフが私腹を肥やすために節約していることや、彼の興味本位でいろいろなことに手を出していることも考えられるが、ソーリンは日頃から彼の土地運用方法について疑問を持っているようだし、もしも不要な土地活用だったら削減を命じるはずだ。そうしないのは、やはり「やりくり」のために最低限必要であることをソーリンも分かっているからだし、ソーリンには心身ともに余裕がないことも要因のひとつだろう。
シャムラーエフがどれほどの利益を上げているかは不明だが、有り余るほどの資産を動かしているそぶりはない。彼の人との接し方を見るに、人の話は聞かないし、馬ひとつ出すにも自分の思い通りにならないことで腹を立てるような幼稚なところもある。アルカージナに会うなり、知っている俳優の話を矢継ぎ早に浴びせる点など、どこをとってもカリスマ性がない。きっとそう顔が広い人物ではないし、大役を担うようなこともなかったのだろう。
彼は今もポリーナのことを愛しているのだろうか。もしマーシャが自分の子ではないと知っていたとしたら、それでも離婚を選ばなかったのはなぜか。確かに劇中、夫婦が会話することは一度もない。しかし、ポリーナは舞台を去るときに彼の腕をとって歩くことはしている。これはきっと、二人は不仲なのではなく、「長年連れ添ったからこその距離感」なのであり、二人を分かたなかった理由が何かあるはずだ。
これはあくまで想像だが、シャムラーエフはポリーナのような女性と一緒でなければ保てないような弱い部分があるのかもしれない。馬車について口論になるシーンで、彼はきっとアルカージナに怒鳴ることをイメージして躍り出てきていることが予想できる。劇中、このような自発的な怒りをあらわにする人物はシャムラーエフしかいない。「怒り」は「恐怖」から生まれる。きっと彼は根底では何かに怯えている。信頼を失うことや、自分の思い通りに行かなくなることや、他人から低く見られることなど。きっとポリーナは、そんな彼の裏の表情を知っているはずだし、だからこそ彼女は、横暴な態度を取られても直接彼に反撃することなく、別のベクトルにエネルギーを受け流してきたのだろう(あるいはそうした方法にたどり着いたのだろう)。
1.⑥では、ポリーナとはどういう人物か?
チェーホフが「かもめ」の最初のプロットを書き上げた際、「女役3人、男役6人」と書き残しており、恐らくポリーナは後から書き加えられた役だったことが窺える。つまり、「書き加える必要があった」のだ。それはきっと、「他の3役(アルカージナ、ニーナ、マーシャ)には担わせられないが戯曲には必要な要素」が残ってしまっていたからだろう。
女性登場人物は皆「母」としての一面を持っている。また、「演じる」という面を持っているということもできるだろう。違う部分はどこかというと、最も顕著なのが「問題に直面した時にどう接するか」だと思う。ニーナは自分の中に責任を見つけ出そうとし、その葛藤に苦しむ。アルカージナは自分の主張を曲げず、達成のためなら演技をしてでも自分に追従させる。マーシャは達観して問題から目を背けようとし、結果的にもう一人の自分を作り上げた。ではポリーナはどうか。彼女は問題が起こったとき、その場ではそれとなくやり過ごすが、後に裏で手を回して解決に向かおうとするように感じる。実は最もしたたかな女性なのかもしれない。
そう考えると、シャムラーエフとの破綻した関係から手を引かないのも納得がいく。彼のいない場では彼をこき下ろし、彼といるときは黙って良妻を演じる。少なくとも一般的な家庭よりはいい暮らしをしているはずだし、経済的なことを考えても、彼との婚姻関係は手放すには惜しい。しかし、おさまらぬ色欲を押さえ込んだり無視しようとはせず、むしろ都合のいい相手と肉体関係を結ぶことで解消しようとしているようにも思える。ドールンは独身だし、しかもマーシャの件もあるため大っぴらにポリーナとの関係を口外しようとはしまい。一番都合がいい。よって、彼に求めているのは駆け落ちや再婚ではなく、このままこの関係をダラダラ続けることなのではないだろうか。
また、そうした不貞を屋敷の中で挑むという大胆さも見上げたものである。これはむしろ、この状況を「楽しんでいる」と捉えても差し支えないだろう。社内恋愛のようなスリルを味わっているのかもしれない。ニーナがドールンに渡した花を奪って引きちぎるシーンで、ニーナはそれを見ているだろうか? 見ていないだろうか? 真相は不明だが、少なくともニーナはその後の独白で花について言及していないことから、あまり気にしていないことだけはわかる。しかし、ポリーナはあの場で嫉妬心を剥き出しにして花を引きちぎる行為をする前に、ニーナに見られはしまいかと考えないものだろうか? 考えた末に行った行動だとすると、きっとポリーナはニーナをちょっと「勘の鈍い子」だと思っているに違いない。事実、ニーナは恋愛には不慣れそうだし、トレープレフを言葉や行動で傷つけたことに無自覚でいる。
マーシャがトレープレフに憧れていることを知っている点などからも、ポリーナは日頃から周囲の人間関係をよく見ていて、特に「男女間の情動」に鋭いことが考えられる。ドールンに迫る時も、「逃げを打とうとする」ドールンの本心を見抜いて、しかもそれに言及することで彼の逃げ場をなくそうとするという戦術を使う。そういう点からも彼女は「問題が起こったとき、その場ではそれとなくやり過ごすが、後に裏で手を回して解決に向かおうとする」ことに長けていると言えるだろう。これこそがきっと、ポリーナに与えられ、この劇に必要不可欠だった要素である。
しかしポリーナのような人間像は本当のところ最も「ありふれた人」の姿なのではないだろうか。平凡・平均というとなんだかマイナスなイメージがあるが、ポリーナの存在は、他の登場人物たちが「それぞれ突出した人物たち」であり、その異端性を助長させる効果も持つ。しかしここで問題なのは、果たしてポリーナは本当にありふれた人なのか、という点である。退役中尉を夫に持ち、領地経営で暮らす妻、そして不倫相手との間にもうけた子がいて、そんな縮図の中で不倫というささやかなスリルを楽しむ日常・・・。これはとてもドラマチックで、日常的な物語とは言えない。ありふれた人の姿ではあるが、彼女が置かれた状況はとても特殊だ。チェーホフはなぜ、この『かもめ』の中で彼女に特殊な物語を与えたのだろう。当時ロシアはまだ男性優位の社会だったので、女性であるポリーナにこのような物語を与えたのには強い意味があるはずだ。
推測だが、「一見ありふれた人」の持つ「物語の強さ」を、チェーホフが信じていたからではないだろうか。問題に対して立ち向かったりスタンスを表明できる人間が全てではないし、むしろ本心を胸中に抱えながら別の何かに楽しみを見出しながら生きる人は多いはずだ。女優、作家、医師、教師、公人、軍人、料理人や小間使い、それぞれ属性を持つ中でマーシャとポリーナはシンプルな「女性」として登場する。マーシャは他人からどうこう言われることが多い。やれ働け、酒はやめろ、たばこは汚らわしい、なんで黒い服を、結婚しろ、などなど。つまり、なんだかんだマーシャは「みんなの妹」のような属性を持っているのかもしれない。ポリーナを一口で説明しようとすれば「妻」となるだろう(マーシャとの接し方の中に「母」らしさを見つけることは難しい)。しかし、「妻」だけでは語り尽くせない背景をポリーナは持っている。その矛盾に、ポリーナが背負っているテーマが隠れているのではないだろうか。
一般に、世の中の女性は結婚すれば「妻」になり、子を産めば「母」になってしまう。しかし、それだけで人間を語ることはできないはずだ。当時は今のように女性が働く環境も整っていなかっただろうし、女性の権利を主張するエネルギーは今よりもさらに意味深いものだったに違いない。チェーホフがポリーナを通して描きたかったのは、「妻化してしまった女性の物語の復権」なのではないだろうか。また、そこに喜劇性を感じたのだろう。ナチュラルな、日常の生活の中に埋没した、「妻」と呼ばれる人間の生態と、本来持っているはずの物語を浮かび上がらせること。その点において、チェーホフの生み出したポリーナという人物は非常に魅力的だ。かつ、いつの時代・どこの国においても再現性の高い、普遍的なテーマを彼女は持っていると思う。
また、アルカージナやトリゴーリンには起伏のない物語を、ポリーナにドラマチックなバックボーンを与えたのは、おそらくこうした対比を作ることによって「階級の差」と「物語の差」を明確に示し、「上流でも平凡なんだ」「逆に平凡な人の方が大変そう」と発見させるという目的も含まれているだろう。
チェーホフはこの劇を、イプセンの『野鴨』を下敷きにしつつ、様々な要素を付け加え発展させて作り上げた。『野鴨』で否定された「優れた人間ならば残酷な真実にも向き合って打ち勝てる、それこそが真の幸福だ」という考え方を、さらに膨らませ進化させて描こうとしたのだ。『野鴨』では暮らすのに精一杯な平凡な家庭が描かれていたが、『かもめ』は貴族の屋敷が舞台。つまり、いかに上流の人間であれど実は平凡な暮らしをしているのであって、どの階級にいようが人間は真実に立ち向かうことなどできず、すなわち真の幸福には誰もたどり着けない、というのがチェーホフの出した結論だろう。こうした構造を浮き彫りにするためにも、ポリーナの持つ物語は重要だ。
2.チェーホフが『かもめ』でやりたかったこと
人物の役割を考える上で、どうしてもついてくるのが「戯曲の構造」や「作者のねらい」だ。チェーホフはこの四幕喜劇『かもめ』で何がやりたかったのか。長くなってしまうので端的にまとめると、以下の要素に集約させることができると考えた。
・ 当時の「ありきたりな演劇」へのアンチテーゼと、そこに執心する自分自身への皮肉
・ 野鴨やハムレットなど既存作品の骨格を用いた上で、人間描写をさらに深めること
・ なるべく現実の日常を切り取り、複雑さはそのままに「喜劇」と冠せしめることで、現実の複雑曖昧な日常を喜劇と捉えることができないかと考えた(現実の虚構化に希望を見出し、その方法論の一つとしての試み)
上記の大まかな要素に、様々な要素が詰まっている。
例えば『かもめ』にはれっきとした主人公がいない。主人公とは観客の目や心の代わりになってくれる人物のことであるが、『かもめ』はそうした「同化作用」を促す人物は登場しない。登場人物たちの「視点」や「感情」は演出・ディレクションされておらず、観客の知らない場所(舞台裏・三幕と四幕の間etcに隠されている。チェーホフは『かもめ』の観客に同化を求めておらず、俯瞰してこの劇を眺めるよう促している。つまり「異化」であり、「虚構の明確化(これが劇であるということの二重説明)」である。これらの要素は「日常を切り取る」ための試みである。かといって、人間描写を深めることを諦めてはいない。むしろ人間社会の様々な関係性や生じうる社会的立場を網羅的に組み込んでいる。チェーホフはせりふや行動ではなく、登場人物たちが背負っている人生と彼らの「関係性」にドラマを託したのではないだろうか。そしてこれは「一度見ただけでわかった気になる演劇」からの脱却を促す構造としても機能する。
他にも、前述の通り「真の幸福には誰もたどり着けない」という絶望的な結論を提示したり、芸術や精神はこうあるべきだ、という答えのない討論がしきりになされたりするなど、観念的なモチーフがふんだんに用いられている。きっと彼は、芸術家や作品を取り巻く人間たちによっぽどうんざりしていて、何もかもがいやになっていたんだろう。
どれだけ優れた作品が生み出されようと、現実を生きる人間が救われることは決してない。それは、人が「死という幕切れ」が訪れない限りその物語を終えることができないからである。区切りがついたならどんなに楽か。トレープレフはチェーホフに代わって一足先に幕を下ろし、喜劇という虚構の中に消えていった。取り残されるチェーホフという悲劇。この構造、俯瞰して見れば、いっそう喜劇的だ。この喜劇は今も繰り返し上演され続けている。
『かもめ』が初めて上演されてから、来年で125年目となる。彼の「人生の喜劇化」という挑戦はまだ達成されていない。
3.「かもめ」を現代日本に置き換えるということ
当時のロシアと現代日本とでは当然、全く違う世の中だし、チェーホフがこの劇でやりたかったことは、現代日本の観客には届かない。「当時のままの形」では。僕はロシア語も読めないし、当時のロシアを知っているわけでもない。チェーホフがかつて何を狙ってこれを書いたのか知っている人間は誰もいない。つまり、完全に「置き換える」なんていうことは最初から不可能だ。だとしても、前述のチェーホフがやりたかったと思しきことを可能な限り再現しようと挑戦することはできないだろうか。先ほど端的にまとめた三つを、一つずつ紐解いて、その理想像をくっきりさせていきたい。
3.①当時の「ありきたりな演劇」へのアンチテーゼと、そこに執心する自分自身への皮肉
2020年の東京におけるありきたりな演劇、とはなんだろうか。様々な形式の演劇が上演され、もはや「新形式なんてない」状態の深刻度は増しているとは思うが、きっと124年前のロシアでも同じくらい深刻に考えていたのだろうと思うと、きっとこれからまだまだ新しい演劇、今までになかった演劇は生み出されていくだろう。
藤田貴大が生み出したリフレインの手法、山本卓卓の映像とリンクした演劇、高山明のアプリを使ったヘテロトピア。劇団ノーミーツのzoom演劇、松尾スズキは感染症パニックの中アクリル板を使って劇を上演、映画監督の長久允は演劇の配信を映像作品として成立するレベルに引き上げ、タニノクロウはVR演劇を発表した。可能性なんていくらでもある。
ただし、今は124年前ほど演劇が世の中の関心の中心でないことを忘れてはならない。むしろ日本の演劇作家たちの先鋭化は、一般層との分断を加速するものですらあると言えるだろう。つまり、チェーホフがアンチテーゼを打ち立てたいテーゼが、そもそも存在していないのであり、『かもめ』をあのまま上演しても全く意味がない。トレープレフの嘆きも、デカダンスな劇中劇の皮肉味も、全く説得力を持てないのだ。ここが観客の目にしっかり映らない限り、ニーナがなぜ錯乱したのか、アルカージナはどんな人物か、トリゴーリンという人間をどう捉えたらよいのか、それらは指針を失い意味不明となる。つまり、現代日本の私たちには謎解きのハードルが高すぎるのである。この劇を「喜劇とする」ことの意味も薄れてしまうことにつながる。そこで僕は、『かもめ』の劇場ではない空間での上演について考えた。
アルカージナは「大きな劇場」に立っていることを誇り、トレープレフがそれを否定する。これは現代日本では「芸能界的な演劇」と「芸術的な演劇」という対立構図になってしまう。芸能界的な演劇で柱となるのはやはり興業的な面である。「興行さえよければ内容はなんでもいいのか!」と怒ってチケットで尻を拭ってやりたくなる舞台を何度も見てきたし、関わってきた。おそらく現代日本で描くべきトレープレフは「芸能界的な演劇」へのアンチテーゼとして存在している必要があるだろう。我々が特殊な形式での上演に挑むことで、観客の頭の中で「これが特殊な形態での上演である」ことへの意識が働くだろう。つまり私たちが「どのようにして演劇を立ち上げるか」という興味の視座を持ちながら劇を見ることになり、それは興業的成功は私たちの目的ではないことを明らかに提示する。そこで初めて、「最近のありきたりな演劇なんて」という趣旨のせりふが輪郭を帯びてくるのであり、かつ、「そこに執心し、自嘲する」ことの体現にもつながるのである。
アルカージナは、トレープレフのデカダンな思想を笑っているのではなく、自分が身を砕いてきた「芸能界的な演劇」に噛みつく彼の工夫一つ一つが、自身の存在意義を根底から覆す攻撃に思えているのであり、それを表すためには彼の劇を単なる退廃的な演劇として上演させるのではなく、工夫が随所に散りばめられていて、ゼロから演劇を立ち上げ直そうとすることを魅力と捉えるトレープレフの奮闘が明らかに見てわかるようなものにしなければならない。『家』の押入れでの上演は、このようなトレープレフの野心を具現化するための演出である。ちなみに演出でカメラ中継を行ったのは、「オンライン演劇の実態を嘲笑的に明らかにする」という試みであり、彼の当時の演劇人たちへの猜疑心が読み取れるものである。
3.②野鴨やハムレットなど既存作品の骨格を用いた上で、人間描写をさらに深めること
『家』では原作どおりのシナリオラインを引っ張って上演したので当然『野鴨』や『ハムレット』を踏襲したものになっている。なぜチェーホフがそれらを下敷きに戯曲を書いたかというと、恐らくそれらが多く親しまれていたからであるからだろう。だからこそ当時の観客はその構造に気付くし、気づいた上でチェーホフが新たな肉付けをしなおしていることも視野に入る。では果たして現代日本においてイプセンやシェイクスピアが、それほど親しまれているだろうか。それほど知られているのはせいぜいディズニーかジブリくらいだろう。しかし僕はどうやら演劇などの文学作品からの引用にこだわりたいようだ。僕が演劇にこだわる理由はただ、演劇が好きだからでしかないのだが・・・。
ちなみに、『家』ではいくつかのせりふにポップス音楽のフレーズが引用されている。チェーホフの技巧へのオマージュだ。『喪』や『女』では、原作の人間関係や大まかなストーリーは変えず、さらに換骨奪胎して他の既存作品のエッセンスをもっと練金術的に混ぜ合わせたものにできたらいいなと考えている。
物語の錬金術で何が一番魅力的かというと、やはりせりふや人物の背景がより深まるところだと思う。これは寺山修司が得意としていた技法で、エリア51の前作『ノゾミ』で寺山作品を上演し終えた自分への挑戦とセルフオマージュでもあり、寺山とカドタの印象をダブらせるためのスパイスでもある。
3.③ なるべく現実の日常を切り取り、複雑さはそのままに「喜劇」と冠せしめることで、現実の複雑曖昧な日常を喜劇と捉えることができないかと考えた(現実の虚構化に希望を見出したため、その方法論の一つとしての試み)
これが大問題だった。なぜというに、この試みはすでに使い古されすぎており、今更その程度の実験に挑んだところでほとんど意味がないからである。「テラスハウス」などがいい例だ。SNSが生活に浸透してから、日常と虚構の線引きはより曖昧になり、その境界を乗り越えようとする試み自体に魅力を感じる人は少ないだろう。だが、『かもめ』において最も偉大で挑戦的だったのがこの「人生の喜劇化」であるため、この点が非常に厄介な問題なのである。そこで喜劇の本質について、改めて考えてみた。
喜劇の本質は「滑稽なすれ違い」や「すり替わり」である。ある時、過去の思い出はだいたい喜劇的だな、ということに気づいた。それは、かつて現実だったものが記憶に変わることで、懐かしみの中で事象に対する視点が変化(すり替わり)し、すれ違いを滑稽だと思えるようになったからである。そうすると事象自体も喜劇と捉えられるし、そもそも時とともに変化してしまう私たち自体も滑稽で喜劇的だ。こう思った時に、今『かもめ』に挑む価値はあるかもしれないと考え至った。
『かもめ』という答えの示されていない複雑でリアルな物語を、解釈しながら、人間関係を構築し、摩擦し合い、そして時と共に変わっていく、そんな「私たち」。これ自体が究極の喜劇であり、『かもめ』が、演劇を通して作り出したかった「現実の虚構化」なのではないだろうか。人と人が連続的に関わっていくことで起こるリアルな人間模様を、私たちはすでに体現し始めている。これは連続企画ならではの視座であり、最大の魅力である。
また、『家』を観た観客が『喪』そして『女』と続けてこの劇に参加した場合、KAMOMEの世界の人間たちの姿が少しずつ明らかになっていくことを感じるだろう。それはまさに、『かもめ』を「一度見ただけでわかった気になる演劇、からの脱却」を促す構造を持つ演劇作品として現代に再誕させることにつながる。
『かもめ』ほど、読めば読むほど、観れば観るほど面白い演劇はないだろう。噛むほど味が出る乾物のような深みを、私たちは2年かけて作り上げ、観客と共に体感し、かつ現代日本という「一度見ただけで分かりたい」人の多い環境に出現させようとしている。
4.登場人物たちを現代日本に置き換える
『かもめ』を現代日本に置き換えるということはつまり、登場人物たちを現代日本に置き換えるということになる。ようやく本題にたどり着きました。ポリーナを中心に、彼らをどのように現代日本に置き換えようと考えているか、まとめていきます。
ここから先は

「KAMOME」旅の記録
エリア51による2020〜2021年演劇企画「KAMOME」。企画・演出の神保による旅の日記(不定期)。チェーホフの名作「かもめ」にのせて…
ここでサポートいただいたお気持ちは、エリア51の活動や、個人の活動のための資金とさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
