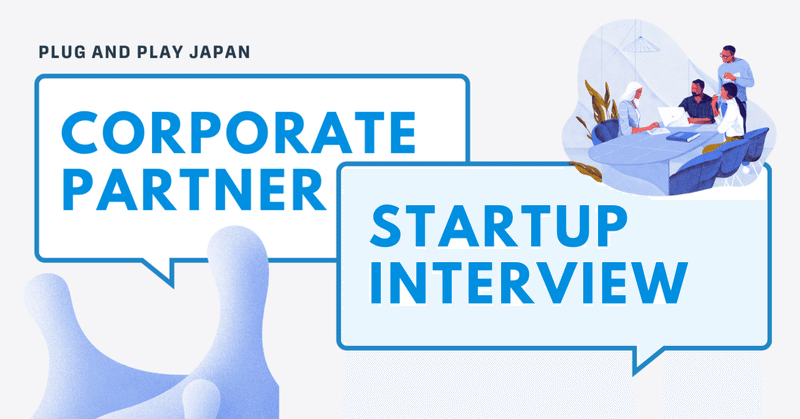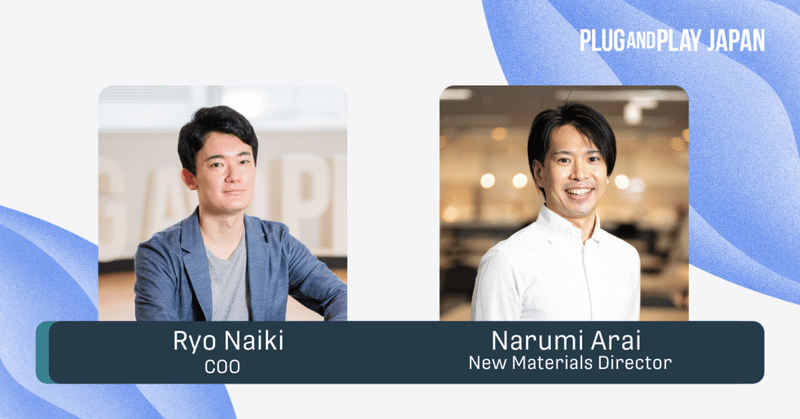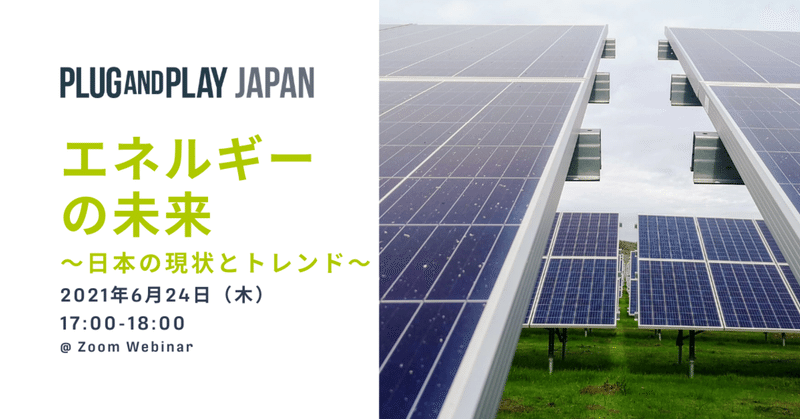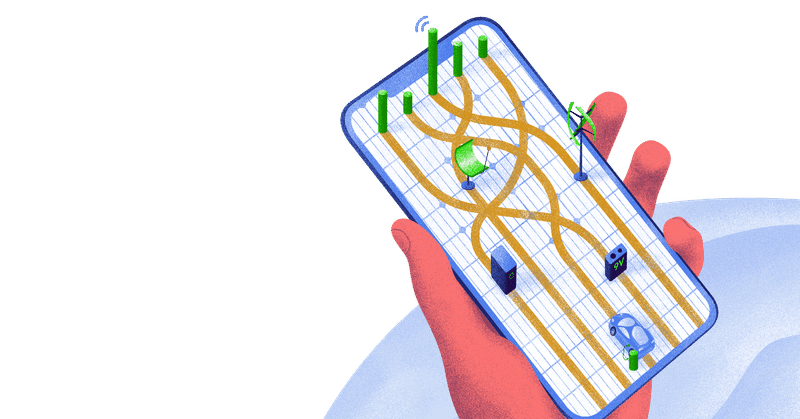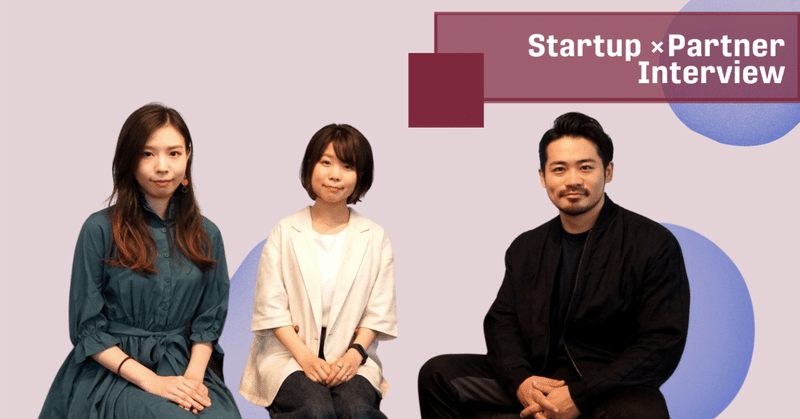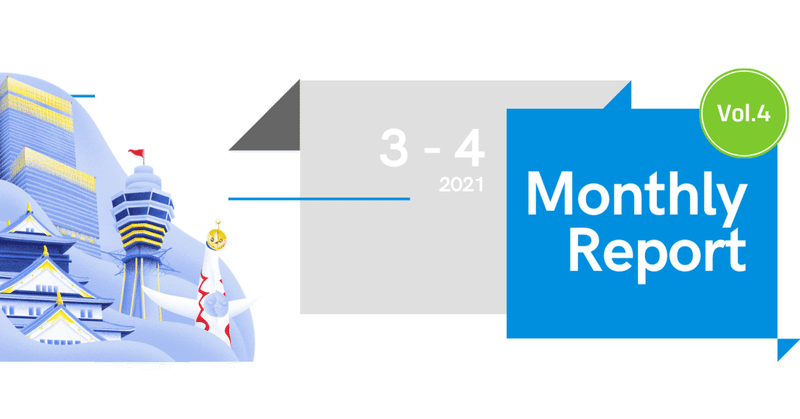#オープンイノベーション
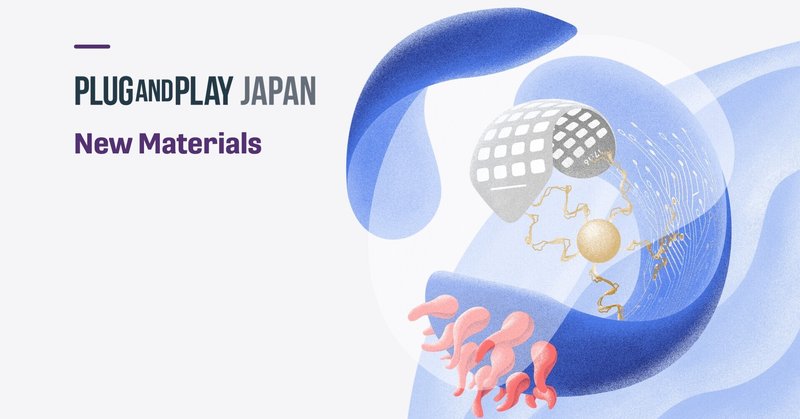
素材・化学分野におけるアクセラレータープログラムの開始 〜 Deep Techスタートアップ×大企業による社会課題解決の可能性 〜
はじめまして、Plug and Play JapanのNarumi Araiと申します。新テーマ "New Materials"の第一弾の記事として、テーマの概要と強調したい点についてお伝えいたします! 素材・化学領域の新テーマ立ち上げ Plug and Play Japanは2021年6月に新テーマである“New Materials”のアクセラレータープログラムを開始した。本テーマでは素材・化学領域のDeep Tech(*1)を用いてグローバルな社会課題解決を企図する8