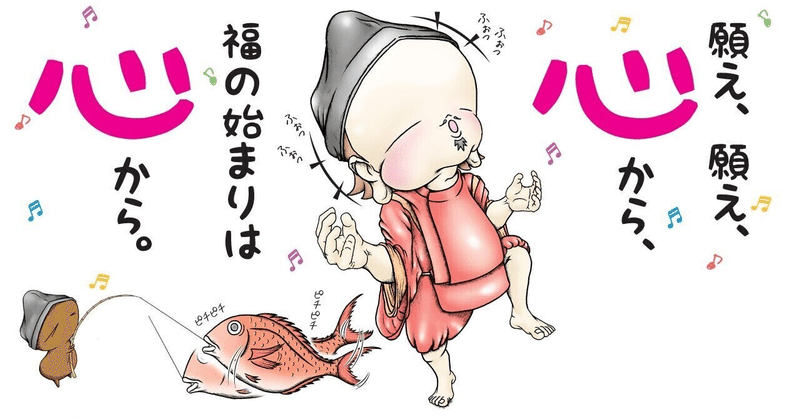
幸福の資本論 橘玲(5/100)
以前、著者のお金に関する本(お金持ちになれる黄金の羽の拾い方)で、人が幸せになる為には人間関係も重要であると述べてたため、本作に興味を持った。また自分が社会人4年目になり、今後の生き方を考えるきっかけにもなりそうだと感じ、読むことにした。
前回読んだ本同様、橘玲さんは非常に論理が明快な人で、一部因果関係を示す具体例が弱いと思った部分があったものの、読んでいて清々しいものだった。結論として、幸福に起因する要素は3つあり、それぞれを個人のライフステージや価値観に応じて最適化できれば、自分らしいストレスレスな社会を生きることができるとわかった。ただ、3つの要素のうち人間関係に関しては、愛情空間と貨幣空間の二元論で語られていたものの、現実はより複雑で人によって最適解が変わるのではないかと思った。一方で、なぜ人間関係で人は悩むのか、そのメカニズムを理解しておくと生きやすくなりそうだと感じた。
幸福を形成する3つの要素
人が幸せになる条件として、「自由、自己実現、共同体=絆」の3つをあげ、そのインフラとして「金融資産、人的資本、社会資本」の3つに大別することができると主張している。これはマズローの欲求5段階説に照合し、生理的欲求と安全の欲求は貨幣で解決でき、社会的欲求は社会資本の最適化、承認欲求と自己実現は仕事で達成できると考えると確かにこの3つに集約できると感じた。そして筆者はこれら3つを各々の価値観に応じて設計すれば良いという一貫した姿勢を持っていた。
金融資産について
自由とは「国家にも、会社にも、家族にも依存せず、自由に生きるのに十分な資産を持つこと」と定義している。
サラリーマンは税金を1億円払う一方で誰もが億万長者になれる時代だと述べつつ、具体的な資産形成の構成は明記していないが、金利や円相場など時代の流れを見極めて分散投資することが大事だと思った。
この章で印象的だったのは「限界効用の逓減」の話と長期的には株式市場は拡大するものの「長期的とはどのくらいのスパンを指すのか」ということ。お金は個人年収800万円、資産1億円を超えるとそれ以上は幸福度に比例しない。また、確かに我々は皆いずれ死ぬことを自分含め軽視している人が多いと思う。この事実を頭に入れた上で資産形成の計画を立てていく必要がある。
また資産形成においては支出を管理することも必須だと思った。金融資産は「収入-支出+資産×運用利回り」で決定する。まずは経済合理性に従った支出の管理をすることから始めたい。金融リテラシーを義務教育にすべきだという声も最近よく目にするが、スキルアップ以外に資産形成の為の勉強もすべきだと感じた。
人的資本について
人は仕事に対して求めていることを集約すると以下の3つとなる。
収入は多ければ多いほどいい。
同じ収入であれば安定していた方がいい。
同じ収入なら(あるいは少なくても)自己実現できる仕事がいい。
これらの前提に加え、今の時代について考えると人的資本の最適解が決まってくる。筆者によると、今は知識社会化、グローバル化、リベラル化が同時並行的に進んでいて、そこに適応する必要があると述べている。これが進むとこれまでの終身雇用、年功序列がますますうまく回らなくなる為、よりプロフェッショナルなスキルを持ち、知識社会に適応する必要がある。
こうした社会における、人的資本の最適化は「好きなことに人的資本の全てを投入すること」これに尽きる。
また、生物社会と同様にニッチを見つけ、そこで生き延びる視点も重要である。スキルを身につけつつ、好きなことをマネタイズできる生きる社会(ニッチ)を見つけ、自己実現を達成する。これを35までに実現する。
自己実現には自己分析が必須。MBTIなどのツールも使って、人生の軸や好きなことを定め、そこから社会や業界の分析を行い、ニッチを攻めていこうと思う。
人的資本の話の最後に仕事への価値観について触れたい。本書では、仕事を収入源として考えるか、キャリアとして考えるか、天職として考えるかの3種類あると述べており、その価値観によって生き方が変わってくると感じた。自分は人に比べて自己実現を追求していることから、労働を天職にしたいと考えているタイプなので、仕事に対しては充実感や社会的意義を求め、金銭的見返りや出世は気にせずに楽しく働き続けたいと思った。
社会資本について
社会資本は、家族や親友で構築される愛情空間と金を払えば構築できる関係性やコミュニティで構成される貨幣空間の二つで世界を分析しており、人は小さい愛情空間と大きい貨幣空間を持つことが重要だと述べていた。ここについては他の2つと異なり個人差が大きいと感じており、外交的な人や内向的な人によっても居心地の良い程度が変わると思った。
これからを生きる為に最適なポートフォリオ
これら3つの幸福要素の最適なポートフォリオとしては、「金融資産は年代やライフステージを考慮して分散投資、人的資本は好きなことに集中投資、社会資本は小さな愛情空間と大きな貨幣空間の形成」と結論づけている。
異論はないが、社会資本の貨幣空間に関してはどこまで広げると幸せかを各々が考える必要があると思う。また、それと同様に幸せの基準や将来の理想の生活を具体化することも大事だと感じた。
幸せには際限がない。実際多くを求めすぎて失敗してる人が数多くいる。特に金融資産や人的資本に関しては「資産1億、個人年収800万円、世帯年収1500万円が限界効用である」という研究結果があるので、まずはここを目標に計画を立てるべきでないかと思った。
私の暫定の基準としては
金融資産: 60歳までに資産1億円(年利4%で切り崩せば、病気になっても1人で生活できる基準)
人的資本: 35歳以降から目標とやりがいのある仕事をしつつ、年収800万円以上を維持
社会資本: 家族を持ち、月に1回会える友人を近隣に2,3人、年に2回会える友人を遠方に2,3組持つ
今回は幸福の構成要素に着目したが、人生の悩みから展開するとこの本には「健康」が抜けている。ストレスの多い現代社会に健康は精神的にも身体的にも重要なファクターだと思うが、健康は最適な睡眠と適度な運動、バランスのよい食生活で解決できると言われている。睡眠と運動はルーティーン化していけばなんとかなると思うが、食生活については知識が乏しいと思うので、いつか勉強しようと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
