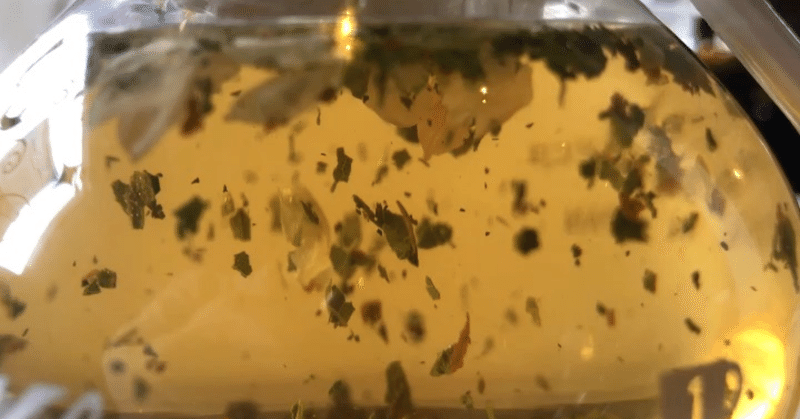
五十路の脳に刺激を ~ 宅建受験の話
40歳過ぎまでは数年に一度、仕事に全く関係のない分野も含めて定期的に資格試験を受けていました。
目的は、だらけた脳みそに刺激を与えるため。
単に「〜の勉強」では絶対にやらないので、少々お金がかかり、期限がはっきり決まっている資格試験が私みたいなケチな怠け者には丁度良いのであります。
過去10年強の間に取った資格は、↓こちら。
・イタリア語検定5級→4級
・愛玩動物飼養管理士2級
・ファイナンシャルプランニング技能士3級→2級
・医療事務
ふと「最近、何も受けてないなー」と思ったのが今年の夏。
昨年の春にはPhonics(発音が良くなると同時にヒアリング力が飛躍的に向上しますのでオススメ!)のマンツーマンレッスンを週1回×3ヶ月通い、それはそれで楽しかったのですが、とにかく楽しくて脳への負荷という意味では全然足りませんでした。
そんな矢先、職場(不動産業)の人に宅建を受けてみれば、とそそのかされたのです。(毎年、資格を持ってない新入社員は強制的に受験させられ、営業社員のほぼ全員が取引士の資格を持っている会社です。)
私は主に調査や資料作成をするPC事務担当者なので、宅地建物取引士の資格は全く必要ありません。
(なんなら不動産業やってる人が皆その資格を持ってるわけじゃありません。)
2019年10月20日の試験日に対し、私が受験を決めたのは申込み期限の7月末でした。
ミラクルで受かれば儲けものですが、さすがに世の中そんなに甘くないでしょうから、脳みそにそれなりに負荷のかかる勉強をすることを目標に掲げました。
スタートからして時間が圧倒的に足りてないのに、これが面白いくらい私のエンジンは全くかかりませんでした!
とりあえず勧められて買った初心者用のマンガ本を読んで、「ふーん」と思うくらい。
子どもの頃から地道にコツコツと勉強するのが大の苦手で、ほぼほぼ一夜漬けで生き抜いてきたタイプです。
ただ、過去に受けたFP2級は一夜漬けでは乗り切れない試験で、3級から受けるという方法を採用し、全体で2~3ヶ月は勉強しました。
あと、社会人になってすぐ会社(銀行のシステム専門子会社)にほぼほぼ強制で受験させられた第二種(現在の基本)情報処理技術者試験も、SEの仕事との区別が難しいですが、そこそこ勉強したはずです。
今回も働きながらですから、最低限そのくらいの期間は必要だとわかっていました。
わかってはいたのですが、私の「波」は1ヶ月前になっても全く来る気配がなかったのです。
それが忘れもしない9月24日、手頃なミニノートを買ったことで、急に勉強がマイブームになりました。
試験までの間に2回くらいの飽和状態がありつつ、体調も崩さず、最終的には試験勉強が楽しくなっていました。
終わってみれば、たぶん合格ラインは前年と同様37点前後(50点満点)で、私の得点は30点くらいだろうという感触。(その後の自己採点で33/50と判明しました。)
あと2週間くらい早く勉強を始めていれば…と「たられば」な欲をかいてもしかたありません。
それだと私の場合、2週間くらい早く飽きが来て終了だった恐れもありますから。
今回は、当初の五十路の脳みそに刺激を与える目的は達成したので、良しとします。
現時点で来年の再チャレンジは未定。
今は、もっと違う刺激を脳が求めていて、ソロバンに目が釘付けです。
とりあえず忘れないうちに、申込から3ヶ月弱の勉強期間(実質1ヶ月弱)における宅建受験の感想を書いておきます。
1.初心者向けの導入にマンガ本は良い
覚えることが多すぎてマンガで済ますのは無理でしょうが、とっつきやすいです。
特に私のようにイメージ(図とか絵)で記憶するタイプには向いてます。
2.テキストは自分に合ったもの1冊でいい
複数あっても意味はないと思います。
自分に合った読みやすそうな本を1冊、主に過去問の確認用に手元に置いておくと良いでしょう。
3.とにかく過去問を解きまくる
経験者は皆こう言うと思いますが、宅建はこれにつきます。
まず、独特の文章(言い回しや長さを含む)に慣れないといけません。
分野も多いし、それぞれの範囲が広いので、過去10年分くらいやっておくと安心じゃないでしょうか。
4.独学者はネットを活用
お金をかけない方法は、そこそこあります。
過去問や法改正のポイント、分野ごとの配点などをまとめたありがたいサイトやアプリが世の中にはたくさんあるので、遠慮なくお世話になりましょう。
私が利用した主なサイトは↓こちらです。
●過去問.com
https://kakomonn.com/takken/
●宅建2019『未来問』(資格スクエア)
https://www.shikaku-square.com/takken/miraimon
5.得意分野や勉強方法は人それぞれ、情報に振り回されない
人と比べると不安になります。
ググると色んな情報が転がってます。
でもまぁ、人と自分は違うので、自分に合った方法を早く見つけて、腹を決めて頑張るしかないです。
これでいいのか、もっといい方法があるんじゃないのか…なんてブレちゃって結局何も手につかないのは最悪です。
迷ったら、とにかく過去問を解きまくりましょう。
6.配点・傾向を考えて、捨てるところは捨てる
過去問や情報サイトを見ると、どの分野から何問出題されるのか、おおまかな配分がわかります。
仮に目標を38点くらいに設定したら、12問は捨てられる計算です。
「1問しか出題されない+どうしても苦手」なら、潔く捨てる決断もアリ。
逆に1問しか出題されないとしても、ここは得意だと思ったら確実に点数を取りに行きましょう。
7.飽和状態になったら無理はしない
超短期決戦だった私だけでしょうか。
1週間くらい調子よく詰め込んだ直後、何も入ってこない日がありました。
ちょうど仕事が休みの日でお天気も良かったため、お茶をしたり散歩したりして丸一日勉強から離れました。
それからまた調子よく勉強が進んだのでそれで良かったんだと思います。
(いや、本当はそういう状況も織り込んで、もっと早く勉強を始めれば良かったという話。)
8.模試は受けたほうがいい
私は受けなかったんですが、受けられるなら受けときましょう。
時間配分などの予行演習的な側面だけでなく、それなりに根拠のある予想問題ですから過去問と同じくらい価値があると思います。
9.前日と当日は心身のコンディション重視
私、これだけは絶好調でした。
前日は早めに寝て、当日は朝10時くらいに行きつけの喫茶店でブランチを食べて、余裕を持って会場について…。
すがすがしいくらい実力を出しきって届かなかったので、敗因は単純に勉強不足。
10.試験で気をつけたこと
①落ち着いて問題を読むこと。
特に、訊かれているのが「誤っているもの」なのか、「正しいもの」なのかに注意しました。
②マークする場所を間違わないこと。
③時間配分。
私は「権利関係や建築基準法などが不得意・宅建業法が得意」でした。
最初の5問の感触で前半に時間がかかりそうだと踏んで26問目に飛び、後半を先に片付けました。
おかげで前半に時間をかけることができ、最後に見直しの時間もできました。
合格ラインには届かないものの、33点まで得点が伸びたのは、このおかげだと思います。
結論:3ヶ月勉強すれば受かる試験です
せめてあと1ヶ月早く勉強を始めるべきでした、はい。
10年くらい前にFP2級で不動産や税の勉強をしたこと、曲りなりにも不動産業界で登記情報を見たり用語くらいは見聞きしていたこともプラスに働いてますが、何せ五十路のおばちゃんでも惜しいところまで頑張れたわけです。高校卒とか大学卒とか、受験資格がない太っ腹な資格。
私の場合、かかったお金は受験料と書籍代くらいなので総額1万円ちょっとです。
模試とかオンライン受講とか2~3万で可能だと思うので、皆さん、受けとくといいですよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
