
ひな祭り、桃の節句の由来と開運のためにやって欲しいこと
今回の記事では、3/3のひな祭り、桃の節句の由来と、人生を好転させていくためにやってほしいことについてガチ解説します。
え、ひな祭りにやることって雛人形を飾ることじゃないの?
と思った方もいるかもしれませんね。
それもいいんですが、雛祭りの本質を知ると、そっちの方がすごく大事なので、今回の記事を最後まで見て下さい。
✅日本文化を深く知りたい
✅東洋医学に興味がある
✅マニアックな話が好き
こんな方むけの内容となっております(`・ω・´)
▼高評価・チャンネル登録してもらえると嬉しいです(^^) 画面左上の陰陽マークをタップするとYouTubeへ移動します
動画の始めではひなまつりの基本的な解説、中盤ではこの解説が一体何を象徴しているのかさらに踏み込んだ解説、最後に紐解ける人生を好転させるためにやるといいことを解説してきますのでぜひ最後まで見てください!
まず結論から先に言うと、生まれ変わってほしい!
これだけいうと、雛祭りなのになんで?ってまったく意味わからないですよね。
五節句とは
五節句とは1/7、3/3、5/5、7/7、9/9の5つを指し、それぞれが別名、人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう)と呼ばれます。
この五節句は、中国では唐時代に定着し、日本に遣唐使を通じて日本に伝わりました。
実は、東洋医学と日本の行事は合体していて、四季の変化がある日本で元気に過ごすための工夫が、節句のような節目の祭り、行事としてみんなが自然とやる仕組みになってます。
日本の年中行事について詳しくなれば、自然と東洋医学の知恵を深めることができるんですよ。
桃の節句の由来

上巳の節句という言葉より、『桃の節句』の方が馴染みがあるかと思います。
「なぜ桃なのか?」というと理由は3つあります。
1つ目は、3月初頭が桃の開花期に重なること。
2つ目は、桃の木は、中国では病魔や厄災をよせつけない不老長寿の仙木と考えられ縁起物として扱われていたこと。
3つ目は、日本神話で黄泉の国に行ったイザナギノミコトが化け物に追いかけられたときに、いろんなものを投げつけて逃げきるエピソードがあり、その中で桃の木から桃の実を三つ取り、投げつけて化け物が退散することに由来して、邪気払いの神聖な木とされた。
こんなことから、桃の節句にするのはうってつけなんですね。
先ほども言った通り、節句にはもともと男女の区別はないのですが、菖蒲を「尚武」にかける端午の節句が男児のものとされるようになり、可愛らしい桃が象徴となる上巳の節句は女の子のお祭りとして変化していきました。
上巳の節句、雛祭りの変遷
上巳とは旧暦3月の最初の巳の日のことをさします。
その起源は古代中国で行われていた「上巳(じょうし)の節句」だといわれています。
この頃はまだ、女の子のためのお祭りというわけではなく、春を祝い、水辺でけがれをはらい、無病息災を願う厄祓いのお祭りとして行われていました。
日本に伝わってから平安時代には同様に人々は3月上巳の日に人間の形をした形代(かたしろ)や人形(ひとがた)を作り、それで身体をなでたり息を吹きかけたりして身のけがれや災いを移し、子どもが無事に成長できるようお祈りして、川や海に流し捨てた風習があったようです。

平安時代には人形に着物を着せて遊ぶことを『ひいな遊び』と呼びました。
雛人形の雛は古くは「ひいな(ひひな)」と書き、ひな祭りに飾る人形のことじゃなくて、女の子が玩具にする、紙や土、木などで作った粗末な小型の人形(ひとがた)のことをさしていました。
で、このひいなの役目は、単なる子供の遊び道具というだけでなく、さきほども解説しましたが、『形代』という役割があります。
つまり、子どもの身代わりになる、という役目です。
これはどういうことか?というと、何百年も前って、乳幼児死亡率が高かったんですよね。
昔の人は『邪気がやってきて、体に入り込んで病気になったり、死に至る』と考えていましたが、現代西洋医学の言葉でいうと『感染症』と言えるでしょう。
その邪気が、子どもの代わりに人形に入って子どもが助かるように祈願したり、流し雛に移したりしてたんですね。
現代に残る流し雛の風習

現代でも鳥取県用瀬(もちがせ)では、祭りが終わった時点で栈俵(さんだら)に乗せて川に流す、いわゆる『流し雛』の古習が見られます。
紙切れを流すというより、少し立派な形になっています。
このひいなが現代でも見かけるような贅沢な人形となっていくのは江戸時代からで、派手にする経済的な豊かさが出てきた頃です。
とはいえ、用意するのにお金がかかりますし、大型化してるので、捨てるに捨てられないですよね。
そんなことから、3/3日が済めば次の年まで大切にしまわれることになっていま
上巳の節句の本当の意味
ここから先がマニアックなお話になっていきますのでもう少し頑張って最後まで見てみてください(`・ω・´)
日本民俗学では流し雛の『穢れを移し、流す』風習を『罪穢れを払う禊ぎの名残、あるいは形が変化したもの』と解釈します。
神道の禊ぎは、日本神話でイザナギのミコトが黄泉の国で穢れた身を清めるため日向(ひむか)の阿波岐原(あわぎがはら)(今で言う宮崎県宮崎市)へ向かい、海水を浴びたのが始まりです。
黄泉の国からイザナギノミコトが還ってきてから行われたミソギは、穢れを祓うことを意味するだけでなく、生まれ変わり、新生の象徴でもあり、そこにもともと罪の意識などなかったわけです。
そして、
民俗学者の吉野裕子さんの解釈によると、流される人形(ひとがた)は、蛇の脱皮、ヌケガラに見立てられたものではないかとしています。
『蛇信仰』は古来の日本にもありますが、蛇の生理・生態から『脱皮』とは
『古い自分を脱ぎ捨てる』『外側を捨てる』『死と再生』『生まれ変わり』
のんなことの象徴でもあり、禊ぎの象徴とも共通点があるのです。
ミソギの語源は、『身体についた穢れを殺ぎ落とす=身殺ぎ』からきていて、身を殺いだものが抜け殻、というわけですね。
『禊ぎと蛇の脱皮が同じなんて、こじつけなんじゃないの?』って思われるかもしれませんが、上巳(じょうし)の節句『巳』は蛇を指す文字であり、上巳の節句とは、蛇の節句であると考えておかしくありません。
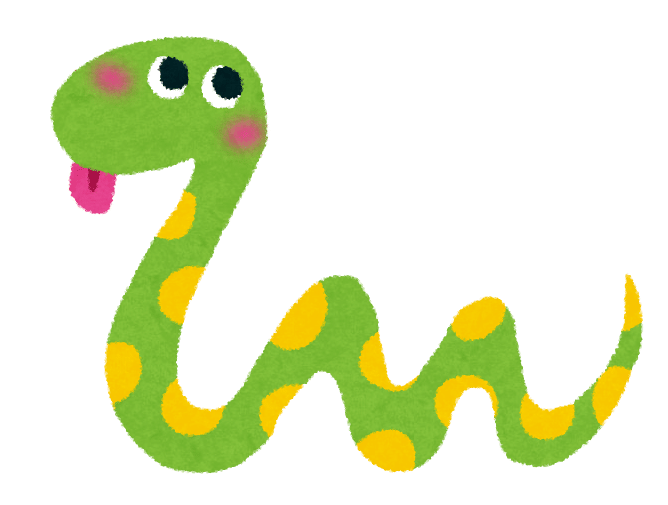
時期からひな祭りを紐解く

こちらは春夏秋冬、一月〜十二月までを十二支と八卦に割り振ったものです。
三月の卦は澤天夬(たくてんかい)、十二支では辰月(たつのつき)があります。
蛇の脱皮は、若い個体であれば月に一度、大人の個体であれば年に一度と脱皮の頻度はまちまちですが、冬眠を終えた蛇は、晩春〜初夏にかけてその年の最初の脱皮をして、生命の更新をはかります。
上巳の節句は蛇の脱皮の季節でもあるんですね。
さらに『脱皮前に蛇には水が必要です』
殻を水でふやかして、脱ぎやすくするんですね。
そこで、この古い習慣が水に深く関係する辰月(3月)の中節句にいつのにか結びつけられたものと考えられます。
澤天夬(たくてんかい)とは

澤…水の集合
天…高いところ
夬…物を裂く、物が裂け破れる
👇
『高いところに上った水は、容易に決潰して溢れ、下に降る』という意味。
地上の万物は、この水によって大いに潤います。
これを政治的にみれば、天子の恩恵が下に及んで、万民がそれに浴する象徴として受け取られます。
澤天夬は、高いところにある水が溢れて下に降る象徴です。
雪解け、水に流す時期
十二支の『辰』も、非常に水に関係します。
辰月、つまり、旧暦の三月は新暦の四月から五月にあたり、乾燥した冬から一転して、雪溶けしたり、雨が降ったり、川の水かさが増えてきます。
これらのことを念頭におくと、辰月の水が豊富な時期に水を使った年中行事が行われるのは自然なことでさが、流し雛を流せるだけの豊富な水は、雪解けの水や、澤天夬から得られるものである。
澤天夬は流れる水を指し、流し雛も『水に流す』のです。
このような水に流す、雪解け、というのは、水が豊富になる春先のキーワードになります。
上巳の節句にやると良いこと
流し雛を川に流したり、豪華なお雛様を飾ったりしなくても、厄払いや禊の形が変わった風習であれば、自分自身が水浴して禊ぎをすればいいわけなんですが、
それよりもとっても大事な意味としては、
冒頭にも言った通り、
✅脱皮=生まれ変わりましょう!
ということです。
さらに脱皮するために必要なことは、
✅雪解け、水に流す…過去のトラブルなどで悪くなった仲を一度リセットして、再度新しく関係性をはじめる。過去のいざこざをいっさいなかったことにして咎めない。
こんなことをするとより一層良いわけです。
こんなことがひな祭りに込められた深ーい意味です!
女の子の節句とも言われますが、男女問わずこの意識を持ってもらえたらいいですね!
『節句』とは一年の中に何回も訪れる節目です。
気持ちを新たにしてスタートし始めるたびタイミングとしてピッタリですし、人生の中に何度もチャンスがあります。
もしこの記事が面白かった、役に立った、という方はこれからも心身の健康と東洋医学のお話をベースとした発信をしていきますのでスキ/フォローお願いします😄
▼YouTubeでも発信してます。画面左上の陰陽マークをタップするとYouTubeへ移動します。高評価とチャンネル登録をしてもらえると発信の励みになります!
最後まで貴重なエネルギーを使ってお読みいただきありがとうございました。あなたが日々、穏やかに楽しく過ごせますよう、心からお祈りしています(╹◡╹)
