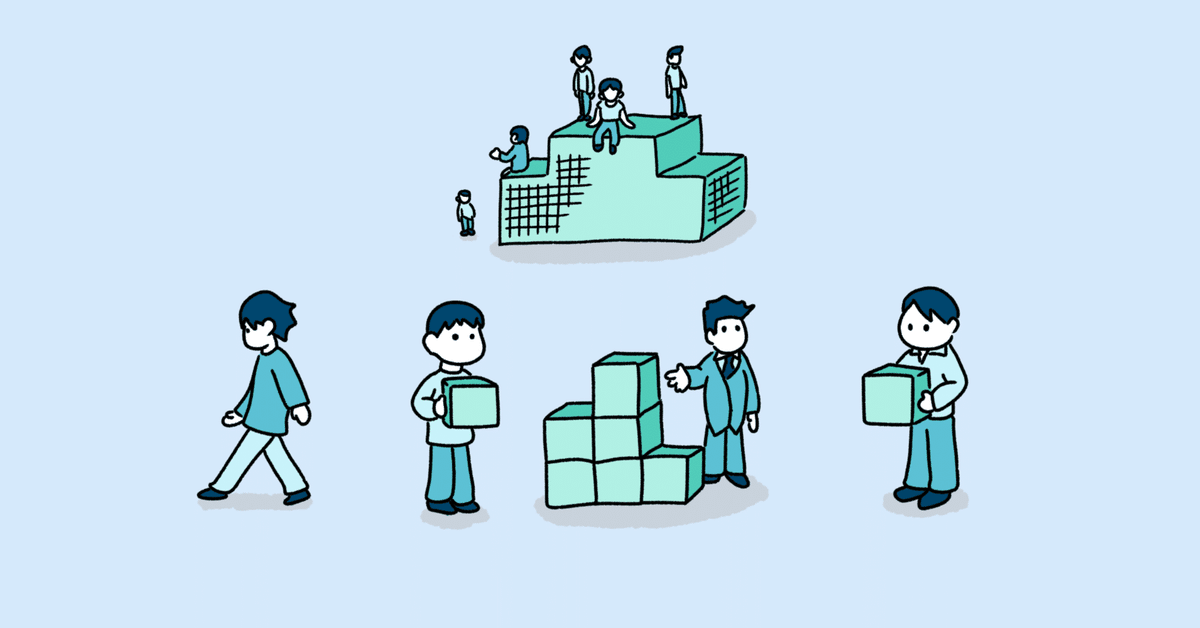
完了したか判断できるタスクの表現
誰であっても何らかの方法で今日やる仕事の予定は決めているはず。付箋だったり、メモ紙だったり、スケジュール帳だったり。
いや、これまで勤めてきた会社の中には、目に入ってきたことからとにかく手をつけるような人がいた。机の上に積みあがった仕事を上から順に処理していく人もいた。
実は過去の自分のことでもある。
片っ端から仕事に手をつけていくと、ほとんどの場合は優先順位を間違えてしまうので常に仕事に追われるようになる。抱えている仕事が積み重なり、とても苦しい。
でも、それがビジネスパーソンとしては当たり前のことだと思っていた。苦しいのは能力が足りないんだ。メンタルが弱いんだと自分を責めていた。
人は完了したことは忘れるが、継続中や中断していることは覚えているという現象がある。心理学ではツァイガルニク効果というらしい。これを知った時に腑に落ちた。
新卒で入社した百貨店では、目の前の仕事と並行して夏に冬のイベントの準備をしていたし、春に秋の商戦を考えていた。常に未完了の仕事を大量に抱えていたので気分がスッキリすることはなかった。もちろん、今考えるとどこでもそんなものなのだが、自分の中で仕事の優先順位が整理されていなかったので、毎晩ように「あっ、あれもしなきゃ、これを忘れていた!」と汗びっしょりで飛び起きていた。これはよくない。
繰り返すが、人は完了したことは忘れる。
忘れると脳の容量が空くので余裕が生まれ、メンタルは安定するし、パフォーマンスも上がる。この仕組みがわかれば解決策も見えてくる。
最低限やらなければならないことは3つ。
(1)タスクが整理されている状態を作ること
(2)その日に処理するタスクをリストアップすること
そして、
(3)タスクが完了したかどうかを判定できる表現を使うこと
例えば、「講演資料の作成」だと、どの時点が終わったという状態なのかが曖昧だ。だからタスクリストの中からなかなか消えない。
それよりも
「講演の構成を決める」決めたら完了する
「配布資料をメールで送る」メールで送れたら完了する
非常に単純明快。
僕は完了したら赤鉛筆で消し込んで自分を承認する。真っ赤になったスケジュール帳を見ると自己肯定感が上がるので、赤鉛筆で消せる状態を作るために特に表現には気を使っている。
仮に、完了しなかったのであれば原因を考えて改善すればいいだけ。
問題なのは、今日の予定が終わったのか終わっていないのかが判断できないこと。ここを曖昧にするから労働生産性も上がっていかないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
