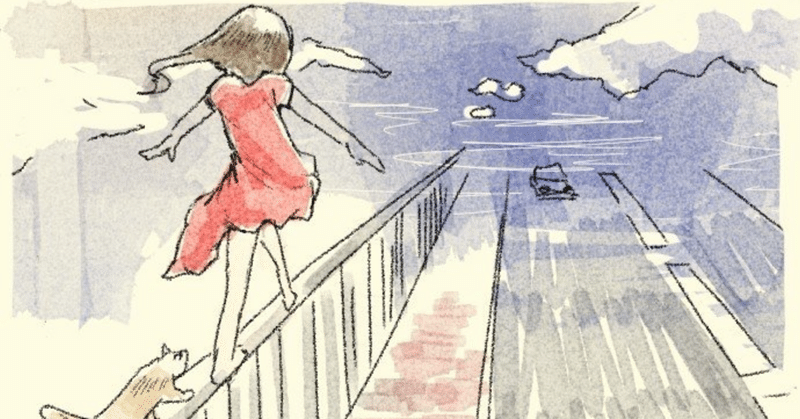
【小説】 声 (前編)
うちの会社の休憩室には四十いくつはありそうな大型のテレビがあるのだけれど、昼にそのテレビがついているところを見たことは一度もなくて、食べているときに何かが見たければ、みんなスマホかタブレットを見るし、食べ終わったあともスマホかタブレットを見るか、本を読んでいるか寝ているかのどれかだ。もちろん、外にランチに行く人もいる。
あの大きなテレビは、ながく続いた昼の番組が終わったあたりから誰も見なくなったんだよとは、スズキより五年先に入社した内海さんが言っていた。
今年初めてその電源が入れられたのは、スズキが知る限り休憩時間ではなくて大掃除をしていたときだった。年末は寒いし最後くらいゆっくりしたいという理由で、大掃除は毎年秋にやることになっている。十月の暇な日、仕事が一段落ついている人たちで。半年前に入社したスズキにとって、大掃除は初だ。掃除に加われなかった人は、その日にできなかった掃除を適当なタイミングでやることになっていて、仕事納めの日にはまたいつもと同じようなところが汚れたり散らかったりしているのだが、特に誰も気にしていないとか。
大掃除当日、スズキと春野さんと内海さんとで休憩室に入ったのは午後二時頃だった。春野さんが、家で掃除するときはテレビつけながらやるんですよせめてそれぐらいしないと気分が上がらないからと言ったので、内海さんがリモコンを探し出して、電源をつけた。スズキはちょうど、給湯室で三角コーナーを洗おうとしていたところだった。その位置からだと音は聞こえるが、画面は見えない。
「それって、けっこう汚れるよね、あみあみになってるとこが」
流し台でひっくり返されているかごを見て、内海さんが言った。
「そうなんです。普通のスポンジだとうまく洗えないんで、家からこれを持ってきました」
年は同じだけれども、学年がひとつ上の内海さんには安心して敬語で話せるが、仕事では先輩でもずいぶん年下の春野さんに敬語をつかうのはためらわれ、スズキはいまだに入り混じった言葉遣いをしていた。
百均で三本ひとまとめで買った歯ブラシで、網状になっている部分の汚れをこすり始める。この前これで水切りかごを洗っていたときには、それってまさか使いかけですかと自分より一月あとに入社した尾関くんに言われ、もちろん新品だと答えたけれど、排水溝でも同じことを部長に聞かれたから、今日一日使いたおしたらもう捨てようと決めている。
テレビからは、たぶんニュースとかドラマではなく、NHKあたりのドキュメント風の音楽が聞こえてきた。
「なんかそういうのって、どれくらいの頻度でやるべきなのかいつも考えちゃいますよ」
モップがけをしていたはずの春野さんまでが、内海さんの後ろから流し台を覗き込んでいる。内海さんが、汚れたなと思ったらでいいんじゃないと返答し、それから二人は各人の清掃に戻っていく。歯ブラシを無駄にするのはわかっていたから、無意味とは思いつつごしごし力を入れてこする。番組導入部のメロディが終わると、まろおみの声が今夜は渡り鳥の不思議を追いますと言うのが聞こえた。今夜と言うからには、再放送か。スズキは何気なく、まろおみも変わったなあと呟いていた。
「スズキさん、いまなんて言いました?」
窓枠を拭いていた内海さんが、再び給湯室に来た。
「まろおみがなんとかって、言いませんでした?」
「言いました。え?言ったかな?もしかして、声に出てたました?」
「出てたよ」
「この声、まろおみじゃないかなって思ったんで」
「まろおみって、絶対サイズあってないきつめの帽子から、いつもくるくるパーマ出してる人?」
「そう、そのまろおみです。はっきりとは、あれですけど」
「待って、調べるから」
内海さんはだっぷりしたニットカーディガンのポケットに手を入れ、またすぐ手を出して反対側からスマホを取り出した。検索をしているらしい指の動きを見ながら、スズキは濡れた手をタオルで拭いた。画面を覗き込もうかどうしようか考えていると、ほんとだ、よくわかったねと内海さんが言った。
「でも声ぜんぜん違くない?」
内海さんはテレビの声に全神経を預けるように目を閉じてから、あ、ほんとにまろおみに聞こえてきたこの前の大河ですぐ殺されたときの感じだよねと言う。いつの間にか、隣で春野さんも目を閉じて頷いている。そう思うのはわかるのだけれど、でも、それは違うとスズキは心のなかで訂正を入れる。
大河ではすぐ殺されるせいか、まろおみは甲高くて癖のある声を出していた。ただあの役のすぐあとに、弁護士役で民放のドラマに出て、その弁護士が今のしぶい声に近いのだ。強いて言うなら、大河の声が二割、ドラマの声が八割のミックス。でも、大河ドラマの持つ重厚さみたいなものが、二人の記憶を今作ったんだろう。
「スズキさんするどい」
自分の足元だけでモップを往復させながら、春野さんが言った。
「声を当てるのが好きなんだよ」
得意なんだと言いたいところを、スズキは好きに置き換える。
「他の人もわかります?なんか、探そう」
「わかるけど、掃除はしなくていいんですか?」
「えー、ちょとだけいいじゃないですか。どうせこの部屋毎日やってるからきれいだし」
内海さんはテレビにリモコンをかざしザッピングを始め、スズキはテレビが見えないように流しの前に留め置かれた。チャンネルが切り替わったのか、急に甲高い声が流れてくる。たぶんテレビショッピングだ。こんなのしかやってないやと内海さんの声が言ったけれど、感嘆詞まみれの短い声だってスズキの耳は正確につかまえられる。ラジオの司会をやっている人のくっきりと高い声と、昔星のついたバトンを手に魔法を使うお手伝いさん役をやっていた女優の声だ。内海さんはともかく、一回り下の春野さんに果たしてわかるものなのかと思ったが、当の春野さんがすごい、あたってますと言いながら次の獲物を探して動画を探し始めたので、給湯室から出られないスズキは、歯ブラシのあらたな使い道を考え始めることになった。
声を当てられるなんて、そんなのはだいたいの人間ができる。縄跳びで三重飛びができるとか、苦もなく箱崎ジャンクションを走れるとか、料理動画を見ずに鍋で完璧に米を炊けるとか、ミスのない仕事ができることよりもずっと簡単だし、どうせならそっちの能力が欲しかった。なんの役にも立たないからこれまで誰にも言ったことはなかったし、せいぜい妹に自慢したことがあるくらいだ。妹はつまらなそうに、それがどうしたのと言っただけだったから、二人の反応は面白い。それに、すこし嬉しい。それからスズキは一人を除いた五人の声を当てた。わからなかったのは、もともとスズキの知らないアイドルだった。
掃除の終わりが、その日の仕事の終わりになった。
「せっかくきれいにしたんだから、今日はあがりにしよう」と課長が言い、「飲みに行く人?」と、挙手を求めてきた。
忘年会がわりっていうか、掃除のあとは結局これなんだよね、と内海さんがスズキの耳元でささやく。手を上げたのは半分ほどで、スズキはまっすぐ帰る道を選んだ。飲みの人たちは常連にしている居酒屋に散り、スズキは電車に乗る人たちと駅まで歩いた。家は駅を通り抜けたところにある賃貸マンションで、電車を使わずに帰れるのは社でスズキ一人だ。いいなあ、スズキさん近くていいなあと羨ましがられながら、お辞儀まじりに手を降る。
日の差す大通りはわりあい暖かく、駅へと続く歩道橋を見上げると、喪服を着た男の人が三人かたまっていた。と思ったのだが、近づいてみると制服を着た男子高校生だ。三人の内の一人と目が合いそうになって、スズキは足を速めた。焦げ茶色をしたマンションの五階建ての五階、一番端がスズキの部屋だ。線路沿いにあるから駅のホームからでも見える。いま頭の上を飛んだムクドリの眼球にも映る。どれほど遠いか知らない場所に漂っている衛星にも映る。
今でこそ、こんなに近いところにスズキの家はあるけれど。
スズキはいつも歩いているか、乗り物に乗って移動していた。ひたすら動くということに時間をかけて生きていた。生まれて思春期もとうに過ぎるまで暮らしていた家は、一言で言えば遠い家だった。どこに行くにも遠い駅に行かなきゃいけない。誰だって駅には行くだろうが、スズキ家はまず駅に行くためにバスに乗った。最寄りのバス停は始発で、裏返せば終点だった。バス停までは徒歩二十分。これだけで遠さがわかってもらえると思う。もちろん、こんなものではない遠さを誇る人はたくさんいるだろう。でも、あのころのスズキにとってスズキの家は本当に遠かった。
玄関を開けると目の前に公園があり、子供の頃のスズキにとっては公園とそこを囲うように建っている家々だけが世界だった。ブランコと砂場と鉄棒、春にはシロツメクサが咲く。周囲をぐるりと松の木が囲い、よく松ぼっくりを拾った。どこかに出かけるたびに、スズキはそのまま公園に足を踏み入れて、ブランコをてきとうに二三回漕いでクローバーの咲く広場に寝転んで太陽の光に打たれ続けたいと思った。四角い公園の先には、工作が得意な友達の家があった。ただの白い紙をハサミとノリだけをつかって椅子やテーブルに変えていくのを見ながら、スズキは自分が極小サイズになって紙の家に住んでいると信じ込んだ。
公園が見えなくなると延々と続く家々の前を歩かされ、ようやく大通りに出たと思ったらガラス屋と電気屋と胃腸内科の前を通り過ぎ、六階建ての白いマンションが見えてくるとその斜向いにバス停がある。マンションの五階には、高学年になってから仲良くなった友達が住んでいた。紫色の絨毯が敷き詰められた狭いエレベーターに乗って上がったり降りたりするたびに、いつでもこの箱に乗る特権を持っている彼女をスズキは羨ましいと思った。そのうえ、ここはバス停からとても近いのだ。
始発だからと座れはしたけれども、どんどん乗客の増えていくバスの中で中学校、信用金庫、外科病院、ゲームセンター、歩道橋を見送るうちにだんだん息苦しくなっていく。途中の交差点でバスはよくひっかかり、乗客はじっと耐えながらシャッターの閉まった店と歩道に不当に置かれた花壇を見続けなければならなかった。あまりに長いので、気持ちが悪くなったこともある。運転手に降ろしてほしいと頼んだが、危険だから無理だと言われ言うだけ無駄だったと肩を落としながら、そのくせスズキは次のバス停で降りずに目的の駅まで乗り続けた。
駅に着いてそれで終わりではなくむしろ始まり、混雑する電車はいつも遅延していた。混雑するからこそ遅延するのかもしれなかった。今はもう、そんな生活とはおさらば、スズキは駅のホームから見えるこのマンションに住んでいるのだった。
★
年末になり、ふつうの会社なら大掃除をやっている日に、スズキは春野さんから声をかけられた。
「わたし、気になってることがあって」
そういう春野さんは、スズキの隣の席に座るとこちらに身を寄せてきて頭を低くしたのだが、本来そこに座るべき人は数秒前にトイレだかコピーだか、単に社内をうろつくために離席していた。だから、いつ戻ってくるかはわからない。
「なんでしょう」
「このまえ三階の会議室に行ったんですけど、会議の後に一人で。忘れ物をとりに」
いつもはなんらかの形でまとめている髪の毛を今日はおろしているせいか、春野さんはいつもより丸くて幼く見えた。スズキにその丸い顔を寄せて、声をひそめる。それでどうしたの。隣から声が聞こえるんですよ、でも隣、使ってないじゃないですか。だから変なんですよ。
「声って、誰の?」
「それがわからないんです。たぶん、二人います。小声で話してるような感じで。人に聞かれないように」
それは、今の自分達に似ているとスズキは思う。
「あ、スズキさん今なにを考えてます?」
「そっちこそ」
「やだー、スズキさん。エッチなこと考えてます?」
「いや、幽霊的なことですよ」
「なんだ、そっちかあ。いや、あれはそっちじゃないですよ。なんていうか、すごく平坦で事務的なんです」
「じゃあ、どっちでもないね」
スズキ達は体を起こして笑った。遠くの席から課長がこっちを見たが、べつに咎める風でもなく単に声に反応しただけの猫みたいに、すぐにパソコンに視線を戻した。そこ、なにしてるんだと言われるかもしれないなとスズキが頭の中で想像した課長の声は、重たい鞠をついているみたいだった。
「スズキさんに聞いて欲しいんですよね」
春野さんにそう言われたスズキは、それからパソコンをスリープモードにして席を立った。
仕事納めの今日は全員昼あがりだからご飯はなくて、スズキは朝ごはんをいつもより多めに食べた。パンをご飯に変えて、味噌汁と目玉焼きと納豆、それにバナナ。味噌汁はチューブだ。
半端すぎて何もすることがなくて、うらうらしている人と、昼までになんとかすべて片付けて今年を終えようと焦っている人と、どちらでもなくいつもどおりの顔をしている人たちを置き去りに、スズキ達は、二人で階段を降りていった。どうしてエレベーターでなく階段を使ったかというと春野さんがそれを選んだからだ。のぼりなら抵抗したかもしれないが、スズキたちの部署は七階で三階まで降りるのはわけもない、それに声を聞き分けることになにか関係があるのかもしれない。
階段から曲がってすぐが会議室で、その隣が例の備品室なのだが、実際に使用されているのは七階の元会議室だった場所で、こちらは手狭すぎたために、今では使いはしないけれど捨てるのはどうかというものを放り込むだけになっていて、誰も管理していない。したがって、人が入ることもめったにない。
抜き足で会議室に入っていく春野さんを見て、スズキは、彼女が声の目の前を通ることを避けたかったのだと気づいた。
二人して壁にはり付いている姿は滑稽だから、なにかの拍子に笑い出しそうだ。春野さんのおろした髪の毛がふわふわとスズキの肩にあたる。感触はないけれど、感覚はある。
社屋の手前の道を走る車の音はするものの、隣からは何も聞こえてこない。そもそも、いつも声がするものなの、今日はいないんじゃないのと言おうとしたとき、壁の向こうでぼそりとひとつ、声がした。
「聞こえる」
スズキが、声を出さずに口を動かすと、春野さんがスズキの目を見ながらゆっくり頷いた。スズキ達は、いっそう強く壁に取り付く。声は、ひとつからふたつとつらなり、ぼそぼそとした意味不明の音声が、少しずつ形をなしていく。
それで…だから…あそこは…ときどき…でも…
スズキの耳は、言葉の切れ端をとらえるけれども、言葉は断片的で、何を話しているのかはわからない。おそらくは女の人が二人。二人ともそれほど年寄りでもそれほど若くもない。そして、内容がわからないからなのか、二つの声を聞き分けられない。会話のようだけれど、なにせ個々の声が聞き取れない以上は、一人の人間が話しているといえなくもない。ただスズキは、なんとなくそれは違うような気がした。言葉を渡し合う感じ、伝え合おうとする感じが伝わってくるからだ。それがわかるのに、声は見えないのがもどかしい。声から感じられる二人が見えてこない。知らない声だからだろうか。
なんにせよ、これはスズキの知っている社内の人間の声ではない。
スズキが顔を横に振り、わからないということを春野さんに伝えると、春野さんはまた頷いた。それからスズキ達は壁から身を離して、会議室の端に移動した。
「たぶん、女の人の声。でも、誰かはわからないな」
スズキは声をひそめたまま言った。
「それは、スズキさんの知らない人だからですか?」
「どうだろう。わからない。隣はほとんど使ってないんですよね」
「です、です。だから気持ち悪いんです。やっぱり幽霊なのかな…」
「さすがにそれはないと思うけど。でも、外部の人間が入り込んでるんだったらまずいですよね。うちの建物って警備がゆるいから、前にも屋上でヤンキーが酒盛りしてたことがあるって、課長が言ってたし」
「やんきーってなんですか?」
「え、説明が難しいな。ちゃらちゃらした人のことかな?」
「そんな人が、あそこに入りますか?」
それもそうか、と考えていると、春野さんがいきなり姿勢を正してドアの方へ向かう。てっきり帰ろうとしているのかと思ったら、
「私、ちょっと見てきます」と言い出した。
「見に行くって、え?」
春野さんが部屋を出る、そのドアの開け方が華々しいのでスズキは隣の二人に聞かれるのではないかとヒヤヒヤする。
「え、待って」
続けて廊下に出た瞬間、二人が目の前に立っているのではないかと思って身構えてしまったが、春野さんが立っているだけだ。
「女の人らなんですよね。なら大丈夫ですよ」
春野さんはついてきてくれとは言わず、さっさと歩いていき、スズキもまた私も行くとは言えず動けないでいた。隣の戸はなぜか引き戸で、立て付けが悪いのか春野さんは開けるのに難儀している。いっそ開かなければいいと思いながら見守っていると、三度目の挑戦で戸は開いて、春野さんのやわらかな導線はすうっと備品室の中に吸い込まれていった。
目の前で扉が閉まり、スズキは一人取り残された。誰もいない三階の廊下は、ものすごく静かだ。スズキはあの交差点に閉じ込められて、窓から見ていた景色を思い出していた。あんなに混んでいたのに、バスの中は今と同じくらい静かだった。
一瞬思案したあとで、スズキは回れ右をして会議室に戻ると、そっと壁に耳をつけた。はじめは何も聞こえなかったけれど、目を閉じて意識を耳にかき集めていると、ぼそぼそとした声が聞こえてくる。
どうして…それは…でしょう…でも…なんなら…
声は、ぎりぎりのところで言葉だと分かる程度に情報を隠しながら、空気の波を使ってくるが、やはり話の内容はわからない。
備品室は、入ってすぐ左側の壁にスチールラックがびったりつけられている。棚には古いラジカセや、なにかの資料がつまったダンボール、ハンガー、忘年会の景品なんかが乗っていて、奥の壁に明り取りの窓があるが、スズキの身長では開けることができない。ぼんやりとした明かりを頭の中で見ながら、スズキはいったい自分はいつその光景を見たのだろうと思う。
やっぱり、ここを出て今すぐ春野さんの元へ行こう。勢い立ってドアを開けると、目の前に課長が立っていた。
課長はいきなりスズキが出てきたので、驚いてのけぞった。ここにいると聞いて探しに来たんだ。声質は重たいけれども、一度も怒っているのを見たことがない課長が、今日は仕事納めの日だからか、いつにもまして機嫌の良い顔でスズキに笑いながら言った。
「驚いたなあ。ここで何やってたの?」
「いえ、あの備品をとりにきて」
「ここに?とりにきたんだ、置きにきたんじゃなくて?」
「え、そうですね。置きにきました」
課長は一瞬腑に落ちないという顔をしたけれど、すぐに要件を切り出してきた。それは、スズキが昨日作成したばかりの資料の件だった。
「それなら」
説明をしようと思ったが、直接見てと言われて、その重たい鞠の声にスズキは戻らざるを得なくなった。隣の備品室からはまだ声が続いていたけれど、課長は聞こえていないのかあるいは聞こえていても気にしていないのか、そちらを見もせずにエレベーターのある西側に歩いていった。
席に戻って資料を作り直したあと、何本か電話がかかってきて、その対応に追われているうちにあっという間に一時間弱が過ぎてしまった。何度も部屋の中を見渡したが、春野さんの姿を見つけることはできなかったので、スズキはまさかねと思いながら、春野さんがまだあそこに居る可能性を考えて、もう一度三階に行く前に、尾関くんに彼女の所在を聞いてみた。スズキがこの会社で何も考えずにタメ口をきけるのが彼だけで、そのせいかなんでもするりと質問ができる。 すると、尾関くんいわく、春野さんは女子数人でお使いに行ったとのこと。最後にみんなで食べるお菓子と飲み物を買うために。
それでスズキも安心して仕事にとりかかろうと思ったが、あいにくもうなんの仕事も残っていない。しかたなく汚れてもいないデスクをアルコール消毒などして、春野さんを含めた買い出し組が戻ってくるころには社員全員がデスクを離れてわらわらと声も顔も混じり合っていたので、帰ってきた彼女の姿は見えなかった。最後の課長挨拶のとき、遠くの方に春野さんのつけていたひよこの形をした黄色いヘアクリップがちらりと見えたような気がしたけれど、それが彼女と結びつくのかはっきりしないままに、スズキはこの会社での年を終えていた。
声 後編に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
