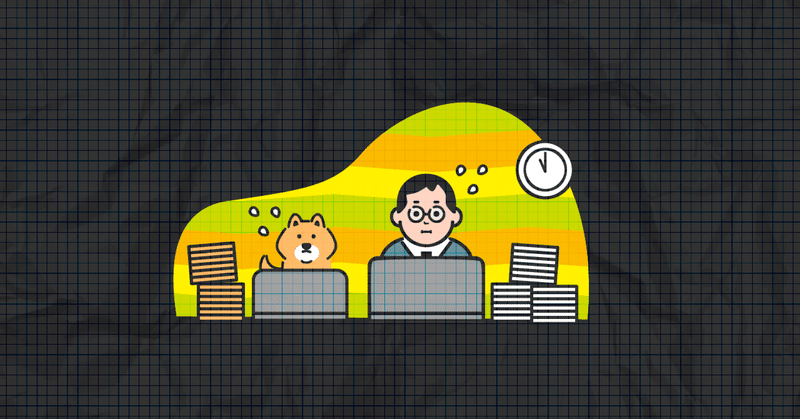
ストレス学会論文
「ストレスの社会的要因: ポジティブ政治心理学の視点から」
厚労省の問題意識
・なぜ政治・外交などマクロの社会的要因を入れ込んだのかは詳しく調べないとわからない
止揚とは
ポジティブだけでなく、ネガティブの方も見る
例) レジリエンス、トラウマの心理学
ボジティブ心理学は、ネガティブな心理学だけじゃだめだから、それに対する補助・補完的役割として使う
*レジリエンス力:うつ病に対する教育方法
子どもの貧困問題に対しても応用可能かもね
・海外の事例を調べたら面白いかもね
「労働者のウェルビーイングとポジティブ心理学・文明論的比較政治学」
ワーク・エンゲージメントとの関係
エウダイモニア志向(高い):ワーク・エンゲージメントが高い
ヘドニア志向(高い):ワーク・エンゲージメントが低い
エウダイモニア+ヘドニアが中央値よりも高い:ワーク・エンゲージメントがもっと高い
コンプライアンスについて
リベラリズム的な考え方:規制
コミュニタリアン的な考え方:善き生を選ぶ
リベラリズム的な考え方より、コミュニタリアン的な考え方の方がパフォーマンスが上がるのでは?
ドムス化とアンチ・ドムス化
ドムス化:特定の動植物に依存する
ex.) 稲作, 定住民
アンチ・ドムス化:特定の動植物に依存しない
ex.) 定住しない移動民, 遊牧民
ドムス化が進んで国家がつくられてきた
=垂直的な一般交換
*ボジティブな面:友愛の広がりやコミュニティ形成の一方で、ネガティブな面:納税しなきゃいけない
→ストレス増加
ドムス化について、ボジティブな面とネガティブな面があるのでは?
アンチ・ドムス化の方がストレスがないのでは?
緩境界化
・複数の組織に属する
・自律(自己コントロール)が必要
=新しい生き方
知覚された組織的支援(POS)
従業員が美徳が大事だと感じることも大事だし、組織においても美徳を重視する環境(従業員のwell-beingを可能にする環境づくり=有徳な組織)を作るのも大事
・美徳・有徳は普通は個人に対して使うが、組織論の文脈でも使われる
・美徳・有徳は組織論の文脈で使われると、卓越性(より良い、優れた)や道徳的という意味で使われる(byキャメロン)
・組織論の美徳には公正・正義も含まれる
・組織のあり方がコミュニタリアン的だと解釈できるという論文はある
公正・正義とwell-beingの関係性
POS:ミクロ的公正さとwell-beingの関係性が示された
先生論文:マクロ的公正さとwell-beingの関係性示された
・公正さや正義を(私が)重視すると、ストレスを感じにくい
犯罪心理学とポジティブ心理学について
犯罪者処遇におけるポジティブ心理学的アプローチの可能性 ―性犯罪者処遇の動向からの考察―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcp/52/2/52_35/_pdf/-char/ja
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
