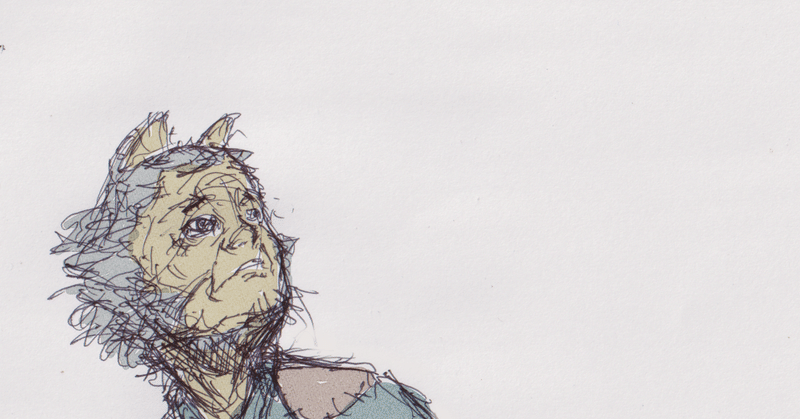
『墓守りバルザックの預かり:行方知れずの行商人』2話目
「タロベェ。これをして付いてきてくれ」
タロベェに耳栓を渡し、自分は部屋の隅にあった木くずを丸めて耳に突っ込んだ。
足音がドアの向こうに集まってきた。蹴破るつもりだろうか。
喧嘩は先手が必勝。蝶番を見て、刀を振った。
パタン。
ドアが倒れたと同時に、音爆弾を人影の中心に投げる。
キィイイイン!!
うずくまるエルフたちの脛を峰打ちして、ぬかるんだ道を逃げ出した。森に入ってしまえば、わからないと思ったが、そこら中に罠が仕掛けてある。
獣の道は通らず、ならべく藪の中を突っ切るように移動した。仕掛けられていた大きな石は坂に転がしておく。
振り返ると、タロベェもしっかりついてきていた。仕事じゃないと思えば、緊急事態でも身体は動くのか。
刀で枝葉を切りながら、進んでいくと山道に出た。この刀は丁寧に扱えば不思議と刃こぼれはしない。元主人が柄に何かまじないを施したらしい。
「どっちに行けばいいかわかるか?」
耳栓を取るように伝えてから、タロベェに聞いた。
タロベェは辺りを見回し、地面を触った。
「わからねぇ。なんだ、この道は? きれいすぎないかい?」
「水はけがいいってことか?」
「いや、そう言うんじゃない。療養所まで登ってきた道より、明らかに新しい。ほら、階段の木材だって……」
月明りで見難いが、確かに新しい木材でメンテナンスされている。
大きく息を吸い込んでみたが、雨の臭いが強くて人の匂いを辿れない。
「登っていけば、潰れた里があるはずなんだけど」
「行ってみよう。どうせ、町に助けを求めるのだって沢を下らないといけないんだ。朝になるまで体を休められる場所を探しておいた方がいい」
タロベェと一緒に、山道を登った。
元歩荷のタロベェが先を行く。体重移動の仕方が上手いのか、真似をして登ると、それほど足に負荷がかからない。
「追ってこられないように速く登っているつもりなんだけど、本当にバルザックさんは鍛えてるんだな」
「動けなくなると早く老けるからな。それよりエルフたちと仲間割れさせたみたいですまない」
「いや、おかしな点が多すぎたんだ。まだ、傷が治っていないはずの冒険者も下山したり、なぜかエルフの行商人が増えたり。炊事場も独占していたのもおかしい。復帰プログラムだってあるのに。そう考えたら、もしかしたら、あの雨の日に俺を捨てに行ったのかもしれない。食べ物が少ないって言うからキノコを採りに行ったのに……」
覆い隠していた木々が消え、里が見えた。
里の家々には明かりが灯り、入り口には山賊のような男がつまらなそうに立っている。
咄嗟に、タロベェの腕を取って藪の中に隠れた。
「里はなくなったはずだ……」
「どこか別の交易ルートを確保したということだろう。山賊に乗っ取られたのか、それとも里の人たちが自らクーべニアとの交易を断ったのか」
「ど、どうしたらいい?」
「とりあえず、入口の山賊から始末するか」
「殺すのか?」
「いや、これがある」
眠り薬の葉を見せた。
手拭いに葉の汁を染み込ませ、タロベェに失敗したとき用の閃光玉を預けた。
石を拾って、道の反対側の藪に投げる。
ガサッ。
「なんだ……?」
山賊の顔が道の反対側に向いたのを確認して飛び出す。
後ろから、口と鼻を手拭いで塞ぎ、眠り薬の葉を嗅がせた。そのまま首を捻転させながら体勢をのけぞらせる。あとは膝の裏側をコンと蹴ってやれば、あっさり後ろに倒れた。
周囲から見られていないことを確認して、藪の中に隠す。
槍とナイフを奪い、足の指を折っておく。鎧をはぎ取り、インナーを細切りにして腕ごと縛った。
「慣れているな」
タロベェが俺の手際を見て褒めた。
「墓守りだからな。眠っている人間の扱いは慣れているんだよ。さて、一番近くの家から行くか……」
明かりが灯る家の裏手に回り、窓から中を覗いてみると、里の人たちが集まって鍋を並べていた。
「こんな夜中に何をやってるんだ?」
タロベェが思わず疑問を口にしていた。
その声に反応して、中の人がこちらに気づいて窓を開けた。
「何をやっている!? 見つかったら、売り飛ばされるぞ」
「お前たちこそ、こんな夜中に何をやってるんだ?」
タロベェの言葉に、里の人が戸惑ったような表情をしていた。
「自分はクーベニアの墓守りをしているバルザックという者です。療養所がエルフに乗っ取られていることを、つい先ほど知って逃げてきたところなんですけど、あなた方はなんの作業をしていらっしゃるんです?」
「俺たちはエルフに騙されて眠り薬と幻覚毒を朝から晩まで作らされてるんだ。どうにか冒険者を呼んできてくれないか? 道が塞がっちまってるんだ」
「わかりました。すぐに呼びます」
すぐに通信袋で、クーベニアの冒険者ギルドと衛兵隊に連絡を取り、部隊を編成して山に入ってもらう依頼を出した。通信袋は少し高価な道具なので、なかなか普及していないが、遠くの人と会話ができる便利な道具だ。自分の場合は元主人が持たせてくれていた。
『人命優先でお願いします』
冒険者ギルド職員から要望があった。
「もちろんです。ただ、山道はすでに塞がれています」
『ちょっと待ってください。……でしたら、沢を使うといいと思います』
冒険者ギルドの職員たちが山の地図を広げて、逃亡ルートを練ってもらった。
「来てくれるのか?」
里の人は汗を拭いながら聞いてきた。外と連絡が取れたことで希望を持てたのだろう。
「いや、今すぐ逃げた方がいい」
「い……今すぐか?」
「エルフたちが俺たちを追ってきています。今のうちに準備をしておいてください。道を使わず、沢を下るんです。地の利がある里の人たちの方が、夜は有利ですから」
「でも、魔物が……」
「これ、コムロ印の魔物除けのお香が入っています。持って行ってください。里は必ず取り戻せます」
「わかった」
里の人たちは戸惑ってはいるものの、準備を始めた。
「山賊たちがいる場所はどこかわかりますか?」
「里の中心にある、ほらあの大きな家だ。これ、使えるか?」
里の人たちが作ったばかりの毒薬を渡してきた。
「助かります」
「頼む」
握った拳に悔しさが滲んでいた。
畑の薬草が枯れずに育っているということは、時間と手間暇がかけたんだろう。
初めのうちは協力していたのか。
本当は自分たちでどうにかしたかったのだろう。ただ、儲け話に飛びついてしまった里の人たちが、自分たちがどうなるのかわかっていなかった。いつの間にか助けも呼べない状況になっているとは夢にも思わなかったのだろう。
タロベェを連れて、里の中心にある大きな家の様子を探る。小さな砦のように物見やぐらを建てて、畑で作業をしている里の人たちを監視していたようだ。
今は家の中で酒盛りをしているようだ。里の人に働かせて、毒で儲かっているのか。
「酒だけじゃなく、毒も喰らってもらおうか」
手始めに里の出入り口にいる山賊を薬で眠らせて、足を折っておく。他の家にも逃げる準備をさせてから、中心の大きな家へ向かった。
「ハハハッ! エルフの国様だなぁ」
「そろそろ反乱が起きて、こっちにも飛び火してくるのか?」
「どっちにしろ俺たちは稼ぐだけよ」
山賊たちの高笑いが聞こえてくる。
ドアの蝶番を切り、タロベェが蹴破って閃光玉で目を潰す。
後は眠り薬の瓶を手当たり次第に投げつけ、出てきた山賊を出口で待っているだけ。
タロベェが理解して頷いたのを確認し、ドアの蝶番を切った。刀も鉄だし蝶番も鉄なのに、やはりこの刀は切れ味がいい。
パキンッ!
タロベェの前蹴りがドアを吹き飛ばした。
ヒュン、カッ!
閃光玉が中で弾け、屋根の隙間から夜空に向かって光の線が伸びた。
「アアアッ!」
「目がっ!」
山賊たちが目つぶしを食らっている間に、空いた入口から眠り薬の瓶を投げ込んだ。
パリンパリンと瓶が割れる音が鳴る。これだけでは山賊たちは眠らない。
「やめろ! こっちに来るな!」
「クソッ! 眠り薬だ! 転ぶな!」
「それは俺の鎧だ! 掴むな!」
揉み合って倒れる音が聞こえてきた。眠り薬が撒かれた床で転び、鼻や口に入って徐々に意識が保てなくなる。
「誰だ? お前は……?」
眠り薬まみれの山賊が、こちらを見ながら出口で倒れた。他の山賊たちは出口まで辿り着けずに玄関の手前に積み重なっていった。
マスクをつけて、タロベェと一緒に武器を集めて籠に放り込む。山賊をロープで縛り上げ、靴を脱がせて、屋根の上に放り投げておく。裸足で山の中を駆けだせるのは、魔物くらいだ。
家の前で篝火を焚き、里の人たちが集まってくるのを待ち、沢へと向かう。
「あんたがたがいれば、エルフも倒せるんじゃないか?」
里の人がタロベェについていきながら聞いてきた。
「そんなに簡単にはいかないもんです。相手は別の国とも繋がってる組織ですから」
橋の下を通り、沢を下っていく。先頭は一番山に詳しい里の老人だ。子どもたちも母親に背負ってもらっている。タロベェは腰の曲がった老人を背負っていた。
「歩荷だったので、これくらいは荷物のうちに入らないですよ。ただ、これから道もなくなって険しくなるし、水に浸かると思うんで勘弁してください」
岸辺を歩きながら、周囲に気を配っていた。
山には魔物も多い。夜になると梟や蛇の魔物も出てくるという。
「一番怖いのは熊さ」
先頭を行く老人が話しかけてきた。
「今は冬眠前ですもんね」
「いや、この山には主みたいな熊の魔物がいるんだ。灰色の毛をして40年は生きてる。あれに襲われて、行商人も一気に来なくなっちまった。他の里も家ごと潰されたところもあるからな。油断は禁物だ。一歩森に入ったら魔物の領域さ」
もしかしたら、行商人ハロルドは熊の魔物に襲われたのか。
「その襲われた行商人って、二年くらい前にお香を売っていませんでした?」
「どうだったかな。もう、時が経っているからなぁ。療養所にも通っていたみたいだから、いろいろ売ってはいたんだろう」
「それ、ハロルドじゃないかい?」
眠っている子どもを背負った里の女が会話に入ってきた。
「知っているんですか?」
「知っているも何も、鎮静剤になるからって、里で幻覚の薬草を育てようって言ったのはハロルドって行商人さ。冒険者ギルドとも話をつけて、全国に卸そうとしてたんだけどね。行商人たちが皆来なくなった後でも、あの人は来てくれたんだけどね……。他の儲け話に飛びついたのかな」
里の女が足元に気を付けながら、ぼんやりと言った。
「ハロルドさんがそんな不義理をするわけない!」
闇夜に声が響いた。声の主はタロベェだった。
「タロベェさん、ハロルドって行商人の方を知ってらっしゃるんですか?」
「俺は歩荷だから行商人の荷物を背負うこともある……。ハロルドさんとはよく仕事をしていたんだ。そうだ……、思い出した……」
タロベェが話し始めた時、沢の上流の方から人の声がした。
「こっちだ! 人の足跡がある!」
「魔法で照らせ! 冒険者にバレると厄介だぞ!」
エルフが追いかけて来たか。
「積もる話は後にして、とにかく今は逃げよう」
里の人は16人で、自分とタロベェを合わせて18人だ。これだけの人が移動していたら、どうしたって見つかってしまう。
沢を渡り、岸辺の砂利を踏み、なるべく足跡を消しながら進んだ。水に浸かって震えるほど身体は冷え、里の人たちの体力を奪っていく。
気持ちは急いでいるつもりでも身体が前に進まない。
「止まってくれ。これ以上いけない……」
先頭の老人が皆を止めた。
「休んでいる暇はありませんが、やはり一度休憩をした方が……」
「そうじゃない。先を見てみろ」
沢の先に、大きな岩の影があった。
じっと見ていると、その岩がもぞもぞと動いているのがわかる。
岩がこちらに気づいたのか、身体を持ち上げて月の明りに照らされて、ようやく姿が見えた。
銀色に輝く毛並み。真っ赤な口には鋭い牙が並んでいる。
鼻を鳴らして周囲を探るように立ち上がった姿は神々しくすらあった。
「あれが主だ」
後方にはエルフたちが迫り、前方には山の主が獲物を探していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
