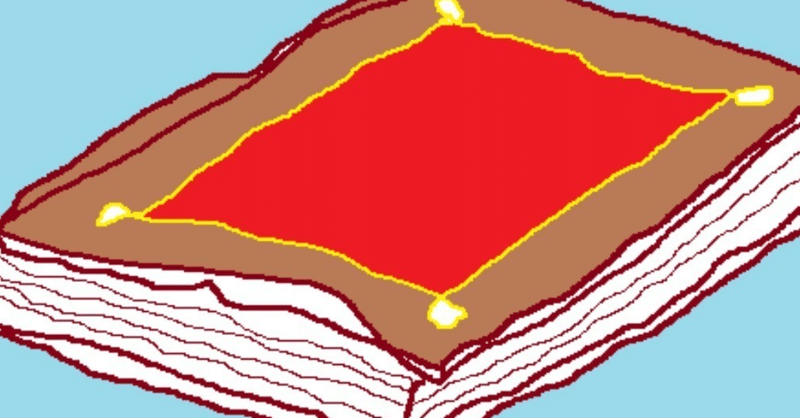
歴史を読む
Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World, 1783 - 1939(James Belich著、2009年)を読み始めています。
何故興味を持ったか?というと、ヨーロッパ中心主義・植民地主義歴史観に対する通り一遍の批判に留まらない、細かい分析がなされているとの書評に出くわしたから。
そう。白人たちは白人たちで自己の歴史を批判的に分析していないわけではない。
けれども、総じてそれほど批判的とも思えない。
そういうじれったさが少しは軽減されないか?という期待を持って(あまり期待はしていないけど)。
何故あまり期待していないか?というと、甘めの自己批判は別に歴史という分野に限ったことではないし、よって、一歴史家による特定時期・特定地域の歴史に限った分析のみで、今の今まで十分とはいえない(自己)批判が一気に大前進するというのはありそうにない話だから。
それはともかく歴史は面白い。
COVID-19による巣ごもりを利して、不朽の大作と言われるFernand BraudelのThe Mediterraneanもぼつぼつ読み始めているんだけれど、実際のところどうだったんだろうなぁ?と想像が掻き立てられるのは楽しい。
有名人がどうしたこうしたとか、法律やら制度の名前や中身とか、、そういういわゆるメジャーなイベントにはほぼ興味はない。
陳腐な喩えだけど、もしも自分がその時代その場所で生きていたとしたら・・・、という感じの、圧倒的大多数の人間がどうやって生きていたのかなぁ?という想像。
『Replenishing…』の主題は本のタイトルにある通りアングロサクソンがどうやって急速に栄えたのか?副題には合衆国独立直後の1783年〜とあるけれど、それ以前、スペインやポルトガルのアメリカ大陸進出にも触れられている。比較のため。
まだまだほんの出だしだけど、ヨーロッパ各国から西インド諸島を含むアメリカへの移住の試みにおいては、相当の人間が命を落としたらしい、という当初の定住(成功?)率の低さに色々と考えさせられるものがある。わりと長い、非常に困難な時期を経て、19世紀終わり〜20世紀初頭あたりから一気に帝国主義・植民地体制が機能するようになったというところは、場所や時代は違えども、『The Mediterranean』にもほぼ相似形のいきさつ(15~16世紀の地中海地域の開発にまつわる艱難辛苦)が描かれていて、アングロサクソンに限らず、ヨーロッパの人々のしつこさというか執着心には恐れ入る。
ただその執着心も、自己批判は大して真剣でないと言った通り、古代ローマやそれ以前から脈々と続けられているやり方、人間観、世界観というのは、強さというよりも、とある一面を意識的にかどうかは分からないけれども、頑なに無視し続けているという弱さにその原動力があるのではないか?と疑っているので、全く肯定的にはとらえてないんだけどね。。。
人間は冒険する動物であることに間違いはないだろうけれど、十分に細やかな神経を持っておれば、そこまでは殺せないだろうし、殺しちゃえば心に傷ぐらいは残る。ところがこれまた人間は習慣の動物ともいえるわけで、あまりに殺し慣れちゃうと大して負い目も感じなくなる。
現代はヨーロッパ由来の人々に限らず全世界で、殺しまくっても気にならない、人命も文化も魂も何もかもモノ扱いでいい。それが一番効率的というやり方になってしまっているんだけれど、多くの人は葛藤の末に自分自身に「それで仕方なかろう」と納得させているわけではない。どちらかというとそんな残忍・冷酷なやり口には断固として反対していると思い込んでいる人の方が多いようだ。
「殺した」んじゃなくて「ただ死んだだけ」なんじゃないの?
それなりのお船に乗って出かける以上、個人の力だけじゃ無理だろう。船団を組織する人、希望者を募る人、応じる人々。。。社会的経済的理由で出かけていかざるを得なかったのか?そうであったにしても、何十万何百万という人間が、長期にわたって、あたかも一攫千金を狙ってでもいるかのように、成功率の低い船旅に乗り出し続け、そしてバッタバッタと死んでいったということは、ただ困窮していたというのではなく、そうなるまでに長期にわたる蓄積が延々となされてきていた、ということなのではないか?
現代の中間層とは生活様式や生計を立てる手段など比べるべくもないのだろうけれど、母国(生まれ育った地域)で奴隷として働かされ続けるのではない層。最下層とはいえない層。そういうものが形成されていて、継続的に大して安全でもない冒険に人材を供給し続けていたのではないか(オーストラリアは囚人たちだったらしいけど)?
『Replenishing…』もそうなんだけれど、批評的分析というと、何かと「〇〇が”優れていた”から・・・」というような分析・言説を避けようとする傾向がある。それ自体は誤りであるとはいえないけれど、そう言っておきさえすれば免罪符が得られるというもんでもない。
社会的分業がゆっくりとでも進んできていたのであれば、分業が進んだなりの生活の仕方があったはず。分業という以上、各々全く日常的には関わり合いのない生活をしていた者同士とはいえ、同じ社会に何がしかの貢献をしていたはず。その”社会への貢献”というのが、とある層では「中々厳しい見通ししかない冒険への参画」というカタチであったわけだから、「見殺し」とまでは言わないまでも、その層の人々には社会のために「死んでもらってた」ぐらいの関わり合いはあったと言えるんじゃないか?そういう経緯があって、今のアメリカ合衆国のような現代文明の権化ともいえるものが出来上がったのだし。
長期にわたって蓄積されていたものというのは分業。つまり、多くの人間が集まって暮らせるぐらいの富の集積(及び分配)の仕組みがあったであろう、ということ。「集中と分配」というのは、特に支配者の側からすれば容易に意識できるだろうけれど、その下で生活する圧倒的大多数の人々が意識していたとは思えない。それは現代の私たちだって同じ。何も知らないわけではないけれど、一人一人の生活、そこでとられる行動が、集中と分配に貢献している、なんて実感はほとんどない。実感なかろうが生きている。そこんとこにある意味に非常に興味がある。
歴史に関わる本というのは、それが全くのフィクションである小説であったとしても、現存する記録に多くを依存する。あまり庶民の日々の生活の意味とかは直接は読み取れない。商取引の記録、経理書類、日記などなどもないことはないけどね。それでも想像する手掛かりぐらいは提供してくれる。
不意に与えられた時間。たっぷりかけて、ゆっくり想像してみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
