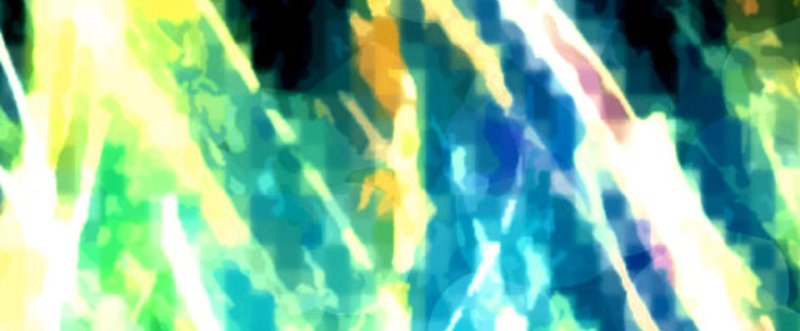
白黒の真昼
微かに煮炊きの香りが漂う街で、虫が鳴り出した己の腹を満たすようにクロワッサンを一つ買った。
カフェのテラス席に腰をかけて、今しがた買ったそれをかじってもぐもぐやりながら、ココ・メアリーはテーブルに頬杖をついて溜め息を吐く。一口かじったクロワッサンをテーブルの上に置き、彼女は期待外れといったような目線でその小麦の塊に視線をやり、眉間に皺を寄せた。
(何これ、味がしない……砂喰ってるみたいだ)
少女――タンポポの髪飾りをつけたとうもろこし色の髪に、天色の瞳、いきなり現れたと思ったら自分に美味しいからと言ってクロワッサンを差し出してきた彼女、自分が別れ際に〝ソライロ〟と呼んだあのおばかさんが自分に渡してきたものと同じのはずだった、このクロワッサンは。あのときは確かに味がしたはずなのだ、それなりに美味いとも感じたはずだった。優しい甘みと、どこか懐かしい香りがこのクロワッサンには在ったのだ。それが今はどうだ、これときたら味もしなければ、飲み込もうとするたびにいちいち喉に引っかかって食べにくいことといったらこの上ない。大方、見習いが焼いたものでも押し付けられたのだろう。ココはそう結論づけてパンを机の端に寄せると、気だるい動作で店員を呼んでこの街に来るといつもこの店で食べる一つの料理を注文した。
(結局、いつもこれだな……)
それからしばらくして目の前に置かれた、飾り気のない白い深皿とその中に満たされている燃えるように赤いスープをココは眺め、右手で木のスプーンを持つとそのスープを掬い上げた。それに口を付けると同時に、目元まで上るような赤みを帯びた香りが鼻を通り抜ける。ココの舌と喉はこれからやってくるのだろう焦げつく辛さを予想して微かに震えたが、ココ本人はさして怯える様子もなく、もう慣れたものだというように木の匙に掬った一口を飲み下した。
(ああ、やっぱり……)
続けざまにスープを掬っては飲む。ココは相当辛いだろうそれを相手に汗も流さず、クロワッサンを食べるときと同じように涼しげな顔でついには深皿を両手で持ち上げ、面倒になったのか一気にそれをすべて飲み干した。唇を舐め、それから口元を拭う。舌はスープのその赤さにひりつき、喉は燃える辛さに焼けて空気を自身に取り込むことを拒んだが、ココは依然として涼しげな顔のままでテーブルの端に載ったクロワッサンを睨み付けた。
(やっぱり、これじゃないと食べた気がしない)
燃えるスープの跳ね回る痛みをその舌に残したまま、ココはクロワッサンを指先でつついた。それは時間が経ったせいでパン屋から受け取ったときよりもぱさぱさになっており、さながら落ちた木の葉の感触を真似ているようである。ココは脚を組んで溜め息を吐く。
……そもそも、少女と別れてから、自分がすぐにこの街に戻ってきた理由が分からなかった。此処が比較的よく来る街だとは言っても、そこまで頻繁に訪れるほど気に入っているわけではないし、特に強い思い入れもこの街にはない。ココは最早食べる気も起きないクロワッサンを眺めた。
おそらく自分は、これが食べたかっただけなのだ――味は、期待外れもいいところだったが。それはそれとして、自分は物心がついた頃から、食べ物の味なんてろくに分からないままなのだ。だから今のように刺激の強い食べ物ばかりを口にする。そうしないと、何かを食べた気がしないのだった。何を食べてもいつも砂を噛み続けているような気分になるのだ、それがどんなに高級なものであろうと、ごみのようなものであろうと、同じように。しかし、あの空の瞳をした少女が手渡してきたクロワッサンには味が在った、それを感じることができた、確かに、確かに在った。だからあのクロワッサンを、このクロワッサンを食べれば、何かが取り戻せるような気がしたのだ。何をだろう、分からないが、何かたいせつなものを取り戻せるような気がしたのだった。ココは瞼を閉じて、吸うことによって喉元で熱を帯びる空気を肺に呼び込んだ。――もしかしたら、家族と食べる料理というものは、あんな風な味をしているのかもしれない。
(……馬鹿らしい)
ココは自嘲するように口の端を歪めると、空っぽの心臓の底より底で微かに羽を広げようとした炎を吹き消した。テーブルの上に幾つかの銅貨と銀貨を置くと、ココは立ち上がってカフェのテラスを後にした。街を抜けるついでに濃いめに淹れたという黒い珈琲を出店で買うと、彼女はそれを一口飲んで顔をしかめる。辛いだけだ、あの液体は。苦いだけだ、この液体は。街から出て少し行ったところでココは手に持った珈琲を逆さにすると地面に飲ませ、そこに黒い斑点を描き出させた。行きたいところはない、だが帰るところもない。死にたいわけではない、だが生きたいわけでもない。生きるために、死なないために始めた博打も、たとえやめたとしても贅沢をしなければ人生を何回か送ることができるくらいの地点にまで登った。わたしはこれが好きなのだろうか?――いいや、好きだ。自分はこれをしないと生きていけないのだ。そう自分へ言い聞かせて、ココは街に背を向けて歩き出した。生きるために、賭けている。自分を生かすために、賭けているのだろう。強い光が閃く緑の瞳は、頭上に輝く太陽とは目を合わせない。土を踏む乾いた音ばかりが今、ココの周りには漂っている。何を取り戻せると思った、自分は? 何を取り戻そうとした、わたしは? こんなにも馬鹿らしいことはない。こんなにも、つまらないことはない。ココは土を踏んだ。眩しい太陽に照らされたココの後ろには、濃く色を映した影が揺らめいている。それを知っている彼女は、振り返らなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
