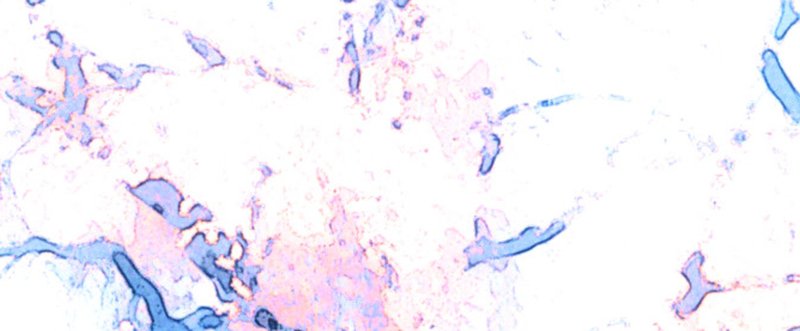
無痛の夢をみるよりも
――心に剣を持て、とその人は言った。
心に剣を持てよ。しなやかで強かな、決して折れない剣を。
あの人があの人を殺めた。その、幽霊が発するような小さい声を、まだ幼い耳が拾う。アマヅツミ・コト――コトという、まだ十になったばかりの少女は、瞼の裏に焼き付いた赤黒い海をその瞳に昏く宿しながら、大人たちのその声を聞いていた。
(あの人、とは……父さまのこと……。殺されたのは、母さま……。父さまが、母さまを……父さまが……父さまが……)
父が母を殺めたことを、コトは言われずとも分かっていた。いや、むしろ、誰よりも分かっていたのかもしれない。この十の少女は、目の前で父が母を殺めるところを見たのだから。
こんにち、コトは自身の叔母に引き取られる。気味悪がられ、たらい回しにされた小さな少女を、叔母は一瞬憐れに思ったのだろう。誰かが名乗り上げるのを待ち望まれていた引き取り手に、彼女は名乗り出た。
コトを見る叔母の瞳にはどこか、悪魔を見るような色がちらついて見えたが、それに対してこの幼い少女に何ができただろう。ただ、何か持っていきたいものがあれば取ってこい、と急かされ、家の玄関にあった母の料理手帳を焦って持って来ることしか、コトにはできなかった。それを見た叔母が、髪をいじりながらコトへ声をかけた。
「……それは何ですか? ああ、料理の手帳ね、姉さんの。……コトさん、あなた、料理ができるの?」
「い……いえ、あの……叔母さまが、もし……よろしければ、これから勉強させて頂くので……料理を、させてもらえたら……と……」
コトが震える声でそう答えれば、叔母は苦虫を噛み潰したような表情を浮かべながらも、好きにすればいい、と呟き、そのままコトを連れて自分の家へ帰るまで、何も言葉を発しなかった。
コトは揺れる電車の中で、ぼんやりと景色が滑っていくのを眺め、自分が十年間育ってきた小さな集落と、やさしかった海が遠のいていくのをただただ、寂しく思っていた。
――叔母に引き取られてから、三年ほどが経った。
最初はまだ優しかった叔母が、自分を都合の良い家政婦か何かにしか思わなくなるまで、それほど時間は掛からなかった。コトは窓辺に座り、ぼうっと空を眺めながら、あれから三年経って未だ自分に降り注いでいる言葉の、黒い雨を思った。
人は、わたしが生まれてからだ、と言う。父と母が少しずつおかしくなりはじめたのは、わたしが生まれてからだ、と。
(……あたしが悪かったと言うの? あのとき、たった十歳だったあたしが? あたしに何ができたというのだろう、自分で死ねば良かった、と? 生まれてこなければ良かった、と?)
存外、そうなのかもしれない、とコトは心の中で溜め息を吐いた。
(もし、そうだったとしても、死ぬなんて……)
また、瞼の裏の赤黒い海が蘇りかけたのを、コトは感じた。彼女はそれを振り払うかのように、膝の上に乗っている母の手帳を開き、ふう、と長く息を吐く。
叔母は自分を家政婦のようにしか思っていない。それが悲しくない、と言えば嘘になる。だが、彼女が何よりも悲しいと思うのは、叔母が自分を見る瞳の中に、いつも悪魔を見る色が混じっていることだった。きっと自分は、自分が思っているより、この叔母のことを好きなのだ。叔母は笑った顔が、母によく似ている。
(もっとも――叔母さまがあたしに笑いかけてくれたことなんて、あったかも分からないけれど……)
叔母は自分のことを嫌っている。嫌っている、と言うよりは、憎んでいる、と言った方がより事実に近いかもしれない。姉を奪ったとも言える自分への憎しみは、叔母の瞳を見ればありありと琴に伝わった。
きっと、いや――絶対に、これから先、叔母が自分を好きになることはない。
それだけは、先の見えない未来でただ一つ、確信をもって言えることだった。
(あたしは……色んな人からどんなひどい言葉を言われることよりも……それがいちばん、悲しいのかも、しれないなあ……)
母の料理手帳をぱらぱらと捲る。母の少し丸みを帯びている字と、やさしい色遣いの絵が、コトの少しささくれ立った心を暖めた。
料理をしよう、とコトは立ち上がる。
料理をしている間は、いろんなことを忘れられる。目の前の料理にだけ、心を傾けることができる。それが琴は好きだった。目の前に並ぶ命に向き合って、時間が経つのを忘れることができるのは、料理をしているときだけだ。それ以外の時間は、本を読んでいても、何をしていても、一日がひどく長い時間のように思える。実際、コトにとってこの三年は、千年よりも長い時間に感じられた。
コトが米を磨いでいると、ふと隣に叔母以外の気配を感じ、彼女は驚きながらその気配の方へ顔を向けた。そこには、朗らかな笑みを浮かべた老人が、それでもこちらの目をしっかりと見ながら立っていた。
コトは気が動転し、流し台に自分の背を勢いよくぶつけてしまった。老人はその様子に苦笑し、コトの頭に手を置きながら、どうすればいいか分からず固まっている小さな少女に声をかけた。
「ああ、随分大きくなったなあ、コト。おれを覚えていないかい」
そう問われ、コトは老人の日に焼けた顔をまじまじと見つめた。そういえば、このあたたかい笑顔には見覚えがある。一呼吸置くと、それが母のものだということに気付き、コトは、はっとして老人の瞳を見た。
「……お祖父――さま?」
それを聞いた途端、老人の顔に、ぱっ、と喜びの色が浮かんだ。
「覚えていてくれたか! よかった、よかった。忘れられていたらどうしようかと思った」
「えっと……お祖父さま、あの、何で?」
「何で――とは? あいつ……そう、叔母さんから何も聞いていないかね?」
叔母、という言葉を聞いてコトの瞳に昏い海がちらついた。その色に老人――コトの祖父は目敏く気が付いたが、ひとまずは何も口にしなかった。
「その……叔母さん、しばらく戻っていなくて――」
祖父の目に、青い怒りの炎が燃え上がったが、彼の瞬きとともにそれは消し去られた。代わりに、彼は深い溜め息を吐き、日々の家事であかぎれたコトの手を取って、それからやさしく微笑んだ。
「君を引き取りたい、と娘――いや、君の叔母に申し出たんだよ。此処は君のいるべき処ではない、とおれは思うのだがね。随分、いいようにされてきたのだろう?」
祖父のその言葉に、コトは俯いた。何を言ったらいいのか分からなかった。消え入りそうな声で彼女は呟く。
「叔母さまは悪くない、と思います……。叔母さまは、どんなにあたしが悪く言われても家に置いてくれる」
「だが、あいつは帰って来ていないのだろう?――このままそれが続けば、君は死んでしまうぞ」
「それでも、叔母さまは悪くない、と……。あたしは、生まれてくるべきではなかった、と……いろんな人から言われます」
祖父はゆっくりと左右に首を振った。
「では、自分が悪いと君は言うのか」
コトが顔を上げる。祖父の瞳が、ここ数年あまり人と目を合わせないで過ごしてきたコトの瞳を捉えて離さなかった。そして彼女も、祖父から目を逸らさずに、少し掠れた声で答える。
「いいえ。――あたしは、悪くない。だからお祖父さま、あなたについていきます」
言葉の黒い雨に晒されている、この小さな少女の揺れぬ瞳を見て、彼女の祖父は声を上げて笑った。彼のその様子にコトは眉をひそめたが、祖父はそれを気にもせず彼女に問いかけた。
「――君、前へ進むためにはどうしたらいいと考える?」
コトが考えを巡らせ、やがて口を開いた。その答えは、今、彼女がしていることとまったく同じことだった。
「耐えること……耐えて、雨が過ぎ去るまで待ちます」
コトの答えに、祖父は頷いてから自らの白い髭に手をやって笑った。
「ああ、君は強いね。けれど、その強さは諸刃の剣だ。そう、時には君のように辛抱強く耐えることも必要なのかもしれない。しかし――それだけじゃあ、前には進めないな。分かるね、戦わなければいけないときもあるんだ。たとえば、君が魚で広い海に泳いでいるとする。もし、そんな君が網に捕まったら、君はそれを噛み千切らなければならないだろう。待っていたら、遅かれ早かれ死んでしまうのだからな。……それと同じだよ」
コトが己の唇に手をやった。祖父の目尻の深い皺を見つめながら、彼女は首を傾げる。
「でもあたし、牙はありませんよ」
「だな。だから君は剣を持ちなさい。――そう、心に剣を持てよ。しなやかで強かな、決して折れない剣を」
「剣――? い、嫌です。父さまと同じにはなりたくない」
祖父は笑いながら、コトの頭に手をやり、彼女の髪を荒っぽく撫でた。
「そう、そこだ。君の父はそこを間違えたんだ。おれは心の話をしている。心の剣だ、君には分かるね。けれど君の父は間違えたんだ。――彼は心の剣ではなく、その辺りにあったナイフを手に持ってしまったのだから。しかし、君は違うだろう? 君はまず、剣の振るい方を覚えなさい。知識を得るんだ。そうして、信じれるものだけを信じ、なりたいものになりなさい」
コトは心臓に手を置いた。鼓動が手のひらに伝わる。祖父の言葉に、幼い彼女が理解ができるものは少なかった。
だからせめて、心の奥に仕舞っておこう、彼の言葉のほんとうの意味が解るようになる、そのときまでは。
祖父の言いたいことを解るようになるためには、きっと、彼が言ったように知識というものが必要なのだろう。コトの曇り空を宿した瞳に、ちかりと光が差した。
「――知識を、あたしに」
コトの言葉に、祖父の目元が悪戯っぽく細められる。
「ほんとうに? ほんとうに君は、こんないかれた老いぼれについてくるのか?――その勇気が、君に?」
祖父の瞳を、コトは見据えた。コトの瞳の奥には未だ昏い血の海が宿っていたが、それに立ち向かうかのように、彼女はひたすらに祖父の目を見つめた。
自分に降り注ぐ、言葉の黒い雨は止むことがないのかもしれない。自分の奥に眠る、赤黒い海が透明になることはないのかもしれない。だとしたら、雨が止むのを待っていても、海が美しい色になるのを待っていても、仕方のないことだ。
少女の心は決まった。
雨が止まないのなら、わたしはこの黒い雨の中を踊ってみせよう。高らかに、歌でも歌いながら、誇り高く。
海がわたしを呑み込もうとするのなら、襲いかかる波の中を泳いでみせよう。力強く、この世界に生まれたことを間違ってはいないと、わたしは幸せだと、叫んでやろう。
コトは頷いて、祖父に言った。
「実は、母の料理手帳の他に……もう一つ、持ってきたものが」
「うん、それは?」
「――勇気です。これだけは、捨てずにとっておこう、と」
祖父は声を上げて笑い、玄関の方へ向かって歩き出した。よく通る、大樹のような太い声で彼は言葉を返す。
「君は身軽だな。だが……むしろその方がいい。――さあ、ついて来い!」
コトは祖父の、希望の匂いがする背中を追って走った。彼女の脚は震えていたが、それでも、その足取りは今までにないくらい軽く感じた。
まず、自分のことを信じよう、と彼女は思った。信じられるものを信じるために。なりたいものになるために。心に剣を持つために。まずは、自分のことを信じよう、と。
コトはもう、覚悟を決めたのだった。彼女のつま先は前を向いている。
波の音が聴こえ、遠くにかもめの姿が見える。
少女と老人は、海の近くの古道を歩きながら、太陽の眩しさに目を細めていた。
「――あたし、お祖父さまって、もっと怖くて厳しい人なのだと思ってました」
「……ははは! そうか! おれは確かに老いぼれてはいるが、少年の心は捨てていない。そうさ、何にだってなれるんだ。おれはまだまだ子どものようなものだからな」
「……あたしも、そうでしょうか」
「もちろんだとも。言っただろう、信じれるものを信じ、なりたいものになりなさい。これが子どものような老いぼれからの助言だ。さあ、君はこれから何になる? 何にだってなれるさ、すべては君次第でな!」
20160204
シリーズ:『仔犬日記』〈遠泳船〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
