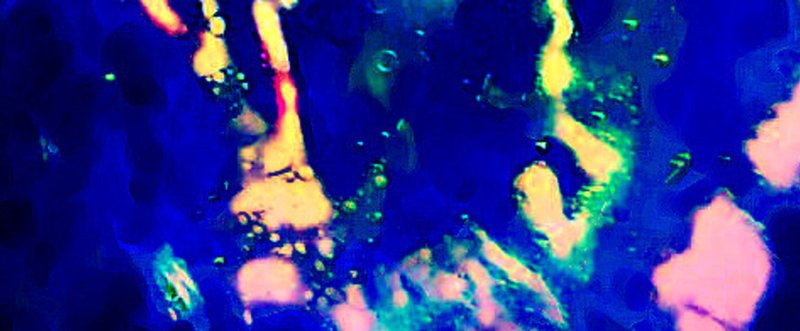
終夜
星を見よう、そう言ったきみに連れられて、こんなところまで来てしまった。
昼間ならば、辺り一面緑色だろう草原に、二人の男女が座っている。青年――アトリは無意識に手のひらの小さな懐中電灯をくるくると回しながら、空を見上げている彼女のことを眺めていた。
アトリの隣に座っている彼女は、手元の、ランタンの明かりに照らされた星座早見盤と図鑑に目線を落とし、なにやら唸りながら、また空を見上げた。アトリがからかうように少し笑い、彼女に声を掛ける。
「ヨタカ、なぁに唸ってるんだよ」
「ああ……分からないな、と思って。こうも星が見え過ぎると、どれがどの星座なのかさっぱり。暗くて図鑑もよく見えないし、困ったものだよ、まったくね」
暗がりで彼女が困ったように笑っている、その顔がアトリには容易に想像できた。それがどうにも可笑しくて、音を出さないように気を付けながら彼は笑う。
「――そういえば、何で急に?」
天体観測をしよう、そうヨタカに言われたときからずっと頭を掠めていた疑問が、アトリの口を突いて外へ滑り出た。ヨタカがちらりと視線を一度彼へやり、再び星空へ戻して呟く。
「あれ、知らないでついて来たのかい。今日は流星群、らしいよ」
「らしい?」
「うん。風の噂で聞いただけだからね」
なんて信憑性の薄い話なのだろう、アトリは内心呆れながら彼女の言葉を聞いていた。そして、そんなことだろうと思った、なんて言って苦笑いを浮かべている自分にも、呆れていた。彼女がそういう人だと分かっていて、それでも言われるままについて来た自分に。これでは、おまえが好きだと言っているようなものじゃあないか。彼は心の中で、熱をもつ溜め息を吐いた。
「流れ星……おまえ、何か願いごとでもあるのか」
「あるよ。願うことが何もない人なんて、いるのかい」
何の迷いもなく、願いがある、と言った彼女の顔をアトリは見た。ランタンのぬるい灯りに照らされているヨタカの頬は、その頼りない輪郭を辛うじて保っている。澄きり凛とした、揺れぬ彼女の声とは裏腹に、アトリは彼女がこのまま闇に溶けてしまうのではないか、という根拠のない不安に駆られた。
その不安を掻き消すかのように彼は口を開いた。
「――そういえば、聞いたことがあるんだ。俺たちが見ているこの星の光は、今じゃなくてもっと、ずっと昔の光だっていうことを」
ヨタカは星に向かって手を伸ばしている。白い肌が闇に浮かんで、アトリの黒い瞳を突き刺した。
「そう――そうなんだね。どれくらい昔の光なんだろう」
風のない夜の空気を、彼女の声だけが震わせられた。ヨタカの声に、アトリは此処へ来てはじめて、星の瞬きをまともに瞳に映した。この光は、どれくらい昔の光なのだろう。その問いの正しい答えを彼は知らない。
「さあ。……一億年前、とか、かもな」
何となく口に出した一億年という年月を、彼は上手く想像することができなかった。隣でヨタカが、目を瞑ったような気がする。空を見上げると、夜の光が雪崩れのように目の中へ飛び込んできた。美しい、というよりは最早、怖い、とアトリは思った。
何が怖いのだろう。それが彼には分からなかった。瞳に映る、あまりにも多くの過去の光が、だろうか。それとも、風のない深い夜の空気が、だろうか。違う、と心臓の奥のつめたいところで彼は思った。おれが怖いのは、おまえの輪郭が夜に攫われることだ。おれが怖いのは、おまえが此処からいなくなることだ。ああ、そうか、と彼は思う。おれが怖いのは、おまえがおれの隣からいなくなることだ。
ヨタカの閉じられていた瞼が開かれ、アトリを捉える。ランタンの灯が彼女の瞳を星のように輝かせた。アトリの脳裏に、星なんか見えなくてもいい、という想いがちらつく。おまえの瞳が見えるのなら、星など、と。我ながら馬鹿らしいことを考えるものだ、彼は喉の奥で笑った。
「――じゃあ、君、一億年後だね」
ヨタカが立ち上がって微かに笑う。アトリは言われたことの意味が解らず、何となく、宙に浮いた心でぼんやりとその様子を眺めていた。
「一億年後?」
「……何でもないよ。――ねえ、星、流れないかな。願いたいことがあるんだ」
「今日は流れなくてもさ、また、来ればいいだろ」
「そう――だね」
――どうやら、少し眠っていたらしい。何だかあの日の夢を見ていたような気がする。
大きな樹の下で、アトリは枝の間から瞬いている星を眺めた。この村は、星がよく見える。瞼を閉じても、過去の光たちが瞳の奥を灼くように燃えている。おれがあの日、一億年前と言った光。彼女があの日、一億年後と言った光。
彼女が逝った今なら、何となく、あの日の言葉の意味が解るような気がする。きっと彼女はこう言いたかったのだ、一億年後にまた会おう、と。もうすぐ自分は星になるから。そういう思いを込めて彼女は、一億年後、と言ったのだろう。
あの日、きみはどういう気持ちであの言葉を発したのだろう。それを汲むこともできず無責任に、また来よう、そう言ったおれを見て、きみはどんな風に思ったのだろう。腹が立っただろうか、こんな風に。哀しかっただろうか、こんな風に。苦しかっただろうか、こんな風に。心臓にぐつぐつと煮えるような痛みを感じる。きっときみは、こんな痛みを毎日抱えながら、それでも笑って生きていたんだ。透明な羽を背に生やして、命に誇りをもっていた美しいきみのことが、おれはこんなにも好きだった。ああ、好きなのだ。
星が夜空を翔けるように流れ、それが何度も繰り返されている。今夜は流星群。星に灰色の心で、彼は願いを掛けた。
おれの命なんて全部やっても構わないから、なあ、あいつを返してくれよ。神様、おまえの欲しいもの何でもやるから、それが此処にないものでも、何だっておれは手に入れてみせるから、神様、あいつの命を返してくれよ。
その願いは星まで届かずに、近くの木へぶつかり、その木を少しばかり揺らしただけだった。揺れた拍子に林檎が一つ、その木から落ちた。そんなことには気付かない、夜に溶けかけた自らの輪郭を何か明かりで照らそうともしない彼は、瞼を閉じて、再びあの日の彼女の面影を夢想する。
星を見よう、そう言ったきみを失って、こんなところまで来てしまった。
結局、あの日、星なんて一つも流れやしなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
