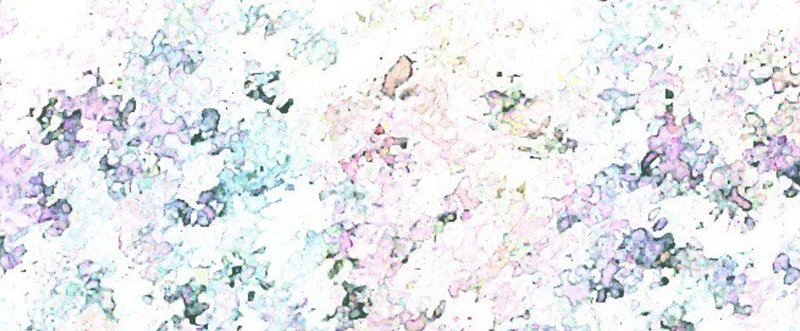
秘めたる汽水
あたしは晴れろと言ったはずよ。花曇りの瞳で雨空を仰いだ少女は、心の中でそうぼやいた。玄関先に置いてあったこうもり傘を差しながら、彼女は彼が待っているだろう海手前の坂道を目指して歩みを進める。彼、卵色の髪と若草の瞳をもった彼、海を見に行こうと言った彼、昨日出会ったばかりの名前も知らない少年、それが彼。彼は誰なのだろう。
何となく後ろを振り返れば、自分が住んでいるカモメ岬の、祖父と二人暮らしをするには少しばかり大きい家が見えた。そういえば、家の脇にいつの間にやらクトゥリコの木が生えていたっけ。一度邪魔になって枝を切り落としたりもしたけれど、あれは何度切ってもまた生えてきた。切り落とすのも面倒になって、今はそのままにしてあるけれど、クトゥリコの木もそろそろ赤い実をつける頃だ。あの木の生命力、泡のように淡い花の色、燃える赤い実の色、嫌いじゃない。
潮の香りが雨の匂いに交じって鼻を突いた。はっとして目線を上げると、こうもり傘の向こうに白い傘を差している彼の姿が見える。こちらに気が付いた彼はからかうような笑みを浮かべて、魔法のかかったような声を出した。
「あれ――君、来たんだ! こんな天気だしさ、来ないと思ってたよ」
「本当に。あたし、どうして来たんでしょうね、こんな天気なのに」
坂道を下って行くと、砂浜と海が見えた。雨粒が波に喰われている。それは、アメンボの群れが波に攫われているようにも見えた。だが、思っていたよりも、こういった表情の海を怖いとは思わなかった。むしろ、カモメ岬から眺めていた海の方が荒々しく獰猛に見えていたように思える。眺めていたのは同じ海なのに。
「そのサンダルは脱がない方がいいと思うよ。貝とか踏むと結構痛いし」
「ええ」
「晴れたらいいなって思ってたんだけど」
「……あたしもです」
そう呟いて少女は足元の砂が絡んだ白珊瑚を拾い上げた。それを波の中で少し泳がせて、砂を洗い落とす。
「そうだ、名前」
「え?」
上から降ってきた彼の声に彼女は少しばかり顔を上げたが、直ぐにまた海に視線を戻した。
「そういえば、名前聞くって言ったよね。教えてくれる?」
彼のその問いに、彼女は視線を波に向けたままで答えた。何故か頭に浮かんだ、切っても切っても生えてくる、家の脇の淡い花と赤い実のことを思いながら。
「――クトゥ、リコ……クコ。クコ、と」
「……それ、本名?」
「いいえ」
「そっか。何か、暗号みたいだね」
何故本名を伝えなかったのだろう。彼の前では魔法にかけられたようにすらすらと言葉が出てくるものだと、昨日は確かにそう思ったというのに。雨音と、潮の香りのせいだろうか。分からない。
「あなたの名前は?」
「ぼく? そっか、確かに名乗らなくちゃだよね」
そう言うと彼は何処か遠いところを見つめるようにして水面を眺めた。そして、ゆっくりと口を開く。続く言葉は真っ直ぐ彼女――クコの耳に届いた。むしろクコには雨音も、波の音さえ息を止めて、彼の声に耳を澄ましているように思えた。彼女はその時、本当に彼の声しか聴こえなかったのだ。
「――イルカ」
「……イルカ?」
クコは自身のこうもり傘から、イルカと名乗った彼の姿を盗み見た。卵色の髪に若草の瞳。とてもイルカといった感じではない。そう思って、はたとなった。クコと名乗った自分も特にクトゥリコの花や実らしい姿をしているわけではない。暗い紺色に灰色の瞳。何処もクトゥリコらしいところはなかった。そのことが何だか少し可笑しくて、彼女は音を立てずに笑った。
「イルカ――くん。……本名?」
「違うよ。君の真似」
「そうよね、あなた全然……イルカって感じじゃないもの」
「君もクコ……クトゥリコって感じじゃないよ」
少し強めの風が二人の髪と傘を揺らした。波もそれに共鳴するように大きく吠える。風を吸い込んで雨を喰らう海は、黒い魔物のようにも見えたが、クコはそれでも構わないと言うように右足を波に浸した。
「クコ。海、怖いんじゃなかったの? 今日なんか特に海が荒れてるのに」
「怖い――けど、嫌いじゃない。むしろ、楽しい……かも」
少し照れ臭そうに少女は笑う。つられて少年もころころと笑った。
「不思議な子だね、君って」
「そうかしら。イルカくんには言われたくないかな」
クコはそう言うと弱くなったり強くなったりする雨粒を睨んだ。髪に時々絡む水滴は鬱陶しかったし、こうもり傘は少しばかり重たかった。
「ねえ、今日会ったときからずっと思ってたんだけどさ」
イルカの言葉に彼女は空を睨むのを止め、彼の方へ振り返った。
「クコ、黒い傘って似合わないよ。君は白の方が似合うと思う、ぼくのと交換する?」
想像もしていなかった言葉をイルカにかけられたため、彼女はしばらくぽかんとした表情を浮かべていたが、少しすると困ったような微笑みを浮かべながら言った。
「あなたにも黒は似合わないよ」
「……そうかなあ」
そう呟いたイルカの若草とクコの花曇りの瞳がかち合う。二人は互いに悪戯に笑って頷いた。それを合図に彼らの傘が宙に舞う。イルカは大きな笑い声を上げながら、クコは少し控えめ笑いながら、吠える海の浅瀬へ両足を無遠慮に突っ込んだ。二人の髪を濡らすのは、相手が掛けた海水か、それとも未だ止まない雨粒か。こんな風に笑うのは随分久しぶりな気がする。クコは頭の片隅でそう思った。
「ねえ、イルカくん」
「なに?」
「――あたしの、友だちになってくれますか」
押しては返す波の勢いにつられるように彼女がそれを告げると、イルカは心底可笑しそうに声を上げて笑った。しかし、それは彼女の不安を煽る表情ではなく、むしろ彼女を安心させるものだった。イルカはクコに近付くと、その頬を優しく抓ってまた悪戯に笑う。その手はひどくつめたかったが、そんなこと、クコにはもうどうでも良かった。
「君が白い傘を買うなら、喜んで」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
