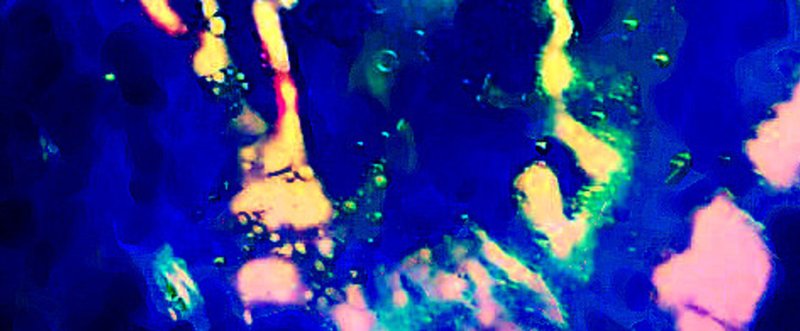
夜明け前、ぼくの星を信じて
深い紺を垂らした布の切れ端に、淡い橙色が揺らめいている。
朝がやってくる前の少し冷たい風を肌に感じながら、それでも夜にしがみつくように白く瞬いている星の光を柔らかな黒の瞳に映して彼はその空から目線を外し、そして、空の紺からぬるい青を受け取る村の姿に目をやった。家も、人も、おそらくは動物も草木もまだ、眠りからは覚めない。辺りは星の囁きすら聴こえてきそうなほどに静かだった。彼は小さく息を吐き、瞼を閉じる。それはまるで、この青い闇に身を任せるように。次に目を開いたとき、辺りの景色がもっと美しく見えるように。
しかし、瞼を下ろした彼の耳に聴こえてきたのは星の囁きなどではなく、小さな小さな、紙が捲れるような音だった。彼は目を開ける。それから彼は自身の座っている大樹を囲う壇から降りて、呼ばれるように音のする方へと歩みを進めていった。
「……村長」
「……アトリ?」
呼びかければ、切り株の上で何やら手帳のようなものを眺めている少女は少しばかり驚いたように顔を上げてこちらを見た。音の在り処は、どうやら此処だったらしい。少女のとうもろこし色の髪が夜風に吹かれ、微かに揺れている。アトリは少女――ホコウの座っている切り株よりも少しだけ低い別の切り株に腰を下ろし、小さな手帳を見つめている少女のその横顔を横目で見た。少女は音も立てずに深く息を吸うとアトリの方へ顔を向けて、それから天色の瞳を細めて笑う。その笑い方に微かな違和感を覚えつつも、アトリはそれを特に言葉にしようとは思わずに少女が何か言葉を発するのを待った。
「アトリは……どうしたの? 星を見てた?」
「まあ……そんなところです。……あなたは、何を読んでいたんですか」
「ああ……これ、父さんが若かった頃の旅の手記なんだ。私もこの手記がきっかけで旅に出て……それはそこまで前のことじゃないんだけど、何かね、懐かしくって……こうしてたまに読み返すんだ」
言いながら、ホコウは手記の表紙を閉じる。その瞳に何か、寂しげな――さながら今の空のような色が浮かんだことに気が付いて、アトリは静かに息をした。或る日、少女に当たり散らしてしまった言葉が冷えた温度をもって心臓の奥へと戻ってくる。――〝大事な人を亡くしたことなんて、あんたにはないだろ〟……
アトリは握った片手に力を込めながら、少女に問いかける。
「……あなたが村長になった理由って、何なんですか」
「私が? そうだなあ……ええと、ね」
思い返すように、少女が顎に人差し指を当てた。アトリはその様子を眺めながら、自分は一体何故、こんな質問をしたのだろうと心の中に疑問符を浮かべる。そして、その答えは存外単純なものであって、しかし複雑なものだということに彼は気が付いた。
「私のね、お祖父ちゃんが此処の村長でね……お祖父ちゃんがもう、年で引退するから……って、私の母さんにその席を譲ろうとしたことがあったんだ。でも、母さんは断ったの。〝自分は家にいたいんだ〟……って。私の家はこの村からけっこう離れた場所に在るんだけど、母さんは今もそこで暮らしてて……〝自分がいないと父さんが寂しがるから、自分はこの家にいるんだ〟ってね。でもそうすると、村長の席は空っぽじゃない?……母さんの言いたいことも分かるし、母さんは家にいるべきだと私も思ったから……だから――だったら私が村長になります!……って感じだったかな、はじめは」
「はじめは?」
「うん。最初はお祖父ちゃんが困ってたから、ほとんど勢いで……それに、旅から帰ってきたばっかりだったから、少し気持ちが上擦っていたのもあるかもしれない。でも今は……違うかな。私、ちっぽけだけど……私にもできることがあるんだって、村長をやっていく内に少しずつだけど分かってきたの。だから私は、自分にできることを自分なりに精一杯やりたい。たぶん、それが……今の私の夢だから」
おそらく自分は、この少女のことを分かっていないようで分かっていて、分かっているようで分かっていないのだ。表情の豊かなホコウから拾えるものは思うよりも多く、そして、そんな少女のことについて知っていることは自分が思っているよりも遥かに少ないのだった。だから、少しだけ知りたかったのかもしれない。少女が手にした林檎をこちらの手のひらへと渡したときのように、少女の想い出を少しだけ分けてほしかったのかもしれない。
アトリは微かに頷くと、紺の果てに揺らめく橙色が赤みを帯びてきたことを視界の端で捉えながら、ほとんどホコウにしか届かないほどの声で呟くように問いかけた。
「あなたは、寂しいんですか」
朝陽が昇ろうとしている地平線を眺めながらそう言う自分の顔を、おそらくは少し驚いた顔で少女が見たのをアトリは感じた。
それから数呼吸の間はアトリもホコウも何も言わず、ただ今日が去って明日になり、明日が今日になろうとしているところを見つめるばかりだったが、横から小さな笑い声が聞こえてくると同時に、先までの沈黙が夜と共に去っていくことを彼は想わずにはいられなかった。
「どうかなあ。でもさ、アトリ……みんな、ね――誰かしら、いつも心の何処かでは寂しいって思いながら生きてるんじゃないかな、少しくらいは」
「……あなたも?」
「私も。……きみも」
「……夜、明けますね」
「うん、明ける」
そう言ったホコウの顔を、アトリは少しだけ顔を傾けて眺めた。朝に塗れはじめた空を見つめるその横顔に、いつもの――柔らかで、その中にどこか楽しげなものがある笑みは全く浮かんでいなかった。
アトリは静かに息を吐くと、何かたいせつなことを言おうとする人間がするように深く息を吸い、しかし彼自身は空の方を眺めたままのふりをして言葉を紡いでいく。
空の果ての橙色は、まだ刺すような光を放ってはいない。
「――あんたが今笑えなくたって、何処かで他の誰かが笑ってくれる。だから……背伸びする必要なんて、きっとない」
言えば、それを聞いたホコウが零すように笑った。
そんな少女にアトリは心底不服そうな顔を向けると、ホコウは柔い朝の陽を頬に受けながらその顔を緩ませて、もう一度小さく笑う。
「……それ、アトリが笑ってくれるってこと?」
「あんたはそんな気色の悪いものを見たいんですか」
「え?……ううん……うん、見たいかも」
「……他を当たってください」
「あはは、そうだね、そうするよ」
他を当たれと言った自分の顔に少しばかり笑みが浮かんでいたことには気付かないまま、彼は少女の天色をその黒に映して、更に言葉を少女だけに届く風へと乗せていった。
朝は、もうすぐそこまでやってきている。未だ頭上でおぼろげに瞬いている星たちも、いずれは今日のまばゆい陽の光に溶けてゆくのだろう。そんな朝陽よりもやさしい光が少女の目にも、そしておそらくは彼の目にも浮かび上がった。
「庭に……庭に、林檎の苗を植えたんです。それで、そのときにふと思ったんですけど……」
「ん?」
「――あなたの、名前は?」
「ああ、そっか、そうだっけ!……うん……私の、私の名前はね――」
20161010
シリーズ:『仔犬日記』〈きみの星を信じる〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
