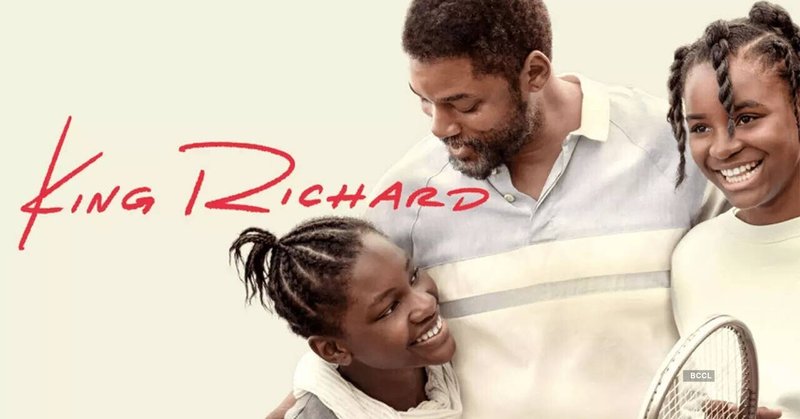
『ドリームプラン』 リチャード≒ウィル
ある程度のテニスファンならウィリアムズ姉妹とその親については、知っていることが少なからずある。しかしそれは彼女たち姉妹が国際的に活躍するようになってからで、基本的にテニス会場での出来事が多い。だからこのジュニア時代の姉妹と両親、とりわけ父リチャードのエピソードは知らないことばかりで驚かされてしまう。いや、驚くというよりは「答え合わせ」を観ているような感覚に近い。
今現在では、姉ビーナスよりも妹セリーナの方がより多くの露出、そして名声を得ているので、今作でセリーナよりもビーナスにフォーカスした内容なのは意外に思われるかもしれない。しかし女子テニス界において、ビーナスの登場こそがまず強烈なインパクトがあったのだ。男子でさえもアフリカ系の比率は極端に少なく、トップ選手ではアーサー・アッシュなどさらに限られる。そしてビーナスは人種だけでなくプレー自体もエポックだった。パワーとスピードで相手を凌駕するスタイルはそれまでも始まりつつあったが、明らかに質が違うものに見えた。それでもWTAツアーで彼女より先を走っていたヒンギスに代表されるように、テクニックと戦術に優れたトップ選手たちとの差はまだあった。絶対値は上回っても勝負には負ける、ということはプロスポーツシーンで珍しいことではない。
しかし次第にアジャストしてパワーとスピードにも磨きがかかり、メンタルもタフになっていくとランキングも上がり、ついにツアーで最上位の大会であるグランドスラムの一つ、最も権威のあるウィンブルドンのタイトルを獲得する。プロに転向して6年後の2000年のことだ。
日本にいる自分が彼女の存在を知ったのは、彼女が本格的にツアーを転戦し始めた1997年だったかと。プロ転向から4年目のシーズンである。テニス観戦がとにかく好きで、継続して変遷を追いかけていたし、当時は地上波でGSといえばウィンブルドンだったので、そこで彼女のプレーを初めて観たんだと思う。そうでなくても翌年には観ていたはずだ。98年にはウィンブルドンでベスト8にまで勝ち進んでいる。
ちなみにGSタイトルを獲るのはセリーナの方が1年早かったりするのだが。こうして彼女たちの栄光のキャリアを知っているだけに、あのボロボロのボールと公営コートで二人が練習する最初のシーンで不意に泣いてしまった。「ここからなのか……」と思わずにはいられなかった。
さて、転向して始めの3年間はどうしていたかと言うと(つまり今作の後の3年)、国内で数も絞って参戦しているにすぎない。この辺りの態度は今作でリチャードの考えを知っているから肯けるものだ。相変わらずだったのである。ただし、あのアランチャ・サンチェス・ビカリオとの対戦でメンタルに傷を負ったことも影響しているだろうが、それ以上にリチャードがナーバスになっていたと考える方がいいだろう。
また、今作だけでアランチャ・サンチェス・ビカリオのことを評価してほしくない。彼女はツアーでも無類のファイターであり、勝負に強く拘る選手として評価されていたから。体格には恵まれていないが、それを補う闘争心があり、GSタイトルを4つ獲得している偉大なチャンピオンなのだ。劇中で、最初にビーナスをコーチングしたポール・コーエンが「対戦相手に噛みつけ、叩きのめせ」というような一見乱暴な声をかけながらテンポ良く球出しをしているシーンがあったが、それは「ツアーを勝ち抜く上で必要」だから。当時黄金期にあった9歳上のサンチェスに対して14歳でデビューしたてのビーナスがそのように振る舞えるわけもないが、当時のビーナスに欠けているものをサンチェスは見切っていたし、自身の最上の武器でもあったということだ。
セリーナよりもビーナスの方がスイングフォームにクセがあるなと感じていたが、今作を観るとその理由がわかる気がした。独学の両親によるトレーニング期間がまず長くあり、その後ポール・コーエン、そしてリック・メイシーによる本格的なトレーニングに接するという流れの中で、あえて残されたクセなのかもしれない。
今作を観て特に感心したのは、ビーナスの体の動きの特徴をとても忠実に再現している点だ。もちろんスタントをつとめたテニス経験者の努力もあったようだが、ビーナス役のサナイヤ・シドニー自身も、撮影に際して半年に及ぶテニスのトレーニングをしたという。しかも左利きである彼女はビーナスのように右利きでのプレーで演じなければならなかった。そこも凄い。おそらく多くのシーンでVFXによるボールの後付けがなされたはずだが、サナイヤとデミ・シングルトンの動きは説得力のあるものになっていた。テニスを描いた映画作品の中でも出色の出来栄えだと言える。
撮影のロバート・エルスウィットはアカデミー賞を獲得しているし、アクション大作も数多くこなしてきている。トスアップのショットでの俯瞰やローアングル&逆光などのアイデアで、普段のテニス観戦では観ることのない映像になった。
父リチャードの描かれ方は微妙である。彼のエキセントリックな部分や妻への態度など、負の面はそれなりに描かれているが、それもうまく取捨選択されていると言えるだろう。あの家族が治安の悪いコンプトンに住んでいたのは、彼がそれを選択したからで、ビーナスとセリーナを「厳しい環境に晒す」ことで彼女たちを鍛えようとしたというのだ。これを知ると、姉たちがあのコートでワルい男たちに絡まれるのは非道い話だなと思うよりない。
またオラシーンとは再婚であり、前妻との間には5人の子供がいて「自転車を買ってあげる」と言ってそのまま帰ってこなかったという。
姉妹のトレーニングも周囲から見れば常軌を逸しているもので、通報されるのも無理はない。しかし事件にまでならなかったのは「一線を超えなかった」からだろうし、「それはさせない」と決めていたオラシーンこそが、隣人に強い口調で非難するのは印象的だった。実のところ、家族を守っていたのは彼女なのだ。
そういう彼女の功績をリチャードが否定するシーンがあった。この夫婦が後にどうなるのかを知っているので、その一因を見せたということなのだろうが、つまるところこの作品はリチャードをフィーチャーし、オラシーンから手柄を奪っているように観える。それは事実に基づいているのだろうし、誰が主役なのかということでもあるにせよ。しかしリチャードが計画した「人種の壁を破る闘い」がなぜ成功したかといえば、それは彼以外の女性たちの犠牲によって成ったのだし、下手をすれば2人の姉妹は壊れる可能性もあったのだ。2人が今でも現役であるというのは稀有なことだが、それを父親のおかげとは思わない。そうした構図の作品で主演したウィル・スミスが、アカデミー賞の有力候補だというのはよく出来ていると言えそうで、もし受賞すれば、それは同じくノミネートされたアーンジャニュー・エリス、そして姉妹役を好演したサナイヤとデミのおかげなのだろう。
作品としてはすごく好きだし、実話に基づいた物語の構図がまずあって、それは問題ない。しかし、そこにウィル・スミスとアカデミー賞という構図が被ってくるのがちょっと鼻につくのだ。とは言え、彼(ら)がアカデミーに抗議の意を表したことでアカデミー会員の構成が変わり始め、その先に『パラサイト』の快挙や、今回の『ドライブ・マイ・カー』のノミネートがある。これは純粋に評価されるべきことだし、そういう彼が受賞するとしたら、それは良いシナリオなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
