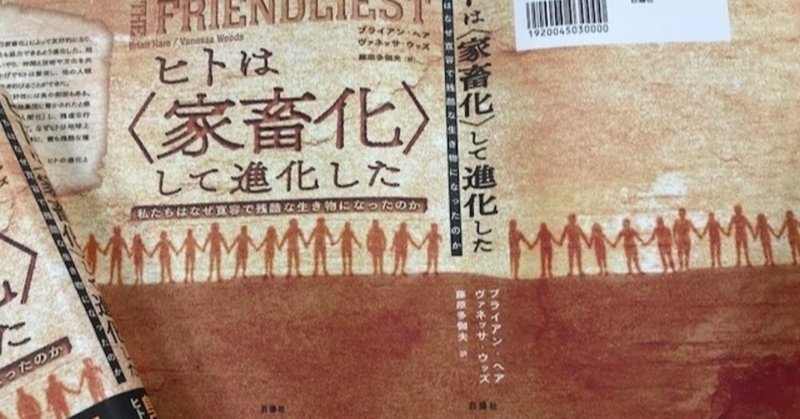
ヒトの自己家畜化とは何か?『ヒトは〈家畜化〉して進化した』試し読み
6/3(金)発売の白揚社新刊『ヒトは〈家畜化〉して進化した——私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか』より、冒頭部分の試し読みをお届けします。
他の人類はすべて絶滅したのに、なぜヒトは生きのびて繁栄することができたのか?
なぜヒトは他者と協力し、友好的に振る舞うことができるのか?
仲間を助ける優しいヒトが、なぜ残虐な戦争を引き起こすのか?
すべての謎を解くカギとなるのが「自己家畜化」。
イヌやボノボ、チンパンジーからヒトに至るまで、数々の研究をおこなってきた気鋭の進化人類学者が、各方面で注目されている「自己家畜化仮説」を軸に、ヒトの進化と本性の深奥に斬り込みます。
お届けするのは、本書の冒頭部分となる「はじめに」の抜粋です。
■ ■ ■

最も友好的な人類
私たちは進化を創造神話として考えがちだ。大昔に一度起きた何らかの出来事が、直線的に続いているという考えである。しかし、進化とはそれほど単純ではなく、生物がホモ・サピエンスという「完成形」に向けて一直線に進んでいくといったものではない。ヒトよりも成功している種はたくさんいる。そうした生物は、ヒトより何百万年も前から命をつなぎ続けてきただけでなく、現存するほかの種を何十も生み出してきた。
人類がおよそ600万~900万年前にボノボとチンパンジーとの共通祖先から枝分かれして以来、ホモ(ヒト)属では多様な種が進化してきた。化石やDNAの証拠から、ホモ・サピエンスが存在していた過去20万〜30万年ほどの大部分で、少なくとも四種のほかの人類と地球上で共存していたことがわかっている。そうした人類のなかには、私たちヒトと同じぐらいの大きさの脳、あるいはヒトより大きな脳をもっていたものもいる。種として繁栄していく主要な必要条件が脳の大きさだとすれば、ほかの人類もヒトと同じように生き延びて繁栄できたはずだ。しかし、その人口は比較的少なく、道具や技術はヒト以外の生物と比べれば目を見張るものではあったが、それほど高度ではなかった。そして、どこかの時点でほかの人類はすべて絶滅してしまった。
ヒトが大きな脳をもつ唯一の人類であったとしても、ヒトが化石記録に出現してから、人口の爆発的増加や文化の急発展が起きるまでに少なくとも15万年かかった理由はまだ説明できていない。ほかの人類と異なる身体的な特徴は進化の初期に形成されたとはいえ、ヒトはアフリカで出現してから少なくとも10万年は文化的に未熟なままだった。左右対称になるように丹念に加工された鋭利な尖頭器、赤い色素で着色された物体、骨や貝殻でできたペンダントといった、後に有名になる技術の興味深い片鱗は見られるものの、何千年ものあいだ、そうした革新的な技術はときおり生じても消え去り、定着することはなかった。
10万年前に人類のどの種が最後に生き残るかを賭けたとしたら、ヒトは本命ではなかっただろう。それよりも有力だったのは、ホモ・エレクトスではないだろうか。遅くとも180万年前にアフリカを出て、当時の地球上で最も広範囲に拡散した種となった。ホモ・エレクトスは探検家であり、サバイバーであり、戦士だった。地球上の大部分の地域に進出し、その過程で火の操り方を学び、火を使って暖をとり、身を守り、調理をした。
ホモ・エレクトスは高度な石器を使いこなした最初の人類だ。たとえば、アシュール文化のハンドアックス(握斧 )は、石英や花崗岩、玄武岩でできていた。使われている岩石の種類によって製作方法(打ち欠くか、剝片にするか)は異なる。そうやってできた切れ味鋭い涙滴形の石器は、あまりにも見事に作られていたため、何千年も後にそれを見つけた人々は、その石器に超自然的な力が宿っていると考えた。ホモ・エレクトスはほかの人類の栄枯盛衰を目の当たりにし、私たちヒトも含め、ほかの人類よりも長い期間、地球上に存在した。
10万年前のヒトは、彼らが出現する150万年も前にホモ・エレクトスが考案したものと同じハンドアックスを依然として使っていた。遺伝的な証拠から、人口は絶滅寸前まで減少していた可能性が示唆されている。ホモ・エレクトスはおそらくヒトのことを、更新世に出現した短命の新参者にすぎないと思っていたことだろう。
時代は飛んで7万5000年前。ホモ・エレクトスはまだ健在だったものの、その技術はそれほど進歩していなかった。当時、繁栄していた人類と言えば、ネアンデルタール人だろう。ネアンデルタール人の脳はヒトと同じか、それより大きかった。身長は同じくらいだったが、体重は私たちより重い。重い分の大半は筋肉だ。ネアンデルタール人は氷河時代の支配者だった。厳密に言えば雑食性なのだが、肉食を好む傾向にあった。これはつまり、彼らは有能なハンターでなければならないということだ。ネアンデルタール人の主な武器は、至近距離で獲物を突き刺すように作られた、長くて重い槍だった。肉食動物は通常、自分よりも小さな動物を狩るのだが、ネアンデルタール人は氷河時代のあらゆる大型草食動物を獲物にした。狩猟の対象は主にアカシカやトナカイ、ウマ、ウシの仲間だが、マンモスを狙うこともあった。どれも人類よりはるかに力が強い動物だ。
ネアンデルタール人は決して、うなり声しか上げられない原始人などではなかった。ヒトとネアンデルタール人はどちらも、発話に必要な運動筋肉の細かな動きをつかさどるFOXP2遺伝子のバリアントをもっている。ネアンデルタール人は死者を埋葬し、病人やけが人の世話をするし、自分の体に色素を塗り、貝殻や羽根、骨でできた装身具でみずからを飾る。ネアンデルタール人のある男性は動物の皮でできた衣服を身にまとって埋葬されていた。その衣服は巧みに伸ばした皮を縫い合わせてできており、3000個近くの真珠で飾られていた。ネアンデルタール人が洞窟に残した壁画には、架空の生き物が描かれている。ネアンデルタール人は、彼らの時代の終盤には、ヒトが使っていた道具の多くを手にしていた。
ホモ・サピエンスが初めてネアンデルタール人と出会ったとき、ネアンデルタール人の数は最大に達していた。寒冷地に適応していたネアンデルタール人は、ホモ・サピエンスが迫りくる氷河を逃れてヨーロッパから脱出したときに、ヨーロッパに進出した。7万5000年前に、どの人類がその後の不確かな気候のもとで生き残れるかについて賭けをしたなら、ネアンデルタール人が本命だっただろう。
しかし、5万年前までに情勢はヒトに有利なほうへ傾いた。アシュール文化のハンドアックスは100万年以上もあらゆる人類に活用されていたが、ヒトはそれよりはるかに複雑な道具類を考案した。ネアンデルタール人は木製の槍を手で持って突き刺すだけだったが、ヒトはそれを改良して、投射する武器を開発したのだ。それは長さ60センチほどの木製の投槍器で、長さおよそ1・8メートルの矢のような槍を投げる。槍は鋭くとがらせた石か骨を穂先に取り付けることが多く、反対側の末端にはくぼみを作り、木製の投槍器の突起にはめる。これは、愛犬家がボールを投げるときに使う「チャキット」という製品と同じ原理だ。強肩の持ち主であっても、標準的な槍を手で投げると短い距離しか飛ばせない。しかし、投槍器を使うと、柄に蓄えられたエネルギーによって、槍を時速160キロ以上の速さで90メートル以上も飛ばすことができる。投槍器は狩猟に革命をもたらした。人間と同じくらいの大きさの草食動物だけでなく、飛んだり、泳いだり、木に登ったりする獲物も狩ることができるようになったのだ。マンモスを捕らえるときも、足で踏みつけられたり、牙で突き刺されたりする心配がなくなった。投槍器の登場で身の守り方も一変した。襲ってくるサーベルタイガーや敵の人間に向けて安全な場所から槍を投げて、重傷を負わせることもできるようになった。武器に使う鋭い穂先、石器を作る道具、切断用の刃、穴を開ける錐きりも作り出した。骨で作った銛もり、漁に使う網や罠わな、そして、鳥や小型の哺乳類を捕らえるための罠も生み出した。ネアンデルタール人は狩猟の能力は優れていたが、捕食者としては並の域を出ることはなかった。一方、新たな技術をつくり出したホモ・サピエンスは究極の捕食者となり、ほかの生き物に捕食されることは少なくなった。
ヒトはアフリカを出てから、あっという間にユーラシア大陸全域に拡散した。数千年のうちに、オーストラリア大陸まで到達したとの説もある。大海原を渡る困難な冒険に挑むためには、いつ終わるとも知れない旅に向けての計画と食料の荷造りが必要だ。さらには、想定外の損傷を修復する道具や見たこともない獲物でも捕獲できる道具を準備しなければならないし、海上で飲み水を補給するなど、旅の途中で起こりうる問題を解決する必要もある。こうした旅に挑んだ当時の船乗りは、仲間と細かくコミュニケーションをとらなければならない。このことから、ヒトはその頃にはすでに成熟した言語を使っていたと考える人類学者もいる。
ここで特に注目したいのは、船乗りたちは水平線の向こうに何かがあると推測しなければならないという点だ。ひょっとして渡り鳥の行動パターンを調べたのか、それとも、はるか遠くで自然に起きた森林火災の煙が見えたのか。仮にそうだったとしても、向かうべき土地があると想像しなければならない。
2万5000年前までには、状況は明らかにヒトに有利になっていた。移動し続ける遊牧民として生きていくのではなく、野営地に数百人が集まって定住するようになった。野営地は用途に応じて分けられ、動物の解体場、調理場、寝る場所、ごみ捨て場はそれぞれ別個の区画に設けられた。全員に食料が行き渡り、食材をひいたりすりつぶしたりする道具も考案されて、生のままでは食べられない食材のほか、有毒な食材でさえも加工して食べるようになった。調理用の炉や、パンを焼く竈かまども作り出し、食料が手に入りにくい時期のために食料を保存する方法も考え出した。
骨製の細い針が考案されたことで、毛皮で体を覆ったり、毛皮をゆるく縛ったりして身につけるのではなく、衣服らしい衣服を作れるようになった。体にぴったり合った防寒着を身にまとえば、ネアンデルタール人のように多くのカロリーを必要とする体を進化させなくとも、寒さに耐えられる。こうした装備を得たことによって、極寒の氷河時代にも北方へ進出でき、最終的にアメリカ大陸に足を踏み入れることができた。その旅は人類史上初の快挙だ。
それは後期旧石器時代と呼ばれる時代のことだった。この時代には武器や住環境が進歩したが、目を見張るのはそれだけではない。ヒトはこの時代に独特な認知能力、特に社会的ネットワークの拡大を示す痕跡を残し始めたのだ。たとえば、貝殻でできた装飾品が、海から何百キロも離れた内陸で見つかっている。これは、実用的な価値がない物体が、遠く離れた場所から運んでくるだけの価値をもっていたか、あるいは最初期の交易路を旅した誰かから入手したということを暗に示すものだ。
岩壁に描かれた動物の絵はじつに巧みで、岩の起伏が動物の体の下で波打っていて、三次元の世界を見ているようだ。ある岩絵に描かれた8本脚のバイソンは火明かりに照らされるとギャロップしているように見え、原初の映画の誕生とも思えるほど生き生きしている。さらには、口を開けていななくウマや、雄叫びを上げるライオン、角どうしが激突した音が聞こえてきそうなほど頭を激しくぶつけ合うサイなど、音までも伝えているような絵もある。人間は現実の場面を描写するだけでなく、ライオンの頭をもつ女性や、バイソンの体をもつ男性など、架空の生き物を想像し、描くことまでしていた。
これは行動が現代化したということだ。当時の人間は現代人のような見かけであり、現代人と同じような行動をとっていた。ヒトの文化と技術は、ほかの人類の文化と技術よりはるかに大きな力を急速に獲得し、洗練された。しかし、それはどのようにして起きたのか? 私たちの身に何が起きたのか? そして、なぜ私たちだけに起きたのだろうか?
ほかの人類が絶滅する一方で、ヒトが繁栄できたのは、ある種の並外れた認知能力があったからだ。それは「協力的コミュニケーション」と呼ばれる、特殊なタイプの友好性である。ヒトは見知らぬ人との共同作業であっても巧みにこなすことができる。これまで一度も会ったことがない人と共通の目標についてコミュニケーションをとり、力を合わせてそれを達成できるのだ。チンパンジーもまた、多くの面でヒトのように高度な認知能力をもっている。ただ、ヒトと数多くの類似点があると言っても、チンパンジーは共通の目標の達成を助けるコミュニケーションを理解するのが得意でない。チンパンジーほど賢くても、他者の動きに合わせて行動したり、さまざまな役割を連携させたり、自分が考え出した新しい技術を他者に伝えたり、いくつかの初歩的な要求以上のコミュニケーションをとったりする能力はほとんどないのだ。ヒトはこれらすべての能力を、歩行や会話ができる年齢になる前に発達させる。それは洗練された社会や文化を築くための入り口だ。この能力があるからこそ、ヒトは他者の気持ちを理解でき、前世代からの知識を受け継ぐことができる。その能力は、高度な言語をはじめとする、あらゆる形の文化や学習の礎だ。そうした文化をもった人がたくさんいる集団が、優れた技術を考え出した。ホモ・サピエンスは独特な共同作業に長けているおかげで、ほかの賢い人類が繁栄できなかった場所でも繁栄できたのだ。
動物の研究を始めた頃、私は社会的な競争にばかり注目していて、コミュニケーションや友好性が動物のみならずヒトの認知能力の進化にとっても重要になりうることに、まったく思いが至らなかった。他者をだましたり、ごまかしたりする能力の向上という面から、動物の進化的適応度を説明できると考えていたのだ。だが、私が発見したのは、賢くなるだけでは十分でないということだ。人間の感情はやりがいや痛み、魅力、嫌悪を感じるうえで多大な役割を果たしている。人間が他者にまつわる問題を解決しようとしたがることは、認知能力を形成するうえで計算能力と同じぐらい重要な役割を果たしている。社会的な理解や記憶、戦略がどれだけ高度であっても、他者と協力してコミュニケーションする能力がなければ、技術革新はもたらされない。
こうした友好性は自己家畜化によって進化した。
家畜化は、人間が動物を選抜して交配する人為淘汰だけで生じたわけではない。自然淘汰の結果でもある。ここで淘汰圧となったのは、異なる種や同じ種に対する友好性という性質だった。私たちは自然淘汰で生じた家畜化を「自己家畜化」と呼んでいる。ヒトは自己家畜化によって友好的な性質という強みを獲得したからこそ、ほかの人類が絶滅するなかで繁栄することができた。これまでのところ、私たちがこの性質の存在を確認できたのは、ヒトと、イヌ、そしてヒトに最も近縁な種であるボノボだ。本書ではこれら三つの種を結びつける発見、そして、ヒトがどのように現在のヒトになったのかを理解する助けになる発見について述べていく。
人間はだんだん友好的になるにつれて、ネアンデルタール人のように10〜15人の小さな集団で暮らす生活から、100人以上の大きな集団での暮らしに移行することができた。ほかの人類より大きな脳をもたなくても、より大きな集団で仲間との連携を深めることによって、ほかの人類を容易に打ち負かすことができたのだ。他者を思いやることのできる人間は、複雑な形での協力やコミュニケーションがだんだんできるようになり、それが人間の文化的な能力を新たな軌道に乗せることになった。ヒトは新たな手法や技術を生み出し、それをどの人類よりも早く共有することができた。ほかの人類は太刀打ちできなかった。
しかし、人間の友好性には負の側面もある。自分の愛する集団がほかの社会集団に脅かされていると感じると、人間はその集団を自分の心のネットワークから除外し、人間扱いしない(非人間化する)ようにできるのだ。共感や思いやりは消え去ってしまう。脅威をもたらすよそ者に共感できなくなると、私たちは彼らを同じ人間だと見なせなくなり、極悪非道な行為ができるようになる。人間は地球上で最も寛容であると同時に、最も残酷な種でもある。
■ ■ ■
【目次】
はじめに
第1章 他者の考えについて考える
第2章 友好的であることの力
第3章 人間のいとこ
第4章 家畜化された心
第5章 いつまでも子ども
第6章 人間扱いされない人
第7章 不気味の谷
第8章 最高の自由
第9章 友だちの輪
【著訳者紹介】
ブライアン・ヘア
デューク大学進化人類学教授、同大学の認知神経科学センター教授。同大学にデューク・イヌ認知センターを創設。イヌ、オオカミ、ボノボ、チンパンジー、ヒトを含めた数十種に及ぶ動物の研究で世界各地を訪れ、その研究は米国内外で注目されている。『サイエンス』誌や『ネイチャー』誌などに100本を超える科学論文を発表。
ヴァネッサ・ウッズ
デューク大学のデューク・イヌ認知センターのリサーチ・サイエンティスト。受賞歴のあるジャーナリストでもあり、大人向けと子ども向けのノンフィクションの著書多数。
藤原多伽夫
翻訳家、編集者。静岡大学理学部卒業。自然科学、考古学、探検、環境など幅広い分野の翻訳と編集に携わる。
最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。
