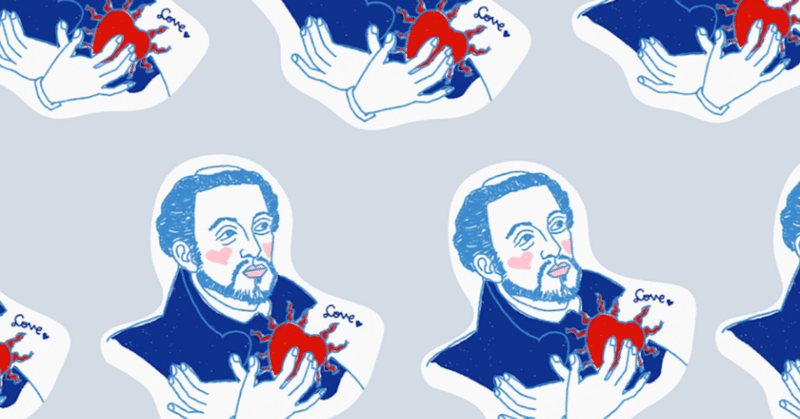
大学生の宗教に対するイメージ
(1)
私はこれまでに神道、仏教、キリスト教にかかわったことがある。まず、神道は初詣を通じて関わった。私は高校生になって初めて、初詣が神道と関わりのあるものだと知った。それ以前は、初詣は正月にする恒例行事としか認識していなかった。次に、仏教は祖父母の家にあった仏壇と葬式を通じて関わった。私が祖父母の家から帰宅する際に、仏壇の鐘を鳴らし、願いを心の中で唱えるように言われていた。また、私が中学生の時に親戚が亡くなり、その葬式で仏教と関わった。印象深いのは、僧侶と数珠である。仏壇に触れているときも葬式をしているときも、特に仏教を意識しているわけではなかった。最後に、修学旅行先の民家でキリスト教と関わった。民泊をした民家がキリスト教を信仰している一家で、キリスト教関連の置物が印象に残っている。
(2)
私は宗教に対し二つの相反するイメージを持っている。一つ目は、ネガティブかつ執着的なイメージである。このイメージは、今までの人生で「宗教」という言葉の使われ方に基づいている。具体的には、「宗教」は友人と話しているときに、自分の想像を超えた執念をもつ個人や集団を揶揄して使われた。例えば、部活において、部員が監督に完全に服従しているさまを、監督を教祖、部員を信者として「宗教」と例えた。見方を変えれば、勝利を目指し一致団結している良いチームともいえる。しかし、「宗教」と揶揄する本人は、そのチームの熱量についていけず、否定的な感情を持っている。
以上のように、私は宗教に後ろ向きなイメージを持っている。
二つ目はポジティブかつ執着的なイメージである。このイメージは、タリバンが原因でアフガニスタンを逃れた家族を特集した番組に基づいている。具体的には、追われた家族は家がなく、洞窟で悲惨な暮らしをしていた。しかし、家族は「神が必ず私たちを救ってくれる」と言い、目を活き活きとさせて生活していた。この場面を見て、私の宗教に対する考えが少し変化した。なぜなら、執着がポジティブな方向へ作用していたからだ。以上のように、私は宗教に対し二つの相反するイメージを持っている。
(3)
私は現時点で「宗教」を「人に根本的かつ精神的な救いを与えるもの」と定義する。救いを与えるという点では、医療も同様である。しかし、医療はタリバンに追われ悲惨な生活を強いられている人に生きる希望を見出させるようなことはできない。ここに、宗教と医療の違いがある。精神的な苦しみに対し、医療は対症療法であり、宗教は原因療法であるといえる。つまり、宗教は人の視点を変え、苦しみを緩和させることができる。
この点で言えば、宗教は「セラピー」である。「セラピー」とは当人を変化させ、根本的な問題解決を図ることである。つまり、宗教は困難を直線的にとらえて、困難から救済への道筋を示すものである。この考えと反対にあるのは、「ケア」という考えである。以上のことから、「宗教」は「人に根本的かつ精神的な救いを与えるもの」である。¹
参考文献
1東畑開人『居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書』(医学書院、2019)
当該270ページ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
