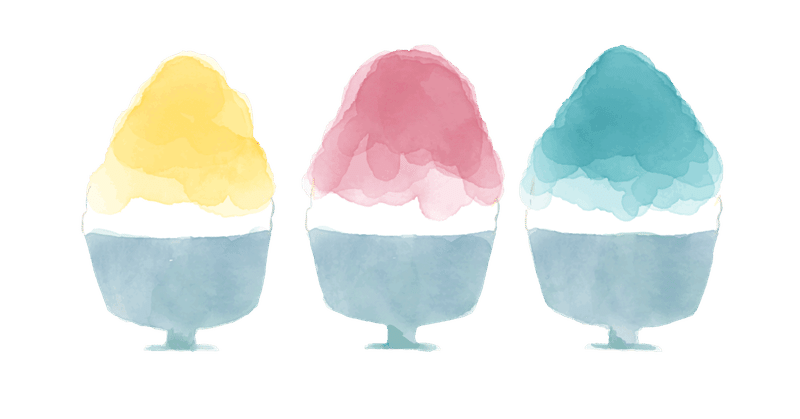
(短編)『だれがいちごを殺したの?』(鵜)
だれがいちごを ころしたの?
わたし と宇治金時がいいました
わたしのおもちで
わたしがころした
だれがいちごをしぬのをみたの?
わたし とメロンがいいました
わたしがあみめで
しぬのをみた
だれがそのしる うけたのか?
わたし と練乳がいいました
おさらでうけて
いちごみるくにした
だれがきょうかたびらを つくるのさ?
わたし とオレンジがいいました
わたしのかわで
わたしがつくる
だれがおはかを ほるだろう?
わたし とブルーハワイがいいました
ビッグウェーブで
わたしがほろう
だれがぼくしに なるのかね?
わたし とくろみつがいいました
袈裟くろぐろの
わたしがなろう
みてられない
と きゅうに氷がいいました
こんな ちゃばん
あまりにさむくていたたまれない
かわいそうな いちごのため
こおりがそのみを けずるとき
のこりのみつは いってきのこらず
おおわらいして とびこんだ
「そうして、この世に新たなかき氷が誕生したの」
八月の昼下がり、かき氷屋の店先の、道路にめんした木のベンチに並んで。
まるで世界でいちばんかき氷にぴったりな舞台装置で、女はもう話を終えた、かのようにブルーハワイをつついている。みょうちきりんで、へんてこな詩。ぜんぜん意味がわからない。一方的に聞かされた私は納得がいかないまま、粗めの氷を口に含む。オレンジのシロップは氷をすり抜けて底に沈んでいる。
「イチゴ味だけがないかき氷?」
はたしてそんな味に需要があるだろうか?
ぺらぺらのストロースプーンでは日差しに氷が負けてしまう。スチロール容器を傾けて、口いっぱいに氷をかきこむと、シロップもどっと流れ込んできた。
「イチゴ味のないかき氷なんてって誰でも思うわよね。そう、彼女だけは殺されてはならなかった。いまこの世界で進み続けるかき氷の衰退は、この時に始まったのよ」
喉元までしたたるブルーハワイを優雅にぬぐって、女はほほえんだ。
実際はイチゴのかき氷なんて今でもどこにでもある。けれど、確かに彼女の言うように、かつて絶大な力を持った女王としてのイチゴの姿はもう、ない。
真夏の太陽の下に最高に見映えのする、嘘みたいに明るい赤と、安っぽく甘い匂いのシロップはいまや日陰ものになっている。子供たちが競って舌を赤く染めた夏祭りやプール帰りの買い食いは、疫病の流行と上昇し続ける気温のせいで姿を消した。
今の王者は冷房の効いた屋内や車ではるばる向かうリゾート地で供される、新鮮な果物や手作りのソースにまみれた氷たち。
ほんものの果汁。
ほんものの匂い。
頭痛を誘う粗い氷とはなにもかもが違う、きめ細かな氷の舌触り。
さらに氷とは縁遠ければ縁遠いほど賞賛の起こる、トッピングの具材たち。
栗だのかぼちゃだのカレーだのに占められたテーブルの上では、作られた色と匂いのイチゴシロップが再び権力を持つことはないだろう。
所詮は期間限定の夢だったのだ。
自分を忘れて夢を見ていたかき氷は、ふと、千年もの昔を思い出した。
ひと握りの貴族の特権中の特権だった、高貴な高貴な自らの姿を。
夢からさめたかき氷は、ほんのいっとき友達だった子供たちをさらりと捨てて、もといた地位に戻ったのだ。
月に帰ったかぐや姫は不死の薬を残したけれど、眠りを解いたかき氷は、最も愛した存在を連れて行ってしまったのだ。
戯れか、贖罪か。
どちらにせよいちごを殺したのは、駄菓子から御菓子へと戻っていったかき氷自身だったのだ。
……ばかばかしい。
炎天下で変な話を聞かされて私もすっかりおかしくなったようだ。
思いがけず再会した旧友といっても、名前しか覚えていない程度の相手だ。懐かしいね、あの駄菓子屋のかき氷覚えてる? 近くだから一緒に食べようおごるから、なんて誘いにのこのこついてくるからこうなるのだ。ばかみたいなパロディに、わけのわからない冗談。子供のころの友達と大人になってから話すと、ぎょっとするようなギャップを感じることが多々あるが今日のこれはかなり上位にくるな。
確かに駄菓子屋は10年ぶりに入ってみて懐かしかったし、氷だけもらってシロップをかけ放題という、子供心をとびきりくすぐってくれた投げやりで良心的なシステムも、やっぱりなんだか贅沢な気持ちになれてうれしかったけど。
もちろんかき氷は悪くない。
おいしさは誰と食べるかが大事、なんて基本の基本をないがしろにしていた私が悪いのだ。
オレンジのシロップが冷たさを残しているうちに飲み干したらすぐに席を立とう。
「あの時もこれぐらい暑かったよね」
突然、女の指が肩に触れる。指先がおそろしく冷たいのはきっと氷のカップを持っていたからだ。
「一緒に食べたことあったっけ?」
「なんだ、今まで覚えてないまま食べてたの? いちこちゃん」
首をかしげると長い黒髪がするすると服を滑る。
「夏休みで、今日とおんなじ空だったよ。青くて濃くて眩しくて」
指先はまったくぬるくならない。
スチロール容器を包む私の手のひらは汗ばんでいるというのに。
「一緒にプールにいったじゃない」
ーー思い出した。
学校のプール開放の日、待ち合わせたクラスメイトの中に彼女もいたのだ。
ほとんど話したこともない女の子だった。
そして帰り道に、2人でかき氷を食べたのだ。
なぜだか他の友達は一人もいなかった。シロップを選ぶまではうきうきと盛り上がったものの、いざ食べだすと話題もなくて、プールでせっかく冷えたからだがどんどん汗ばんでいくのを感じながら、もくもくと氷をつついた記憶。私の短い髪はあっという間に乾いて、日差しを受けてなんだか焦げているみたいだった。視界の端では、彼女の長い黒髪がいつまでも乾かずに、濡れ濡れと光る先端から垂れた水滴が服に染みをつくり続けていた。
「あの時なにを食べたか覚えてる?」
「さあ……」
「いちこちゃんはね、いちごを食べてたよ。名前と一緒だからって」
そういうと女は立ち上がり、べろ、と青く染まった薄い舌で唇をなめるとカップを捨てた。
軽い容器は音もたてずに箱に消えた。
「ねえ、どうして今日は、いちごにしなかったの?」
「え?」
「またね」
見上げた時にはすでに後ろ姿で、どんな表情をしていたかはまったく見えなかった。
遠のく背中もすぐに見えなくなった。
帰りそびれて私は、残ったオレンジシロップを地面にこぼした。
いつのまにか、飲めないくらいぬるくなっていた。
みっしりと並んで足元にたかっていたアリの行列が、蜜の濁流に呑まれて乱れて流されていく。翳り始めた西日を受けたオレンジ色が赤みを増す。
まるでいちごのシロップみたいに。
ふと、首から胸元につたう汗が冷えた気がした。
いちごのかき氷シロップ。
そうだ。
さっきのへんてこな詩にずっと違和感があったのだ。
けれどそれを、隣でほほ笑む彼女にはとうとう言えないままだった。
まして他の人にはこんなこと、ばかばかしくて話せない。
『ほんとうに、いちごをころしたのは宇治金時だったの?』
『どうしてあの歌には、あなたの名前は一度も出てこなかったの?』
かき氷のはじまりは、削った氷にかずらの蜜をかけたもの。
とろりと甘くて透明な蜜は、すべてのかき氷の原点だった。
『ほんとうにいちばん、いちごをいちばんころしたかったのは、だれ?』
彼女の指に触れられた肩が、氷のような冷たさを思い出す。
その一点からぞっとする冷気が体全体を包んでいく。
視界が歪む。
『いちごにするならかけてあげようか?』
目を細めて私に尋ねる彼女の白い指は、赤いシロップに伸びていた。
『オレンジにするから大丈夫』
こたえた私の言葉に、ほほえんだまま目をそらした彼女の名前はたしか、
みぞれちゃん。
(終わり)
鵜狩愛子 2021 KGB vol.2録
雰囲気不穏。
なんかやたらと思わせぶりなこと言う子っていませんでした?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
