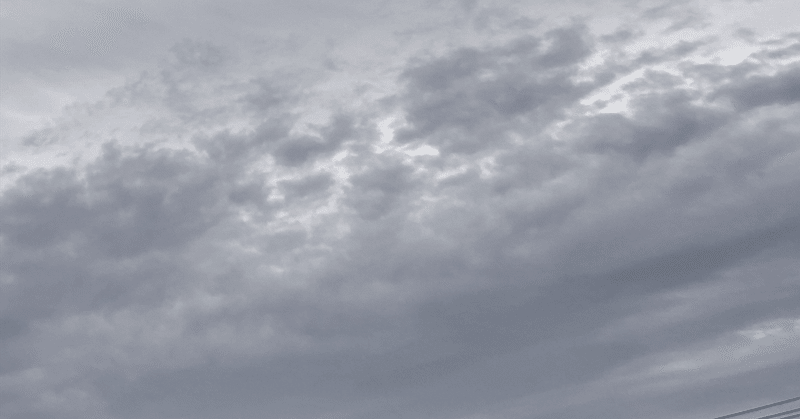
Photo by
hina_sakurae
雨滴〈掌編小説(488文字) 短歌〉
雨あがりの道の、そこかしこにまだ雨滴は残っていた。
四月の終わり、新緑は曇り空のもと少し重たげに見えた。犬が、ぐんとリードを引っ張るので、慌てて手に力を込めた。
道をそれ、草むらに入っていこうとする犬の両頬に、たんぽぽの綿毛がまとわり付いている。犬は気にせず突き進もうとするけれど、押しとどめ、体に付いた綿毛をそっと払った。湿りを帯びた綿毛は指にくっつき、指を擦り合わせて取ろうとすると、綿毛がよじれて萎れたようになった。
指先から離れ、ぽとりと綿毛は地面に落ちた。ああ、果たして君に芽吹く日は来るのか、と、切ないような申し訳ないような気持ちがふいに押し寄せた。
はやく行こうよ、というように犬が振り返る。そうだ、行かなくちゃ。気を取り直して、リードをしっかりと握った。
歩きながらもしきりに私の顔を見あげてくる犬の額に、綿毛がひとつ付いていた。綿毛に付いた小さな雨滴が、光を反射し、犬の嬉しそうな顔も一緒に輝いているように見えた。可愛いなと口元が緩む。そうだ、綿毛も一緒に行こうか、行けるとこまで。そう思った先から、ひゅうとかすかに吹く風に、あっけなく綿毛は宙に舞った。
〈短歌〉
名を付ける間もなく消えた思いには雨滴がひとつ付いてるだろう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
