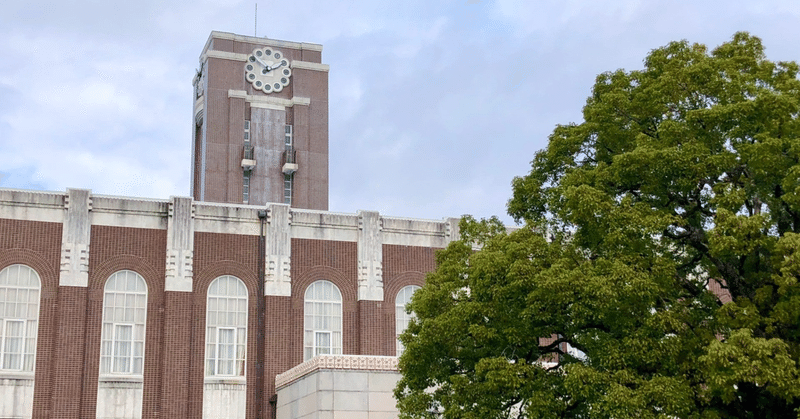
”鶏鳴狗盗”な総人(京都大学総合人間学部)
この記事は,2014年に発行された以下の冊子に掲載されたエッセイを,許諾を得た上で公開したものです。「文理融合」や「学際」を謳う京都大学総合人間学部に在籍していたときの,ひとりの学生としての正直な気持ちを記事にしました (厳密には,当時すでに同大学医学部人間健康科学科に転学部したあとだったので,総合人間学部の学生ではなくなっていたのですけれど…)。
萩原広道 (2014). ”鶏鳴狗盗な総人". 総人・人環連絡協議会 (編), 総人・人環紹介冊子∫ (integral), vol. 1, pp.29–30.
なお,文中に出てくる2つの用語についてあらかじめ補足しておきます。
総人=京都大学総合人間学部。いわゆる旧教養部系の学部。
人環=京都大学大学院人間・環境学研究科。総合人間学部の上にのっかっている大学院。
”鶏鳴狗盗”な総人
萩原 広道
京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻
高校のころ、漢文の授業で「鶏鳴狗盗」という話を習った。何か1つでも特技があれば、それがどのようなものでも食客として迎え入れた孟嘗君という人物の話で、彼が他国に捕らえられた際、スリの達人や鶏の鳴き真似の上手い者が食客にいたおかげで逃げ出すことができた、という故事である。ご存知の通り、故事成語としての鶏鳴狗盗には、くだらない技能しか持たない者、どんなつまらない技能をもつ者でも役に立つことがあること、といった意味がある。ところが、私がこの意味を知ったのは京大に入学して以来のことで、それまでは「面白い人間が集まると大きな力が発揮される」という、全くもって的外れな解釈をしていたのである。ゆえに鶏鳴狗盗は私にとって、お気に入りの故事成語となっていた。「総人は鶏鳴狗盗のような場所だね」などと、今考えるとひどい悪口を言ったことさえあった。当時は褒め言葉のつもりだったが、最近は本来の意味を知った上で、同じことを言いそうになってしまうときがある。
総人・人環がいかに魅力的で素晴らしい場であるかについては、多くの寄稿者が既に触れていることと思う。せっかくいただいた紙面を台無しにするようで恐縮だが、私はあえて、自身が体験した総人・人環の ” いやぁなところ ” をここでは紹介することにしたい。
ある教員が、総合人間学、または人間・環境学という学問とは何たるかについて説いたことがあった。確か、「総人・人環という場は素晴らしい。教員同士で話をすると、それは物理学ではこういうのですよとか、心理学ではこういう捉え方をするんですとか、面白くて深い議論ができる。これこそ
が総合人間学、人間・環境学なのだ」という内容だったと思う。私は素朴に、違和感を覚えた。本当にそれが総合人間学なのだろうか。既存の学問の専門家同士が議論して情報交換しているだけで、「総合する」ことにはなっていないのではないか。しかもこのとき、教員ではなく、学問的なバック
ボーンを持たない学生が総合人間学を創出しようとしたらどうなるかについては触れられることがなかった。理念上は「新たな『人間の学』の創出を目指す」と掲げられているが、教育カリキュラムや組織図を見る限り、理念が現実から遠くかけ離れているような気がしてならない。
一昨年ほど前、教養教育(全学共通教育)の主要な実施機関としての総人・人環の姿勢が問われる事件が起きた。このとき、別の教員がこういうことを言っていた。「教養教育を担当する幅広い分野の教員が集まって、教養教育の在り方について議論したことはこれまでなかった」。個々人で創意工夫する教員は確かにいた。しかし、全体としての交流やまとまりに欠けていたとなると、総人・人環の理念はどこへやらと言いたくなる。隣の研究室で誰が何を研究しているのかなどほとんど知らない人環の教員や院生はかなりいると聞くし、総人の学部生同士の交流も学年が上がり専門分化するにつれ
て限られたものになっていく。この話を聞いて以来、少なくとも教養教育について度々耳にする総人・人環への批判――「入学したての学生に学んでほしいことが総人では提供されていない」「総人・人環という場は素晴らしいが、所属する教員がちっともシャキッとしてくれない」など他学部教員の話、「教養教育はつまらなかった」「パンキョーはオマケだった」など学生の話――に対して、私は上手く反論できなくなった。また、教員同士が分野を跨いで教養教育について議論することも、全体として意思統一されることもなくこれまで教養教育が行われてきたと考えると、総合人間学、人間・環境学という学問についても同様のことが起きているのではないか、と疑わざるを得なくなる。総人は「総合人間学部」ではなく、平行線のまま総合されることのない「パラレル人間学部」なのではないか、という疑念が頭にこびりついて剥がれない。
「総合人間学をつくっていくのは、総人に入った君たちの役目だ」という教員までいる。ある意味で夢のある言葉かもしれないが、捉えようによっては完全に学生を突き放した言い方である。総合人間学なるものができるとして、そのために学生に何を提供したらよいかを現実的に検討しないだけでなく、自分たちで総合人間学をつくっていこうという気などない教員も(少なくとも一定数は)いるようだ。そのような状況の中で、よくこんな学部・研究科ができたものだと思う。
私は総人から去った身なので(2012 年度に転学部して今の所属に至る)、何を言ったところで所詮は外野の野次に過ぎない。しかし、総人・人環内部でも同じようなことを感じ、危機感を抱いている学生は確実にいる。その上で、卒論の指導教員も自分の所属も既に総人から離れている私の方が、かえって遠慮なくこういうことを口にできるのではないかと考え、この際だからと総人・人環に対する疑念をぶつけてみることにした。ただし、本当にこれで良かったのかは読者の反応を待った上で判断したいと思う。
最後にある教員の言葉を引いて終わりにしたい。個人的には、総人・人環は私の勘違いのままの “ 鶏鳴狗盗 ” の場であってほしいが、それはなかなか難しいようだ――。「そもそも、総合人間学なんてないんだよ。教員はほとんどそれを知っている。学生はそれを知らずに入学してきて、入学後に現実を突きつけられる」。
補足情報
文中で,「教養教育(全学共通教育)の主要な実施機関としての総人・人環の姿勢が問われる事件が起きた」とありますが,当時の状況や経緯については以下の書籍をご参照ください。
また,今回公開した記事の発行以降に,京都大学総合人間学部/大学院人間・環境学研究科による教育理念・実践の見直しが行われたり(厳密にはもっと前から行われていましたが,学生を含めた部局構成員に周知されるようになったのは少なくとも上記の事件後だったと記憶しています),学生が教育活動に主体的に取り組んだりしてきました。
それらについては,以下の2つの報告書に記載があります。うちひとつはオープンアクセスなので,どなたでもご覧いただけます。
臼田泰如・佐野泰之・瑞慶覧長空・須田智晴・寺山 慧・萩原広道・渡邉浩一 (編) (2017). 学際系学部の教養教育 報告書:教員にとっての学際/学生にとっての学際. 京都大学大学院人間・環境学研究科 学際教育研究部.
人間・環境学研究科院生による総合人間学部生向け模擬講義企画「総人のミカタ」運営委員会 (編) (2018). 「総人のミカタ」活動報告書:2017 年度前期~ 2018 年度前期. 京都大学大学院人間・環境学研究科 学際教育研究部. http://hdl.handle.net/2433/235245
さて,私はもう学生ではなくなってしまったわけですが,当時の自分に恥じない研究者になっているかと問われると,正直冷や汗が止まりません。この記事の公開に自戒を込めたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
