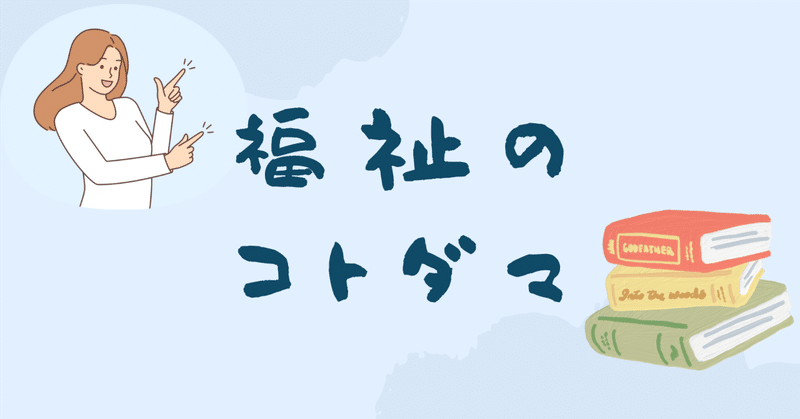
【コトダマ014】「助けてもらった経験を・・・」
「助けてもらった経験をたくさんしていれば、助けを求めたいと思えるようになる」
「グローバル時代の海外福祉事情 フランスの家族政策①」(p.94)
平日はなるべく毎日アップしようと思ってたんですが、昨日はいろいろバタバタしていて手が回らず。毎日noteを更新されている方々は、本当にスゴイと思います。
さて、気を取り直して本日は、新鮮な採れたてのコトダマをお届けします。福祉関係者必読の雑誌『月間福祉』(全社協)の最新号です。特集テーマの「身寄りのない人を地域で支える」もとても充実していたのですが、個人的にもっとも目を引いたのが上のフレーズ。フランスの家族政策を紹介する文章の中に出てきました。
あくまで家庭や子どもに関わるソーシャルワーカーの話である、という前提ですが、フランスでは早い段階から、親たちの専門職への信頼を育てようとしているそうです。その背景にあるのが、上のような考え方。「助けを求めてくるのを待つ」から「助けを求めてくるようなクライエントを育てる」への、発想の転換です。だから、フランスのソーシャルワーカーは早い段階から積極的に親たちにアプローチしていくそう。
でも、これって、いろんな場面で言えることですよね。ヤングケアラーとか、夫の暴力に耐える妻とか、会社を辞めて一人で介護を背負い込む中高年とか。
よく言われるのが「助けを求めてこないからしょうがない」という言葉。でも、そうじゃないんです。「助けを求めてこられるような環境を作る」んです。それがソーシャルワーカーの役割なんです。
残念ながら、現場では全く逆の話を聞くことも多いです。長年にわたり重度障害のある息子を介護してきたある親は、なぜ誰にも相談せず一人で抱え込んできたのか、と問われて「この子が子どもの時に相談したけど、冷たくあしらわれた」「自分でできなくなったら相談するよう言われた」と言いました。まあ、相談したのは何十年も前のことで、今ではそんなことはないと思いますが、相談したほうは一度そういう扱いを受けてしまうと、二度と相談しなくなってしまうことも珍しくありません。
最初に相談を受ける行政機関(今なら地域包括支援センターとか基幹相談支援センターとかも)の責任は重大です。「助けを求めたいと言われるような」初期支援を、私たちはできているでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
