
野口体操を体験した。
以下の記事は私が雑誌「自由時間」に書いたものです。おそらく1993年くらいでしょうか。当時80歳近かった野口三千三先生の生き生きとした所作が思い出されて、あらためてすごい方だったんだなあと思います。いまの自分があの動きをできるかといったら? まったく無理! 画像は「みんなのフォトギャラリー」より。先生が高層ビルも自然だ、とおっしゃっていたので。
最近、「体操」という言葉を使うことが少なくなった。たとえば書店に行って体操の本を探したとしても、並んでいるのはスポーツの本であり、トレーニング、フィットネス、エクササイズの本である。
ではこれら横文字の言葉と日本語の「体操」は、同じものを差すのだろうか。確かに身体を使って何かをやるという意味においては、似ているように思える。 しかし、野口三千三さんの行う「体操」を体験してしまうと、両者の意味は百八十度違うということが分かる。
野口さんは「体操」と書いて「からだに操(き)く」と読ませる。「からだに操を立て、ひたすらからだの声に耳を傾ける」というほどの意味だろうか。さらに進んで、
「自分自身のからだの動きの実感を手掛かりにして、自分とは何か・人間とは何か・自然とは何かを探検する営みを体操という」
とも。そこには自分が主体となって、道具としての身体を「使う」とか「鍛える」という概念は一切ない。逆に自分にとって最も身近な自然であるからだに対して、ひたすら「伺いを立てる」ようなニュアンスだ。 このユニークな体系は、一体どのようにして生まれたのか。それを行うことは私たちにとってどんな意味を持っているのか。野口三千三とは、そも何者なのか。
そのことを探る前に、まず野口体操では具体的にどんな動きを体操と呼ぶのか。ある日の授業風景を見てみよう(今回の取材では写真撮影が許可されなかったので、実際に体操を体験したイラストレーターがその様子を絵に描いた)。
からだの中身はつぶ
ここは新宿駅からふたつ目のバス停で降りた、小さなビルの一室。50平方メートルほどのスペースに、下は20代から上は60代くらいまでの男女が約30名集まっている。
「はい、ぶらさげ」
野口さんの号令で、ひとりの女性が進み出る。両足はごく自然に踏みしめ、口をぽかんと開けて、目は宙をさまよう。
次の瞬間、彼女のからだのなかで何か劇的な変化が起こったのだろうか。全身がやわらかく揺れ、骨盤のあたりから前へ折れ曲がり始める。その動きは次第に上体に伝わり、肩、腕がゆらゆらと漂う。まるでひとつひとつの関節を外していくような、動きである。そのままおじぎ草がすっかり頭を垂れるように、上体は腰のところから「ぶらさがった」。
両手はだらりと床に着いているが、立位体前屈のような窮屈な感じはない。むしろ操り人形が糸でぶらさがっているようにさえ見える。
「重さに任せて。気持ちいいかどうか、からだに問い掛けて」
野口さんが言う。記者も見よう見まねでやってみるが、もともとからだが固いためか腹の脂肪が邪魔をしているのか、さきほどの女性のような動きにはぜんぜんならない。見かねた野口さんが透明の容器のようなものを持ってきた。プラスチックの板を3ミリほどの間隔で重ね、その間に直径1ミリのベアリングを何千個も閉じ込めたものだ。それを耳に当てたまま上体を前に倒すと、ザーッという砂浜に波が打ち寄せるような音がする。
「からだの中に細かいつぶがいっぱいつまっているような感じで、ね」
野口さんはみんなの間を動きまわり、いいところを褒め、悪いところを指摘し、ときには女性の生徒をからかいながら、喜々としている。今年79歳になるとは、とても思えない。
信用できるのはからだだけ
野口三千三さんは週一回ここで授業をするほか、朝日カルチャーセンターでも体操を教えている。戦後ずっと東京芸術大学で体育の教授職にあり、現在同大学の名誉教授でもある。
大正3年群馬県の生まれ。昭和9年群馬師範学校を卒業し小学校の教師となるが、教員生活と平行して勉強を続け、師範学校教師の検定試験に一番の成績で合格する。この間まったくの独学で、解剖学の専門書を何冊も暗記し、そん理論を自分のからだの感覚で確かめていくという作業を続けた。その結果皮肉なことに、死体の解剖を基礎とした体操の理論には、どうも現実のからだの動きと矛盾するところがあると気がついた。
さらに第2次世界大戦の敗戦で、価値観のどんでん返しを体験。自分にとって一番信用できるものだけを手掛かりにして、新しく出発しようという思いが湧き上がってきた。その信用できるものというのが、焼け野原となった東京に厳然としてあった大地=自然であり、その自然の最も身近なあらわれとしてのからだだった。
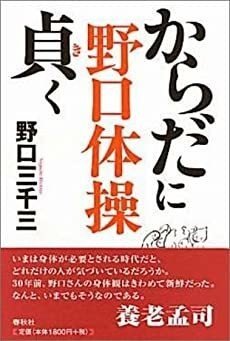
自分の実感を手掛かりに
ふつうスポーツの世界では100メートルを何秒で走ったとか、どれだけ難しい動きが出来たかを評価する。身体のサイズや筋肉の質、柔軟性の違いなど無視して、ある特定のワクの中で記録を競い合う。
野口体操では、その動きが自分にとって気持ちいいかどうかを、からだに聞きながら行えという。あくまでその人の個性、能力、好き嫌い、快・不快を大事にするのだ。その結果、
「力ずくでなければ出来ないような動きは出来なくてもよい」
という言葉が出てくる。しかしそれは同時に、
「力を抜けば抜くほど力が出る」
という言葉にも通じる。
腹筋運動に似ている「おへそのまたたき」という動きがある。床に仰向けに寝て両手を頭上に伸ばし、臍の周辺の筋肉の緊張だけで上体を起こす。そのとき使う力が小さければ小さいほど上体の動きはなめらかに、腹から胸、首と順番に持ち上がって、一番遅れて頭がついてくる。
周囲を見回して真似してみるが、これが出来ない。どうしても首に力が入ってしまい、やわらかい動きにならないのだ。そのときこちらの当惑を見越したのか、野口さんが、
「あんた、ひとりでやってみて」
という。みんなが注目するなか、床にころがった記者の頭の中には、うまくやろうという気持ちはすでになかった。それまでは他人の動きの外見をそのまま真似していたのだが、そんな意識もふっとんでいた。「ふっ」と息を吐く感じで臍に力を入れると、自然に腰のあたりから折れ曲がり、胸が突き出て最後においてけぼりになった頭が前に倒れた。気持ちいい動きだったな、と思っていると、みんなが拍手をしてくれた。野口さんも、
「2、3回目で、そのからだで、よくできましたね」
と褒めて(?)くれた。もっとも、その後、得意になってもう一回やったらできなかった。やはり頭で考えすぎると力が入ってしまうみたいだ。
すべての理屈を無化する
ここまで読んで、読者は「そんなことをして何の役に立つんだ」と思うかもしれない。しかし野口体操の「効用」を説明するのは難しい。
野口体操とは何かという問いに対しては、様々な答えが可能だ。からだを通じて自分に気づくボディワークといってもいいし、直感的洞察を大事にする「動く禅」とも呼びたい。体操の前に様々な話題(映画『レックス』だったり遺伝子の話だったり)による講義があるのだが、知的刺激に満ちている。
いうまでもなく単純にリラックスする効果もあるし、もっとも身近な自然であるからだに向かい合うということから、環境問題とのリンクも可能だろう。
でも教室に来ている老若男女の晴々とした顔を見ていると、こうした説明はどうでもいいように思えてくる。結局浮かんだのは「遊び」という言葉だ。
「臀たたき」という動きがある。要するに踵や足の裏で臀部を叩くだけなのだが、足の力でやろうとしても絶対に出来ない。足の力は抜いて、全身がバネのようになってふわっと浮いた瞬間、パシッといい音がするのだ。
馬鹿らしいように見えて、あらゆる理屈を無化してしまう衝撃の音である。リラックスと真剣さが同時に存在する、根源的な意味での遊びのこころが、そこにはあると思う。
もちろんこの遊びが、自然としてのからだに対する畏敬の念とつながっていることは、繰り返すまでもない。いやむしろ、自然を前にしたら人間は遊ぶことくらいしか出来ない、というのがほんとうかもしれない。

_
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
