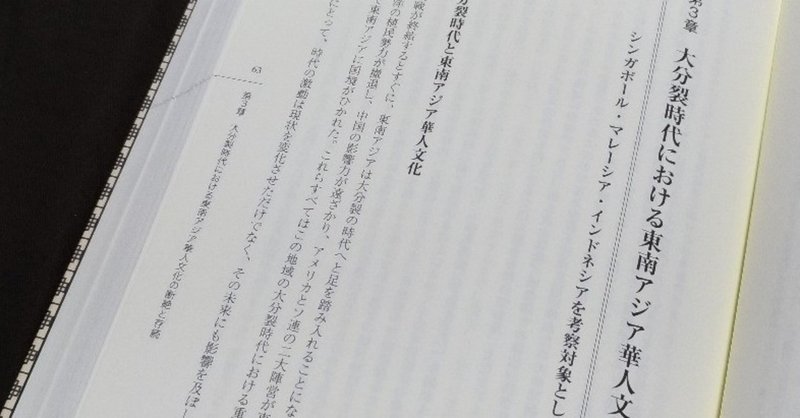
東南アジア華人の文化生き残り作戦を学んだ(漂泊の叙事)
今日は「漂泊の叙事(勉誠出版)」を読み進めました。
漂泊の叙事とは?…1940年代以降の、東アジア大分裂時代に、主に中華圏において、音楽・文学・詩・劇・旅行記etcに関わった表現者たちが、時代に翻弄されるなかで、どのように文化を作ってきたのかを紐解く文化史です。
で、世の中的にはこういう本を「学術書」と呼ぶらしく、大学の授業とかで使う本とのこと。
私専門卒だから知らなかったヨー。
でも、どうしても知りたい知識があったのをきっかけに、購入しましたー。
で!
全部で500ページくらいあるのと、内容が結構むずかしいので、興味がある章(主に台湾関連)から読み進めていたのですが…!
今日は、この章にビビっときました!

「大分裂時代における東南アジア華人文化の断絶と存続」
ここには、「シンガポール・マレーシア・インドネシアに分散した華人たちが、中国との距離が遠ざかるなかで、どのようにして華人文化の生き残りを図ってきたか?その歴史は?」というテーマについて書かれています。
それぞれの国家の状況、政治の方針、華人の割合が異なるなかで、それぞれ文化生き残り作戦を展開していくのですが、歴史に翻弄されて、まー色々あるんですね。
華人人口比率は高いものの、イスラム教への気遣いetcで抑圧されたシンガポール。(ただ、1980年頃からまた華人文化推しになってるそう)
政府がマレー人推し、華人教育が葬られる方針に危機感を感じ、経済的に独立する道を選び、【華人の学校】を守ることで、文化を継承したマレーシア。
宗教によって、華人文化を残したインドネシア。
なんか、ここから言えるのって結局、「文化を守れるかどうかって、経済的に自立できてるか?経済の恩恵を受けられるか?」にかかってくるんじゃないかと思いました。
だって、本書を読む限りでは、シンガポールでまた華人文化推しになったのは、中国経済の伸長を受けてのことだし、
マレーシアで華人学校が生き残れたのは、経済的な独立があってのことだし。
前から薄々感じてたけど
文化って正直、「水道」とか「米」とかに比べてみれば、重要度が伝わりにくいもので、利用価値がなければ、まっさきに【国】や【政治】から「切られやすい」存在で。
(大切な存在じゃないと言ってるわけではない。実際に私も芸術や、音楽ライターの仕事を通して学んだことや出会えた人たちがたくさんいた。それがなければ今の自分はない。)
だからそうならないためには、守りたい文化を守れる資金を確保しておいたほうがいいし、自力で調達する努力はしておいたほうがいいし、自立するのが難しいようなら、政治の影響を受けない会社とコラボして守ってもらう努力をしたほうがいいのかなと思いました。
私も頑張ろうと思いました。
Twitterやってます!
中華文化や、中華圏のインディーズミュージック、そしてWebマーケやSEOに、興味のある兼業フリーランスです。とっちらかりがちな私ですが、お気軽にフォローしてくださいませー!
Twitterアカウント⇒ 中村 めぐみ✏ライティング・コンテンツ担当 (@Tapitea_rec)さんをチェックしよう
サポートをどうもありがとうございます。大切に使わせていただき、新しい行動を起こして、また役に立つ情報をお届けしますね。
