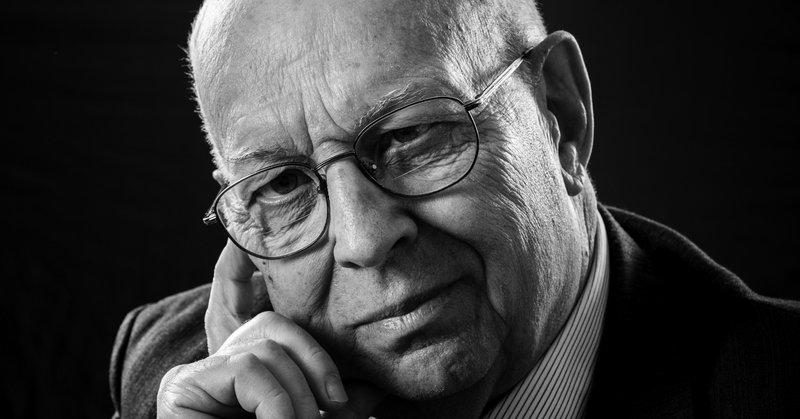
混沌とする『デザイン』の行き先は
こんにちは、グランドデザイン代表の西克徳です。
今日はNoteを回遊していて思い至った『デザインの行き先』についてまとめてみたくて書き始めます。このnoteはデザイン業界でそれなりに長く仕事してきた方たちが感じているであろう、今までにない変化から生まれている不透明感から、その先にある希望を確認する事にたどり着けたらと思っています。多分それは、これまで重視されてきた『技術信仰』から『知見と技術のアセットこそが大事』な方向に向かいそうだという、まとめです。
デザインは時代に合わせて働く場所を変化させてきた
ご存知のようにデザインはドイツ生まれで、資本主義経済の発展の中で育った技術ですから、時代の要請に答えながら姿を変えたり分岐したりしてきています。日本の歴史でいえば前回オリンピックのポスターをデザインされた、亀倉雄策さんに始まり、広告がデザインを取り込んで日本をバブルまで牽引した時代があり、バブル後WEBの普及で多くのデザイナーはWEBデザインに移行し、さらにはデジタル系のサービスデザインに足を踏み入れていった人達も多かったですね。一方広告に情熱を注いできた絵作り系デザイナーは、広告をはじめとしたコミュニケーションを手掛けながら、主にブランディングに移行しているのがこの100年ほどの「ざっくり歴史」と言っていいと思います。中でもデジタルとネット技術の出現で生まれたWEBやデジタル系サービスデザインの流れは誰にも分かりやすい分岐点だったと言えます。
いまはルネサンス前夜
そんな中で今が次のルネサンス前夜(〜変化の前触れ)だと感じている理由は、以下の2つ。
まず、僕も30年ほどデザインの本はいろいろ読んできましたが、今ほど多くの人が『デザイン』について語っている時代はなかったのではないかと思っています。いやそれなりには語っていたかも知れないが、少なくともSNS(日本ではnote)によって語りが可視化されたことで、いっそう議論が進んでいる。この議論からは絶対新しい動きが加速してきそうだなと感じるのがひとつ目。そしてデザイン会社を20年経営していて感じる、一般大学からのデザイナー志望の多さが年々増加している状況です。これはWEBの普及と相まって加速しているのは確かですが、WEBなら初心者歓迎な会社はたくさんあるものの、弊社のようなブランディング系の会社に興味を持つ優秀な一般大学生(非美大生)にどう向かい合うべきかは、僕の最近のテーマになっています。
そんなことを思いながらnoteを流し見ていたら、知り合いの石坂くんが同じようなことをnoteに書いていて、びっくり。彼も同じ問題意識持ってるんだと思い、ここに共有します。
石坂くんのnoteの次に、モンブランさんのこのnoteもあってまたビックリ。
これもしっかり僕の意見を代弁してくれています。
このシンクロニシティはなんでしょうか?
石坂くんもモンブランさんもnoteでデザインの語り部として有名だし、多くの人がこの『非美大系学生のデザイン界への流入量の多さ』を背景にしたnote記事を目にしているはずです。これは、デザイナーが他の職種へ『流出』しているということではないから、美大系デザイナーである我々が怯えるような事態ではないと、たかを括っていると痛い目に遭います。
この流れはここ20年間で、UI,UXをはじめとし、ゲーム、広告、販促、ブランディングから、D2CやスタートアップのCDOまで、デザイン技術を使った職業のパンデミックを受けたものであり、この変化には我々が求められる技術への『変化』を伴わない訳がありません。いろいろ活躍の場が広がって嬉しいなぁ〜と言う能天気な話ではないと思っています。
今まで重要とされてきた『汎用的技術』の価値低下が起こる
こんな話をしている僕は、バブル崩壊後社会に出て、80年代に昇華した日本の『グラフィックアート』の洗礼を受けた世代です。サイトウマコトさんや、戸田正寿さんの作る『グラフィックアート』は世界中のデザインコンペティションを席巻し続け、日本のグラフィックデザイン最強説に心を躍らせた若者でした。
同時に大貫卓也さんの作る広告は、知的で美しく、なのに面白くもあり、こちらもまた当時のカンヌ広告賞でグランプリを獲得するなど、この時代のこの国に生きていることを幸せだと感じれるほど当時(85年から95年)の日本には優れたデザイナーがひしめき合っていました。すなわち日本で一番は、世界で一番だと言えた時代です。ちょうどF1グランプリで言うところの『セナ&プロスト』が日本人だったようなものです。(この例えもわからない人が多いかな?)だからこの時代に養われた日本のデザインの技術は伝統技術となり、今も残り続けています。文字詰めや絵作り、造形の発想方法、写真の扱い方、などですね。
一方、時代は変わり社会も変わっていく中で、サイトウマコトさんも戸田正寿さんも知らない世代がデザイン界に流入してきており、中にはデッサンもせずにデザイナーを志す世代も生まれてきているのが現代です。
確かに日本のこういった伝統的汎用技術は、長年日本のデザインのアベレージを上げてきた。しかしそれば『グラフィックデザイン』と『広告』の範囲で有効な技術であって、これほどまでに広がったデザインの範囲全てを網羅できる技術と言えるのか?と問えば、僕は無駄にハイスペックすぎると感じています。そんなクオリティを求めている人は相当レアです。
改めて、デッサンができなければデザインはできないのかと言えば、そんなこともない。一部のデザインをする時にちょっと不利であるに過ぎない。だから美大を卒業しなければデザイナーになれないわけでもない。高い技術だけを持っていてもそれは『無用の長物』で、むしろデザイナーにもデザイン以外の知見が重要となりはじめている。
ましてや、デザインをイノベーションの道具にしたり、社会課題の解決の道具に使うのなら、美術大学で教えてくれる一般教養ってあんなのでいいんだっけ?が問われている。そう、技術だけでなんとかなってた時代はもう終わっているのです。
これからのデザイナーは、盲目的に『伝統的汎用技術の習得』を追い続け、ただ上手になればなんとかなるってことはなく、『独自の専門知識』と基礎的なデザインの技術を掛け合わせた『専門知識と技術のアセット』を持っている事がとても重要じゃないかと言うことです。簡単に言えばデザインばっかしてたら何もできない人になるよ、って事です。
例えば、
◯D2Cブランドの立ち上げ知見とデザイン技術
◯デジタルサービスの知見とデザイン技術
◯SNSを数十万フォロワーまで育てた知見とデザイン技術
◯AI知見とデザイン技術
◯企業経営知見とデザイン技術
◯ワークショップデザイン知見とデザイン技術
などなどいくらでもあります。
デザイン技術と組み合わせる相手は、自分の好きな事で熱中できる事で良いのだと思います。って、なんだか前の投稿と似てきちゃったな。。。
次は全く違うこと書こうと思います。
ちなみに上の写真と僕とはなんの関係もありません(笑)
Twitterもやっています。フォローしてくれると嬉しいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
