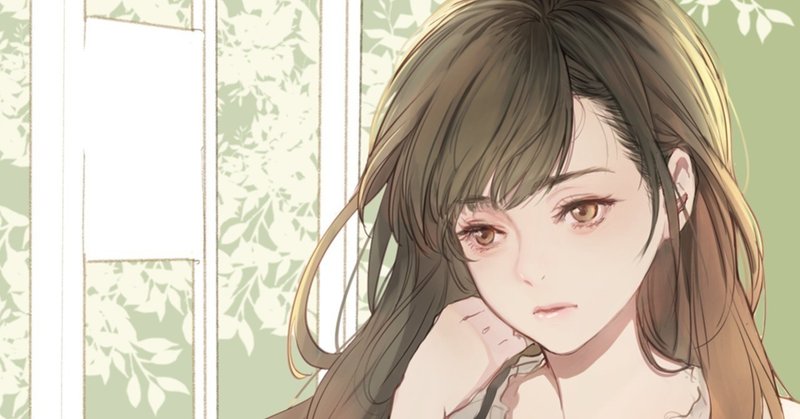
『壁の中のside-B』試し読みページ
電子書籍『壁の中のside-B』の試し読みを用意しました。
気になってる方、ぜひぜひこちらでチェックしていただけると嬉しいです。
壁の中のside-B
著者 館山緑
表紙イラスト 二上ネイト
kindle、kobo、BOOK☆WALKERにて電子書籍発売中
定価400円
あらすじ体が溶けて死んでしまう奇病、通称『メルト』が急に勃発した波南町は、外部への感染を防ぐために急遽高い壁で隔離された。
波南町に住む『わたし』は、壁の中に閉ざされたまま、壁の外にいる友人にも恋人にも排斥され、壁の中にいた人々も死に絶えた……はずだった。
死ぬまで一人でいることを覚悟した少女が、誰もいない町で見つけたのは、真新しい落書き。自分しか生き残っていないと思っていた場所に残される誰かの痕跡。
たった二人だけ生き残った町で『もう一人』の名前を呼ぶまでの物語。
プロローグ 消去
『……もう、これから誰もあんたの電話には出ないと思うよ』
わたしと最後に電話することになった怜奈は、言いづらそうにこう呟く。
どうして、とは言えなかった。
それ自体はもう、今まで何人もかけた電話で想像が付いていたからだ。
『えっとさ、あんたはそっちにいて知らないかもしれないから言っておくけど、警察やニュースとかで、今、向こうの人間から電話とかかかってきても、出ないようにって言われてるんだよね』
「どういうこと?」
それは初耳だった。今まで電話をかけた相手は誰一人そんなことは教えてくれなかったのだ。
『よく解んないけれど。あたしもこの電話切ったら着信拒否させてもらうから』
「……そう。しょうがないよね」
警察や政府が、わたし達と話をしないように注意するのは、解らなくもない。
どんな工事よりも早く、波南町を囲う何メートルもの『壁』が作り上げられつつある最中、壁の近くで作業音でも消せないほど悲痛な叫び声がよく聞こえてきた。
『こんなことをしても無駄だ! 俺達を閉じ込めても、外にいても、おまえ達も無事では済まない! おまえ達だって、いずれは感染するんだ!』
叫びすぎて喉がすっかり嗄れた、痛々しい声。
あれを壁の向こうで聞いていた人達は、しばらく安眠することもできなかっただろう。
心やさしい人なら、罪悪感を抱いたかもしれない。
あれを聞かせまいという国の対応はそんなに間違ってないと思う。
『どうしたの?』
「あ、ごめんね。ぼうっとしてた」
『もう。あんまりいつもみたいなこと、してないでよ……いたたまれなくなるから』
怜奈はどこか呆れたような、困ったような溜息を漏らした。
この電話は結果的には、絶交の連絡ということになったのだ。
それなのに暢気な態度を取っているわたしは、確かに場違い以外の何物でもない。悪いことをしてしまった。
『でもさ……思ったより落ち着いてるみたいだね』
「うん。もう、泣いたりショックを受けたりなんて時期は過ぎちゃった。ありがたいことに死なずに済んでるし」
『そっか』
怜奈は黙り込んでしまった。
何を話したらいいのか解らなくて、わたしも黙ってしまったけれど、一分くらい経った頃、怜奈はぽつりと漏らした。
『……誰かに伝えてほしいこと、ある?』
怜奈が何を考えていたのか、何となく解った。
わたしが今までに連絡を取った何人かから、わたしのことを聞いているのだろう。
一番仲のよかった亜理のこと、亜理の紹介で付き合い始めて二ヶ月経った彼氏、研矢のこと……怜奈は友達グループの中ではそれほど仲がよくなかったから、彼女に電話をしたのは最後だったのだ。
彼らが今どうしているのか訊いてみたい気がしたけれど、決していい話は聞けないような気がした。
でも、勇気を出してひとつだけ質問してみることにした。
「亜理と研矢、どうしてる?」
一番親しかったはずなのに、それほど親しくないはずの怜奈よりも冷たい言葉でわたしを罵った二人。
怜奈は息を呑んだ。
『あいつら、最低だよ。何か言われたからって気にすることないよ』
「どういうこと?」
わたしの知らないことを、怜奈は知っているらしい。
彼女の声色から察する限りでは、どうやら亜理も研矢も、わたしを罵っただけでは済まないことを言っていたようだ。
「二人とも、そんなにひどいこと言ってたの?」
わたしの口調から、自分がまずいことを言ったことに気付いたらしい。怜奈はますますしどろもどろになった。
『そうじゃなくて……その、あいつら、付き合い始めたんだよね』
「は?」
頭が真っ白になった。
『あいつは二度とこっちに戻ってこないんだから、別に付き合ってもいいだろって……さすがにあの態度にはみんなむかついてて……』
「そうなんだ」
多分、怜奈の言葉は真実なのだろう。
でもわたしがいなくなった後に二人が付き合い始めたり、それについてみんなが嫌な思いを抱いたりしていることに、あまりショックは受けていなかった。
わたしの話題でもあるけれど、同時に永久に関係ないことでもあった。
もう、亜理にも研矢にも怜奈にも、二度と逢うことはない。声を聞くこともない。だからこそ、二人は平気で(かどうかは解らないけれど)わたしを罵った後に付き合うことができたのだろうし、怜奈はこんなことをわたしに話したりできる。
もし、わたしがみんなといつでも逢える立場だったら、怜奈はこの話をしなかったに違いない。仲間内の付き合いに関わってくるからだ。
だから、わたしはなるべく穏やかな声で告げた。
「ありがとう、怜奈。二人にはお幸せにって伝えておいて」
『マジ?』
有り得ないと言いたげなその声に、わたしはむしろほっとする。
「うん、どうせ逢わない人達だし。幸せになっても不幸になっても、わたしにはどうでもいい話だもん」
怜奈はしばらく黙っていたけれど、やがてこう言う。
『だったら代わりに、おまえらみんな死ねって伝えておいてもいい?』
「いいよ」
怜奈が「お幸せに」と伝えるのが不愉快だというなら、そうすればいい。
どちらでも同じことだ。
わたしには永久に確認のしようがないのだから。
「それじゃ、またね」
『あ……』
「ちゃんと番号は消しておくから、安心していいよ」
返事を待たずに電話を切った。
わたしがどう思っていようと、怜奈がどう思っていようと、もう話はこれでおしまい。
だから、これでいいんだ。
少なくともこの時はそう思っていた。
その考えは半分正しく、半分間違っていたのだけれど、携帯電話を切ったばかりのわたしにとっては、世界の何もかもを無感動に終えたばかりといった心境だった。
確かに怜奈や研矢、亜理にとって、わたしは存在しない人になった。彼らには『おしまい』はちゃんと訪れた。それは間違いない。
でも、わたしにとっては全くそうじゃなかった。
この後訪れたのは『おしまい』なんかじゃなく、もう少しささやかで『あっち』にいたらそんなものなど欲しいと思いもしなかった何か。
それは──『有り得る全ての可能性』のひとつ。
わたしにとって、一番大切な可能性だった。
でも、この時点のわたしはそんなことなど知っているはずもない。ごく無感動に『おしまい』を受け容れ、電話を切っただけだった。
そんな些細な『はじまり』の話。
1章 苺色の空
わたしは電話を切った後、登録してある全員の電話番号を消した。
怜奈や亜理、研矢だけでなく、今まで番号を登録した全部をひとつずつ消していった。
そして最後に残った番号。
(ここ……わたしの家)
このまま部屋を出てリビングまで行けば、電話機がある。わたし以外には誰もいない自宅からは、二度と電話がかかってくることもない。そして、ボタンひとつでこの家の番号も消去してしまえる。
でも、たったそれだけのアクションをすることができず、何となく携帯電話をそのまま放置して、ベッドに散らばっている荷物を詰め始めることにした。
お気に入りの服、下着、ブラシやシャンプー、コンディショナー。読みかけの本や好きなお菓子。いつも使う枕。まだ始まらないけれど、ナプキンもいくつか入れておく。
昨日本屋から持ってきた(買ってきた、ではない)波南町の地図と、葡萄のシャーベットに似た色合いの軸が気に入っている三色ボールペン。
なるべく荷物は増やさないようにしたつもりだったけれど、枕以外をリュックサックに入れてみると、いっぱいになってしまう。どうしようか迷ったけれど、後で困るようなら捨てればいいと思い直して、そのまま詰め込んでしまった。
リュックサックを背負って、携帯電話をポケットにしまい、枕を抱える。
ミッドナイトブルーの低反発枕。
わたしは自分の枕じゃないと眠れないので、枕は必需品だ。ここに戻ってくるつもりはないのに、枕を忘れていったら大変なことになってしまう。
部屋の中はなるべく見ないようにして、枕を抱き締めて部屋を出た。
この部屋にいると、いつまでも以前の生活にしがみついてしまう。
一番仲良しの亜理との時間。研矢との思い出。そして、父や母のいた、当たり前のはずの生活。
階段を下りて、三和土のところまで直行する。今まで暮らした家の中を見ないように、急いで玄関のところまでやってきた……つもりだった。
だけれど、馬鹿なことにわたしはふと、横を見てしまった。
カーペットの上にぶちまけられた、汚い色の染み。
不器用な人が腐汁で人型を描いたようなものが、二週間前からそこにある。
(お母さん……)
あれは、母の『痕跡』。
父の『痕跡』はベッドの上だったから、ほとんど見ずに済んだけれど、リビングの目立つ位置にあるそれは、どうしても見ないではいられなかった。
わたしはそれ以上考えるのをやめて、そのまま靴を履いた。
外に出て、扉に鍵をかける。
これがこの家の住人としてできる最後のこと。
「もう、これで終わり」
今まで大事に持っていたキーホルダーから鍵を外して、庭に放り投げた。
石か植木鉢にでも当たったのか、チンと安っぽい音がした。
あとはもう、ここから立ち去るだけだ。
わたしはなるべく力強く庭から足を踏み出した。
「あっ」
忘れてた。
ポケットに放り込んだ二つ折りの携帯電話を開くと、自宅の番号を表示している。
消去しますか?
今度はためらわなかった。
ボタンを押して最後の番号を消すと、そのまま歩き出した。
わたしが友達や恋人に着信拒否され、家を出なくてはならなくなったきっかけになった事件は、三週間くらい前に起こったらしい。
波南町の商店街で突然、歩いていた人が『溶けてしまった』というのだ。その翌日、学校でその話を聞いた時、わたしは意味を摑めなかった。人がなめくじみたいに溶けてしまうところを想像して、思わず笑ってしまったほどだ。何もイメージできていなかったのだ。
だけれど、事実はそんなに可愛いものじゃなかった。
そもそも溶けたという人は、そのまま消えてしまった訳ではなかったのだ。
溶けかけたまま病院に運ばれたその人は、最初、劇薬などをかけられたか、重度の皮膚病なのではないかと疑われ、どこかに隔離されて検査を受けたらしい。
だけれど、その結果が出る前にもっとひどいことになった。
その人がどうなったのか解る前に、波南町のあちこちで、何人もの人が同じ症状を訴え始めたのだ。
それから十日間くらいのことは、思い出したくない。
外に出なくても、あちこちから叫び声が聞こえてくる。最初の数日間くらいは救急車などが出動する音が聞こえていたけれど、やがてそれもなくなってしまった。
近所が大変なことになっていたので、わたしは学校に行くのは諦めていたけれど、父は隣の市にある会社まで最初は通勤していた。一週間ほどしてから、父も会社に行かなくなった。
「しばらく出社するなと言われたよ」
ひどく疲れたような声で、父はそう言っていた。
わたしも同じように学校から連絡を受けていたので、何となく納得した。
「早く出社できるようになるといいんだが……」
でも、父の願いは叶わなかった。
テレビでは波南町で起こっている異変を大きく報道し、ものすごいスピードで対策が練られているのを知っていくうち、家族みんなの表情が少しずつ沈んでいった。
波南町は何らかの生物兵器での攻撃を受けたのだと推定され、一時的に隔離されることになったのだ。
それからはあっという間だった。
「波南町の皆さん、もうしばらくの辛抱なので、我慢してください!」
言葉だけは誠意と情に満ちた呼びかけがなされる。
でも、誰ひとりとしてそんなことは信じていなかった。
有り得ないほど早く、高い壁が建造されていく。工事現場では制服姿の面々がわたし達に銃を構えているのを、波南町の住人は見ているしかできなかった。
何もしていない『ただの住人』に、銃を向けられる状況。
ほとんどの人は自分達の置かれている状況に絶望するしかできなかった。
もちろん、黙って見ている人達ばかりではなかった。さすがにそこまでみんな従順じゃなかった。体が溶けたりしていない、健康な人達は抗議した。出してくれるように懇願したのだ。
でも、まるで波南町にいる人間全員が、感染者か生物兵器ででもあるかのように、みんなの言葉を一切聞かず、代わりに食糧やいろんなものを置いていくようになった。
これからどうなるのだろう。波南町の住人は全員不安だった。
このまま壁が完成したら、わたし達は閉じ込められて死んでも助けてもらえない。
閉ざされたままでは、食べ物だって入ってこない。
働いている人達はお金を稼ぐこともできない。
本当に……不安でならなかった。
その頃には『メルト』と呼ばれるようになった、体が溶けてきた人達のことも、少しは情報が流布していた。
体が溶け始めて早くて一週間強、遅くて二週間ほどで死んでしまう。
その症状と直接関係があるのかは解らないけれど、メルトは溶け始めて数日ほどで知能が減退して、暴れることも増える。ただ、筋肉が溶けて長時間体を動かすのがつらいせいか、長距離移動をしなくなってくる。
だから家族にメルトが出ると自宅から逃げたり、人によってはパニックを起こして殺してしまうこともあった。
母がメルトになった時、最初は父もわたしも最後まで母を支えるつもりだった。不安がっていた母も、頑張っていくからと言ってくれた。
でも、それは果てしなく甘い気構えだった。
三日もしないうちに、母の言動が大きく変わってしまったのだ。
人間の声とは思えない奇声を上げて暴れ始めた母を見た時、父はショックを受けてしまった。当然のことかもしれない。愛する人が自分の理解の範疇を一足飛びで越えてしまい、あっという間に意思の疎通もできなくなってしまったのだから。
父はキッチンから包丁を持ってきて、わたしが止める間もなく母を刺してしまったのだ。
「ごぼっ……ぐじょごぶっ……!」
やさしい声の代わりに湿って汚い音を立て、母の口から腐汁が噴射した。
最愛の人が何だか訳の解らないものになってしまう。
もう、わたし達に愛に満ちた視線を向けてはくれない。
それどころか今までの何気ない表情の代わりに、穢らわしいほどの凶暴さ、胃液と体液の混ざる湿った音。そんなものに取って代わられた時、どんな思いになるのか全く解ってはいなかった。
母は刺された時にも、悲しそうな表情すら浮かべてくれなかった。痛がっている様子もなかった。ただ、全く『違う存在』になってしまった母の命が尽きていくのは、あまりにもあっけなくて、とても、違和感があった。
母の吐いた液をもろに浴びた父は、三日後……メルトになった。
でも、わたしは襲われなかった。
「今日から寝る前にバリケードを作って寝なさい。いいね」
寝る前にゴルフクラブを渡し、そう言い渡した父の眼は、赤く充血していた。
その体からは、母から漂ってきたのと同じ、嫌な臭いがした。
たったそれだけを言うのもつらそうに、父は部屋に戻っていく。
父に言われた通り、自分の部屋にバリケードを築いて眠ったわたしは、お昼過ぎになっても母の時のような暴れる気配を何ひとつ感じられなかったこともあって、一度バリケードをずらしてゴルフクラブを構えながら一階に降りていった。
誰の気配もなく、ひっそりとした家。
見えるのは母の溶けていく死体だけ。
触るのも怖くて、なるべく息を止めて通り過ぎる存在になってしまった母から眼をそらし、わたしは呼びかける。
「お父さん、どこ?」
ほどなくわたしは、両親の寝室で父を見つけた。
ベッドの上で、お腹に包丁を刺して死んでいたのだ。死んでから少し時間が経っているせいなのか、お腹のあたりは溶解がかなり進行していた。
もしかしたら、わたしもメルトになるのかもしれない。
寝室から出て扉を閉めると、足早に二階へと戻っていった。
もう、守ってくれる家族はいないのだ。もちろん波南町の人間は全員、メルトになるかその家族になる危険を抱えながら生きている。
ずっと、ずっとだ。
もし、わたし以外に無事な人がいたとしても、警察や役所を含め、不安を聞いてくれる余裕など誰にもあるはずもなかった。みんな同じようにメルトの恐怖と隣り合わせで、普通の人間であり続ける保証はない。何でもない日常を期待することすら贅沢だ。
誰かと話したくてたまらなかった。
波南町以外に住む、わたし達にとっても当たり前だった『日常』に住んでいる人と。
わたしが最初に電話をかけたのは、研矢だった。
『俺だけど』
コールしてほどなく研矢が出た。
「研矢^!?^ あのね、わたし……」
『ああ、解ってる。波南町のことはニュースで見てるから』
彼の声を聴いた時、本当にほっとした。
研矢はただの高校生でしかなくて、この惨状から助け出してくれることはできないけれど、脅えているわたしのことを安心させてくれる。
「よかった……わたしどうしようかと……」
『あのさ、俺に何をしろと?』
イライラした声に、わたしは戸惑った。
「え?」
『波南町ってドロドロに溶けた化け物ばっかりになってるんだろ? おまえもそのうちそうなるんだよな』
あまりにショックで、何を言われたのか全然解らなかった。
「研矢……?」
『もう、かけてこないでくれ。二度と逢いたくないし、逢わないだろうし。溶けてドロドロになるかもしれない女と付き合ってたなんて、正直、ものすごく気持ち悪い』
そのまま電話は切られた。
そのショックから少しだけ立ち直ってから、もう一度研矢へ電話をかけてみた。
こんなのは間違いだ。研矢もショックが大きくて、ついひどいことを言ってしまっただけなんだ。話せばもう少し落ち着いてくれる。そんな甘い期待を抱いていたけれど、すぐに打ち砕かれた。
ものの数十秒の間に、電話は着信拒否になっていたのだ。それが一応恋人ということになっていた高橋研矢と話した最後だった。
その後に電話をかけた亜理から冷たくあしらわれた時には、研矢の時ほどのショックはなかった。
『もう電話してこないでよ。あんたなんか友達でも何でもないんだから!』
「そんな……」
ショックはなかったけれど、ただ、とても心が冷えきってだるい気がした。
「最初からそう思ってて、今まで友達でいたの?」
『あんたが波南町の人間じゃなかったら、ずっと友達でいられたかもね』
亜理の言葉に少しでも澱みがあったら、わたしは心を落ち着けることができただろう。
波南町の異変で亜理は脅えているんだと、自分に納得させることができただろう。
でも、その言葉はすんなりと口から飛び出て、容赦なくぶつけられた。嘘とかごまかしの一切ない、クリアな響き。元々亜理は嘘はついても感情をごまかしたりするタイプではない。よく知っている相手だったからこそ、これがごくシンプルな本音なのだと理解できる。
もう充分だった。
「……そういうの、あんまり友達って言わないと思うけれどね」
それがわたしに言えた精一杯の言葉だった。
さすがに言い過ぎたかと思ってもう一度電話をすると、やっぱり着信拒否されてしまっていた。一緒にいた時間までもが、安っぽく薄っぺらに思えてしまう幕切れだった。
その後、何人かに電話をしたけれど、みんな早々に電話を切ってしまった。
最後に話した怜奈のように、警察やニュースで波南町からの電話に出ないように注意を呼びかけていることを教えてくれる子はいなかった。ただ、迷惑そうにしながらもわたしのことを少しだけ気遣ってくれる子はいなくなかった。
それだけでも充分すぎると思うべきなのだろう。結局、ここしばらくの間は誰にも頼ることのできないまま、たった一人で生きてきたのだ。
壁が完成してから、食糧の配給は途絶えたも同然になった。
二週間に一度、上空から生鮮食品などを投下してくれるというのを、大音響で流していたけれど、今の状況で二週間はあまりに長すぎた。
そんなの、想像もできないほど長かった。
でも、ありがたいことがあった。
波南町在住のものすごいお金持ちが全財産で備蓄食糧や電気、水道代などを支払ってくれたらしく、壁の中で助かる望みもなく生きていくのさえ我慢できれば、ぎりぎり生活していけなくもないのだ。
わたしは今日まで、駅前の商店街やデパート、コンビニなどでいろんなものを持ち出して、何とか生き延びてきた。
ガスは来なくなったけれど、カセットコンロやよその完全電化のキッチンに入り込んで料理することもできた。生鮮食品が全滅する前に、大人が冷凍コーナーにかなりの食料を移していたらしく、配給が途絶えた後にもすぐ食事がなくなることもなかった。
あと二週間なら何とか我慢できると思った。
しかも、オール電化にしている家を探して侵入し、お風呂に入ることすらできるのだ。
(世界終末よりは、ずっと条件はいいよね)
わたしは無理に微笑んだ。
悩んでも仕方ないことをいつまでも考え込むのはよそう。
電気、水道が確保されているのなら、何年も生きていけるだけの備蓄は、波南町には充分あるのだ。故障した時のメンテナンスはできないけれど、その方法も本屋かどこかで探せば見つからなくもないだろう。
正真正銘のサバイバル生活に直面するまでに準備期間がある。
これはすごいことだ。
(それに、わたしだっていつメルトになって死ぬかもしれないんだし……何年も生きられるかどうか疑問だよね)
それなら、無駄に考えても仕方がない。
何とかなる。
何とかなるんだ。
自分にそう言い聞かせる以外に、わたしにできることなんかなかった。
家族も友達もみんな捨てて、家を出たわたしがその日向かったのはデパートだった。
そんなに大きなデパートではないけれど、ある程度のものは何でも揃う。家具売り場まで一番綺麗な柄の毛布を持ち込んで、気に入ったベッドの上に愛用の枕と一緒に置くと、ちゃんと家のような気がする。
「何ていうか……この生活、はまりそう……」
消費期限の短い生鮮食品はとっくに駄目になっているけれど、レトルト食品や缶詰、ペットボトルの飲み物は無事だ。
ジュースなんかは冷えたのをおいしく飲むこともできる。
わたしは店から持ってきた新品のパジャマに着替えて、ゆったりと横になった。
煌々と輝く中で眠るのはあまり落ち着かないけれど、広すぎるデパートを真っ暗にして眠るのはもっと嫌だった。
「本の続き読もう」
リュックサックから取り出した本を広げる。
前に古本屋で一巻だけ買って、その後は全巻読もうと心に誓った『ウィーツィー・バットブックス』の2巻『ウィッチ・ベイビ』。
魔女の子は泣かないの、と心の中で叱りつけても、どうしても涙が止まらない。
そのフレーズに何となく自分が重なってしまって、読むペースが落ちる。
波南町の住人であるだけで、わたしは友達にとって『魔女』そのものなのだ。高い壁が立ちはだかっている以上、この中で起こっている異変がみんなに影響を及ぼすことなんてないのに、そんなところにいるだけで充分穢らわしい存在だ。
やりきれなくなってきた。
残り三分の一くらいだから、今日中に読んでしまえそうだと思ってたのに、結局本を読むのは諦めてしまった。
消してしまった携帯の電話番号や、みんなと連絡を取らないと決意したことなんかが、心の中にちらちらよぎって、本の世界に入れなかった。
いつも傷ついているウィッチ・ベイビが、傷ついていながらも心を通じ合わせることのできる人と出逢い、成長していくのを見ていると、自分の取り残された状態がどんどん悲しくなってくるのだ。
本当はこういう時こそ、ぐるぐる回って解決できない思いを誰かに吐き出したい。
もちろん、そうすることができない立場だと解っているから、ないものねだり以外の何物でもない。無意味なことを考えている自分が少し嫌だった。
よく考えたら、ここ数日父以外の人が生きている気配を感じられなかった。
そこから導き出される何かについて、考えるのが怖かった。
「……はぁっ」
このまま眠れそうにない。
眠らなくても誰にも咎められはしないのだから、覚悟を決めて起きていよう。
わたしはこのフロアの二階上にある、あまり品揃えのよくない本屋に行って、イラストロジックの雑誌と色鉛筆を取ってきた。クロスワードパズルは変に連想が進みそうだから、眼を酷使するけれどあまり考えずに済みそうな、こういう暇つぶしがいい。
わたしは結局、いくつかのパズルを完成させた後、眼の使いすぎで疲れ、そのまま突っ伏して眠ってしまったのだった。夢も見ない、何よりも望んでいた眠りだった。
起きた時、枕元にあった携帯は午前十時四十分だった。
最後に時間を確認した時には、昨日の午後十一時くらいだったから、半日くらいは眠って過ごしたことになる。
「うわぁ」
普段の睡眠時間は七時間程度だ。
本当に心が疲れていたんだなと思って、改めて落ち込んだ。
少しだけだけれど。
でも、本当に孤独だった今までよりも、すっきりしたような気がする。
立場は全然違うけれど、前に亜理が「男と別れた時って、グダグダだけれどスカッとする」と言っていた気持ちが何となく解ってしまった。
本当に望んでいたものじゃない、何となくあってもいいかなという居心地のよさは、なくたって別に困りはしないのだ。
寂しいのはその時だけ。
今が『その時』だっていうのだけが問題なのだ。
波南町の生活が、昨日と今日とそれほど変わる訳でもない。
もちろん、ある程度町の状況や生き残っている人達について、ちゃんと調べておいた方がいいに決まってるけれど、そういう前向きな気持ちにはまだなれそうもない。
他の誰がいて、誰がいないなんてことは、わたしが正真正銘、自分の知っている人全てから分断されたのだという事実のインパクトが大きすぎて、悲しいくらい気にならない。
とりあえず、前向きになるべきなのだろう。
でも考えれば考えるほど、頭は思考停止していく。
こんな自分がものすごく嫌だ。
「食べる物を探しに行こう!」
何が悲しくて、起き抜けから後ろ向き全開のことで悩んでいなければならないのか。
食べよう。
甘いものがいい。
甘いものを食べて、お茶でも飲もう。
このまま荷物をまとめて、食品売り場で何か探そう。
たまには外で食べたっていい。
天気がよければピクニックを兼ねて歩き回ってみよう。それで少しでも気持ちが晴れないことにはやっていられない。
今日は晴れだった。
気持ちいいくらい澄んだ空を飾るように、小さな雲が浮かんでいる。
甘いお菓子とお茶を持って遊びに行こう。そんな気分になれたのが嬉しくて、思わず深呼吸をした。
(案外、一人でも何とかなるよね)
ここ何日か、実際にわたしは一人で生活してきた。
誰とも逢わないままで、友達の番号も全部消した。
快晴の空の下、とても前向きになれていた。
でも、しばらく歩いているうちに徐々に気になってきたことがあった。
「あ……」
静かだ。
静かすぎた。
今までわたしはひとつ、大きなことを考え忘れていたのだ。波南町がこんなことになって、両親が死んで、今になるまで。
阿鼻叫喚の叫びを上げていたはずの、他の人達はどうしたんだろう?
近所に食べ物を調達に行く時も、よそのオール電化の家へお風呂に入りに行く時も、たまに誰かとすれ違ったり、家から生活音が聞こえたりすることが皆無ではなかったのに、今日は……誰ともすれ違わない。
嫌な予感がした。
どんどん減っていく波南町の人達を見ていても、馬鹿なことにわたしは一度も『誰もいなくなる』なんて考えてみもしなかったのだ。
ひとりぼっちだというのも、本当にわたし一人だなんて想像していなかった。
公園に向かう途中も、マグボトルに入れて持ってきた冷たい紅茶と、苦みのきいたチョコレートが空になってしまっても、太陽が傾いてきて、繁華街の方へ戻ってくる途中にも、誰ひとりとして見かけることはなかった。
夕食を入手するために、途中で見かけたスーパーに入った時、わたしは悟った。
わたしの前に誰かがここを訪れたのは、最低でも何日か前のことだろう。
生鮮食品の入れ替えが行われなくなってから、大抵の食品売り場では悪くなったものを片付けていくようになった。
最初は肉や魚を冷凍スペースへ移動させ、紙パックの牛乳なんかを流しに捨てていく。
しなびて腐った野菜や肉は、どこからか運ばれてきていた生ごみ処理機に入れて処分していく。
乾いた生ごみは、敷地の隅にまとめて置かれていた。
そうしないと、いくら電気が通っているといっても、どんどん店内に腐ったものの臭いがこびりついていく。閉鎖されて波南町から出られない状態だからこそ、食料を入手できる場所がそんなことになってしまうのは、みんな嫌なのだ。
もちろん、最初は自暴自棄になって店を荒らしたりする人もいた。
でも、それでも食事はしなくてはならない。
だからこそ、暴れるような人もしばらくすると、生鮮食料品を扱う店ではおとなしくしているようになった。
自分があっさり死んでしまうのか、長生きしてしまうのか、現状では簡単に判断できるはずもない。もしかしたら、これから死ぬまでずっとここから出してもらえないのだとしたら、食べ物を得ることのできる場所で心証を悪くして、分けてもらえなくなる……なんてことも充分有り得るのだ。
人数が減れば減るほど、周囲の人間に気を遣って生きていかなくてはならない。
そう思った人が多かったからこそ、生鮮食料品を売る店はお客さんもなるべく清潔にしようと心がけていた。
店員や店主がすべきだろうという考えは、メルトが起こって数日で消えた。
メルトはお店をやっている人にも同じように襲いかかる。かといって、たくさんの生鮮食料品を保存しておける設備は決して多くない。
彼らがメルトになろうがなるまいが、どうしてもお店の設備を使うしかないのだ。
だからこそ、このスーパーでわたしは違和感を抱いた。
悪くなった生鮮食料品がそのまま並べられていて、変な臭いがするのに誰も片付けた様子もない。そもそも、最近誰かが食べ物を入手しに来た形跡が──ないのだ。
わたしは思わず身構え、店内を歩いた。
別に何かいると思った訳ではなくて、誰も来なくなった理由がここにあるかもしれないと考えただけだった。でも、それらしいものは何も見つからなかった。
ただ、人がいない。一箇所、メルトが溶けた痕跡が残っていたけれど、それだけ。
シートを上からかけたり、隔離した様子がないから、多分、ある程度メルトで人が死ぬことが珍しくなくなってからのものだろう。
本当に『いつも通り』だ。
だからこそ、非常事態が起こってもいない店にお客さんが来ていないのが異様だった。
結局、その店にはお菓子とペットボトルのお茶と缶詰を持って店を出るまで、誰も現れることはなかった。
わたしの違和感が限りなく確信に近くなったのは、陽が暮れてからだった。
夕食を手に入れるために、何人かは歩いていても当然の時間なのに誰ともすれ違わず、その間どの家からも一切生活音がしなかった。
「まさか……」
その言葉の続きは、どうしても言えなかった。
音声にしてしまうと、その事実を認めたような気持ちになりそうで、昨夜も泊まったデパートに辿り着くまでずっと黙っていた。
どうしても拭い去れない不安を紛らわせるために、あたたかい飲み物が欲しかった。
今日はもうスーパーに寄っていたから、わざわざ地下の食品売り場に行く必要はなかったけれど、ティーバッグやコーヒー、ミネラルウォーターなんかを取りに行って、家電売り場から電気ポットを運んできた。
コンセントを探してお湯を沸かすと、紙コップでティーバッグのお茶を淹れる。
今までは自宅にいたから、お茶を淹れるためにここまで面倒なことをする必要もなかったけれど、これからは違う。あたたかいものを飲みたいのなら、自販で買うのでなければ、こうやって飲み物を淹れる方法を確保しておかないといけない。
(もう、家には帰らないんだから……)
問題なのはお茶だけじゃない。
わたしの家は半年前にオール電化にしていたのが幸いして、ガスが止まってもお風呂に入れなくなることはなかったけれど、これからはお風呂に入れる場所もちゃんといくつか確保しておかなくてはならない。こうして考えてみると、友達や彼氏のこと『なんか』で一喜一憂していた自分が間抜けに見えて仕方がなかった。
今まではオール電化の家で、よそから食べ物を持ってきて過ごしていたけれど、これから生鮮食料品はなくなっていくし、電気や水道だっていつまで使えるのか解らないのだ。
面白そうな小説とかを読むより先に、もう少し真剣にこれからのことを調べたりした方がいいはずなんだけれど、自分の置かれている状況を細かく知ってしまうのが怖くて、どうしてもそんな気が起こらなかった。
自分が本当の意味でたったひとりであることと、これまで向かい合ったことはなかった。
でも……これからは嫌というほど向かい合うことになるのだ。
その後、どうやって戻ってきたかは解らないけれど、わたしはいつの間にか駅前付近をふらふらと歩いていた。
空はすっかり苺ゼリーみたいな色に変わっている。
可愛くて、いつもなら胸が詰まりそうな気持ちになるはずの空の色なのに、その苺色の可愛さはただ、不安を余計に増やしただけだった。
(そう言えば、ストロベリーブロンドって赤っぽい金髪のことだっけ)
無意味にそんなことを思い起こす。
すっかり頭が現実逃避に入ってしまっていた。
ふらふらとデパートに帰ってきて、食品売り場からロータスのキャラメルビスケットとミネラルウォーターを取って、昨日眠った家具売り場に戻る。
もちろん、誰もいない。いるはずがない。
悲しくなってきて、CDを大音響でかける。
CDショップの棚からでたらめに引っこ抜いてきたCDは、今まで一度も聞いたこともないオペラだった。
「……『エレクトラ』……リヒャルト・シュトラウス」
シュトラウスという名前だけ、音楽の教科書で見た気がするけれど、詳しいことは全然思い出せなかった。
止めてしまおうかとも思ったけれど、何となくそのままにしておいた。
いつも聞いているようなJ-POPは、研矢や友達の趣味に合わなかったら困るから押さえていた部分もかなりあって、すごく好きって訳でもなかった。
よく考えたら、特に音楽が好きでたまらないなんてこと、一度もなかった。
でも、こんな場所で無音に堪え続けるのがつらかったから、そのまま聴き続けた。
こんな、気持ちが揺れてる時には、思い出もない、ただメロディが美しいだけの意味も解らない歌の方がずっとよかった。
建設的なことを考える気力が全く出ず、寝そべって『エレクトラ』を聞きながら、キャラメルビスケットをぽりぽり食べ、イラストロジックをやってるうちに、伏せって寝てしまったらしい。
翌朝、夢ひとつ見ないで、突っ伏したまま瞼を開けることになったのだった。
館山の物語を気に入ってくださった方、投げ銭的な風情でサポートすることができます。よろしかったらお願いします。
