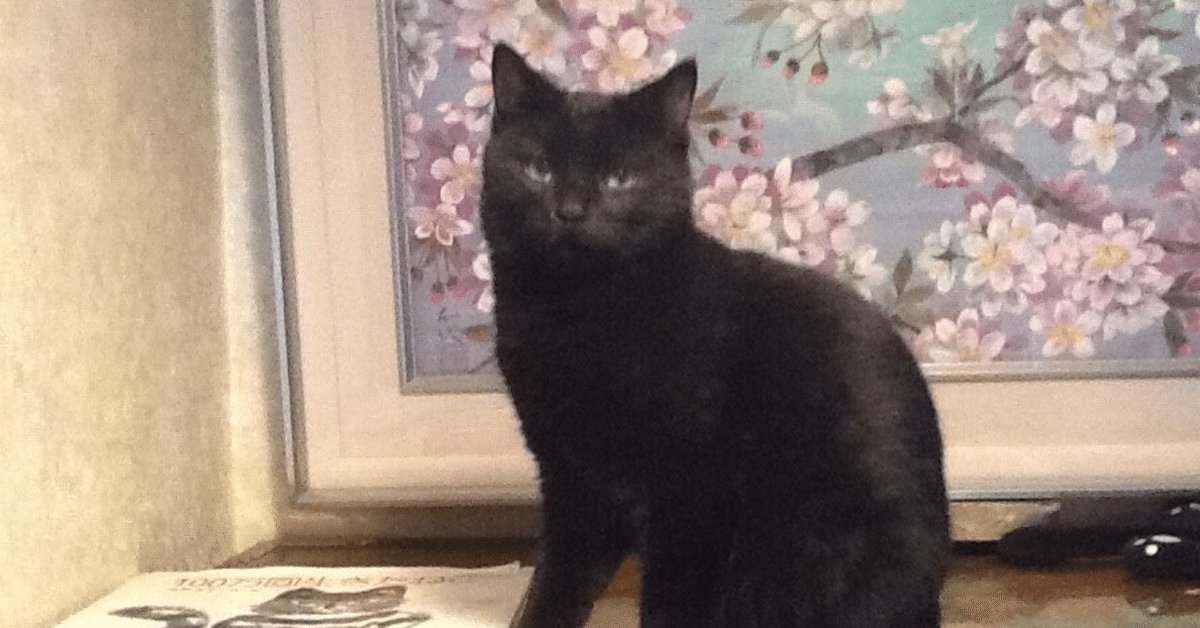
物語になれない思い出
亡くなった佐野洋子の『100万回生きたねこ』に寄せて、『100万分の1回のねこ』という本が編まれていたことを知った。多くの作家が『100万回生きたねこ』に花を捧げるように寄せた短編集だ。
生きること、死ぬこと。生まれること、死なれること。猫といること、猫でいること。
たんたんとした日々の営みのなかで、これらのエピソードは、やはりたんたんと記されていて、少しずつ読んでは思い返すなかで、私のなかの「水位」が喉元まであがっていることにふと気付く。それは、数年前までうちにいた猫を思い出すときと似ている。
もっといてくれたらよかった。もっとやさしくしていればよかった。あんなひどいことをした。あんなふうにしてくれていた。
当時はそれほどに感じていなかったできごとが、あの子の姿とともに思い出すことで胸の中で水を吸ったように膨れ上がる。
ちなみに、ごめんなさい、とか、あのころにもどりたい、とか、そういうものではなぜかない。
だから、こんど猫がやってきたときは――こんど誰かに対してもし機会あれば、できるかぎりよくしたいと思う。うまくできるかは分からないが、愛とか慈しみのようなもの(だけ)が伝わっていればいいと思っている。
* * *
でも、どうだろう。日々の出来事は、いつも同じように振り返られるわけではない。言葉にしようのない「体験」とはそういうものかもしれないけれど。
もはやディスクールのない地のかなたにまで理論が前進してゆかねばならないときには、ある特別な問題がもちあがってくる。いってみれば、突然、デコボコ道にさしかかってしまうのだ。言語にしようにも、言語が踏みしめる地面そのものがなくなってくるのである。
言葉にしたくても、できない。その感覚はどこからともなくやってくる。しかも全身が見えないうちに姿を消してしまう。唯野未歩子の短編を読んでいた時もそうだった。
とはいえ、実際わたしはすでにそんなようなものだったのかも知れない。人間のそばにいたい。名を呼ばれたい。兄さんさえいなければ。兄さんさえいなければ。憎い。恨めしい。憎い。恨めしい。でも飼い主を愛することをやめはしなかった。
そうして、また生まれ変わる。それじたいは珍しい事柄ではないが、ひとりきりでこの世に生まれ落ちて、兄弟姉妹がいないだけでなく、もう誰の妹でもない。
少ないながらも本を読んでいると、そんな感覚が多く残されていく。昔の体験の残り滓なのか、あるいは見たこともない世界の「経験」なのか、それが分からないものだから、私は読み、思いふけり、考えることがやめられない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
